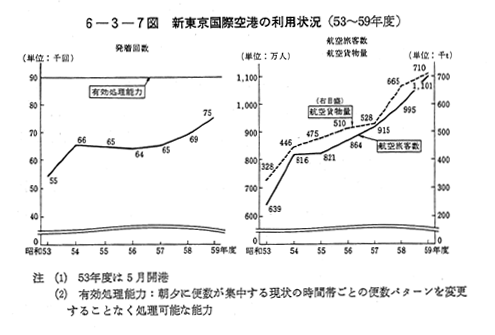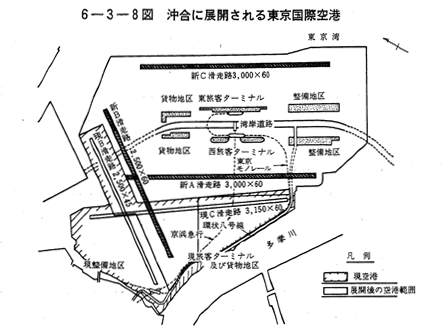|
2 基幹空港の整備
(1) 関西国際空港の整備
ア 関西国際空港建設の進捗状況
(67年度末開港を目途に)
現在の大阪国際空港は,我が国の国際及び国内航空ネットワークの2大拠点の一つを形成しているにもかかわらず,環境対策上の配慮から離着陸回数の制限等多くの制約を受けているため,特に西日本を中心とした航空輸送の面で同空港は大きなボトルネックとなっている。また,我が国には,いまだ本格的な24時間運用可能な国際空港が整備されていないため,我が国の国際航空の発展にも大きな支障が生じている。
このような状況に適切に対応し,大阪国際空港の環境問題の抜本的な解決にも資するため,関西国際空港の早期実現が望まれている。
このため関西国際空港株式会社は,59年10月設立以来,漁業補償交渉,環境アセスメント,護岸,埋立,空港連絡橋等の設計等の着工準備を行っており,引き続き公有水面埋立及び飛行場設置のための手続きを行い,これらの着工準備の完了を待って60年度末に本格的工事に着手することとしており,開港は,67年度末を目途としている。
また,本会社は,60年7月に72億円の増資(国48億円,地方公共団体12億円,民間12億円)を行ったところであり,資本金は123億円となった。
なお,本会社の設立に際して民間約800社から出資希望があり,60年度の増資に当たっては約770社から出資を受け入れ,関西国際空港事業に対する民間の熱意の吸収が図られている。
イ 関西国際空港計画の概要
関西国際空港は,大阪湾南東部の泉州沖の海上(陸岸からの距離約5キロメートルの沖合)に設置する。また,本空港は全体構想を踏まえ段階的に整備を図ることとし,第1期計画の規模は,3,500メートルの滑走路1本,面積は,約500ヘクタールとしている。能力は,年間離着陸回数16万回,開港は,67年度末を目途としている。また,建設工事費は,合計約8,000億円(事業費約1兆円)(58年度価格)と見込まれている。
なお,関西国際空港の全体構想は,4,000メートルの主滑走路2本,3,400メールの補助滑走路1本,面積約1,200ヘクタール,年間離着陸回数約26万回となっている。
ウ 関西国際空港関連施設の整備
関西国際空港の立地に伴い必要となる関連施設整備については,関係10省庁の局長等で構成される関西国際空港関連施設整備連絡調整会議において,国土庁を中心に,地元府県市の意見・要望を踏まえ,関連施設整備に関する国の基本的な方針をとりまとめた関西国際空港関連施設整備大綱(仮称)の策定作業を進めている。
エ 今後の進め方
関西国際空港の建設運営に際しては,民間活力を導入するとともに空港と地域社会との調和を図るため,民間の創意工夫の活用,環境保全等に十分留意し,併せて関係地方公共団体等地元の理解と協力を得る必要がある。
また,関西国際空港が関西全域のための空港としてその機能を十分に発揮できるように関西国際空港関連施設の整備を図っていく必要がある。
(2) 新東京国際空港の早期完成
ア 現況
60年5月で満7周年を迎えた新東京国際空港の利用状況は,開港以来堅調に推移し,59年度には旅客数が1,100万人(対前年度比10.6%増,我が国国際旅客数の約3分の2に相当),貨物量が71万トン(同6.7%増,我が国国際航空貨物の約8割に相当),航空機発着回数が1日平均204回(同8.5%増)と,いずれも高い伸びを示した 〔6−3−7図〕。また,現在33か国37社の外国定期航空会社を含め40社の定期航空会社が乗り入れているが,新たな乗入れを希望する国が32か国にも及んでいる。
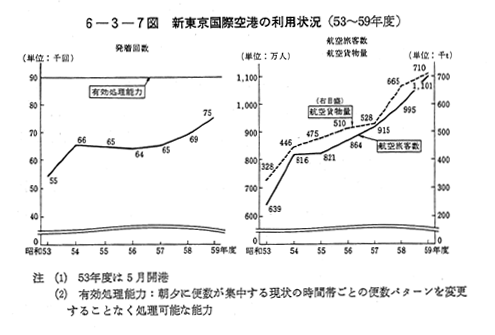
イ 早期完成の必要性
このように新東京国際空港は,我が国の表玄関としての役割を十分に果たしてきているが,同空港は,当初計画の半分の規模で開港したものであり,旅客ターミナルビルについては既に限界に達しており,また,滑走路についても発着回数の伸びに伴い近い将来能力の限界に達するものと見込まれている。さらに,同空港は,世界の主要空港としては他に例をみない本の滑走路で運営されている。このため,今後も増大する航空需要に対応するとともに安全性,定時性の確保を図るためできるだけ早期に当初計画に従い空港の完成を図る必要がある。
ウ 地元対策の推進
空港の早期完成を図るためには,空港と周辺地域社会との調和のとれた発展を遂げるようになることが必要であり,従来から,環境対策,農業振興等の地元対策を推進してきた。その結果,58年から59年にかけて地元地方公共団体の議会等は相次いで空港の早期完成を求める議決を行う等今や新空港は,周辺地域社会の発展にとって欠くべからざる存在として地元に定着してきている。さらに,60年7月にはB・C滑走路に係る騒音区域の告示を行い,これにより地元との重要な懸案事項はほぼ解決し,空港の早期完成に対する地元の積極的な協力が得られる状況が確立された。
エ 今後の課題
(ア) 未取得用地の取得
現在,早期完成のために残された課題は,空港敷地内農家等の有する未買収用地の取得である。
これまで,12戸の空港敷地内農家等の用地が未買収であったが,地元地方公共団体の協力も得て60年8月にはその内4戸の用地について買収が行われ,残る未買収用地(22ha,全体の2%)の話合いによる取得に向け努めている。
(イ) 国民の理解と協力
空港の早期完成を図るためには,成田空港の諸問題に対する国民の理解と協力が得られることが必要であり,空港の早期完成の必要性等について世論に訴えているところである。
(ウ) 空港保安対策の強化
いわゆる過激派集団は,空港反対農民を支援すると称してはいるものの,航空燃料パイプライン破損事件,金属製の羽根付き飛翔物による空港襲撃事件等の農民にも被害を及ぼすこととなる過激なゲリラ活動を展開している。このため,「新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法」に基づき3か所の団結小屋の使用禁止命令を出すなどの対策を講じているが,現空港施設を過激なゲリラ活動から防護しつつ新たな工事に着手できるよう,警備当局と協力しつつ,民間警備員を増強する等自主警備体制の強化に努めている。
(3) 東京国際空港の沖合展開事業の推進
ア 事業の経緯
東京国際空港は,国内航空交通の中心として全国34空港との間に1日約410便のネットワークが形成され,年間約2,600万人が利用している。
運輸省では,同空港を中心として増大する航空需要に対処するため,長期的視野に立って,処理能力の限界にある同空港の沖合展開の検討を進めてきた結果,58年2月,東京国際空港整備基本計画を決定した。その後,航空法に基づく飛行場の施設変更の手続き,東京都条例に準じた環境影響評価の手続きを経て59年1月に工事に着手した。
イ 計画の概要
本計画は,3本の滑走路を設ける等空港施設を拡大し能力増を図ることにより,首都圏における国内航空交通の中心としての機能を将来にわたって確保するとともに,懸案であった航空機騒音問題を解消することがねらいである。また,本事業の特長として,東京都の廃棄物処理場の有効利用及び空港跡地の利用があげられる。
空港へのアクセスとしては,鉄道については東京モノレールが60年7月に路線免許を取得しており,新ターミナルまで延伸する計画であり,将来的には京浜急行の乗入れも計画されている。道路については,建設中の湾岸道路との取付け,環状8号線の延伸を行う予定である。
ウ 事業の推進状況と今後の見通し
本事業は,用地を造成する廃棄物埋立事業,東京湾岸道路等の道路事業及び東京モノレール等の鉄道整備事業と整合性を取りつつ進める必要があり,全体の工程を次の3期に分けて行うこととしている 〔6−3−8図〕。
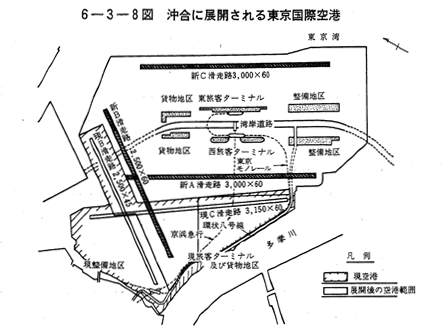
〔第1期〕 現廃棄物処理場の陸側部分は,ほとんど陸地化しており,この土地を利用して現在,63年7月供用に向け新A滑走路の工事を鋭意推進している。これが供用されると離着陸処理能力が増大するとともに既成市街地に及ぼす航空機騒音が軽減される。
〔第2期〕 湾岸道路等アクセスの整備に合わせ,駐機場及びターミナルの一部を完成させ,現在のターミナル機能を移転させる。
〔第3期〕 新廃棄物埋立地の陸地化を待って,新B滑走路,新C滑走路の整備やその他の工事を実施し,沖合展開を完了する。
これにより,現空港と沖合展開後の羽田空港について規模を比較すると滑走路処理能力は現行の年間16万回が23万回に,乗降客数は年間2,600万人が8,500万人になり空港の処理能力は飛躍的に増強される。
|