|
2 交通安全対策の推進
(1) 道路交通の安全対策
ア 車両の安全確保
(保安基準の強化等)
自動車の安全を確保するため,道路運送車両法に基づき,自動車の構造・装置等について,保安上の技術基準(道路運送車両の保安基準)が定められている。この保安基準については,最近における交通環境の変化等に対応するため,60年9月にシートベルト装備義務の拡大,前面ガラスの性能要件及び衝突時の燃料漏れ防止要件の強化等の改正を行った。
また,輸入車に対する日本市場解放の見地から自動車の安全基準の国際的な整合化が求められており,安全基準の国際的調和活動に積極的に参画するための調査・研究の充実に努めている。
(検査・整備制度)
自動車の安全の確保と公害の防止を図るため,自動車のユーザーに対し,その責任において一定期間ごとに定期点検整備を行うことを義務付けるとともに,国は,自動車の検査(車検)を行っている。
また,自動車の整備事業者(自動車分解整備事業者数80,101,うち指定自動車整備事業者数19,287(59年度末現在))に対しては,その業務の適正化を図るよう指導・監督を行っている。特に,整備事業の近代化を図るため,60年度より経営方式の適正化等を内容とする経営戦略化構造改善事業を推進することとしており,さらに,国の検査業務を実質的に代行している指定自動車整備事業の維持・拡大を目的として58年12月に創設された自動車整備近代化資金制度の資金総額を60年3月には60億円に増額して,その適切な活用を推進している。
イ 自動車運送事業の事故防止対策
道路交通事故が,近年増加傾向にあるなか,自動車運送事業者による1台当たりの人身事故発生率は自家用自動車の3〜7倍と極めて高く,また,59年7月国会決議により自動車運送事業者の運行管理体制の充実強化が強く要請されたことも踏まえて,運行管理者研修,自動車運送事業者に対する監督・指導の徹底を図っている。
特に,60年1月28日には長野県長野市において貸切バスが笹平ダム湖に転落・水没して死者25名を含む多数の死傷者を生ずるという自動車事故において戦後6番目の大事故が発生した。このような事故の再発防止を図るため,60年1月31日には,関係5省庁において,「レジャー客輸送バスに係る交通事故の防止対策」について申合せを行い,2月1日には,運行経路の緊急調査,運行管理等の徹底,安全運転の徹底を重点とする事故防止対策を全国のバス事業者に指示した。
また,60年5月6日には東京都目黒区の環状7号線において,ガソリン等の危険物を輸送中のタンク・ローリが転覆し,タンク内の危険物が流失・発火し,民家等が焼失する事故が発生したが,これに対して安全運転の徹底,車両の安全確保,関係法令の遵守等に関する緊急総点検を実施し,事故防止の徹底を図った。
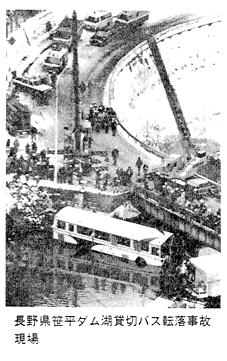
さらに,60年10月5日には山梨県内の中央自動車道において,2階建て貸切バスが転落し,死傷者64名を生ずるという2階建てバスとしては我が国初めての重大事故が発生したことにかんがみ,安全運転の徹底等を重点とする運行管理,車両管理業務の総点検の実施を全国の貸切バス事業者に対し,指示した。
ウ 自動車事故被害者の救済
(自賠責保険の保険金支払限度額引上げ)
自動車事故による被害者の救済を図るため,自動車損害賠償責任保険等の自動車損害賠償保障制度の適切な運用を行っている。自賠責保険の保険金支払限度額については,59年12月の自動車損害賠償責任保険審議会の答申を受けて,60年4月に,7年ぶりに死亡及び後遺障害1級を2,000万円から2,500万円に引き上げるなどの改定を行った。また,保険料についても,自賠責保険の収支が悪化し,早急な収支改善が必要とされていたため,同時に,全車種平均で約29%の引上げが行われた。
このほか,自動車事故対策センターにおいて,交通遺児等に対する生活資金の貸付け,重度後遺障害者に対する介護料の支給,附属千葉療護センター(60年4月には50床に増床)における重度意識障害者に対する治療及び養護等を実施しており,(財)交通遺児育成基金においては,育成給付金の支給等の事業を行っている。また,59年9月に設立された(財)自動車事故被害者援護財団が,被害者家庭への越年資金の支給等の事業を行っている。
(2) 鉄軌道交通の安全対策
鉄軌道における事故は,近年減少の傾向にあるが,安全性を一層高めるため,施設面では,自動信号化,ATSの設置・改良,CTC(列車集中制御装置)化,軌道強化,列車無線設備の整備等による交通環境の整備を,車両面では,コンピュータの利用等新しい技術を取り入れた検査方法の導入等による車両の安全性の確保を,運転面では乗務員等に対する教育訓練の充実,厳正な服務と適正な運行管理の徹底等による安全運行対策を推進している。
60年7月11日,国鉄能登線古君〜鵜川間において急行列車が脱線・横転し,旅客7名が死亡,29名が負傷するという事故が発生したが,運輸省は直ちに国鉄に対し,原因の究明と再発防止を図るよう指示した。これを受けて国鉄は,現在までの調査結果では,事故原因は断続的に降り続いた長雨により盛土にすべりが発生したものと判断し,能登線の当該箇所については,当分の間,徐行を行うとともに,全国の盛土構造物の総点検の実施,重点警備箇所の見直し,長雨時における運転規制の強化等を実施した。また,恒久対策として,学識経験者を含めた委員会を設置し,長雨に対する運転規制のあり方等について検討している。
また,踏切事故の防止については,第3次踏切事故防止総合対策に基づき,59年度においては,立体交差化による踏切道の除去91か所,構造改良699か所,保安設備の整備731か所を行った。国鉄に対しては,踏切保安設備の整備費の一部を補助しており,また,民鉄事業者には,これらの整備のために必要な資金を財政投融資により確保するとともに,経営の苦しい民鉄事業者に対しては,地方公共団体と協力して踏切保安設備の整備費の一部を補助している。
(3) 海上交通の安全対策
(旅客船の安全の確保)
多数の旅客や自動車を運送する旅客船の安全を確保するため,事業免許の際,事前に事業計画等について審査するとともに,旅客運送活動全般を通じ一貫した安全対策を講ずるため,旅客航路事業者に運航管理者の選任,運航管理規定の作成等を義務付けている。
また,地方運輸局に配置された運航監理官により,旅客船及び事業所の監査,運航管理者に対する研修等を行い,安全確保体制の確立に努めている。
(船舶の安全性の確保)
船舶の安全を確保するため,技術革新による輸送形態の多様化等に対応し,船舶検査体制の充実強化を図るとともに,型式承認,事業場認定等検査の合理化を推進し,併せて放射性物質,化学物質等危険物の海上輸送量の増大とその物性の多様化に対応した安全審査体制の整備強化に努めている。
また,船舶の救命設備基準の改正を主たる内容とする1974年の海上人命安全条約の第2次改正の発効を61年7月に控え,これを国内法化するための改正作業を行っている。
さらに,国際基準を満足しない欠陥船を排除し,我が国の国際的責務を果たすため,外国船の立入検査を本格的に実施し,監督を強化している。併せて,従来から実施している危険物を輸送する船舶を中心とした検査のほか,漁船についても,正規の手続きを経ずに改造している事例が多く,人命の安全に係ることからその立入検査を強力に実施した。
また,60年は漁船や遊漁船等の海難事故が多発したため,安全指導を強化するとともに,事故防止や遭難時の早期発見対策等の検討を行うこととしている。
(船舶の安全な運航の確保)
船員に着目した安全対策としては,航海の安全を確保するとともに船員災害の防止を図る観点から,船員法に基づき,船内作業基準の遵守等につき,船員労務官による監査及び指導を行うほか,船員災害防止活動の促進に関する法律に基づき,58年度に策定した第4次船員災害防止基本計画を実施するため,60年度においては,船舶所有者の自主的な安全衛生管理体制の機能強化等に重点を置き,種々の対策を実施している。
しかしながら,近年,船員災害の発生率の減少傾向が鈍化しており,特に,60年2月から5月にかけて第52惣宝丸,第71日東丸等の漁船の大規模海難が多発するなど,船員災害防止対策の一層の強化が望まれている。
また,我が国に入港する外国船舶に対し,「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」(STCW条約,59年4月発効)の定める航海当直及び船員の資格証明に対する基準の適合性についての監督を実施している。このうち,特に船員の資格証明に関する監督については,全国一斉に集中的な監督を実施する等によりその実効を期している。
その他,60年6月から新たに大阪湾全域(大阪湾水先区,阪神水先区及び内海水先区の一部)を総トン数1万トン以上の船舶を対象とした強制水先区とし,海上交通の安全の確保に努めている。
(港湾等の整備)
59年度は,第6次港湾整備五箇年計画の4年度目として,港内の船舶の安全を確保するため,事業費287億円をもって新潟港等34港において,防波堤,航路,泊地等の整備を行った。また,沿岸海域を航行する船舶の安全を確保するため,事業費106億円をもって関門航路等13の開発保全航路において開発又は保全の事業を行うとともに事業費70億円をもって輪島港等11港の避難港の整備を行った。
(海上交通の安全対策の推進)
海上保安庁では,海上交通の安全を確保するため,海上交通関係法令に基づく諸規制や各種の安全対策を講じている。
特に,船舶交通のふくそうする海域においては,安全確保に関する情報提供と航行管制を一元的に行う海上交通情報機構の整備を行ってきており,瀬戸内海について,現在,関門海域及び備讃海域において整備を推進している。
また,60年3月の瀬渡船開洋丸の転覆海難やプレジャーボートの海難の増加にかんがみ,この種の船舶の海難を防止するため,協議会等の設置促進等民間における自主的な海難防止活動の推進を図った。
さらに,浮標式の国際的統一に伴う灯浮標等の様式の変更工事を計画的に行っており,59年度は,四国南岸等で約260基の工事を実施した。また,海図等の水路図誌を整備するとともに,船舶交通の安全に係る情報を航行警報等により提供した。
(SAR条約の発効と海上捜索救助対策)
60年6月10日,我が国はSAR条約に加入した。同条約は6月22日に発効したが,この条約の規定に基づく救助調整本部を各管区海上保安本部に設置し,円滑な捜索救助活動を実施するとともに,隣接国と捜索救助業務に関する協力体制をより緊密なものとするため,この条約に基づく合意に達するよう実務担当機関間で協議を進めている。
また,本邦から1,200海里にも及ぶと予定されている広大な海域における国際的な捜索救助活動の責任を果たすため,航空機とヘリコプター搭載型巡視船を中心とする広域哨戒体制の計画的な整備を推進しており,その一環として,61年3月にはヘリコプター2機搭載型巡視船が就役することとなった。
さらに,遠距離海域における捜索救助活動は,海上保安庁の勢力による対応に加え,SAR条約でも要請されている船位通報制度を整備する必要がある。このため,海上保安庁は,日本の船位通報制度(ジャスレップ)を60年10月から運用開始した。この制度は,遭難船舶の位置の推定,捜索区域の迅速・的確な決定,救助船の早期選定等のために有効なものである。また,海難発生時の民間船舶相互の救助活動を促進するものであり,海上保安庁では,より多くの船舶がこの制度に参加するよう周知するとともに加入の促進を図っている。
(4) 航空交通の安全対策
(充実する航空保安システム)
航空機は,特定の電波を発射する無線施設(VOR/DME等)によって構成された航空路上を飛行している。これらの航空機を管制するために航空路監視レーダー(ARSR),空港周辺を飛行する航空機を管制するために空港監視レーダー(ASR),また,ASRから得られた情報を電子計算機で処理し管制官に必要な諸情報を提供するターミナルレーダー情報処理システム(ARTS)を整備してきている。一方,地方空港のジェット化に伴い,効率的運航とより安全な着陸を行うために計器着陸装置(ILS)及び進入灯(ALS)を整備してきている。
なお,59年度においては,豊田VOR/DME,奄美ARSR,新潟ASR,名古屋ARTS,女満別及び出雲にILSの整備を行った。
(日航機墜落事故に関する安全対策)
60年8月12日,東京発大阪行日本航空B-747型機が,伊豆半島東方上空で操縦不能に陥り,群馬県上野村の山中に墜落炎上し,死者520名を出すという大惨事となった。
事故原因については,目下,航空事故調査委員会において鋭意調査が進められているが,すでに8月19日,27日及び9月14日の3回にわたり,操縦室内音声記録装置(CVR)及び飛行記録装置(DFDR)の解読や,現地調査により判明した事実について経過報告がなされている。
運輸省としては,かかる事故の再発防止を図るため,8月15日及び17日には,関連航空会社に対し同型機の垂直尾翼及び胴体与圧室後部の構造の一斉点検を指示し,9月9日には,69機全機について点検を完了した。
また,8月22日及び23日には,日本航空の整備部門に対し緊急の立入検査を実施し,9月4日には,その結果を踏まえB-747型機の与圧室構造の総点検,社内体制の強化等安全運航確保のための業務改善について勧告を行った。これに対し,日本航空は今後抜本的な安全対策を実施する旨,10月1日に報告している。
航空行政において安全の確保が最も基本的な課題であることはいうまでもなく,運輸省としては,事故原因の究明を急ぐとともに,今後とも航空機の安全確保のため一層努力するよう関係者を強力に指導することとしている。
(航空機乗組員の健康管理に関する改善策の進展)
57年2月の羽田沖DC-8型機墜落事故のような航空機乗組員の心身の状況に起因する航空事故の再発を防止するため,(財)航空医学研究センターの設立(59年6月)等の一連の措置がとられたが,60年1月には航空機乗組員の身体検査基準について,航空機関士に適用される基準の格上げ等を主な内容とする改正が行われ,4月から施行された。
(超軽量動力機の事故対策)
航空スポーツの分野においては,通称モーターハンググライダー,ウルトラライトあるいはマイクロライト等と呼ばれる簡易な構造の動力付きの航空機(以下「超軽量動力機」という。)が普及しており,現在,その機数は700〜800機と推定されている。これらは航空法上の航空機に該当するものであり,飛行に際しては同法に基づく所要の手続きを必要としている。
超軽量動力機の事故は,58年に10件,59年に6件発生しているが,これらのほとんどが航空法上の手続きを経ない無許可の飛行であり,また,操縦者の経験不足あるいは技能未熟による事例が多い。そのため,所要の許可を取得するように一般への周知徹底を図るとともに,さらに,飛行を許可するに際しては,段階的に高度な飛行を行うものとし,一般の航空機,地上の第三者及びその他の物件に危害や損害を及ぼさないように,必要な条件を付する等事故防止に努めている。また,超軽量動力機の飛行の安全性を更に確立するため,その中長期的な対策の検討を進めている。
(航空大学校の充実)
近年の航空機の大型化,高速化,電子化に伴い,操縦士に要求される知識及び能力の内容がより高度なものとなってきたことなどを踏まえ,航空大学校の今後のあり方について検討を行っていた航空大学校検討懇談会から,入学資格(年齢)を短期大学卒以上及び25歳未満(現行,高等学校卒以上及び21歳未満)に引き上げること,高性能訓練機材の導入等の検討報告が60年6月に得られた。
|