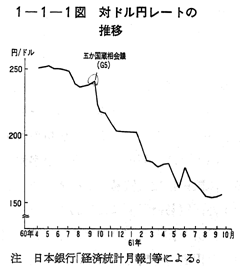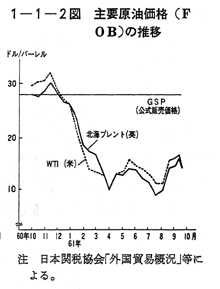|
1 円高・原油安等の我が国経済への影響
(急速な円高,原油価格の暴落等国際経済フレームの基本的な変化)
この1年の我が国をめぐる円高・ドル安,原油安等の国際経済環境の変化は,極めて急速なものであり,かつ,我が国経済に大きな影響を与えるものであった。それまで,第2次石油危機以降の世界経済フレームは,いずれも異常ともいうべき高水準のドル高,高い原油高金利に特徴づけられていた。こうしたことから,アメリカの経常収支の大幅な赤字,我が国の経常収支の大幅な黒字,発展途上国の累積債務の増大等の国際的不均衡が生じ,特に我が国にとっては,拡大を続ける貿易不均衡の是正が大きな課題となっていた。しかし,昭和60年以降,世界的なインフレの鎮静化を背景として,ドル高,高い原油,高金利はいずれも大幅な水準調整局面に入ることとなった。
まず,円の対ドルレートについては,アメリカ経済の拡大速度の鈍化,金利差の縮小等を背景に,60年2月をボトムとしてドル高・円安修正局面に入り,緩かな円高が進んでいたが,60年9月の先進五か国蔵相・中央銀行総裁会議(G5)においてドル高是正についての合意がなされて以降の協調介入をきっかけとしたドル高修正の進展は急速であり,G5直前に242円程度であった対ドルレートは,61年5月までに150円台にまで大幅に上昇し,10月末では160円前後となっている 〔1-1-1図〕。
また,高い原油の修正については,もともと世界的な原油のダブつきを背景に原油需給は緩和基調にあり,原油価格も弱含みに推移してきてはいたが,特に,60年12月のOPEC(石油輸出国機構)総会以降の原油の値下がりは極めて急激なものであった 〔1-1-2図〕。OPECが実質的に調整機能を失っていくなかで,60年11月には30ドルを超えていた原油スポット価格は,わずか4か月で10ドルに達し1/3まで低下した。60年10月現在10ドル台半ばで推移しており,市況回復の兆しも見せているが,先行きはまだ不透明な部分も多い。
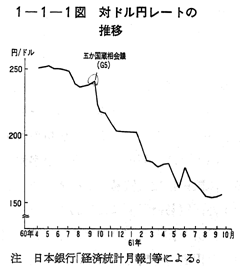
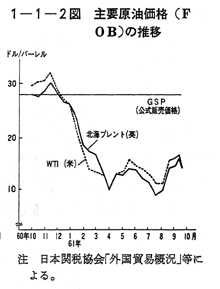
世界的な高金利についても,アメリカの金利低下,ドル高修正等から次第に是正に向かい,特に61年に入って,日本をはじめとして欧米主要国で相次いで,公定歩合,介入金利の引下げが行われた結果,各国の金利は1970年代後半の水準にまで低下している。
(経常収支の大幅黒字と対外経済摩擦)
こうした国際経済フレームの変化は,当然ながら我が国経済にも大きな影響を及ぼした。まず,我が国の経常収支についてみると,円高は,本来,我が国の経常収支の黒字を縮小させる効果を持つことが期待されるものであるが,60年度には,円高の急速な進展にもかかわらず,59年度を上回る550億ドルという大幅な黒字となり,特に貿易収支は,616億ドルの黒字と拡大を続けた。
61年度に入っても,貿易収支は依然として黒字の拡大傾向が続いているが,これは,いわゆる「Jカーブ効果」(円高により,数量調整に先立ってドルベースの輸出価格が速やかに上昇し,一時的に金額ベース収支の黒字が拡大する現象)や,原油をはじめとする一次産品価格の大幅低下の影響で輸入額が減少したことにより,金額ベース収支は黒字幅が拡大したものである。しかしながら,数量指数(貿易数量を金額でウェイト付けしたもの。日本関税協会「外国貿易概況」による。)でみると好調を続けてきた輸出は,アメリカ経済の拡大速度の鈍化に伴う世界貿易量の停滞と,60年9月以降の急激な円高の影響等により,60年度下期には弱含みとなり,60年度全体でも58,59年度の二けた増に比べ,3.2%増にとどまった。特に,61年に入ってからは円高による輸出抑制効果が顕著に出始め,3月以降8月まで連続して前年実績を下回った。
一方,輸入量を数量指数でみると,60年度は伸び悩み(1.1%増)であったが,製品輸入への円レートの影響は60年度下期において次第に大きくなり,61年初めより,製品類を中心に大幅に前年水準を上回って推移している。
このように,数量指数では輸出,輸入ともに円高の影響は現われているものの,経常収支の面では依然として大幅な黒字基調が続くなかで,アメリカを中心に対外経済摩擦はますます強まってきており,我が国は,外需依存型から内需主導型への転換,製品輸入の促進等国際的役割分担の変更を強く求められている。
(国内経済への影響)
円高・原油安が国内経済に与える主要な影響としては,①貿易数量の変化に伴うデフレ効果と,②交易条件の改善に伴う実質所得の増加が挙げられる。既に,輸入品価格の低下等の効果が出始め,物価は安定もしくは低下傾向にあり,個人消費が堅調に推移するなど円高・原油安のメリットも現れているが,他方,輸出の低迷等に伴うデフレ傾向も出てきており,特に,輸出関連企業や,これらの集中しているいわゆる輸出産地は大きな影響を受けている。
また,輸出関連企業は,ドル建て価格の引上げや,企業内の合理化等当面のコスト削減策のほか,販売先の国内市場への転換,内需関連産業への事業転換や,海外現地生産への移行,部品・材料の海外調達の増大等の長期的な対応を迫られている。
|