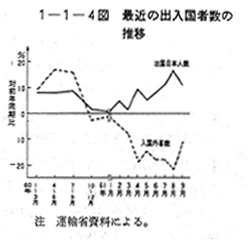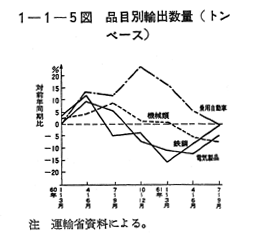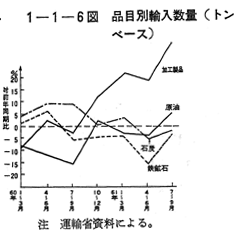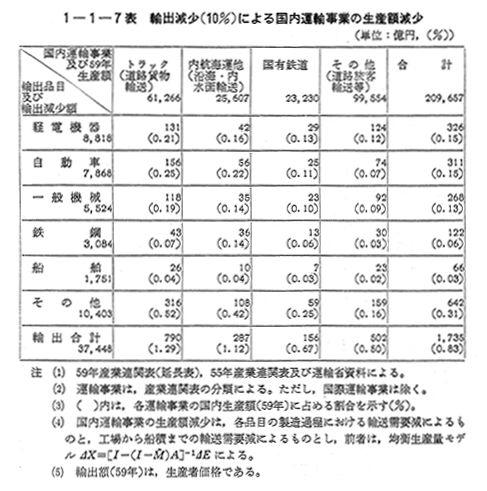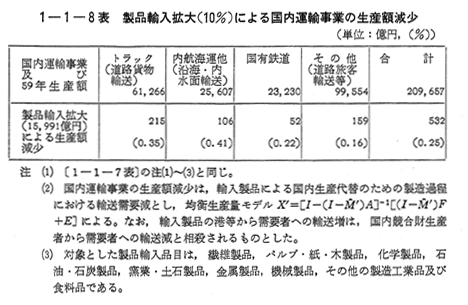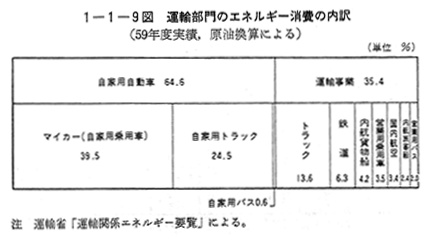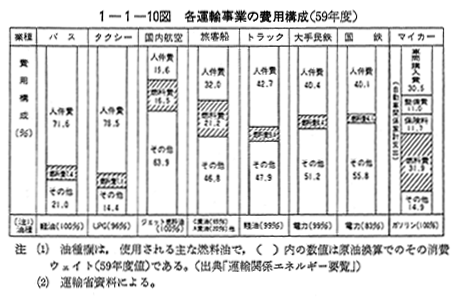|
2 運輸経済への影響
(1) 輸送需要に与える影響等
(国際貨物輸送は輸出面で低迷,製品輸入は増加)
国際貨物について, 〔1−1−3図〕で60年以降の動きをみると,まず輸出は,先にも述べたように金額ベース(ドルベース)ではJカーブ効果により増大傾向となっているが,数量ベース(運輸省において貿易数量をトンに換算したもの。)では円高に伴う輸出量の低迷傾向が明らかに出てきている。一方,輸入については,輸入で大宗を占める原油の価格が低下し,原油,鉄鉱石が量的にも減少傾向にあるため,製品輸入の増大にもかかわらず,金額ベース,数量ベースともに全体では円高の影響は顕著には現れていない。

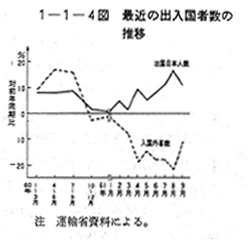
これを品目別にみると, 〔1−1−5図〕, 〔1−1−6図〕のとおりであり,輸出では,鉄鋼,電気製品等が大幅に減少している。輸入では,原油,鉄鉱石等の原材料が減少しているのに対し,機械,食料品等の加工製品が大幅に増加している。このような輸出墨の減少傾向,製品輸入の増加基調は,円高の効果が浸透するに従い,ますますその傾向を強めるものと考えられる。
また,我が国の海上輸送は,従来から産業構造の変化の影響を受けてきているが,海外生産における賃金コストの有利性や,貿易摩擦への対応等を要因として増加傾向にあった工場の海外進出が,最近の急速な円高の進行により一層活発化することが予想され,これにより,我が国の海上輸送の内容もかなり大きく変わることが予想される。すなわち,生産拠点が海外に進出することに伴って,素材,資源の我が国への輸入量と我が国からの製品の輸出量は減少し,部品,半製品の我が国から現地生産工場への荷動き,製品等の我が国への荷動きという新たな輸送需要が発生することが予想されるとともに,最近著しい伸びを示している三国間の海上貨物輸送も,ますます増加の傾向を強めていくこととなろう。
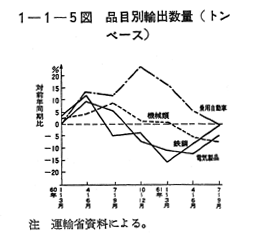
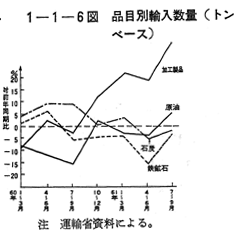
(出国日本人数は増加,入国外客数は減少)
国際旅客の動向についてみると, 〔1−1−4図〕にみるとおり,出国日本人数については,日航機事故の影響等もあり60年10月以降伸び率が鈍化したが,61年度に入ってからは,円高の影響もあって出国日本人数の増加が顕著となった。入国外客数は,61年に入って以降,円高の影響に加え,60年3月より筑波で開催された国際科学技術博覧会への来客増の反動もあり,減少が顕著に現れている。
(国内輸送にはマイナス要因)
次に,国内貨物輸送に与える影響についてみると,全体として,まださほど顕著ではないものの,輸出の減少等に伴う需要の減少傾向が出始めている。
運輸省が61年10月に,各地方運輸局を通じ,各種運輸事業を対象に全国的に行った調査によると,特に,いわゆる輸出産地といわれる地域を中心に,トラック,内航海運,港湾運送,倉庫等の国内物流部門において,円高に伴う波及効果により輸出関連貨物を中心として需要の減少が現れているとするものが多い。また,61年8月に,運輸省が別途行った各種運輸事業者へのアンケート調査(全97社)によっても,内航海運,トラック等の貨物運送関連事業者のうち約69%が,この円高傾向が続けば,今後ますます輸送需要の減少傾向が強まるとみている。
以上のほかに,円高が国内貨物輸送に与える影響としては,前に述べた工場の海外進出に伴い国内における生産が減少した場合のマイナス要因や,さらに,製品輸入の拡大による国内製品の輸入品への一部代替に伴うマイナス要因も考えられよう。
なお,輸出の減少及び輸入の増加による国内輸送需要への影響について試算してみると,次のとおりである。
ア 輸出の減少による国内運輸事業への影響輸出の減少による国内運輸事業への影響をみるために,仮に59年の輸出が各品目一律に10%減り,この分だけ国内生産が減少し,これに伴う直接,間接の国内輸送需要が減少するとして産業連関表により試算すると,国内運輸事業全体の生産額は約1,700億円減少することとなる。このうち,主要輸出品目について輸出額が10%減ったとして同様の試算を行うと,軽電機器の輸出減に対しては国内運輸事業全体で326億円の生産額が減少することとなり,このほか,自動車で311億円,一般機械で268億円鉄鋼で122億円の国内運輸事業への影響が考えられる 〔1−1−7表〕。したがって,運輸事業のなかでも輸出型産業に大きく依存する企業にあっては,かなりの影響を受けるものもでてこよう。
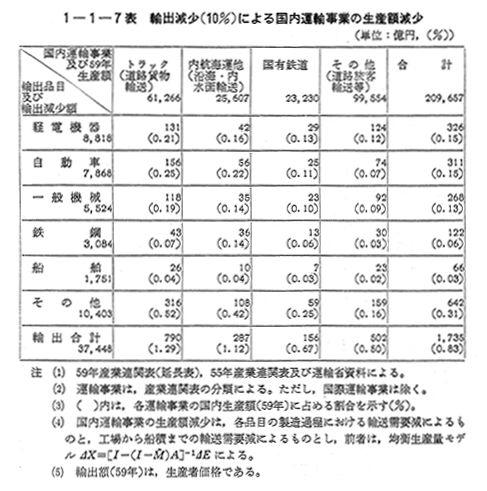
イ 製品輸入拡大が国内運輸事業へ与える影響次に,製品輸入の拡大が国産製品需要の減少に結びついたと想定したときの国内運輸事業へのデメリットをみるために,我が国の59年の製造工業品及び食料品の輸入が一律に10%増加し,国内競合財の生産を代替したと仮定した場合について産業連関表により試算すると,各品目の製造段階の輸送需要減を通じて,国内運輸事業全体の生産額が約530億円減少することとなる 〔1−1−8表〕。
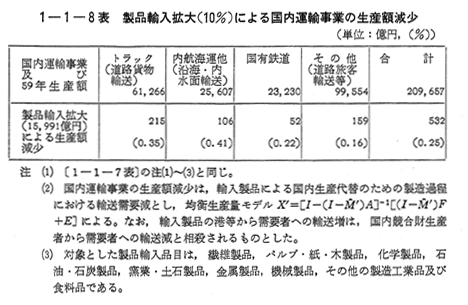
(2) 事業経営面に与える影響
(国際運輸ではデメリットが大きい)
国際的な事業活動をしている外航海運,造船等の国際運輸について円高・原油安が事業経営面に与える影響についてみると,原油安によるコストダウン効果はあるものの,他方で,円高によるデメリットも大きなものとなっている。
外航海運については,円高による燃料油,外国用船料等のコストダウン効果も大きいが,一方で,収入面でのドル建て比率が支出面でのそれをかなり上回っているため,円高による相当の為替差損が発生している。また,燃料油価格の下落が運賃収入の低下に連動する仕組みがあるため,原油安の収支改善効果はわずかなものと見込まれる。外航海運は,現在,米国の1984年海運法の影響で,北米コンテナ航路を中心に定期船運賃は下落し,また,不定期船,タンカーも厳しい状況が続いているが,これに円高の影響等による需要減が加わり,さらに東南アジアや米国の船社との競争も激化する一方で,当面の経営環境は依然厳しいものとなっている。
造船については,ドル建て契約による為替差損,円高による新規受注の減少,受注船価の低落等の悪影響が生じ,それでなくとも冷え切った造船需要のなかで,不況に更に追い打ちがかかるといった厳しい状況となっている。
61年8月時点での運輸省調査による見通しでは,1ドル=160円ベースで試算すると,61年度における為替差損は,外航海運において海運助成対象企業40社で約790億円,造船業では270億円の見込みとなっている。国際航空については,燃料費軽減のメリットはあるが,収人面支出面でのドル建て比率がほぼ均衡しているため,円高の影響はほとんど受けない見込みである。
このように,外航海運,造船については,特に円高によるデメリットが大きく,これら業種に対しては従来からの構造的不況対策に加え,円高による追討ちに対する救済,援助対策が必要となっている。
(国内運輸にはプラス効果も)
先にも述べたように,円高・原油安は,一般的には,貿易数量の変化に伴うデフレ効果がある反面,交易条件の改善に伴う原材料コストの低下により,多くの国内産業にとってはコスト削減のメリットを生むことになる。
周知のように,運輸は国内における石油の一大消費部門であり,石油製品の最終需要のうち,運輸部門は59年度で34%のシェアを占めてい為この石油製品消費の内訳は, 〔1−1−9図〕にみるように,マイカー等自家用自動車によるものが多く,これが約65%を占めている。その他のいわゆる運輸事業によるものは約35%で,トラック13.6%,鉄道6、3%,内航貨物船4.2%,ハイヤー・タクシー3.5%,国内航空3.4%等となっている。
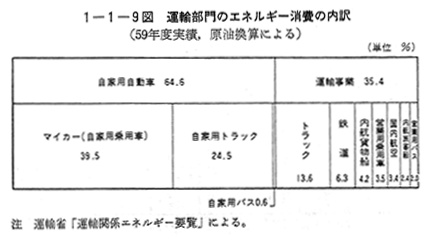
(運輸における円高・原油安のコストメリット)
そこで,自家用車も含めて,これら運輸における円高・原油安のコストメリットについて見てみる。
〔1−1−10図〕は,各運輸事業の費用構成である。石油製品の値下がりは,このうち燃料費部分にメリットを与えるものであるが,この燃料費の総費用に占めるウェイトは,各事業によってかなり異なっている。
運輸事業は労働集約的な産業であり,一般に人件費のウェイトが高いが,例えばバス,タクシーではこれが7割を超えており,燃料費のウェイトは7%台と低い。国内航空の燃料費は165%,旅客船においては21.2%と比較的高くなっている。トラックについては,9.4%,大手民鉄,国鉄は,それぞれ8.4%,4.1%となっている。また,マイカーについては,経済主体が家計であることから,総費用に当たるものとして自動車関係家計支出を使用すると,燃料費は,このうち31.9%を占めている。
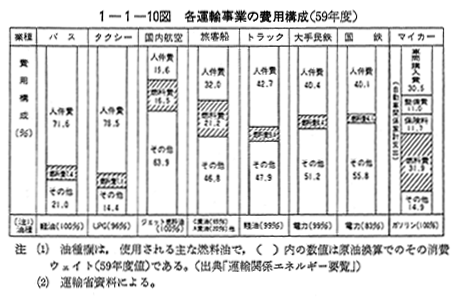
各事業等によってその使用油種は異なるが,その油種毎の製品価格の値下がりが,この燃料費部分を引き下げてコストメリットを生じさせることになる。
しかし,運輸事業においては,人件費をはじめその他の諸経費の増加,円高の影響による輸出減等に伴う需要の減少等のマイナス要因や各事業のおかれた経営環境等個別の事情もあり,コストメリットのみでなく,それぞれの個別の経営状況も考慮しなくてはならない点に留意する必要がある。
なお,金利については,公定歩合の引下げに伴い順次低下の傾向にあるが,長期資金については一般に固定金利が多いため現在のところあまり大きな影響は出ていない。しかしながら,この金利安の傾向が継続すれば,短期資金についての金利負担が軽減されるとともに,中・長期的には,鉄道,海運,航空等特に資金需要の多い業種を中心に,長期資金の金利負担の軽減と,新規投資意欲の拡大といった好影響が期待される。
|