|
3 運輸における円高・原油安等への対応
(内需拡大,円高対策等対応急ぐ政府)
先にみたように,特に外航海運業及び造船業においては,従前からの構造的不況が今回の円高等により,さらに深刻化する事態となっていることから,運輸省としても,次のような不況対策を講じてきている。
ア 海運不況対策
また,61年6月には「特定外航船舶解撤促進臨時措置法」が公布・施行され,現在,これに基づく老朽・不経済船の解撤促進により過剰船腹の解消を進めている。これは,解撤促進基本指針に従って行われる船舶の解撤について,産業基盤信用基金による債務保証により,解撤に必要な資金の調達を容易化しょうとするものであり,基本指針においては,64年央までの解撤目標量を520万総トンとしている。 さらに,船舶整備公団の近海貨物船に係る船舶使用料等について,61年6月から1年の間に生ずる支払負担の軽減措置を講じている。
イ 造船不況対策
また,海運造船合理化審議会より構造不況に抜本的な対応をするための方策が61年6月に示されており,この中では,過剰設備の削減,企業の集約化等による産業体制の整備,事業転換の促進等の対策が指摘されている。
ア 国際航空運賃の方向別格差の是正
イ 国内航空運賃の割引の拡充
ウ 海外パック旅行料金の引下げ
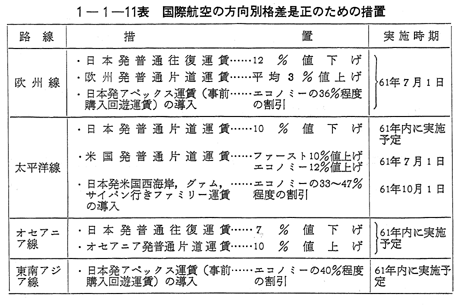
海外パックの旅行料金については,宿泊料等の地上費用に対する円高の効果があるため,61年10月から対北米,欧州等を中心に引下げが行われた。例えば米国向けの場合,対前年比で数パーセントから10数パーセントの引下げとなっている。
工 その他の公共料金等について
用中相当な部分を占める人件費等のコストの増大が今後とも見込まれること,②運輸事業は,構造的不況業種が多く,また需要の低迷傾向が進んでいるなど全般的に厳しい経営状況にあること,により,一般的には難しい状況にあると思われる。 このため,61年4月の総合経済対策及び9月の総合経済対策に従い,車両,船舶の代替更新を促進するなど利用者利便の向上のためのサービス改善を行うとともに,可能な限り現行運賃水準を維持することにより,差益を還元するよう指導している。また,やむを得ず運賃改定が必要な事業者については,今後とも引き続き燃料費の下落による適正な原価を織り込むこととし,極力改定幅を圧縮することにより差益を還元するよう指導している。
ア 公共投資等の拡大
61年4月の総合経済対策に基づき,61年度上半期における公共事業等の前倒し施行が決定され,政府全体で61年度施行予定額の77.4%の上半期施行をめざすこととなった。運輸省関係では,61年度の公共事業等(空港,港湾等の公共事業等並びに国鉄,日本鉄道建設公団及び新東京国際空港公団の公共投資関係事業をいう。)の額約1兆5,077億円のうち71%に当たる約1兆702億円を上半期に前倒し施行することとした。これは,過去最高の前倒し率である57年度の69%を上回る割合である。 また,これに伴い61年度下半期における事業量の確保が必要となり,61年9月の総合経済対策において,公共投資等の追加により総額3兆円の事業規模を確保することとされた。運輸省関係では,空港,港湾及び海岸の各公共事業費の追加,日本鉄道建設公団の事業費の追加等を行うこととしている。
イ 民間活力の活用の促進
公共的事業分野における民間活力の活用等に資するため,関西国際空港については,関西国際空港(株)が61年度において空港島護岸,空港連絡橋の建設等を行うこととしている(61年度事業費として750億円を予定)。 また,61年5月の「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」(民活法)の成立を踏まえ,運輸関係民活プロジェクト(対象施設:国際見本市場,国際会議場,旅客ターミナル,港湾業務用施設)の推進を図ることとしており,61~62年度において東京竹芝地区再開発等4プロジェクトが差手される予定である。 さらに,61年9月の総合経済対策において,民活法の対象施設整備事業の前倒しを促進するため,61年度又は62年度に着工される事業に対する建設費の助成及び日本開発銀行,北海道東北開発公庫からの貸出金利の引下げ並びに62年度税制改正における民活特償制度の償却率の引上げが決定されている。
|