|
2 交通公害対策
(1) 自動車公害対策
(NOx問題への対応)
公害対策基本法に基づく二酸化窒素の環境基準は,60年7月にその達成期限が到来したが,東京をはじめとする大都市地域においては自動車交通量の多い幹線道路の周辺地域においてこれが達成される見通しが得られていない。このような自動車公害問題については,関係省庁が協力して各種施策を講じていくことが求められている。
運輸省としては,これまで排出ガスの規制基準の強化等の対策を講じてきているが,今後は,①61年7月の中央公害対策審議会答申を踏まえたトラック等への新たな規制基準の強化,最新の規制基準に適合した車への代替促進,低公害車としてのメタノール自動車の導入・普及等のいわゆる発生源における対策や,②自家用から営業用へのトラック輸送の転換,共同輸送等の物流合理化施策の推進等,交通総量の削減対策等の環境改善のための諸施策について積極的に検討を進めていくこととしている。
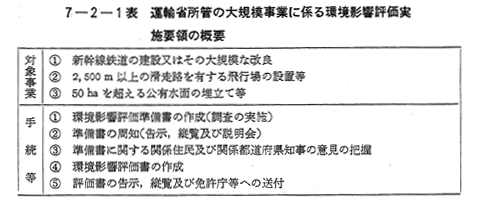
(メタノール自動車導入のための施策の推進)
メタノール自動車は,現在営業用トラック,バスの大半を占めているディーゼル車に比べ,NOx及び黒煙の排出量が少なく低公害性に優れている。このため,自動車の燃料の多角化の観点と併せ,自動車公害対策の面からその導入が有効とされ,61年度からメタノール自動車の自動車税及び自動車取得税の軽減措置が講じられることとなったところである。また,運輸省においては,61年7月から運送事業者及び日本メタノール自動車(株)等の協力を得て営業用車両による市内走行試験(フリートテスト)を東京地区において開始する等都市内のトラック,バス部門への導入のための具体的施策を推進している。
(規制の進む発生源対策)
自動車公害に係る発生源対策としては,自動車の構造及び装置の面から排出ガス及び騒音に係る規制を順次強化してきている。
しかしながら,排出ガス特にNOxについては,自動車台数の増大,交通量の増加等により,大都市等自動車交通量の多い地域において一層の排出量低減が必要となっている。このため,運輸省としては,61年7月の中央公書対策審議会答申を踏まえ,NOxに関し,大型ディーゼルトラックの15%削減,ライトバン等軽量トラックの乗用車並みへの低減等の規制強化を行うこととしている。
騒音については,新車に対しては,61年から大型車(全輪駆動車等)及び第二種原動機付自転車,62年から二輪の小型自動車についてそれぞれ規制を強化することとしている。また,使用過程車に対しては,暴走族等によるマフラー等を不正に改造した車両を排除するために,61年6月から二輪車に対して簡易測定方法である「近接排気騒音測定方法」を導入するとともに規制値を強化し,実効性のある使用過程車の騒音規制を行っている。
(スパイクタイヤによる粉じん問題への取組み)
近年,積雪寒冷地域におけるスパイクタイヤの使用による道路粉じん増加等が問題化している。
運輸省では,公害の防止と安全確保の観点からスパイクタイヤの構造のあり方について検討すべく,58年度から3か年計画により「スパイクタイヤ等対策技術調査」を進めてきた。また,59年度から3か年計画で「スパイクタイヤの性能等の評価法に関する研究」を実施しており,これらの調査結果を踏まえ,構造基準の検討を行うこととしている。
さらには,自動車の使用者に対して不要期における普通タイヤへの取替えの促進等について指導を行っている。
(2) 新幹線鉄道公害対策
(新幹線鉄道騒音,振動対策の推進)
新幹線鉄道の騒音,振動対策に関し運輸省は,「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」(50年7月環境庁告示),「新幹線鉄道騒音対策要綱」(51年3月閣議了解)等に基づき,具体的な対策の実施等につき日本国有鉄道及び日本鉄道建設公団を指導してきている。
東海道,山陽新幹線について,60年7月に騒音に係る環境基準の達成目標期間が経過したことに伴い,61年5月に新たな施策を策定し,レール削正の深度化,新型防音壁の設置,ハンガー間隔縮小架線の採用等各種の対策を組み合わせた総合的な音源対策を住宅密集地域が連続する地域について,5年間を目途に行うこととしている。なお,騒音レベルが75ホンを超える区域における住宅について従来から実施している防音工事の助成等については,申し出のあったもの全てに対策を講じており,残部についても申し出があるものは早期に完了するよう努めることとしている。
東北,上越新幹線については,環境に十分配慮して建設されたが,開業後も引き続きレールの削正等の音源対策を実施するとともに,58年度から家屋等の防音工事の助成を行っており,61年8月末現在,防音工事の進捗率は,東北新幹線で75%,上越新幹線で99%となっている。
新幹線鉄道振動については,家屋の防振工事の助成及び移転補償の対策を申し出のあったものについては全て講じており,今後も申し出があれば対策を講ずることとしている。
(解決をみた名古屋新幹線鉄道公害訴訟)
49年3月に名古屋地区で提起されていた新幹線鉄道に係る騒音,振動の差止め及び損害賠償を求める訴訟は,60年4月に名古屋高等裁判所の判決があったが,当事者である国鉄,名古屋住民双方ともそれぞれこれを不服として同月最高裁判所に上告した。一方,法廷外での話し合いを続けてきた結果,①国鉄は,64年度末までに名古屋の7km区間において発生源対策により75ホン以下とするよう最大限の努力をする,②国鉄は,和解金4億8,000万円を支払う,③名古屋住民は,本件訴訟を取り下げる,等を内容とする話し合いによる和解が61年4月に成立し,12年にわたる訴訟は円満解決をみた。
(3) 航空機騒音対策
(新たな展開をみせる航空機騒音対策)
航空機騒音に係る環境基準の達成に向けて,「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」等に基づき,低騒音型機材(B-767等〉の導入等の発生源対策及び住宅防音工事,移転補償等の周辺対策を二つの大きな柱として,航空機騒音対策を進めてきているが,これらの対策のうち住宅防音工事は60年度にほぼ完了し,環境基準の改善目標に定める屋内環境が保持されることとなった。
一方,移転補償跡地が蚕食状に散在し,街づくりの上で問題が生じているため,次のような対策を講じて空港と周辺地域との調和ある発展を図っている。
① 大阪国際空港については,大阪府の提案に基づき,運輸省,大阪府が共同して空港周辺地域において都市計画手法を活用した大規模な緑地の整備を行うこととしている。
また,発生源対策の進展に伴い周辺地域の低騒音化が進んだことを踏まえ,移転補償跡地を周辺地域整備に有効に活用するため,同空港周辺の騒音区域のうち第二種及び第三種区域を縮小することとし,関係地方公共団体等との調整を進めている。
② 函館,仙台,大阪国際及び福岡空港に加え,61年度から新たに松山,高知及び宮崎空港において,移転補償跡地の増大に伴い緩衝緑地帯整備事業を開始した。
このほか,地方公共団体が移転補償跡地の一時使用許可を受けて公園等を整備する周辺環境基盤施設整備事業を大阪国際及び福岡空港において行っている。
③ 大阪国際,福岡の両空港においては,空港周辺整備機構が61年度から新しい再開発事業として移転補償跡地の使用許可を受けて荷さばき場等の騒音斉合施設を設置する事業を開始した。
(空港騒音調停等)
大阪国際空港騒音調停のうち残る損害賠償請求については,現在公害等調整委員会において調停手続が進められている。
また,福岡空港については,周辺住民から夜間の飛行差止め等を求める訴訟が提起されており,福岡地方裁判所で審理中である。
|