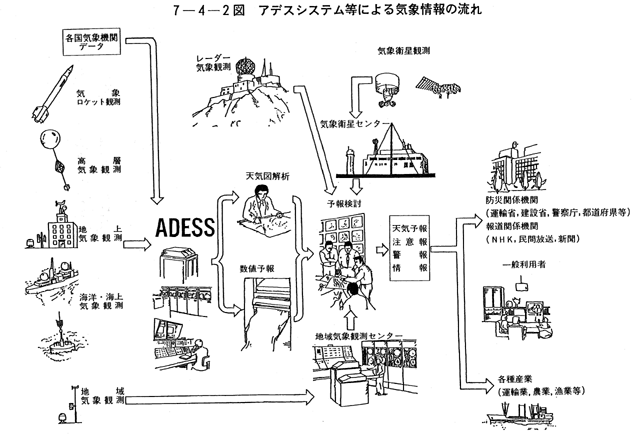|
2 気象業務と気象情報提供体制の整備
気象庁では,台風や集中豪雨雪等の災害防止対策上の観点からはもちろんのこと,国民生活の利便や運輸・観光業,農業,漁業,電力その他の産業の利用に供するため,気象予報,注意報・警報,海水象予報,レーダーアメダス雨量合成図等実況情報などの各種気象情報を提供している。さらに,これらの気象情報について,地域の利用者の要望に応え,きめ細かい情報の提供を可能にするなど,その内容の充実を図るとともに,無線放送,テレビ,ラジオ等から刊行物に至る種々の形態・手段を用いて,気象情報を迅速に提供できる体制の確保に努めている。
(1) 気象庁の気象情報提供体制
気象情報は,全世界的な広範囲に分布する情報であり,この情報を即時的に集めることができなければ,情報の利用価値は半減する。
(気象データ処理の整備と利用の促進)
気象庁では,世界各国の協力を得て,ワシントン,モスクワ,北京など世界主要地域を結ぶ世界(全球)気象通信回線(GTS:GlobalTelecommunication System)(以下「GTS気象通信回線」という。)を通じて,これら気象情報を迅速に収集できる体制を整備している。
国内的には,全国6つの地方中枢(札幌,仙台,東京,大阪,福岡,沖縄)を専用通信回線で結んだ気象資料自動編集中継システム(ADESS:Automated Data Editing and Switching System)(以下「アデスシステム」という。)を整備し,迅速な気象資料の収集,編集,解析,配信を行っている 〔7−4−2図〕。
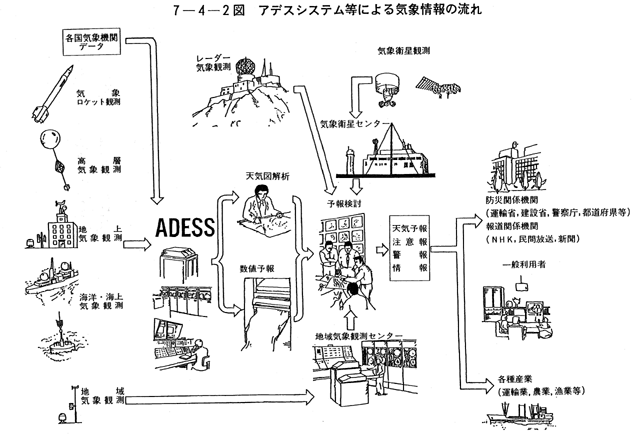
アデスシステムでは,世界及び全国各地の気象官署の地上・海上・高層気象観測データや全国約1,300か所のアメダスデータ等をリアルタイムに収集し,これらデータを気象解析等利用自的に合わせて編7-4-2図 アデスシステム等による気象情報の流れ集して専用回線網で配信し,国内の気象業務の遂行に役立てている。また,外国に対してもGTS気象通信回線を介して観測データ等を配信することにより,気象業務の国際協力に貢献している。
さらに,気象資料の十分な活用を図るためには,それら資料の管理,保存,提供体制を確立することが必要である。このため,気象庁では,GTS気象通信回線を通じて入電する世界各地の気象情報を蓄積するとともに,これまで蓄積してきた国内気象資料をより簡易かつ安価に利用できる体制の整備を検討している。
(2) 気候変動への対応
前述したように,近年,熱波,干ばつ,異常低温などの気候変動が,経済社会に大きな影響を与えるようになり,こうした影響を軽減するための対策が求められている。このため,気候の予測や過去の類似事例の分析・調査の必要性が高まっている。
気象庁では,世界全体の過去30年間の値を平均した月平均気温や月降水量などの気候情報を整備し,作付け時期の選択などに利用できるようにしている。また,長期予報の精度向上,気候の予測技術の開発を図るなど気候の解明に努めている。
(気候変動の人為的要因)
気候変動の原因は,まだ十分には解明されていないが,火山爆発,海況変動等の自然要因に加え,人間活動の拡大から人為的な要因が増大している。
例えば,二酸化炭素濃度の増大による温暖化(温室効果)や森林破壊等による砂漠化の問題があり,二酸化炭素以外の温室効果に寄与する気体として,一酸化二窒素,メタン,オゾン等も考慮する必要がある。
気象庁では,昭和61年度から岩手県三陸町において,東アジア地域
における唯一の定常的な大気中の二酸化炭素観測を開始することとしている。
(気候変動対策)
気候変動対策において,研究・調査の果たす役割は大きい。気象庁では,世界気象機関が人間の社会・経済活動に及ぼす気候の影響を明らかにする目的で計画した世界気候研究計画の一環として,気候予測の実現をめざした数値気候モデルの開発等の研究を推進している。また,57年度から異常天候と地域産業の関連に関する調査を進め,気候変動に際しての社会的対応の具体案を策定する等資料の蓄積に努めている。
|