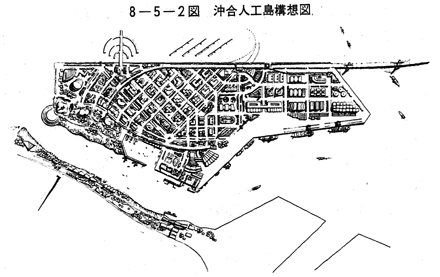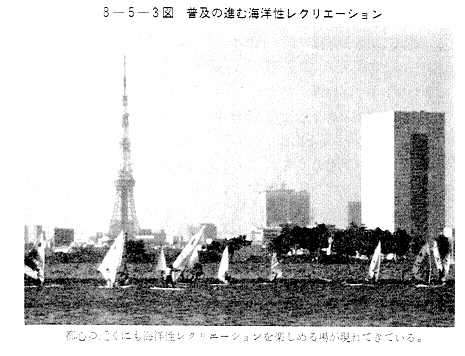|
3 海洋の開発・利用の推進
(1) 海洋調査及び海洋情報の収集・提供の充実・強化
海洋の開発・利用を進める上で,海洋に関する各種の情報は必要不可欠であり,海洋の開発・利用の進展に伴い,海洋情報に対する需要は増大しつつあるのみならず,多様化,高度化してきている。
運輸省は,人工衛星,調査船,沿岸観測施設等による広範な海洋調査の実施等により,波浪,海流,水温,海底地形等各種の海洋情報を収集し,必要に応じて適切な処理を行ったうえリアルタイム(即時)あるいはノンリアルタイム(非即時)で利用者へ提供しており,広域かっ総合的な海洋調査及び海洋情報の収集・管理・提供を恒常的に行う我が国唯一の機関として,海洋の開発・利用の推進に大きな役割を果たしてきている。
また,運輸省では,これらの海洋情報をファクシミリ等により船舶等へ提供するほか,総合的な海洋データバンクである日本海洋データセンターを通じて提供しており,今後,海洋情報の高度化を図るため,これらの業務のより一層の充実・強化を進めていくこととしている。
このほか,海洋情報の収集・提供の充実・強化のため,全世界海洋情報サービスシステム(IGOSS)計画,西太平洋海域共同調査(WESTPAC)等の国際的な活動にも積極的に参加するとともに,危険海域を調査する自航式ブイの開発,人工衛星を利用した海流等の調査技術の研究,広域の水温等の変動をモニターする音波断層観測システムの開発等を行っている。
(2) 海洋の開発・利用のための諸施策の推進
(海域の特性に応じた施策の推進)
海洋空間の中でも,沿岸海域は国民生活と密接に結びついた空間として開発・利用が進められてきているが,その中でも港湾や内湾・内海の一部とこれら以外の沿岸海域では,波浪等の自然条件や海域利用の形態が大きく異なっている。このため,今後海洋空間の有効利用を進めるに当たっては,それぞれの海域の特性に応じた施策の推進が必要である。
三大湾等の利用が稠密な海域においては,旺盛かつ高質な海域利用1へのニーズに対応し適正な利用及び保全を図っていく必要があり,運輸省では沖合人工島等の整備,廃棄物の広域的処理(フェニックス計画),広域的な海洋環境改善(シーブルー計画)等を含め,一層,計画的利用を推進していくこととしている。
一方,外海に面する沿岸海域は,波浪等の厳しい自然条件等が原因となって,そのポテンシャルが十分に発揮されていない。このため,これらの海域においては,海域のポテンシャルを生かし,海域の開発・利用を促進していく必要があり,そのための先導的プロジェクトの推進が必要である。このため運輸省では,沖合人工島構想や静穏海域整備構想を推進していくこととしている。
(沖合人工島構想の実現化)
運輸省で従来から検討を進めてきている沖合人工島構想 〔8−5−2図〕については,これまでの成果等をもとに,地方公共団体等による沖合人工島計画策定のガイドラインとなる計画指針を作成し,この指針をもとに,現在,東京湾,清水,玉野・倉敷,下関等でフィージビリティスタディを行っており,船舶航行の安全対策等にも十分配慮しつつ構想の実現化を図っているところである。
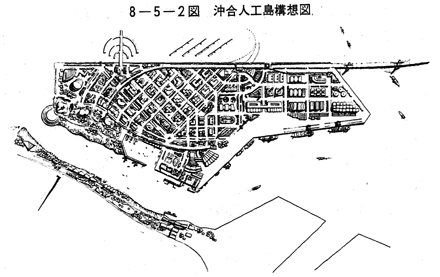
(海洋の開発.利用を支援する技術の開発)
海洋の開発・利用の推進のためには,波浪等の厳しい自然条件を克服するための技術開発が必要であり,運輸省では,港湾整備等で培われた海洋土木技術及び世界をリードしてきた造船技術等を結集することによりこれらの技術開発に取り組んでおり・海洋空間の有効利用を図るため,マルチセルラー式防波堤,軟弱地盤着底式防波堤,ハイブリッド海洋構造物等の開発を進めている。
(3) 海洋性レクリエーションの振興
(普及・発展の進む海洋性レクリエーション)
生活水準の向上,余暇時間の増加等を背景として,国民の余暇活動は活発化・多様化してきているが,海洋性レクリエーションについても,従来の海水浴,釣り等に加え,ヨット,モーターボート,ボードセーリング,ダイビング等多様化が進むとともに急速な普及・発展を遂げてきている 〔8−5−3図〕。今後も,海洋性レクリエーションに対する国民のニーズはますます高くなると考えられることから,これを海洋の利用の一分野として位置づけ,その健全な発展を図っていく必要がある。
(海洋性レクリエーション振興のための施策の推進)
運輸省では従来から,公共マリーナ,人工海浜,観光レクリエーション地区等の整備による海洋性レクリエーションの環境づくり,船舶検査,海技資格免許,海難防止活動等による安全の確保,海難救助,海象・気象等の情報提供など海洋性レクリエーションに関する業務を多面的に展開している。今後,海洋性レクリエーションの普及・発展に対応するとともに,その健全な発展・振興を図るためには,民間活力も活用した施設整備等の環境づくり,関係者による自主的な安全活動の推進等の安全対策などハード・ソフト両面のバランスのとれた総合的な施策の推進が必要である。
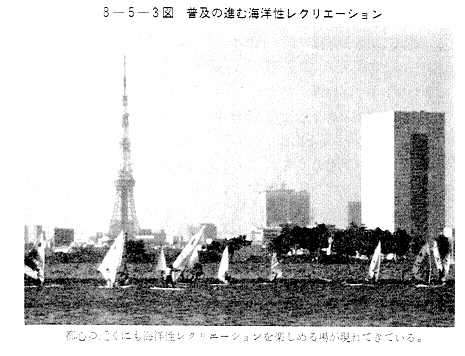
(4) 海洋・海事思想の普及
運輸省は,従来より「海の記念日」(7月20日)や「海の旬間」(7月20〜3旧)等における全国各地での行事の開催,あるいは海洋性レクリエーションの振興等を通じて海洋・海事思想の普及を進めているが,さらに,海への理解と関心をより一層深め,7月20日を「海の日」として広く国民的に定著させるため,61年度より主要港湾都市持ち回りで「海の祭典」を実施することとした。61年度の第1回は,7月19日から22日まで,北九州市において礼宮殿下をお迎えして開催され,多彩で地方色豊かな各種イベントが繰り広げられた。62年度は,神戸市で開催することが予定されており,全国的な盛り上がりを図っていくこととしている。
|