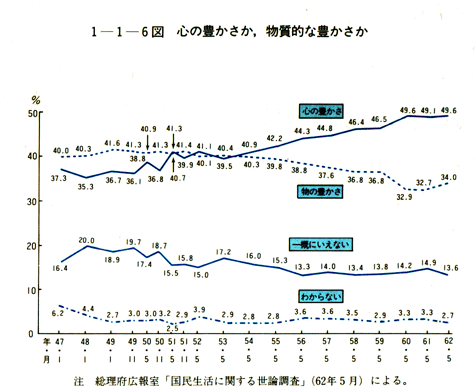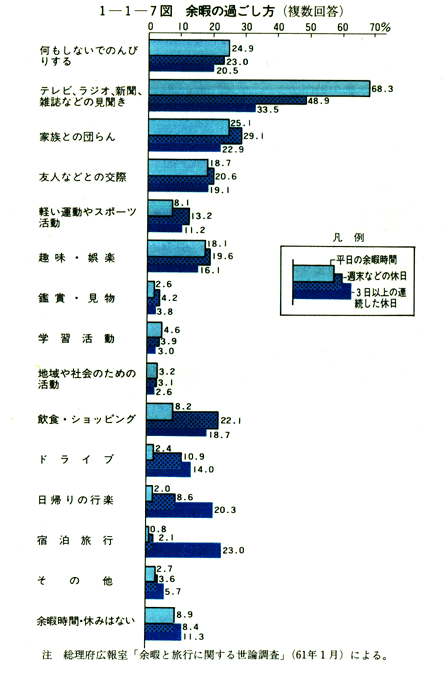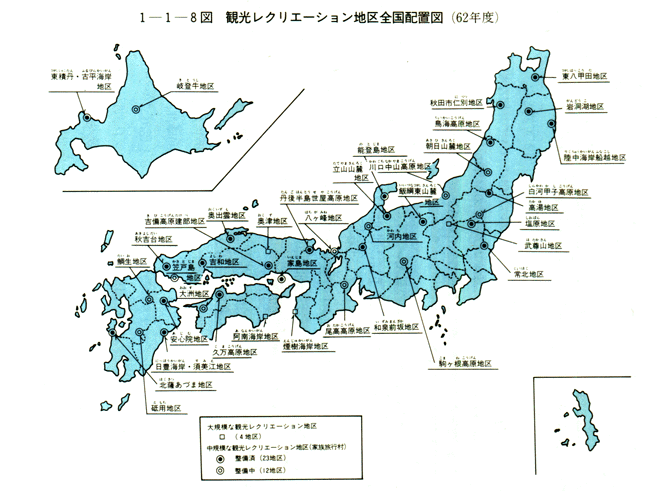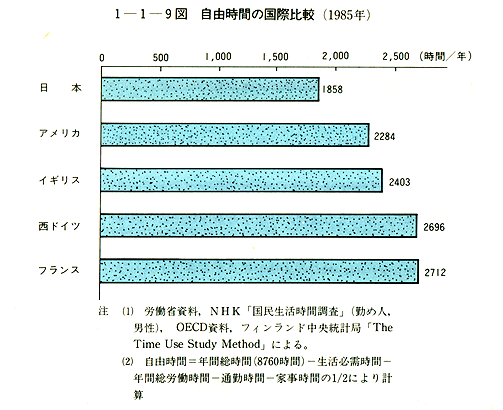|
4 余暇活動の充実
(1) 余暇活動の多様化と今後の課題
ア 余暇活動の意義
近年,国民の価値観は多様化している。総理府の世論調査(62年5月)によると,「物質的な豊かさ」より「心の豊かさ」に生活の力点をおく国民がはるかに多くなってきており 〔1-1-6図〕,余暇活動に対する認識も,仕事を離れた「休養」,「骨休め」として捉える消極的なものから,各自の自的に応じ,自己の可能性を試し,新しい自分を発見する場として多種多様な活動を行うなどの積極的な意義を有するものになってきている。余暇活動はまさに人間がその本来の人間性を取り戻すための価値ある活動であるといえよう。
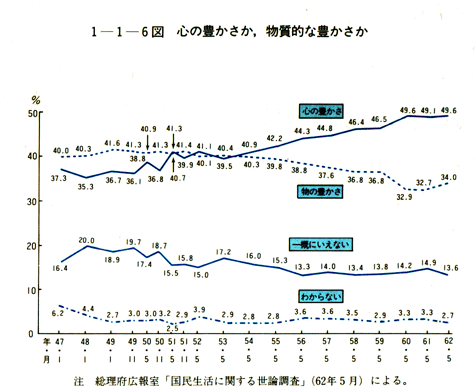
イ 余暇活動の動向
国民の余暇時間は,週休2日制や長期連続休暇の普及,高齢化社会の到来,主婦の家事時間の減少などにより拡大している。これら余暇時間の拡大は,国民の所得水準の向上と相まって,国民の余暇活動に対する潜在的需要を量的に増大させてきている。国民が余暇時間の大きさによってどのような過ごし方をするかを総理府の世論調査(61年1月)によってみると,週末などの休日や3日以上の連続した休日のように余暇時間が長くなるに従って,「宿泊旅行」,「日帰りの行楽,「ドライブ」などの観光レクリエーションで過ごす人の割合が急に増えるのがわかる 〔1-1-7図〕。
また,国民の価値観の変化,余暇に対する認識の変化などによって余暇活動に対する需要はますます自然志向,スポーツ志向,健康志向など多様化の様相を呈してきており,今後とも余暇活動に対する需要の量的拡大,質的多様化の傾向は強まるものと予想され,観光レクリエーション活動の形態も名所,旧跡を見て歩くなどの「見る観光」から,スポーツ,レクリエーション活動をしたり,郷土色豊かな工芸品作りに参加するなどの「する観光」への変化,旅行の小グループ化,家族単位や高齢者の旅行の増加,長期滞在型旅行の増加等,いわば参加型,能動型,複合型,滞在型の傾向が顕著になってきている。
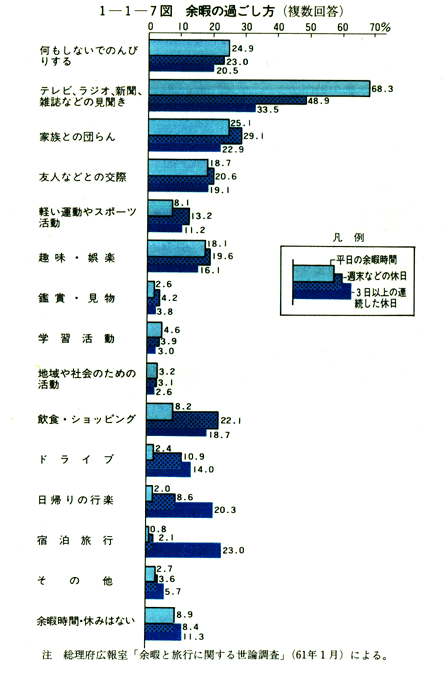
ウ 余暇活動促進のための課題
このような国民の余暇活動に対する需要の増大や意識の変化に対応し,余暇活動特にその中心を占める観光レクリエーション活動を促進し,又はそのための環境整備を行うことが必要である。また,消費及び投資機会の増大による内需拡大,経済構造の転換等の現下の要請に応えるためにも,余暇活動を促進することは喫緊の課題となっている。
この課題に応えるためには,完全週休二日制の普及等労働時間の短縮による自由時間の増大に努めることはもちろん,新しい国民ニーズに応えうる観光関連施設の整備,観光地への容易なアクセスの確保,既存観光地の再開発等にも考慮したリゾート開発のための施策を推進するとともに,情報化社会及び新たな国民ニーズに的確に対応した観光情報システムの充実,旅行者保護の一層の確保等を図ることにより,ハード・ソフト両面から国民の観光レクリエーション活動促進,容易化のための環境整備を推進していく必要がある。
また,日本人の海外旅行者数は着実に増加しているものの,他の先進諸国に比べると極めて低い水準にあり,余暇活動を促進する観点からも国民の海外旅行の大幅な増加対策を講ずる必要がある。
(2) 21世紀へ向けての魅力ある観光地の整備
ア 魅力あるリゾート地域の形成
近年,国民の自由時間の増大,生活様式の多様化に伴うゆとりある国民生活の実現,経済のサービス化の進展等産業構造の変化に伴う観光・レジャー産業をはじめとする第三次産業を中心とした新たな地域振興策の展開,国際協調の観点からの内需の拡大等が緊急かつ重要な政策課題となっている。このような状況に対応し,広く国民が余暇を利用して滞在しつつスポーツ,レクリエーション,教養文化活動等の多様な活動を行うことができるリゾート地域を整備することが必要となっている。このため,所要の施設整備を行う民間事業者に対し税制・財投等の支援措置を講じる等民間事業者の能力を活用しつつリゾート地域の整備を推進することを内容とする「総合保養地域整備法」(いわゆるリゾート法)が,62年6月,公布,施行されたところである。
魅力あるリゾートの要件としては,①日常生活圏にない良好な自然環境や質の高い観光資源を有すること(非日常性),②地域の特性を生かし,定の開発思想をもって地域づくりと連携した整備が行われること(一体性,地域アイデンティティ),③連泊・長期滞在の可能な低廉かつ快適な宿泊施設が整備されていること(居住性),④国民のニーズに合致したスポーツ・レクリエーション機能,教養文化機能,国際交流機能,保養機能などを複合的に備えていること(複合性),⑤日常の生活空間がもつ都市的サービス機能が整っていること(日常空間との連続性),⑥多様な機能を備えた諸施設が一定の地域内に集積していること(施設の集積効果),⑦アメニティ及びホスピタリティを備えた一体的なリゾート運営が行われること(質の高いリゾート・オペレーション)等が必要と考えられる。運輸省としては,リゾート法に基づき,周辺の既存観光地との調和やその積極的活用により地域全体の活性化を図りつつ魅力あるリゾート地域の整備を推進することとしている。
イ 海洋リゾートの整備
リゾートの中には,スキー場等を中核としたウインターリゾートなど,様々な種類のものがあるが,例えば,フランスのラングドック地方に開発されたグランドモットは,マリーナを中心にホテル,コンドミニアム等が建ち並び,一大海洋リゾートを形づくっており,海の生活,ヨットなどが,日常生活と異なる環境を形づくっている。最近の国民の親水ニーズの高まりとも併せ,このような海洋リゾートの意義はますます高まりつつある。運輸省においては,このような海洋リゾートを整備するために,従来より港湾整備事業等を中心に,海洋リゾートの中核となるマリーナ,緑地,イベントバース,広場魚釣り施設,人工海浜等の整備を公共事業,起債事業により進めてきている。また,リゾート法の制定により,民間施設に対する財投等の支援措置が創設され,従来の公共事業と共に民間事業者も一体となった,総合的な海洋リゾートの整備が可能となった。
また,本法には,港湾に係る水域の利用について適切な配慮をすることが位置づけられ,海洋リゾートの整備の上で,港湾の果たす役割がますます重要となってきている。
ウ 家族旅行村の整備
家族旅行村は,国民の観光レクリエーション需要に対応して,家族が恵まれた自然の中で手軽に利用できる観光レクリエーションの場を確保することを目的として整備するもので,整備予定のものを含め,現在35地区において整備が行われている 〔1-1-8図〕。
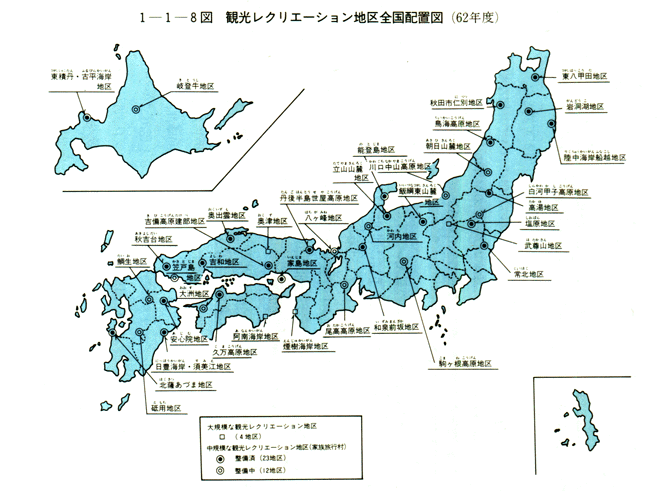
(3) 観光レクリエーション活動の容易化と利便の増進
ア 自由時間の増大と費用の低廉化
我が国における観光レクリエーション活動は,諸外国と比較した場合,未だ量的にも質的にも必ずしも十分なものとは言えない。経済企画庁の調査(62年8月)によれば,勤労者の自由時間は年間約1,850時間であり,フランス,西ドイツの約2,700時間,イギリスの約2,400時間,アメリカの約2,300時間と比べると極めて少ない 〔1-1-9図〕。このため,国民観光レクリエーション活動促進のための条件整備としては,まず,余暇時間拡大のための努力を引き続き行っていく必要がある。運輸省においても,観光週間(8月1日~7日〉キャンペーン等を通じ,「ほっとウィーク」を標語とし,労働省等の関係省庁と連携して,夏季における1週間以上の連続休暇の普及の促進を図っているが,さらに,交通機関,道路,宿泊施設その他のレクリエーション施設への過度の集中による利用者の不便を避けるために,休暇の平準化及び観光の通年化のための施策を検討することが必要である。
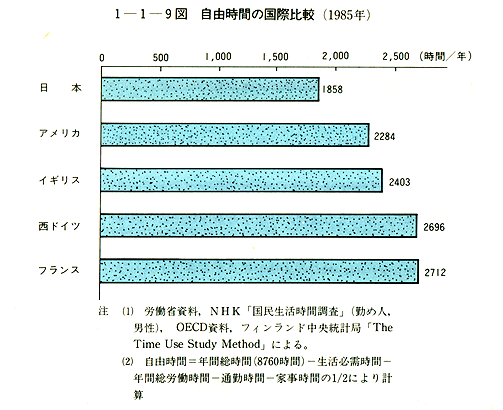
また,交通機関,宿泊施設その他のレクリエーション関連施設について,その費用の低廉化を図ることが必要となる。62年5月,JR東日本旅客鉄道会社の会社創立を記念して発売された割引乗車券「E・Eきっぷ」の利用者アンケートによれば,「E・Eきっぷがなければ,旅行しなかった」という人が全体の約5割を占めたことからも,その運賃の設定が新たな旅行需要を掘り起こしたことが明らかである 〔1-1-10表〕。このため,オフ・シーズン割引等の各種割引料金の充実による経済的な観光レクリエーション活動を促すための施策を今後更に検討する必要がある。

イ 身近なレジャー等と足の確保
余暇活動を重視する国民意識の変化に伴い,余暇活動の多様化と,時間的,地理的な拡大が進んでいる。その中で,ささやかな休日の1日を利用した家族,あるいは,グループでの身近なレジャーが容易に実現されることもまた,ゆとりある国民生活の実現のために,極めて重要である。
しかしながら,日々の生活の拠点からさほど遠くない位置に豊かな自然や歴史的遺産,余暇活動にふさわしい施設が存在しているにもかかわらず,多くの地方都市等においてはこれらへのアクセス手段は必ずしも便利なものとは言い難い状況にある。
今後の余暇活動の充実促進に当たっては,観光レクリエーション施設へのアクセスの確保という視点からの対応が,施設の設置管理者等と公共交通機関のタイアップにより進められることが重要である。
さらに,観光地における随意性の高い輸送サービスに対するニーズの高まりに応じ,鉄道駅,空港等を拠点としたレンタカーの重要性は今後ますます高まるものと思われるので,予約システムの拡充,乗り捨てシステムの整備等その利用がより容易となるような施策を講じていく必要がある。
ウ 観光情報提供体制の整備
国民の観光レクリエーション活動の多様化に対応した観光地の最新情報を正確かつ迅速に提供する体制の充実が求められている。また,今まで知られていなかった観光地に関する情報又は観光地におけるオフ・シーズンのイベント等の情報を提供することを通じて,新たな観光需要を喚起し,観光地活性化を図るという観点から観光情報システムを整備していこうとする動きが,地方公共団体を中心に観光地側においても活発になっている。
このような状況に対応して,(社)日本観光協会,国際観光振興会等の観光関係団体が中心となって,国内観光地情報,訪日外客のための情報等の収集体制の整備を進めており,このようにして収集された情報を運輸機関,宿泊機関,旅行業者等のシステムとの連携により効率的に提供するシステムの整備を図るなど,引き続き高度情報社会の進展に対応した観光情報システムを充実していく必要がある。
エ 旅行者の保護
(ア) 旅行業に関する旅行者保護施策
旅行に関するサービスは目に見えないものであり,かつ,予定どおりのサービスの履行そのものに意味があるので,旅行を扱う旅行業者の適正な運営,旅行取引の公正さが確保されることが必要である。
このため,旅行業法に基づき,旅行者保護の見地から旅行業者を登録制として種々の規制を行っているほか,主催旅行広告の適正化等について,きめ細かな指導・監督を行っている。
さらに,62年3月に警察庁,都道府県,旅行業協会等の協力を得て「いい旅しよう'87」キャンペーンを展開し,①旅行者に対する登録業者の利用の呼びかけ,②無登録業者に対する監視体制の整備,③登録業者に対する立入検査等,旅行業法の遵守の総点検を行い,また無登録業者の取締りのため,警察との連携を一層強化するなど旅行業法の遵守を徹底し旅行者保護の一層の充実を図っている。
(イ) モデル宿泊約款の制定
登録ホテル・旅館業を営む者は,国際観光ホテル整備法に基づき宿泊約款を定めなければならないこととされている。運輸省では,39年に宿泊約款例を作成し,約款の内容の適正化を図ってきたが,60年末に必要な見直しを行い,新たなモデル宿泊約款を作成した。現在,このモデル約款をもとにより一層の利用者保護を図っている。
|