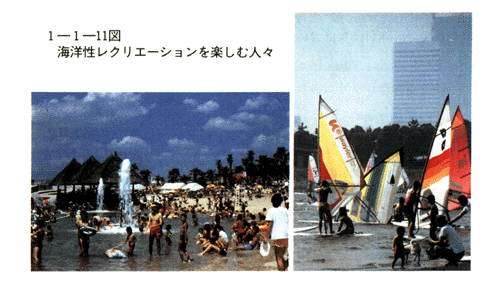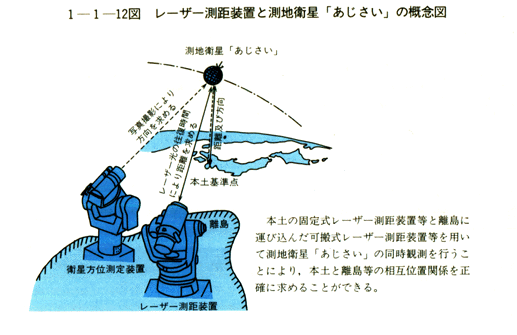|
5 海洋の開発・利用
(1) 海洋の開発・利用の推進
ア 海洋の開発・利用のための諸施策の展開
海洋空間の中で,沿岸海域は国民生活と密接に結びついた空間として古くから盛んにその開発・利用がなされてきた。特に港湾や自然条件に恵まれた内湾・内海については,多目的かつ高度に利用されている例が多い。しかしながら,一般的にはこれらの海域を除いた沿岸海域は,総じて海域利用の程度は低く,単機能的な利用にとどまっており,今後の海域の開発・利用に関し高いポテシャルを有している。
このように,今後国民生活の質の向上等をめざし,海洋空間の有効利用を進めるに当たっては,各海域特性に応じた施策の推進を図っていく必要がある。
(三大湾等の計画的利用の推進)
三大湾等(東京湾,伊勢湾,大阪湾,瀬戸内海)の利用が稠密な海域においては,旺盛かつ高度な海域利用へのニーズに対応し,適正な利用及び保全を図っていく必要があり,運輸省では沖合人工島の整備,海上浮体施設の整備,廃棄物の広域的処理(フェニックス計画〉,広域的な海洋環境の改善・整備(シーブルー計画)等を通じ,一層,計画的利用を推進していくこととしている。
(外海に面する海域の有効利用の推進)
一方,外海に面する沿岸海域は,波浪等の厳しい自然条件等が原因となって,そのポテンシャルが十分に発揮されていない。このため,これらの海域においては,海域のポテンシャルに対応した先導的プロジェクトの策定と推進によりその有効利用を図る必要があり,運輸省では沖合人工島や静穏海域整備構想を推進している。
(沖合人工島の実現化)
従来から検討を進めてきている沖合人工島については,これまでの成果等に基づき作成した沖合人工島計画策定のガイドラインである計画指針をもとに,現在,東京湾,清水,横須賀,玉野・倉敷,下関でフィージビリティスタディを行っている。今後は,事業主体の設立,事業実施の方策等について地方公共団体等との調整を図り,船舶航行の安全対策にも十分配慮しつつ実現化を図っていくこととしている。
(海上浮体施設の整備)
海洋の利用・開発を推進していくという観点のほか,我が国造船業が直画している困難な状況に対処するための新たな造船需要を喚起するものとして,用地取得費が不要で,工期が短く,周辺環境に及ぼす影響が小さい等のメリットを有する海上浮体施設の整備を推進していくこととしている。なお,現在,構想の具体化に向けて長崎,呉,尾道において地方公共団体等を中心として検討を進めている。
イ 海洋性レクリエーションヘの対応
(高度化・多様化する海洋性レクリエーション)
近年,国民の所得水準の向上,余暇時間の増大等を背景に,レクリエーション需要は量的に増大するとともに,質的にも高度化・多様化してきている。こうした中で,我が国は狭あいな国土を各種の活動の場として稠密に利用してきており,国民の旺盛なレクリエーション需要に対する海洋空間の有するポテンシャルは高いものがある。
我が国では,従来から海水浴,釣り等が広く国民に親しまれてきたが,近年は,ヨット,モーターボート,ボードセーリング,ダイビング等の多彩な海洋性レクリエーションが普及・発展してきており,高度化・多様化するこれら海洋性レクリエーション需要にこたえるため,海洋空間の有する高いポテンシャルを最大限に発揮する施策の展開が求められている 〔1−1−11図〕。
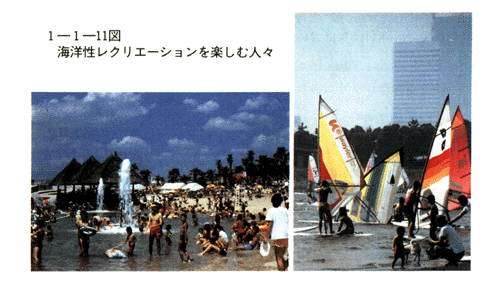
また,洋上クルージング需要にもその萌芽がみられ,今後,海上旅行の推進を通じてその健全な発展を図っていく必要がある。
このため,省内に設置している海洋性レクリエーション対策協議会において,62年9月21日に,海洋性レクリエーションに関する総合的な施策として「海洋性レクリエーションに関する基本方策」を策定した。
(海洋性レクリエーション施策の展開)
運輸省では従来から,公共マリーナ,人工海浜,観光レクリエーション地区等の整備による海洋性レクリエーションの環境づくり,船舶検査,海技資格免許,海難防止活動等による安全の確保,海難救助,海象・気象等の情報提供など海洋性レクリエーションに関する多面的な業務を展開してきている。
また,62年5月に制定された「総合保養地域整備法」では,国民の多様なライフスタイルに応じ,スポーツ,レクリエーション,教養文化活動,集会等を行うことができる複合性,今後の連続休暇の普及に対応した長期滞在性を備えた大規模リゾートの開発を民間活力を活用して推進することとしている。この場合には,海洋の良好な自然環境をいかして,スポーツ・レクリエーション施設,教養文化施設,休養施設,集会施設,宿泊施設,交通施設等を相互の有機的連携に配慮しつつ,地域の特性に応じ,マリーナの整備,海上浮体施設の活用等を含めた施設整備を行い,総合的なウォーターフロント空間の整備を図ることが重要である。
このほか,マリーナの不足に対応するための施策として,ハロー・マイボート構想(内陸保管施設等に舟艇を保管し,利用海域まで輸送するシステム)の検討を実施しており,さらに安全意識,知識,技術の向上等安全指導の充実及びこれに伴う指導者の養成,関係者による自主的な安全活動の推進等ソフト面の充実や海上旅行の推進を図る等総合的な施策の展開を図っていくこととしている。
(海洋・海事思想の普及)
運輸省では,「海の記念日」(7月20日)を中心とした「海の旬間(7月20〜31日〉等において,全国各地で行われる海上防災訓練,海上パレード,マリンフェスティバル等の多彩な行事を支援し,あるいは海洋性レクリエーションを振興すること等により海洋・海事思想の普及を進めている。
また,国民各層,特に日本の将来を担う若い世代の海に対する関心を喚起するために,61年から主要港湾都市持ち回りで「海の祭典」を開催している。61年,62年はそれぞれ第一回が北九州市で,第二回が神戸市で開催され,63年は第三回が名古屋市で行われる予定である。
ウ 海洋調査及び海洋情報の収集・管理・提供の充実・強化
海洋の開発・利用を進める上で,海洋に関する情報は必要不可欠であり,海洋の開発・利用の進展に伴い,海洋情報に対する需要は量的に増大するとともに,質的に高度化・多様化してきている。
運輸省は,人工衛星,航空機,測量船,観測ブイ,沿岸観測施設等による広範な海洋調査の実施等により,波浪,海流,水温,海底地形等各種の海洋情報を収集,分析し,リアルタイム(即時)あるいはノンリアルタイム(非即時〉の情報として各方面に提供しており,広域かつ総合的な海洋調査及び海洋情報の収集・管理・提供を恒常的に行う我が国唯一の機関として,海洋の開発・利用の推進に大きな役割を果たしてきている。なお,これらの海洋情報をファクシミリ等により船舶等に提供するほか,総合的海洋データバンクである日本海洋データセンターを通じて提供してきたが,これらの海洋情報を地域の特性に応じてきめ細かく提供することを自的に,62年度より五か年計画で「地域海洋情報整備事業」を推進することとしている。
このほか,海洋情報の収集・管理・提供の充実・強化のため,全世界海洋情報サービスシステム(1GOSS)計画,西太平洋海域共同調査(WESTPAC)等の国際的な活動にも積極的に参加し,その推進を図っている。また,今後の海洋調査の一層の充実を図るため,危険海域を調査する自航式ブイの開発,人工衛星を利用した海流等の調査技術の研究,広域の水温等の変動をモニターする音波断層観測システムの開発等も行っている 〔1−1−12図〕。
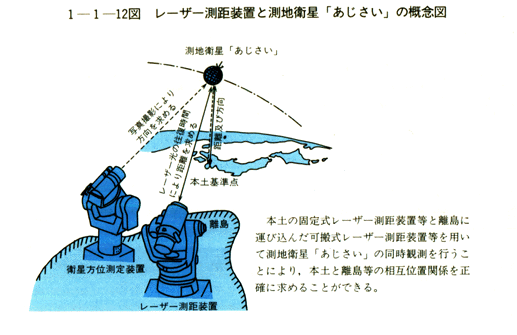
エ 海洋の開発・利用を支援する技術の開発
海洋の開発・利用の推進のためには,波浪等の厳しい自然条件を克服するための技術開発が必要であり,運輸省では,港湾整備等で培われた海洋土木技術及び世界をリードしてきた造船技術を結集しこれらの技術開発に積極的に取り組んでおり,マルチセルラーケーソン式防波堤注1),軟弱地盤藩底式防波堤,ハイブリッド海洋構造物注2)等の開発を進めている。
また,実際の沖合海域で実証実験を行うことにより海洋構造物の設計・施工技術を確立するため,現在,浮体式海洋構造物「ポセイドン」を山形県由良沖に係留し,安全性・信頼性を確認するデータを収集している。
(2) 新海洋秩序への対応
(海洋法条約を35の国等が批准)
海洋の開発・利用の前提となる海洋秩序については,57年に採択された「海洋法に関する国際連合条約」(以下「海洋法条約」という。)により,新たな基本的枠組みが形成されようとしている。
海洋法条約は,領海,200海里排他的経済水域,大陸棚,海洋環境の保護,深海底開発,国際海峡の通過通航等,運輸省の所管している行政に広く関わるものであることから,運輸省では同条約の批准に備えて所要の準備を進めている。なお,同条約は,60の国等が批准又は加入した後1年で発効することとされているが,62年11月3日現在,署名数159,批准数35となっている。
(管轄海域確定のための調査の実施)
海洋法条約の下では,各国は排他的経済水域や大陸棚において,漁業,資源開発,海洋調査等に関し主権的権利等を有することになっており,同条約の発効に備え,我が国が一定の管轄権を有する海域(以下「我が国の管轄海域」という。)を確定することが必要となる。
このためには,まず世界測地系における我が国の正確な位置を求める必要があり,従来より測地衛星「ラジオス」のレーザー測距による測地観測を行ってきたが,さらに,61年に打ち上げられた国産測地衛星「あじさい」を用いて,62年度より本土と離島の位置関係を高精度で求めることとしており,可搬式レーザー測距装置等所要の施設整備を進めている。
また,我が国の管轄海域の限界線等の基準となる領海基線を確定するための詳細な調査を実施するとともに,大陸棚の範囲の確定等に資するため,大型測量船「拓洋」により,61年度は南西諸島海溝付近等3海域において調査を行った。
注1) マルチセルラーケーソン式防波堤:水平方向に作用する波力を,ケーソン内部に設けられた多段の曲がり斜面により鉛直方向の成分に変換し,滑動や転倒に対する抵抗力に利用する防波堤
注2) ハイブリッド海洋構造物:鋼の高強度,耐張力とコンクリートの耐蝕性,耐低温性を生かした鋼-コンクリートハイブリッド(複合)構造物
|