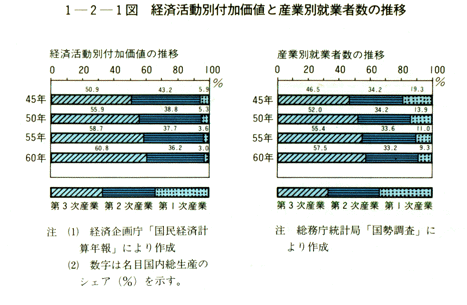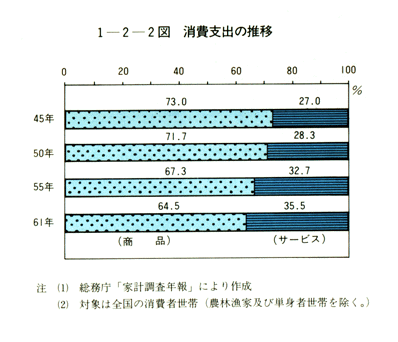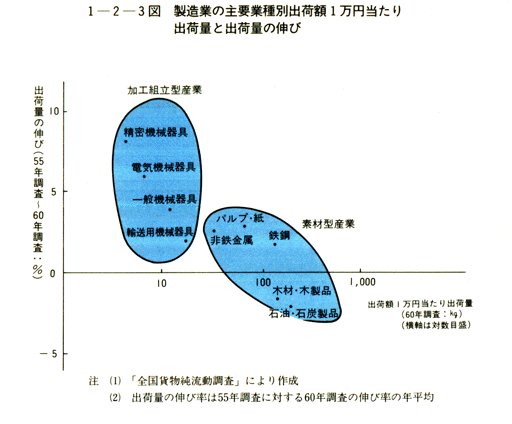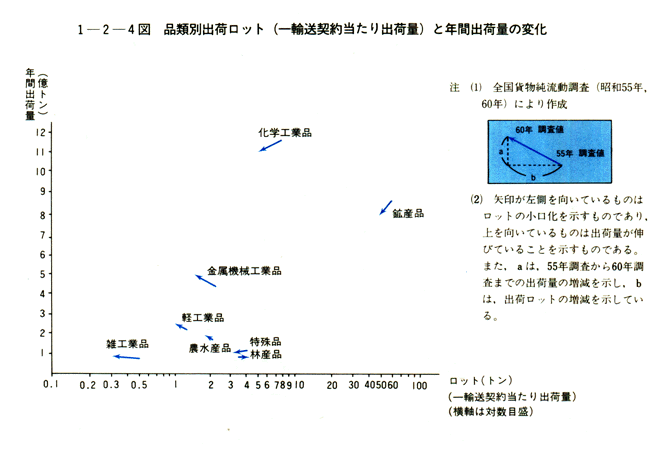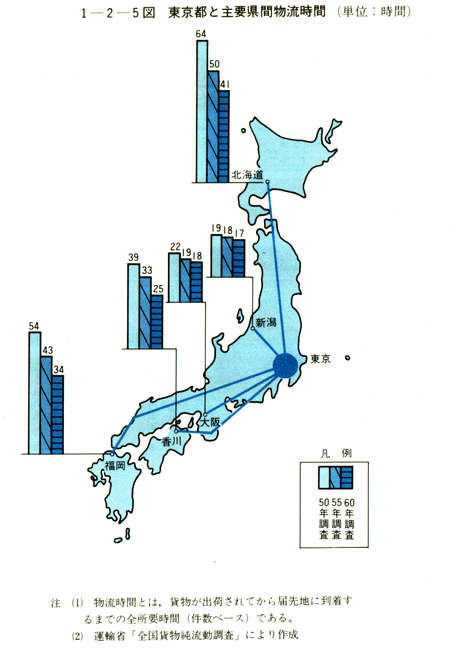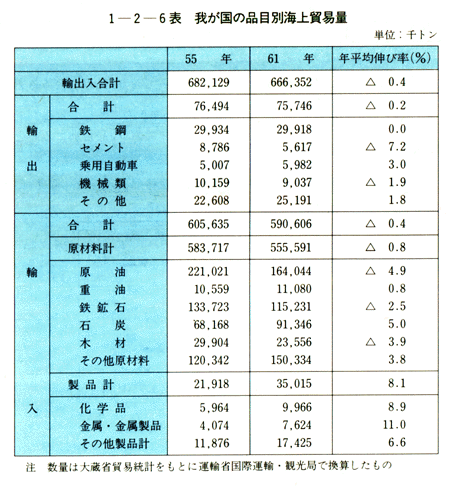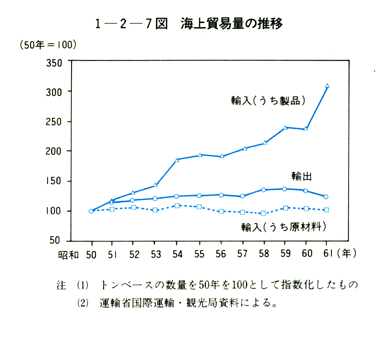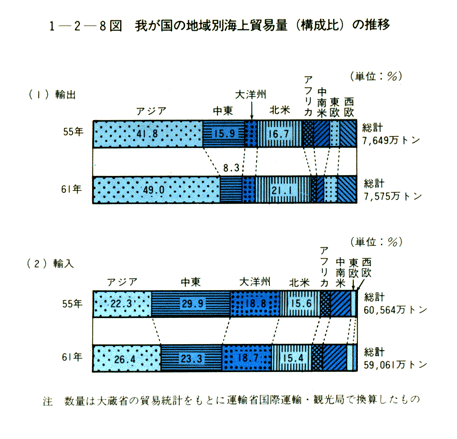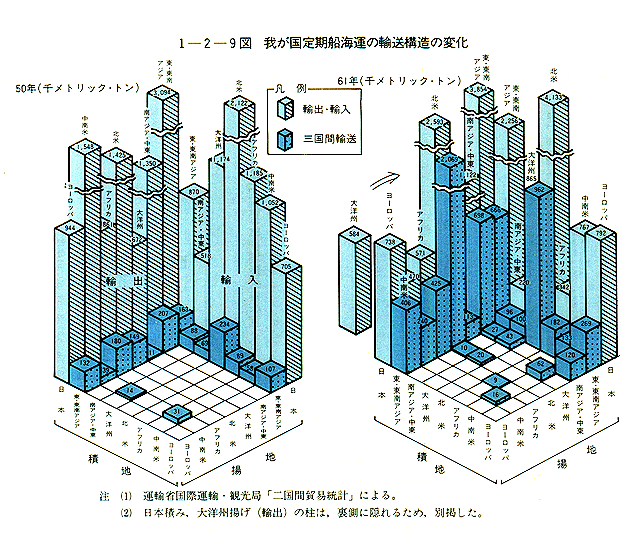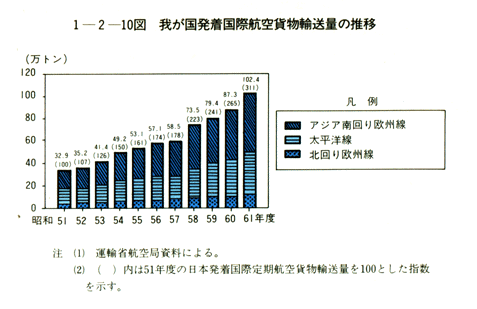|
1 進展する輸送構造の変化
(1) 変化する国内物流構造
(産業構造の変化と物流量)
我が国の産業構造は,経済の成熟とともに着実に変化している。第1次及び第2次産業のウェイトが減少し,第3次産業のウェイトが増加するサービス化・ソフト化の傾向は,付加価値額の構成比でみても,就業者数の構成比でみても進展している 〔1−2−1図〕。また,消費面からみても,家計支出に占めるサービス支出の割合は一貫して増加しており 〔1−2−2図〕,国民生活の変化に伴ういわゆる「モノ離れ」現象が進んでいるといえる。
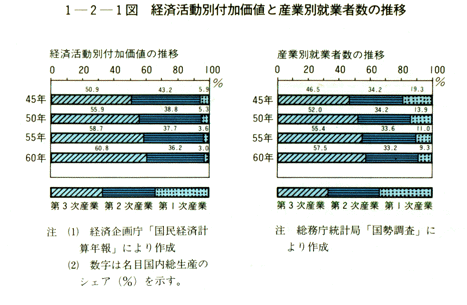
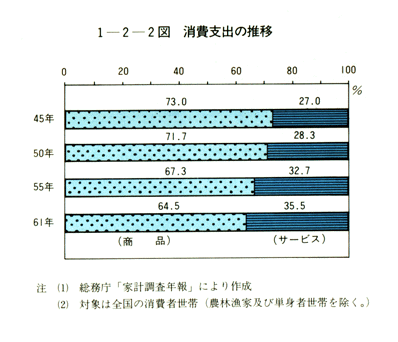
また,製造業の生産動向をみると,ハイテク分野を含む高付加価値分野の成長が顕著であり,素材型から加工組立型へのシフトとともに高付加価値化が進んでいる。 〔1−2−3図〕は全国貨物純流動調査をもとに業種別の単位出荷額当たり出荷量と出荷量の伸び率をみたものである。出荷額当たりの出荷量が大きく重量当たり付加価値が低い素材型産業に比べ,出荷額当たりの出荷量が小さく重量当たり付加価値が高い加工組立型産業の出荷量の伸びが高いことがわかる。これは,製造業の生産額の伸びが量的拡大へ結びつかなくなってきていることを示している。このように産業構造の変化を背景として,物流量は,安定した経済成長が続いているにもかかわらず停滞を続けている。
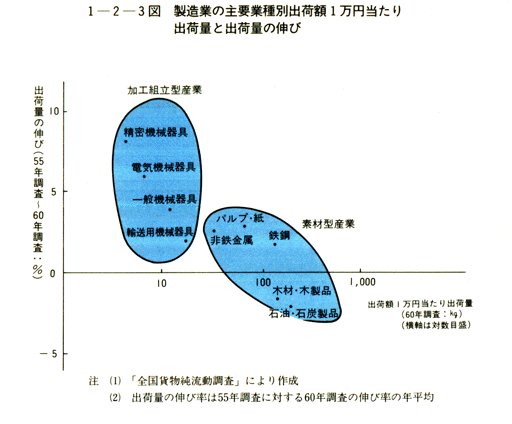
(物流構造の質的変化)
こうした産業構造の変化は荷主ニーズの変化とあいまって物流構造にもさまざまな面で影響を及ぼしている。 〔1−2−4図〕は品目別に一件当たり出荷量(ロット)と年間出荷量の変化を55年と60年で比較したものである。林産品を除きすべての品目で「出荷の小口化」が進んでおり,平均ロットは55年から60年の間に3.80トンから2.63トンへと約3割小口化している。また,小口品目の出荷量割合が増大しており,出荷量が停滞するなかで「出荷の高頻度化出がうかがえる。これらの変化は,重厚長大型から軽薄短小型へと産業構造が変化しているなかで,荷主企業が国民生活の高度牝に対応して多品種少量生産体制をとっていることを反映しているものと思われる。
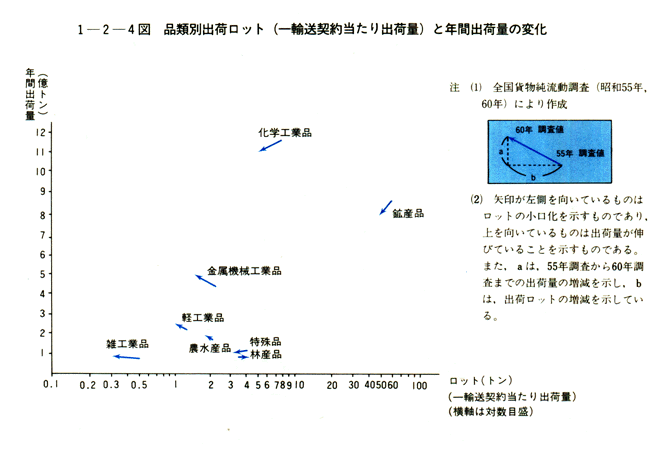
一方,安定経済成長下の限られた国内市場においてますます厳しい競争を強いられるようになっている荷主企業の間で,在庫コストの圧縮という意識が定着してきた結果,「必要なものを必要なときに必要なだけ輸送する」という,いわゆるジャスト・イン・タイム輸送の要請が高まってきている。こういった荷主ニーズの変化によっても,物流の小口化,高頻度化さらには到着時間の正確化が進んでいると考えられる。また,物流の迅速性の要請を背景に,航空貨物の増大や高速道路網の整備によって物流時間が短縮化している 〔1−2−5図〕。
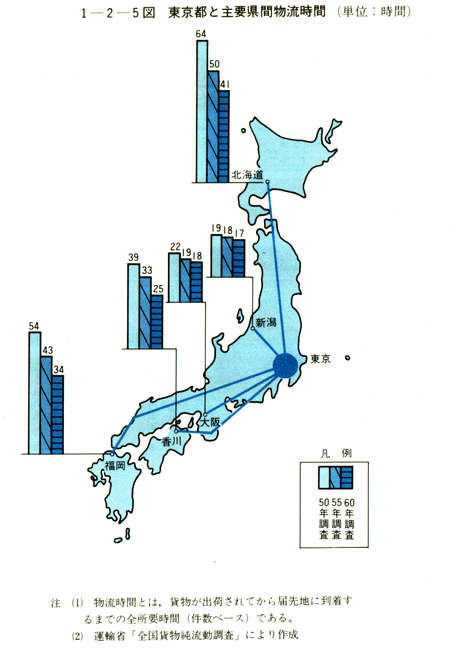
(2) 国際物流構造の変化
(我が国の海上貿易構造)
61年の我が国海上貿易量(トンベース)は,60年に引き続き輸出入とも減少し,合計で対前年比1.3%減の6億6千万トンとなった。
これを55年の実績と比較し,最近における品目構成の変化をみてみると, 〔1−2−6表〕のとおり,我が国の産業貿易構造の変化を反映して製品輸入の増大等の変化がみられる 〔1−2−7図〕。
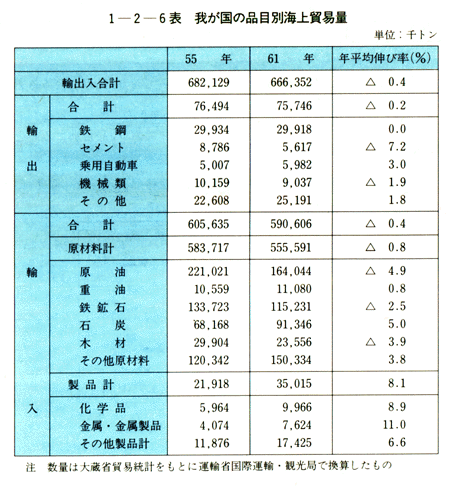
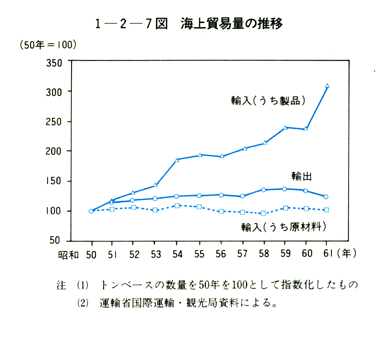
輸出については,年平均0.2%の減少となっており,品目別にみると,主要な輸出品目であるセメント,機械類の大幅な減少が目立っている。
輸入については,年平均0.4%の減少となっており,品目別にみると,原油,鉄鉱石,木材といった原材料の減少が自立っている。これに対して化学品,金属・金属製品,機械類等を中心とした製品輸入は大幅に増加した。
このような輸出や原材料輸入の減少,製品輸入の増加の傾向は,近年のアジアNICsの台頭にみられるような国際分業の進展を反映しているものと思われる。特に,韓国台湾等アジアNICsにおいては,為替安,資本や技術の蓄積,人件費の安さ,国家の助成策等により,工業化が急速に進んでおり,さらに,60年9月のG5(5か国蔵相会議)以降急速に進んだ円高により日本の輸出が伸び悩んだことから,アジアNICsからの工業製品の輸出が引き続き増加した。
次に,我が国の地域別海上貿易量をみてみると, 〔1−2−8図〕のとおりで、輸出については,中近東向けがセメント及び鉄鋼の半減により輸出量が大幅に落ち込んだ。一方,アジア向けは,中国向けをはじめとする鉄鋼が,北米向けでは,機械類がそれぞれ大きな伸びをみせ,相対的にシェアを増大させた。また,欧州向け輸出は,東欧向けの鉄鋼,西欧向けの自動車を中心に増加した。
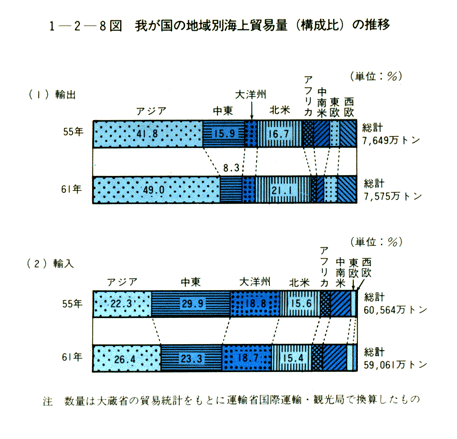
輸入については,原油,重油の減少により中東のウェイトが減少した。一方,ドル安の影響により競争力を強めた韓国台湾等アジアNICsからの機械類等の大幅な増加によりアジアのウェイトが高まった。
(進展する三国間輸送)
〔1−2−9図〕は,61年の我が国商船隊による世界の地域間定期船輸送の状況を,50年の状況と比較して示したものである。
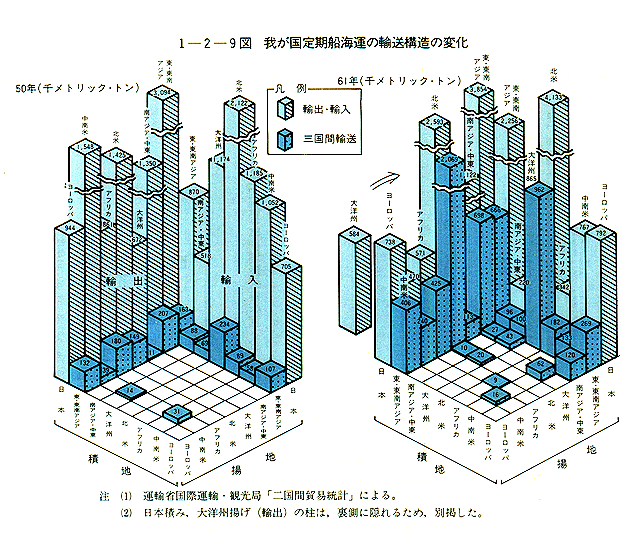
これによれば,我が国からの輸出については,中南米,ヨーロッパ,アフリカ向けの輸送量が減少しているのに対し,北米向けの輸送量の著しい増加が目立つ。また,我が国への輸入については,東・東南アジアからの輸送量が急増して北米からのものに次ぐ規模となっており,これらいずれも,北米及び東・東南アジアとの輸出入の拡大という我が国の貿易構造の変化を反映しているものと考えられる。
ここで注目すべきは,日本発着以外の貨物輸送,いわゆる三国間輸送の伸びである。我が国定期船海運による三国間の輸送量はこの10年余りの間に約4倍にもなっており,我が国定期船海運の輸送量中に占める比率も50年の8.1%から61年には,25.8%と拡大した。これは,貿易構造の変化,特に日本企業の進出等により工業化が進展した発展途上国からの製品輸出の増大,日本発貨物の停滞等によるものであり,当該諸国を中心として米国,欧州諸国等の先進国との定期船市場が大きく開けてきたためであると考えられる。
我が国商船隊の三国間輸送は,かつては東・東南アジア発着の貨物や大洋州から中南米向け,中南米諸国間にみられたにすぎなかったが,最近では東・東南アジア発着の貨物輸送がさらに増加するとともに,その他の地域間の三国間輸送の比重が高まっている。
(比重を増す国際航空貨物輸送)
国際分業による半製品の国際流通の増大に加え,円高の進行に伴う製品や食料品を中心とした輸入の拡大を背景として,我が国発着の国際航空貨物輸送は着実に成長を続けており,61年度においては,対前年度比17%増の102.4万トン(直送貨物及び継越貨物)を記録した 〔1−2−10図〕。これに伴い,我が国をめぐる国際物流における航空輸送のシェアも金額ベースで,60年の約12%から61年には約15%と,着実にその比重を増してきている。このような流れの中にあっても,円高の影響が顕著にみられるようになっており,61年度には,輸入航空貨物量が対前年度比35.2%増と著しい伸びを示したのに対し,輸出航空貨物は同1.5%減と微減に転じた(直送貨物のみ)。
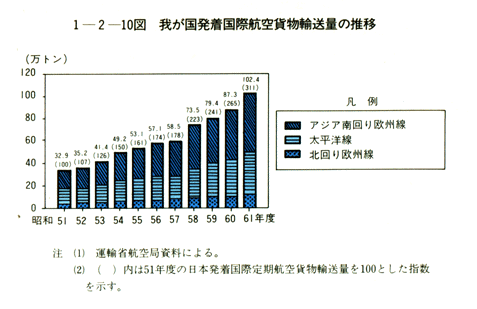
わが国発着の国際航空貨物輸送を地域別にみると,これまでと同様,米国を含む太平洋線の占める割合が約35%と1地域として最大の市場となっているほか,近年の傾向として,輸出入ともにアジアNICsを中心として,東南アジアとの物流が増加していることが注目される。
|