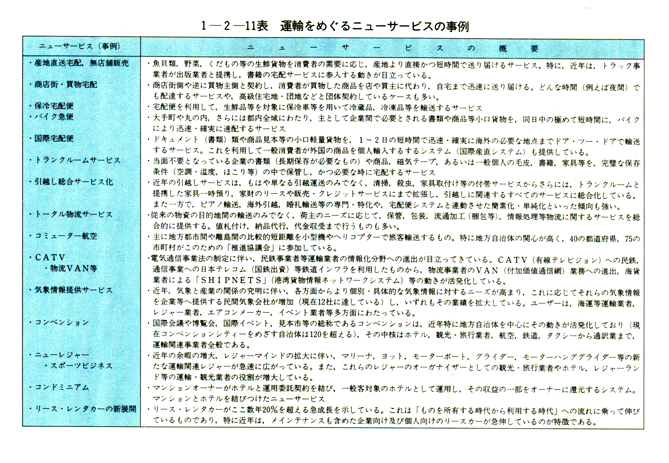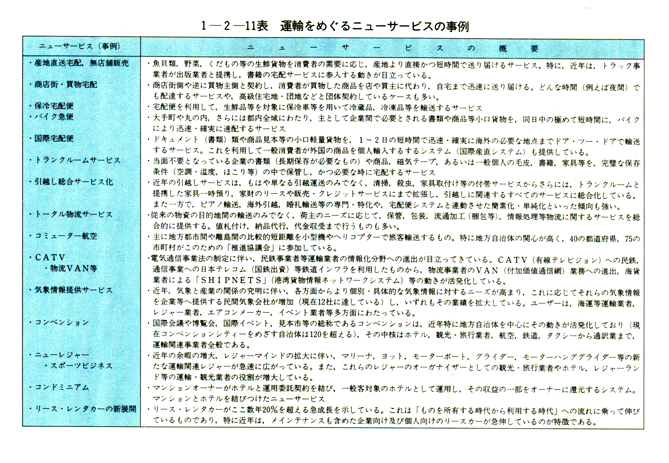|
2 輸送構造の変化に対応する運輸
(1) 新しい運輸事業の展開
(経済のソフト化・サービス化と運輸)
近年,国民生活の面においては,「ゆとり指向の増大,女性の社会進出の進展,ライフスタイルの変化等に伴って家庭向けサービスニーズが増大している一方,企業活動の面においても,技術革新,情報化,外注化の進展等に起因する事業所向けサービスニーズが増大しており,我が国経済はソフト化・サービス化の傾向を一段と強めている。
安定成長下におけるこの経済のソフト化・サービス化の進展に伴い,運輸の分野においては輸送・保管量が伸び悩みの傾向をみせる一方,安定成長下における荷主企業間の競争の激化や消費者の嗜好の変化を反映して,より高度化・多様化したサービスの提供が求められるに至っている。
運輸事業者は,高度成長期においては,主として需要の量的増大に対応して供給力を増強することにより事業の拡大を図ってきたが,ここにおいて輸送・保管量の伸び悩みに対応して経営の合理化や資産の有効活用等により経営体制の強化を図る一方,ニーズの高度化・多様化等を踏まえて安定成長下における新たな事業展開の途を模索しており,その一環として,既存のサービスの高度化・多様化や,新たなサービスの創出に取り組もうとする動きが顕著になっている。
(多種多様な運輸関連ニューサービスの出現)
このような動きを反映して,運輸に関連したニューサービスの出現が相次いでいる。これら運輸関連ニューサービスの業態は,宅配便,トランクルームサービスのように,既存のサービスとは差別化されたより高度なあるいは専門的なサービスを提供し,物流ニーズの高度化・多様化に対応するもの,気象情報提供サービスのように,情報システムを積極的に活用し,高度情報化の要請に対応したもの,コンベンション,ニューレジャー・スポーツビジネスのように,余暇の増大・国民のレジャー指向の高まりに対応したもの等多種多様であり 〔1−2−11表〕,様々なアイデアに基づいて新しい業種が生まれている。
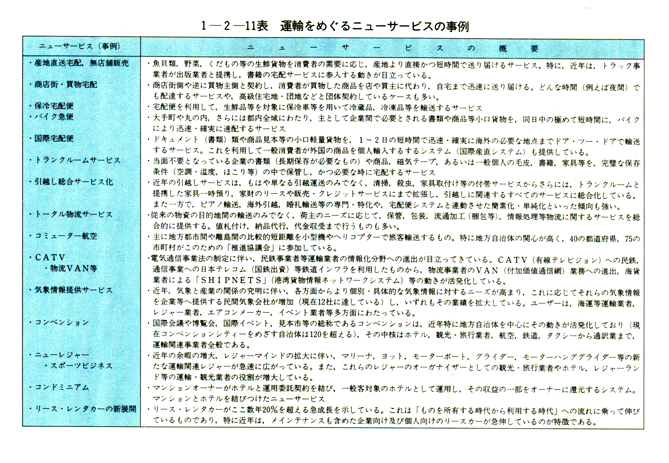
この結果,現在では,200業種前後の運輸関連ニューサービスが存在すると想定されている。
(運輪関連ニューサービスの課題と今後の行政上の対応)
運輸省では,これまで既に市場規模が拡大して一般消費者との接点が多くなってきた宅配便,トランクルームサービス及び引越輸送について,標準約款の制定や運賃・料金体系の整備により消費者保護対策等を推進してきたほか,国際宅配便による個人輸入の推進やコンベンションの振興に取り組む等ニューサービスに対する積極的な対応を行ってきている。
しかし,宅配便等の一部の例外を除き,ニューサービスの大部分は発展段階としては未だ萌芽期ないしは導入期にあるため,情報力,資金力,業界秩序,人材確保等の面で様々な問題を抱えている。
これらニューサービスの発展は,国民,産業界のニーズに応えるのみならず,中小零細事業者が大半を占める運輸事業全体の活性化をもたらす可能性があるほか,内需の拡大等を通じ,我が国経済社会が国際的に調和のとれた姿で発展していくことにも資すると考えられる。しかしながら,また一方では,ニューサービスの内容によっては既存業界との間で様々な摩擦を引きおこしているものもある。
従って,今後行政としてもその実態の継続的な把握に努めながら,ニューサービス出現の背景となっている国民,産業界のニーズの動向をも十分に踏まえた上で,ニューサービスが健全な発展を遂げていくための施策を講ずる必要がある。
(2) 物流の分野における新しい事業展開め動向
(ジャスト・イン・タイムの生産・販売体制に対応した物流システムの構築)
産業構造の変化,国民生活の向上に伴う荷主企業の販売戦略の転換,コスト意識の向上等は,物流にも大きな変化を与えている。近年,特に,注目されているのがジャスト・イン・タイムの生産体制・販売体制に対応した物流システムの構築である。
ジャスト・イン・タイムの生産体制・販売体制は,自動車メーカーをはじめとする製造業において広く採用されているが,最近では卸・小売業界にも浸透している。これは,国民生活の多様化・個性化が進み,商品の短サイクル化が著しいため,在庫の極少化を実現するシステムが求められているためである。こうしたシステムは,60年代になってスーパーやコンビニエンスストアー等においてPOSシステム注)やオンライン受発注システム等情報システムの導入が進んだことによって,一層,普及している。こうした状況に応じて,物流業界でもトラック事業者を中心に,ジャスト・イン・タイム方式へのとりくみがみられる。具体例としては,60年代に入って目立っている「時間指定便」の商品化が挙げられる。これは,集荷した貨物を翌日の牛前中あるいは翌日の指定された時間帯に配送するといった内容のものが多い。また,コンビニエンスストアーはその売場スペースの有効活用等の観点から極力在庫を減らそうとする傾向が特に強いが,これに対応して日配品を中心とした24時間配送体制を構築するトラック事業者もある。このほか,特定のメーカーを対象として,ジャスト・イン・タイムの部品の輸送を行っている物流事業者もある。
ジャスト・イン・タイム方式は,必要に応じた物流VAN,移動体無線等の情報システム,高度な機器類,専用施設の整備や車両・人員の配置等により,高度なサービスを提供するものであり,これによって荷主を固定化し,また,新規荷主を開拓することも可能であるが,相当のコストがかかり,中小物流事業者では対応が難しいことのほか,指定の時間に遅れた場合の損害賠償や契約解除等の問題点も指摘されている。
(国際化,情報化に対応する物流サービス)
荷主ニーズの高度化・多様化,物流の小口高頻度化は,国際物流の分野においても例外ではない。一人の運送人が異なる輸送機関を組み合せて,一貫した運賃と責任で輸送する国際複合一貫輸送は,輸送手配をドア・ツー・ドアで一人の運送人に任せることにより輸送手配,トラブル処理等について荷主の利便性を高めるとともに,トータルコストの削減にも資するものである。特に,海上輸送と航空輸送を組み合せたシー・アンド・エアについては,運賃は航空運賃より安く所要日数は海上輸送より短いという特徴があるために,物流コストを切りつめながら迅速な輸送を行いたいという荷主の意識を反映して,近年,注目されている。また,航空機を利用して小口貨物や書類をドア・ツー・ドアで輸送する国際宅配便が,小口化,高付加価値化の進む物流ニーズに対応して進展している。国際宅配便については,国際ビジネス活動の高度化・多様化を反映して,企業の書類や商品のサンプル,部品等法人の利用が中心となっているが,今後は,外国製品の個人輸入等一般消費者の利用が増大することが期待される。
一方,高度な物流サービスを提供するためには情報システムの構築が不可欠である。国内物流の分野においては,トラック運送事業者が物流VANを構築し,荷主に対し貨物追跡情報を提供しているほか,受発注,代金請求,在庫管理を荷主に代わって行うサービスを提供している。物流VANは,小口高頻度化した輸送を合理的に行う共同輸送システムの構築にあたっても,有効に利用されることが期待される。また,国際物流の分野においても、港湾における輸出手続きに係るデータ交換をオンライン化したSHIPNETS(港湾貨物盾報ネットワークシステム)が61年4月から本格稼働しているほか,航空貨物,海上コンテナ貨物の追跡管理のためのネットワーク化の動きも活発化しており,62年9月,本格的な国際VANの実現をめざした電気通信事業法の一部改正が施行されたことと相まって,情報化が一層進展するものと予想される。
(新しい物流サービスの開発)
また,潜在的需要を掘り起こすような形で,新しい物流サービスを開発する物流事業者もあり,特に,一般消費者向けの物流サービスを多様な形で提供しようとする動きが目立つ。
なかでも,宅配便を軸にした展開が活発であり,宅配便市場そのものが成熟する一方,競合する郵便小包がサービスを強化するなかで,ゴルフ・スキー用具はもとより,冷蔵品,冷凍品の輸送にも参入し始めたり,宅配便のネットワークを利用した産地直送宅配便や書籍宅配便に取組むなどの動きもみられる。
宅配便を利用した保冷輸送は61年から始まり,現在,2社が手がけている。生鮮品の産地直送が定着していることに対応したもので,貨物の種類に応じて冷凍輸送,氷温輸送,冷蔵輸送を行うものである。
書籍宅配は,62年に入って本格化している。主に大手路線トラック事業者が出版業者と提携し,書籍を宅配サービスするもので,読者が電話,はがき等で出版業者に申し込んだ書籍についてオンラインで在庫情報を検索し,宅配便で読者のもとへ届けるという仕組になっている。書籍宅配は,若干の配送料はかかるものの,家庭に居ながらにして書籍が入手可能なうえ,従来の出版店→取次店→書店→読者というルートに比較し,迅速に入手できるという利点がある。
このほか,都市内の緊急輸送の需要が増加していることに対応して,オートバイを活用し,交通混雑を回避して,時間指定のニーズに応えようとするものもある。オートバイによる輸送事業を比較的古くから行っている専業者もあるが,トラック事業者の参入が本格化したのは61年になってからである。
一方,引越運送についても,従来からの輸送サービスの向上を図るのみならず,家具の防虫,不用品の廃棄,冷暖房機具の取付け,取外しといった付帯サービスを併せて提供するようになってきている。
また,国際物流の分野においても,企業間の書類やサンプルの急送を中心に著しい進展を示してきた国際宅配便のネットワークを,一般消費者が外国の製品を個人輸入する際に利用するシステム(国際産直システム)に応用したり,国際引越運送について,トランクルームサービスと連携させたり,海外生活の情報提供やコンサルティングといったサービスを併せて提供するといった例が目立つ。
なお,住宅内の当面使用しない荷物を過疎麺域等に保管し,必要に応じて宅配便等で出し入れを行う「フレイトビラ構想」が提唱されている。これは,既存の消費者物流サービスを応用することにより,新しい消費者物流サービスを創出し,住空間の拡大による豊かな都市生活を実現しようとするものであり,今後の展開が期待されている。
注) POSシステム:Point of Salesシステムの略で,販売時点情報管理システムと呼ばれ,光学式自動読み取り方式のレジスターにより,単品別に収集した販売情報や仕入れ,配送などの段階で発生する各種の情報をコンピュータに送り,各部門がそれぞれの目的に応じて有効利用できるような情報に処理,加工し,伝送するシステム
|