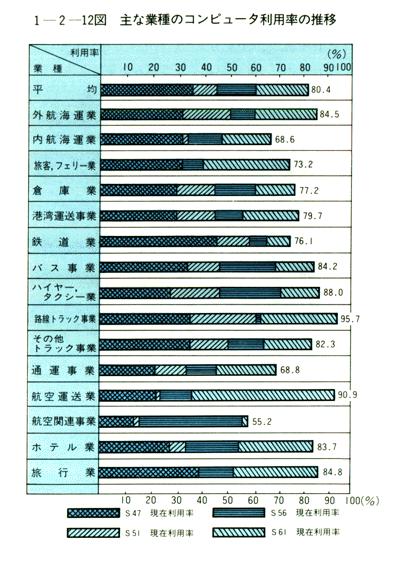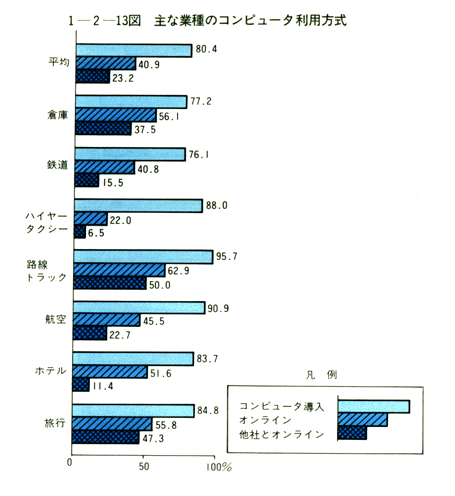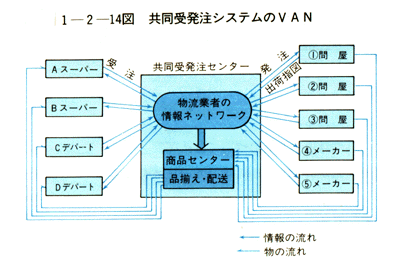|
3 情報化の進展と運輸
(1) 情報化の必要性
(運輸産業にとっての情報化のメリット)
近年,運輸産業における情報化が重要な課題となっているが,情報化を推進することは,運輸産業にとって次のようなメリットがある。
① 安全性の確保
新幹線のコムトラック注1)等の運行管理システムの導入などにみられるように,輸送の安全性の向上が図られる。
② 運輸サービスの向上
タクシ事業においてAVMシステム注2)を導入したことにより,配車待ち時間が減少したこと,宅配便等の高度なサービスの拡充が図られたこと等,情報化により利用者サービスの向上が図られる。
③ 事業の効率化
運輸事業分野での事務の合理化・事業の効率化が図られるほか,給与計算・経理・財務等の一般事務分野での省力化が図られる。
④ 需要の喚起
情報化の推進による運輸サービスの向上の結果,売上の拡大が図られるほか,新規分野の需要が創出される。
例えば,マルス注)の導入によって,それ以前は手作業だった座席予約の業務が機械化され,事務の効率化が図られたのみならず,二重予約等のミスの防止,予約・発券の待ち時間の減少等利用者サービスの向上も図られた。
このように情報化は運輸産業にとって大きなメリットを持つものであり,運輸産業が良質で安価なサービスを提供していくためには,情報化に積極的に取り組んでいくことが不可欠である。そのため,運輸産業においては,早くから多くの情報システムが開発導入されており,今後ともその推進を図っていく必要がある。
(経済社会の変化と運輸の情報化)
運輸産業の情報化の推進は,情報化のもたらすメリットという観点からのみならず経済社会の変化への対応という観点からも必要とされている。
我が国においては経済社会のサービス化・ソフト化が急速に進展し,産業構造変化が進んでいる。また,所得水準の向上,余暇の増大等を背景として,国民の意識やニーズも多様化・高度化している。このような状況に対応するため,各産業分野で高付加価値化・知識集約化に努めるとともに,新規事業分野の開拓が求められており,このためにも物流情報ネットワーク化等の運輸産業の情報化の推進の必要性が高まっている。
(2) 運輸産業の情報化の動向
(情報化動画の概観)
現在,運輸産業の各分野で情報化が進展しているが,その進展は各分野で必ずしも一様ではない。
運輸産業における情報化は,マルスが35年に導入されたこと等からもうかがえるように人流の分野で先行した。しかし,近年は物流分野の情報化の進展が著しく,POSシステム,貨物追跡システム,受発注オンラインシステム等が導入され,このような情報化の進展が,宅配便の進展,産地直送等のニューサービスの形成,物流業者の商流分野への進出等,物流業界に極めて大きな影響を与えている。
一方,人流の分野においても,近年メディア・ターミナル注1),ホテル総合情報システム注2)等にみられるように,利用者に対する情報提供システムの構築が進められている。
(業種別の情報化動向)
運輸省では,運輸関連企業の情報化動向について,資本金5,000万円以上の企業を主たる対象として,61年度に実態調査を行った。
集計対象企業のコンピュータ利用率についてみると, 〔1-2-12図〕に示すとおり,80.4%が何らかの形でコンピュータを利用しており,56年度調査より約20%増加しており,運輸関係事業者におけるコンピュータ利用が着実に伸びていることがうかがえる。
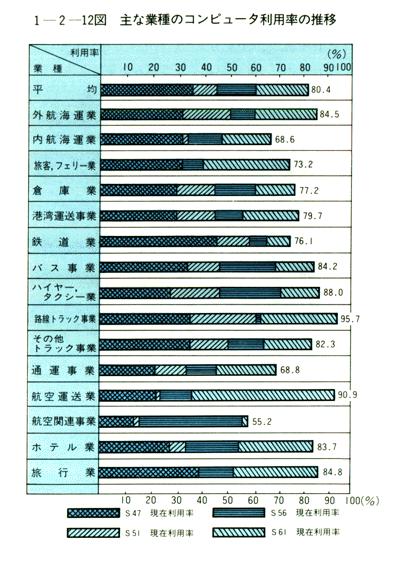
業種別の利用率では,路線トラック事業,航空運送業,ハイヤー・タクシ業旅行業等の利用率が高い。路線トラック事業,ハイヤー・タクシー業においてコンピュータ利用率が高い理由の一つとしては,コンピュータを日報からの転記,加算や乗務員の給与計算等の業務に利用していることが挙げられる。
コンピュータ利用方式については, 〔1-2-13図〕に示すとおり,集計対象企業のうち40.9%が何らかの形でオンライン処理を行っており,前回調査の16.9%から著しく増加している。オンライン化率の高い業種としては,宅配便の貨物追跡管理や配送管理等の輸送情報管理業務に利用する路線トラック事業,集荷・保管時の輸送情報管理業務に利用する倉庫業,予約発券業務に利用する旅行業等が挙げられる。
また,他社とオンライン処理をしている企業は全体の23.2%となつており、同業他社と運送ネットワークを形成している路線トラック事業,運送・宿泊機関の予約・発券業務を行う旅行業等が他社とのオンライン化率が高い。
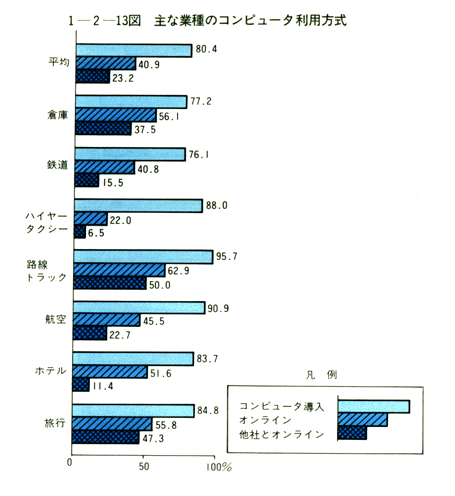
次に,コンピュータの具体的利用方式としては,オンライン処理を行っていないコンピュータは,主に給与計算・経理・財務等の一般事務管理,販売在庫管理等に利用されており,自社内でのオンライン処理を行っている場合は,販売在庫管理,一般事務管理,受発注管理などに利用され,他社とオンライン処理を行っている場合は,販売在庫管理,受発注管理,輸送情報管理などに利用されている。
(3) 情報化の進展が運輸産業へ与える影響
情報化の進展は運輸産業に広範な影響を与えているが,以下において運輸産業の新規事業分野への進出,運輸産業の構造変化,情報化に伴い生ずる問題点に焦点をしぼって述べることとする。
(運輸産業の新規事業分野への進出)
情報化の進展により,宅配便等の高度な運輸サービスの拡充が図られたのみならず,情報化を進める過程で形成された情報ネットワークの活用等により,運輸事業以外の新たな事業分野に進出する事業者も現れている。例えば,物流業者のカタログ販売等の無店舗販売への進出,航空事業者のオンライン予約発券ネットワークシステムを活用した情報提供・通信販売事業への進出,鉄道事業者の通信事業への進出等が挙げられる。
このうち鉄道事業者については,国鉄を中心として設立された(株)日本テレコムが62年9月から電話サービスを開始したのをはじめとし,他社においても駅等の交通ターミナル,鉄道線路敷などの運輸関係施設を活用して,CATV事業やビデオテックスによる情報提供事業等に着手している。
(運輸産業の変化)
情報化の進展により,新たな事業分野への展開が進められているのみならず,運輸事業の機能・役割が変化してきている事業分野も現れてきている。例えば,物流部門においては,多頻度・少量・ジャストインタイムの物流が求められており,メーカー,問屋,小売店等の荷主サイドで受発注のオンライン化,POSシステム化,生産・販売・物流のネットワーク化等の情報化が進められている。また,物流業者に対しても,物の輸送と保管だけでなく,届け先での商品販売情報,クレーム情報等を荷主サイドに提供するなどの販売促進サービスも求めるようになってきている。
物流業界では,このような荷主サイドの情報化とニーズの変化に対応するため,主に荷主の端末を設置し,荷主のネットワークに参加し,荷主の物流情報システムを支援するという形で情報化が進められている。しかし,一部物流業者においては, 〔1-2-14図〕のとおり,自ら情報ネットワークを形成し,物流VAN事業に進出しているところもある。
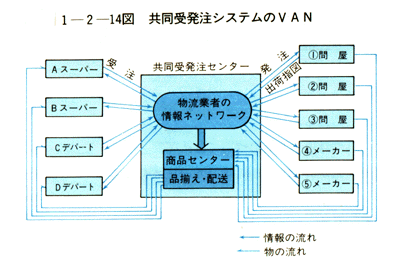
今後このような動きが進めば,物流業者は物流のみならず商流・情報サービス機能も併せ持ち,総合的なサービスを提供することとなろう。
(情報化に伴い生ずる問題点)
このように,情報化は運輸産業にとって,新たな事業展開を可能とし,その事業基盤の強化,事業の活性化に寄与するものであるが,一方,情報化の進展により新たな問題が発生する可能性がある。
一例として,情報化推進による費用の増大が挙げられる。情報化を進めるためにはコンピュータ導入経費,ソフトウェア開発,要員経費等のハード・ソフト両面で多額の費用を必要とし,特に中小企業においては企業経営を圧迫する恐れがある。また,情報化を進め,競争力を強化した企業と情報化対応が困難な中小企業等との格差が広がる可能性がある。このような問題に対処するためにも,人材育成等中小企業の情報化推進のための施策の実施が必要となっている。
(4) 新しい情報化の動き
(ネットワーク化の進展)
情報化はコンピュータの導入,企業内のオンライン化,企業間のオンライン化,そして企業間,異業種間を結ぶネットワーク化へと発展しつつある。ネットワーク化の一つの例が前述の貨物流通ネットワークであるが,このようなネットワーク化により情報の収集,処理,伝達を一層容易かつ迅速に行うことができ,運輸活動の効率化,利用者サービスの向上に寄与することから,ネットワーク化を推進する必要がある。
その一環として,運輸省では,海貨業者,検数,検量業者,船会社をオンラインで結び,港湾貨物に係る情報の伝達,交換を行う港湾貨物情報ネットワークシステム(SHIPNETS)の整備を推進している。船積貨物の輸出手続き業務においては,従来は,多業種間を数多くの情報が書類の搬送や電話連絡の形で行き来していたが,同システムを整備することにより,これらの情報がオンラインで伝送されるようになり,情報伝達の迅速化,データの相互利用によるデータ入力作業の省力化と入力ミスの防止等が図られる。同システムは,61年4月に京浜港において本格稼働したのをはじめとし,大阪,神戸,名古屋港においても導入されつつある。
(国際ネットワーク化の動き)
ネットワーク化は,国内のみならず,国際間においても着実に進展しつつある。例えば,人流の分野においては,世界各国の航空会社のシステムと接続し,各航空会社の航空券の発券,運賃計算,ホテルの予約,フライトスケジュール等の旅行関連情報の提供などの機能を有する日本航空(株)のマルチ・ジャパンが61年5月に運用開始されるなど,国際オンラインネットワークシステムの構築が進められている。
また,物流の分野においても,国際複合一貫輸送の進展等に対応し,事務処理の効率化,サービスの向上を図る必要から,貨物追跡システム,受発注管理システム等の自社内国際ネットワークシステムが構築されつつあるが,今後,外国企業とのネットワーク化が進められることとなろう。
(地域における情報化の推進)
運輸関係情報の中には,気象情報,交通情報,観光情報等地域の経済社会活動においてニーズの高い情報が多いことから,これらの情報を地域のニーズに的確に応えて提供する情報システムの開発・整備を進める必要がある。
この一環として,積雪地帯における交通関係情報提供システム整備に資するため,運輸省では,62年度においては,富山県をモデル実験地に選定し,気象情報や公共交通機関の実運行状況の情報等を提供するシステムのモデル実験を行っている。
(気象情報サービス)
高度情報化が進むにつれ,気象情報についても,利用者の個別ニーズに対応したきめ細かい情報の提供が求められている。このため,気象庁では,アデス注)と呼ばれる大型コンピュータからなる全世界を対象とする通信システムなどにより,世界各国から集められる膨大な各種気象データの処理及び大型コンピュータによる数値予報と予報官の高度な知識・判断によって作りだされた情報などの内容の充実・高度化を図るとともに,必要な地域に,必要な時刻に伝達するよう,的確な気象情報の提供に努めている。
また,アデスからは,気象観測データ,予・警報,その他の情報が,防災機関,報道機関,気象事業者等に分岐提供されている。気象事業者においては,利用者の多様なニーズに応じて,これらの情報を迅速に処理・加工し提供するために独自の気象情報提供システムを整備したり,ビデオテックス,CATV等ニューメディアによる情報提供を行っている。
例えば,(財)日本気象協会のマイコスシステムは,全国ネットワークを保有する代表的な気象情報提供システムであり,中央気象情報サービスセンター及び地域気象サービスセンターを通じ,各地の利用者のニーズに応じた各種気象情報のオンライン即時サービスを実施している。
注1)コムトラック(COMTRAC;Computor Aided Traffic Control):列車の運行状況に関する情報を収集,処理し,自動的にポイントの切り替え等の進路制御等を行う新幹線の運転管理システム
注2)AVM(Automatic Vehicle Monitoring System):稼動中のタクシーの状況(現在位置,実車・空車の別)を自動的に配車司令室のパネル面に表示させ,迅速かつ効率的な配車を可能とする車両位置等自動表示システム
注) マルス(MARS;Magnetic electronic Automatic Reservation System):JR旅客会社で利用しているオンライン予約・発見システム
注1) メディア・ターミナル:交通ターミナルにビデオテックス,CATV等のニューメディアを設置し,各種情報を提供することにより,交通ターミナルを地域における情報拠点とするもの
注2) ホテル総合情報システム:ホテル内のCATV網等により,宿泊客等に各種情報を提供するシステム
注) アデス(ADESS;Automated Data Editing and Switiching System):国内外の気象データを収集,編集し,各気象機関に自動的に伝送する気象資料自動編集中継システム
|