|
4 運輸技術の開発
経済社会環境や国民意識の変化に伴って,運輸技術開発に対する要請にも新たな要素が加わってきている。運輸機関は,その公共的性格から,経営の効率化,利便の向上,施設建設の低コスト化,省エネルギー,安全の確保,公害の防止等広範な要請を受けており,そのための技術開発が常に求められている。これに加えて,最近においては,国際的に調和のとれた経済社会の達成のための経済構造調整の必要性が認識され,国内的にも,社会資本の整備等による豊かな国民生活の実現や需要構造の変化に見合った産業構造の円滑な転換が求められている。さらに,生活水準の上昇に伴って,国民の意識も,従来にも増して,日常生活における安心感や安全性を求める方向に変化してきている。このため,運輸技術についても,このような要請に対応した開発が必要となっている。
上述したような運輸技術に対する新しい要請を踏まえ,以下では,現在行われている技術開発の例について,①豊かな国民生活の実現のための技術開発,②産業構造変化への円滑な対応をめざした技術開発,③安心で安全な国民生活の実現のための技術開発に分けて具体的に記述する。また,運輸における人工衛星の開発・利用についても記述する。
ア 豊かな国民生活の実現のための技術開発
① 磁気浮上方式鉄道
61年度においては宮崎実験線の電源強化を行い62年2月には2両編成での有人走行による時速400㎞の走行に成功した。また,3月には将来の営業用車両の原形であるプロトタイプ車が完成した。将来における短距離システムの実用化のためには,建設・運営コストの見極め,機器の安定性の確認異常時における安全対策の検討等残された技術的課題の解決が必要であり,今後これらの課題解決のために,プロトタイプ車による走行実験等の積み重ねを行っていくほか,これらの技術開発の進捗状況を考慮しつつ,新しい超高速輸送機関としての輸送特性等の検討を行っていくこととしている。また,62年度以降長距離システムへの対応として,複数変電所間を円滑に走行するために必要な変電所渡り制御装置や,追い越しを可能とするための超高速で通過可能な分岐器の技術開発を行うこととしている。 また,常電導磁気浮上方式鉄道については,現在は(株)エイチ・エス・エス・ティにおいて開発が進められ,60年度の筑波,61年度のバンクーバーにおける国際博覧会でデモンストレーション走行を行い,要素技術の開発の成果を確認した。62年度は,より実用型に近づいたHSST-04型車両を試作している。
② リニアモーター駆動小型地下鉄
リニアモーター駆動小型地下鉄は,トンネルの小断面化,急勾配急曲線走行による低コスト化が可能であり,技術的にはほぼ実用のめどがついている。62年3月からは大阪南港において実験線による実験を開始し,62年度中にメリットの定量的な評価,標準仕様の策定等を行うこととしている。
③ 海洋開発のための技術開発
都市化による土地の供給不定,親水空間に対する欲求の高まりに伴って,沿岸部の海洋スペースの利用は,特に大湾域及び内海に面した大都声周辺を中心に著しく増加している。したがって,今後の海洋利用は沿岸部のみならずより沖合に場を求める必要があるが,沖合の大水深域という厳しい環境において,洋上プラント,海上貯蔵倉庫等の大規模な海洋構造物を建設するためには革新的な技術が必要である。 このため,これまで開発されてきた要素技術を集大成した実物大模型により日本海の山形県沖での実証実験を行い,安全性,信頼性を確認し,その成果を海洋構造物の設計,施工技術の確立のために活用することとし,61年度から5か年計画で海洋科学技術センター等との官民共同研究により「海洋構造物の沖合展開のための開発研究」を進めている。 (港湾技術の開発) 近年,港湾の建設は,大水深,大波浪,超軟弱地盤という苛酷な条件の下で行われるために,これに対処する技術や,建設コストの低減,沖合人工島構想の実現等のための革新的技術が求められている。 こうした要請に応えるため,62年度においては,波力の低減を図ることにより建設コストを下げることのできるマルチセルラーケーソン式防波堤注)及び軟弱地盤域において地盤改良を必要としない軟弱地盤着底式防波堤の現地実験を完了させ,今後,事業化を図ることとしている。また,波のエネルギーを空気エネルギー
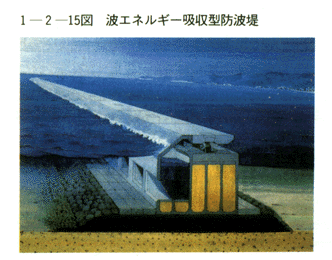
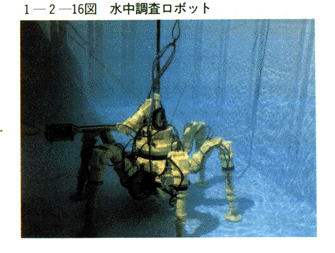
このほかにも,港湾整備の円滑化のために,大型構造物施工法,捨石作業の機械化,大型岸壁の設計法の改良等の技術開発を進めている。また,大水深,軟弱地盤海域において活用が期待される浮体式構造物の技術の確立を図っている。
イ 産業構造変化への円滑な対応をめざした技術開発
① 造船技術開発の推進
(高信頼度知能化船等の研究開発) 57年8月,運輸技術審議会は今後開発すべき重要技術課題として「船舶の知能化・高信頼度化技術」及び「造船のロボット化技術」を取り上げ,それを受けて運輸省では,産学官の協同により研究開発を進めてきている。「船舶の知能化・高信頼度化技術」は信頼性を飛躍的に向上させた「高信頼度プラント」及び海陸一体化と知能化による「高度自動運航システム」の開発により運航経済性の抜本的向上をめざすもので,これまでに実施した基礎実験等に続き,テストエンジンによる検証試験を開始したほか,今後高度自動運航システムの総合シミュレーションの実施を予定している。一方,「造船のロボット化技術」は労働集約型産業である造船業の生産工程を大幅に省力化し生産性の向上を図ろうとするものであり,その研究成果は一部実用に供されている。 また,最近のコンピュータ,情報関連技術等先端基盤技術の革新に対応して,船舶に関する製品技術及び生産技術を高度に情報化,自動化するなど新世代造船技術の研究に積極的に取り組むこととしている。 (次世代船舶の開発) 1990年代に生産が開始されると考えられている北極圏の豊富な石油資源の氷海輸送に必要な氷海可航型船舶の開発に向けて,氷海水槽による模型試験,南極観測船「しらせ」による実測データの収集を実施しているほか,日加科学技術協力の一環として研究者の交流を行っている。 また,省エネルギー化及び高速化された次世代船舶を開発するため,超電導等先端技術の活用による推進性能の飛躍的向上のための調査研究を行っている。 原子力船については,国が定めた基本計画に基づき,日本原子力研究所において,原子力船「むつ」による研究開発を実施している。また,「むつ」による研究の成果を取り入れて,経済性,信頼性等の向上をめざした舶用炉の研究を実施している。
② 物流技術の開発
ウ 安心で安全な国民生活の実現をめざした技術開発
① 自動車の安全・公害防止・省エネルギ技術
また,排出ガスについて,沿道周辺におけるN02に係る環境基準達成率が低い一因としてディーゼル車による影響が指摘されていることを踏まえ,ディーゼル自動車から排出されるNOx,粒子状物質の有害物質を低減させるため,発生要因の解明とその防止策について研究を行っている。 省エネルギーについては,ガソリン自動車に関し,公害防止とも両立する燃費特性改善のための稀薄燃焼化技術や,有害ガスの発生が少ない石油代替燃料であるメタノールのガソリンエンジンへの適用技術等について研究を行っている。
② 鉄道の安全等のための技術
③ 海上交通の安全,海洋汚染の防止技術
海洋開発の進展に伴って種々の大型海洋構造物が登場してきているが,輸送に対する配慮が十分なされていないこと,輸送の場合によるべき技術基準が確立されていないこと等のために,その海上輸送時の事故が極めて多い。このため,海洋構造物の輸送時における複雑な現象を解明し,安全性評価技術を確立するための研究を行っており,様々な環境下での輸送時のシミュレーション手法の開発により,輸送時の安全性の向上が期待できる。 また,原子力発電所の低レベル廃棄物が66年度以降大量に船舶輸送される計画があることを踏まえ,船舶における多種多様な放射性廃棄物の最適な大量積載法及び遮蔽設計法を確立するための研究を行っている。 さらに,現在,小型漁船,レジャー用モーターボート,ヨット等のほとんどが繊維強化プラスチック(FRP)注)製であるが,その物理的耐用年数からここ数年の間にFRP船の廃船が大量に出てくることが予想されるため,二次公害のない,低コストでかつ作業性の良い実用的な処理システムを確立するための研究を行っている。 (港湾技術研究所における研究) 港湾及び航路の計画において,船舶航行の安全性を確保しなければならない。このため,海上交通の実態を把握し,海上交通の特性を明らかにするとともに,海上交通シミュレーション及び水域計画シミュレータを開発し,これらを利用して水域計画手法を確立する必要がある。61年度は水域計画シミュレータの開発を終了し,62年度からはこれを利用して船舶操縦性能を考慮した港湾の形状に関する計画手法の開発を行うこととしている。 水質改善のために海底の有機汚泥の浚渫,覆砂等の浄化対策を円滑に行う必要があり,このための技術開発を行っているほか,水質改善効果の予測シミュレーションの改良を実施している。また,新しい海水浄化工法として,水生植物による栄養塩の除去を目的としたリビングフィルター注)に関する研究を行っている。 (海上保安試験研究センターにおける研究) 産業の発展に伴う新規物質の増加に対応し,海洋汚染の監視取締りを的確に行うため,61年度から3年計画で海水中に溶存する複数の新規物質等を同時かつ迅速に識別する手法の開発に関する研究に着手した。
④ 航空機の安全運航のための技術
特に,電子航法研究所では,従来のILS(計器着陸システム)に比べて高精度で多様な進入着陸が可能なMLS(マイクロ波着陸システム)注),航空機間のデータ通信によをり衝突の危険性を警告し回避するCAS(衝突防止装置)などの研究開発を推進するとともに,61年度からは新たに,増大する航空交通量に対応した管制のあり方を研究する高密度交通空域の設計評価手法の研究,高信頼性が要求される多数の航空保安無線施設を効果的に保守するための障害発生予測技術の研究等に着手した。
⑤ 地震予知,気象観測技術
気象庁では,「直下型地震予知の実用化に関する総合的研究」を59年度から5か年計画で進めており,61年度には,60年度に引き続き前兆現象資料の分析・評価を行い,異常判定の基準作成に着手するとともに,観測機器の特異地点への設置及び研究観測を続けている。 (気象変動の解明等をめざす研究) 気象庁では,62年5月より気象研究所に気候研究部を設置し,異常気象・気候変動の解明及び長期予測精度向上を図るために,スーパーコンピュータを利用した大気大循環のシミュレーションモデルの開発等を進めている。また,異常気象・気候変動に大きな役割を果たしている雲と放射について,62年度より4年計画で「雲の放射過程に関する実験観測及びモデル化の研究」を開始した。これらは,世界気象機関等による世界気候研究計画これに対応する我が国の測地学審議会の建議に沿うものである。 (天気予報の精度向上のための研究) 気象庁では,天気予報の精度向上のため,61,62年度に導入するスーパーコンピュータを用いて,従来の北半球のみの資料に基づく予報から南半球も含めての資料による予報や新しい台風モデルの採用などを計麗し,実用化のための研究を進めている。また,週間天気予報で日毎の気温を予測する技術の開発を進めている。
エ 人工衛星の開発・利用
(気象衛星による観測手法の研究) 静止気象衛星「ひまわり3号」は,東経14O度の赤道上空で運用され,世界気象監視計画(WWW)の一環としても活躍している。「ひまわり3号」の資料は,我が国のみならずアジア・オセアニアの19か国で受信・運用されるなど,各国の気象業務に多大の貢献をするとともに,国際衛星雲気候計画(ISCCP)等国際的な気候資料の整備にも不可欠となっており,今後ともその安定的運用が望まれている。このため,観測機能の高度化,信頼性の向上が必要であり,現在,64年度に打ち上げる静止気象衛星4号(GMS-4)を開発中であるが,さらに,これに続くGMS-5の開発についても検討を開始した。 また,現在,海面水温,雲頂高度等の測定精度の向上を図るため,データ処理方法の改良開発に関する研究を実施しているほか,将来の衛星用搭載センサ及びそれによる観測法の研究も推進している。 (衛星を用いた航行援助実験) 現在,地上からの電波見通し距離外にある洋上減等における航空交通管制は低品質の短波通信に頼らざるを得ず,大きな制約を受けている。これを抜本的に解決するとともに,船舶の測位,捜索救難に活用するため,衛星を利用した通信・測位技術等の開発をめざして,62年8月に打ち上げられた技術試験衛星「きく5号」を用いた航行援助実験の計画を進めている。この計画は運輸省,郵政省及び宇宙開発事業団の共同研究として進められているが,この中で電子航法研究所は,衛星搭載用中継機の開発,航空機搭載装置の開発,地上局設備の開発等62年度から予定されている本格的な衛星実験の準備を進めている。 このうち特に航空管制への利用をめざした通信・測位実験は,航空衛星の早期導入を目指すICAOをはじめとする世界の民間航空界から注目されている。 (多目的な衛星システム) 以上のように,運輸省では,様々な面で人工衛星の開発・利用を進めてきているが,近年,これらの行政上のニーズに加え,測位,移動体通信等民間におけるニーズも高まってきており,このような様々なニーズを効率的かつ経済的に満たすための大型で多目的な機能を有する衛星システムの実現が求められている。 このような状況のなかで,62年6月,運輸技術審議会に「運輸における宇宙技術開発のあり方」について諮問を行い,同年9月に「衛星利用ニーズ及びこれに対する技術開発の動向にかんがみ,運輸に関する多目的な衛星システムの開発は十分検討に値するものであり,可及的速やかにその可能性を明らかにすべく,検討に着手すべきである。」との中間答申がなされた。運輸省においては,今後,この答申を踏まえつつ,その調査研究を行っていくこととしている。
注) マルチセルラーケーソン式防波堤:水平方向に作用する波力を,ケーソン内部に設けられた多段の曲がり斜面により鉛直方向の成分に変換し,滑動や転倒に対する抵抗力に利用する防波堤に変換することにより波力及び反射率を低減させるとともに,変換したエネルギーを用いて発電もできる波エネルギー吸収型防波堤 〔1-2-15図〕の現地実証実験のための設計に着手する。さらに,大水深域など危険な環境に対処するための水中調査ロボット 〔1-2-16図〕の水中仕様機を完成させ,62年8月に水槽実験を行い,12月には実海域実験を行うこととしている。
|