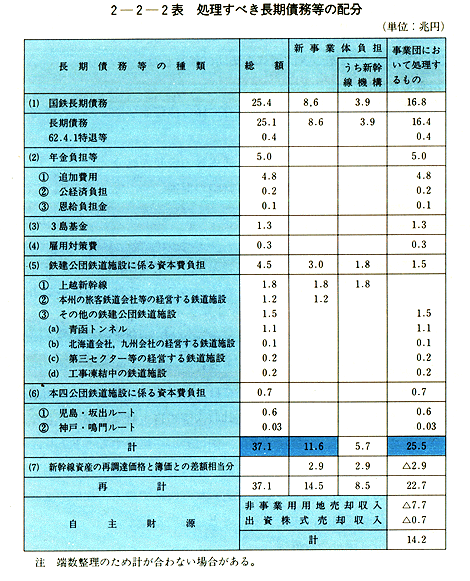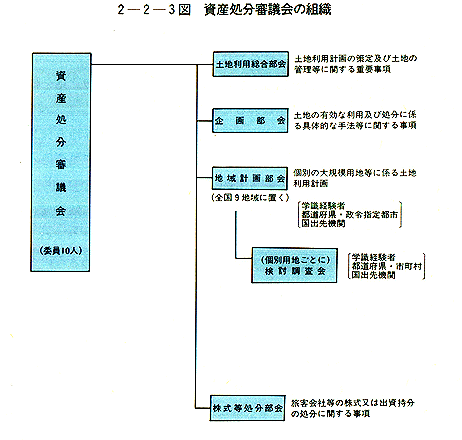|
2 今後の課題
62年4月1日に国鉄は,日本国有鉄道清算事業団法(以下「清算事業団法」という。)に基づき,清算事業団に移行した。
清算事業団は,
(i) 国鉄の長期借入金及び鉄道債券に係る債務並びにその他の債務の償還及び利子の支払
(ii) 清算事業団に帰属した土地・株式等の資産の処分
(iii) 再就職を必要とする職員の再就職の促進
等の業務を行う特殊法人である。
(1) 長期債務等の処理
国鉄長期債務等については,新事業体の健全な経営に支障が生じない範囲で旅客会社等に承継させ,残るものについては,清算事業団に帰属させて処理することとし, 〔2-2-2表〕に示すとおりその総額は37.1兆円,そのうち11.6兆円を新事業体が負担し,残る25.5兆円を清算事業団において処理することとされている。
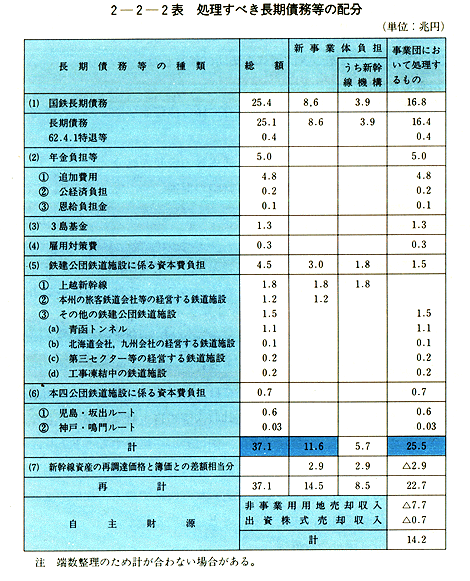
これら長期債務等の処理については,先に述べた61年1月の閣議決定では清算事業団において用地売却収入等の自主財源を充ててもなお残るものについては,最終的には,国において処理することとし,そのために必要な「新たな財源・措置」については,雇用対策用地売却等の見通しのおおよそつくと考えられる段階で歳入・歳出の全般的見通しと併せて検討,決定することとしている。
(2) 資産処分審議会の設置等
ア 資産処分審議会の設置
清算事業団資産の処分の公正の確保と国民負担の軽減を図るため,清算事業団法第20条に基づき資産処分業務に関する重要事項を審議する資産処分審議会が清算事業団に設置された 〔2-2-3図〕。
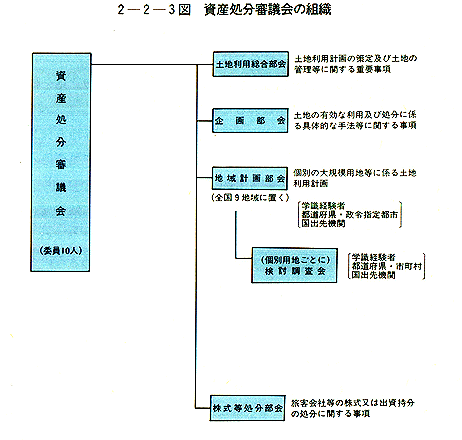
資産処分審議会は,重要財産の処分,資産処分業務に関する基本的な方針の決定等を行う場合に清算事業団理事長の諮問に応じ審議を行う機関である。第1回審議会(4月27日)においては,同審議会の運営規則,部会の設置規則の制定等が行われ,第2回審議会(6月1日)においては,資産処分業務の基本方針,一般業務方法書等が審議の結果了承された。
イ 資産処分業務
土地処分業務については,資産処分業務の基本方針に基づいて進められており,現在,各地方資産管理部の所管地域ごとに置かれた地域計画部会において大規模用地について土地利用計画の策定が進められるとともに,逐次売却準備が進められている。なお,同基本方針の概要は以下の通りである。
(ア) 土地・建物等の資産処分業務の基本方針
① 清算事業団に帰属した土地は,資産処分審議会の意見を聴きつつ計画的に処分を進めるものとする。
② 貨物ヤード跡地等の大規模用地については,関係地方公共団体等の意見を聴いたうえ,資産処分審議会において処分地の土地利用計画の検討を行うものとする。
③ 債務の償還等に有利な場合には,処分に先立って鉄道施設の撤去又は移設及び道路,下水道等の公共施設の整備を進め,必要に応じ用途地域等の変更を経たうえで処分を進めるものとする。
④ 土地の処分契約は,原則として公開競争入札により行うものとし,地価高騰地域においては,不当な地価の高騰の防止のため,必要な条件を付するものとする。
公共公益目的に使用するため,国,地方公共団体,その他の公法人と契約を締結する場合等については随意契約によることができるものとするが、用途指定等の必要な条件を付するものとする。
⑤ 売却が困難な土地についてはその有効利用の方法,処分までに長期間を要する土地については処分するまでの間の暫定利用の方法の検討を進め,資産の活用を図るものとする。
⑥ 地価を顕在化させない土地の処分方法の導入の可能性について検討を進めるものとする。
(イ) 株式等の資産処分業務の基本方針
① 旅客会社及び貨物会社の株式の処分については,個々の会社の経営状態を見極めつつ,市場動向等にも十分に配慮したうえで,適正な価額により行うものとする。
② 帝都高速度交通営団に対する出資持分(以下「営団出資持分」という。)は,政府からの貸付金の償還に代えて,政府に譲渡するものとする。
ウ 営団出資持分の譲渡等
清算事業団の保有する額面310億円の営団出資持分については,日本国有鉄道改革法等施行法附則第24条により,適正な価額で政府に譲渡するものとされているが,その評価については,第3回資産処分審議会(9月16日)において審議が行われた結果,同審議会より7,088億円とすることが適当である旨の答申を得,答申に従い9月30日に譲渡が開始された。
エ 緊急土地対策の推進
土地処分については,62年10月16日に臨時行政改革推進審議会答申を受けて閣議決定された緊急土地対策要綱に従い,国鉄改革のための施策との整合性に留意しつつ,当面,地価が異常に高騰しつつある地域での清算事業団用地の売却を原則として見合わせることとした。また,地価を顕在化させない土地の処分方法を精力的に進めていく等の対策を推進していくこととし,10月20日には,資産処分審議会に置かれた企画部会において,地価を顕在化させない土地の処分方法についての検討が開始された。
(3) 清算事業団職員の再就職の促進
ア 国鉄等職員の再就職対策の経緯
国鉄等職員の再就職対策については,60年12月の閣議決定「国鉄余剰人員雇用対策の基本方針について」,61年9月の閣議決定「国鉄等職員再就職計画について」,また同年12月に施行された「日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法」(以下「再就職促進法」という。)に基づいて公的部門を始め各分野の協力の下に対策を進めてきた。この結果,61年4月1日に在籍していた277,020人の国鉄職員については,62年4月1日までに公的部門に21,020人が再就職し又は再就職が内定したほか,一般産業界に12,400人,関連企業に10,450人が再就職する等により計39,090人がいわゆる希望退職をし,さらに一般退職により8,580人が退職し又は退職が予定されるなど順調に対策が進められてきた。
また,新会社等の承継法人への採用数は,予想以上に希望退職者があったこと等により,当初予定を14,350人下回る200,650人にとどまったが,再就職対策が順調に進んだ結果,62年4月1日現在で再就職先未定のまま清算事業団に移行した職員数は,北海道及び九州地域を中心に7,630人となった。
イ 再就職促進基本計画の策定
政府は,今後における清算事業団職員の再就職の促進のための基本となるべき計画として,62年6月5日,再就職促進法に基づき,「日本国有鉄道清算事業団職員の再就職促進基本計画について」を閣議決定した。この閣議決定においては,今後の再就職対策については,再就職先未定の清算事業団職員が雇用情勢の厳しい北海道及び九州地域に集中していることにかんがみ,新会社の行う追加採用によりできる限り多くの清算事業団職員が再就職するようにすることを前提としてそのための必要な措置を講ずるほか,承継法人以外の雇用の場に再就職しようとする清算事業団職員に対して全国的観点から各分野における再就職の機会の確保,清算事業団等における教育訓練等の再就職の援助等の再就職対策を進めることにより,3年内にすべての清算事業団職員の再就職を達成することとしている。
ウ 承継法人の追加採用
再就職先未定の清算事業団職員が雇用情勢の厳しい北海道及び九州地域に集中する一方,新会社の62年4月1日の職員数が承継基本計画に定められた採用予定職員数を下回ったため,運輸省は,両地域の雇用情勢も踏まえて,旅客会社及び貨物会社において両地域の再就職先未定の清算事業団職員を対象に,採用予定数との差の職員数につき速やかに追加採用を行うことを指導した。
この結果,北海道旅客会社及び九州旅客会社は,6月1日に採用予定職員数との差の職員数692人の追加採用を完了し,また引き続き本州3旅客会社,四国旅客会社及び日本貨物会社においても追加採用を実施した結果,935人の清算事業団職員が8月1日付けで各社に採用された。
エ 今後の対策
新会社の追加採用後においても清算事業団に残ることとなった再就職先未定の職員数は,62年11月1日現在で5,430人であるが,今後とも,これら職員個々の希望,能力等を踏まえてきめ細かな再就職対策を講じていく必要があり,このような観点から,再就職促進法に基づき再就職に必要な教育訓練,個別求人開拓,職業紹介等を実施することにより,62年度以降3年内に再就職を希望する職員全員の再就職を図ることとしている。
また,厳しい雇用情勢の下にある北海道及び九州地域においては広域再就職を促進することが重要であり,このため,住宅確保の円滑化,学校の転入学のための情報提供等きめ細かな措置を講じていくこととしている。
(4) 日本鉄道共済年金問題
日本鉄道共済年金の財政問題については,60年度から64年度までの問は,国家公務員共済,日本たばこ産業共済及び日本電信電話共済の3共済の拠出による財政調整事業を行うことにより対応していくこととしていたが,国鉄改革に伴う職員数の減少,年金受給者の増加等により,日本鉄道共済年金財政は極めて厳しいものとなり,新たな対策の確立が必要となった。
この問題については,第103回国会において,政府として「国鉄共済年金については,財政調整5箇年計画の終わる64年度までは,政府として,国鉄の経営形態等の動向を踏まえつつ国鉄の自助努力と国の負担を含め,諸般の検討を加え,支払に支障のないようにする。以上については,61年度中に結論を得,その後できるだけ速やかに具体的立法措置に入ることとする。なお,65年度以降分についてはその後速やかに対策を講じ,支払の維持ができるよう措置する。」旨の統一見解を示したところであり,この見解に沿った各般の措置を検討・実施することにより,将来にわたって日本鉄道共済年金の円滑な支払を維持することが必要である。
このため,61年8月に大蔵大臣,運輸大臣,内閣官房長官及び年金問題担当大臣の4大臣で「日本鉄道共済年金問題に関する閣僚懇談会」を設け,政府統一見解を踏まえた対策の検討を進め,64年度までの対策については,62年3月,同懇談会において,過去の追加費用の見直し及び日本鉄道共済年金の積立金の充当により対応していくことを決定した。 また,65年度以降の対策については,64年度までの対策に引き続き「日本鉄道共済年金問題に関する閣僚懇談会」において検討を行っていくこととしており,政府統一見解の趣旨を踏まえ,できる限り早期に結論が得られるよう適切に対処していく必要がある。
|