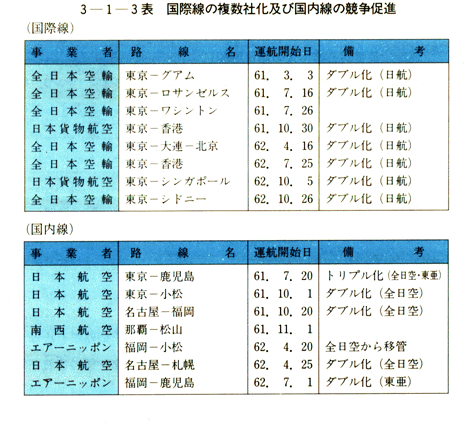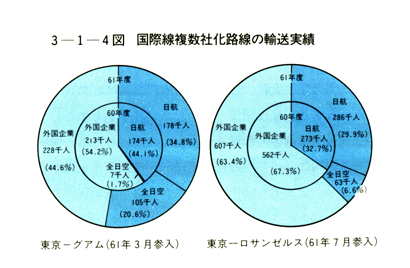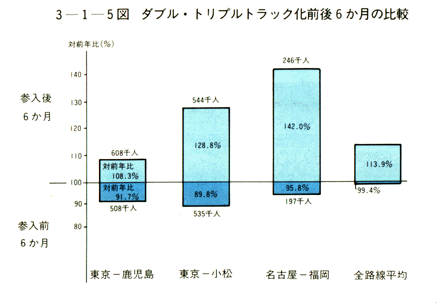|
2 新たな航空政策の推進
(1) 進展する路線展開
(運輸政策審議会答申後の路線展開
61年6月,運輸政策審議会は,安全運航の確保を基本としつつ,航空企業間の競争促進を通じて利用者利便の向上を図ることとする答申「今後の航空企業の運営体制の在り方について」を行ったが,その中で国際線の複数社制及び国内線のダブル・トリプルトラッキングの推進が提言されている。
運輸省としてはこの答申の趣旨に沿って新たな路線開設,増便に努め,航空企業間の競争促進を通して利用者利便の向上に努めてきている。
(国際線の複数社化)
国際線においては,全日本空輸が東京からグアム,ロサンゼルス,ワシントン,北京・大連,香港及びシドニーへ国際定期路線を次々と開設したほか,東亜国内航空が61年9月以降チャーター便の運航を始めた 〔3-1-3表〕。
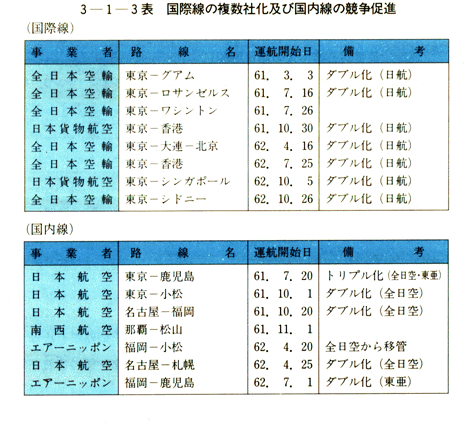
このうち,東京-グアム線においては全日本空輸の新たな参入により日本航空を含めた我が国企業全体の輸送実績が60年度18万人から61年度には28万3千人に伸びており,積み取りシェアも60年度の45.8%から61年度55.4%と大幅に拡大している。これは,全日本空輸が昼間便で参入(日本航空は夜間便のみ)したメリットを生かし,外国企業からの昼間帯利用旅客の転移を促したものとみられる。同様に東京-ロサンゼルス線においても輸送実績は60年度27万3千人から61年度35万人に増加し,シェアも60年度32.7%から61年度36.6%に拡大しており,複数社化による我が国航空企業全体としての国際競争力の向上がみられる 〔3-1-4図〕。
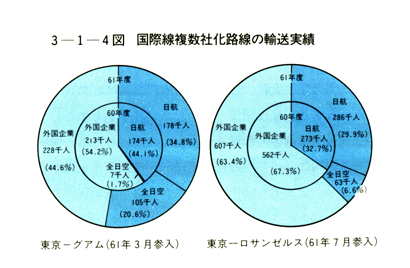
しかしながら,日本人旅客のウェイトの低い東京-ワシントン線においては,全日本空輸のアメリカにおける知名度が低い等の要因もあり,ロードファクター(座席利用率)は低迷している。
貨物についても,日本貨物航空が参入したことにより日本航空との複数社化が図られたが,このうち60年5月に参入した太平洋線においては我が国企業全体の積み取りシェアは,参入前の59年度に42.8%であったのに対し,60年度46.9%,61年度49.2%と,日本貨物航空の便数増に対応してシェアを拡大している。
(国内線のダブル・トリプルトラック化)
国内線については,答申後直ちに以下の基準を策定し,これに沿ってダブル・トリプルトラック化を推進している。
① ダブルトラック化
年間需要70万人以上の路線
ただし,札幌,東京(羽田,成田),名古屋,大阪,福岡,鹿児島及び那覇の各空港間を結ぶ路線にあっては,年間需要30万人以上の路線
② トリプルトラック化
年間需要100万人以上の路線
具体的には,日本航空の参入により東京-鹿児島線がトリプルトラック化され,東京-小松線等がダブルトラック化されている 〔3-1-3表〕。
このうち,61年度においてダブル・トリプルトラック化された3路線(東京-鹿児島,東京-小松,名古屋-福岡)の輸送実績をそれぞれダブル・トリプルトラック化を境にして前後6か月の対前年度比でみると,東京-鹿児島線は91.7%から108.3%(16.6ポイント増),東京-小松線は89.8%から128.8%(39.0ポイント増),名古屋-福岡線は95.8%から142%(46.2ポイント増)に伸びている。これは,事故後の需要回復も寄与しているものと考えられるが,一方,この間の全路線平均の対前年度比は61年10月を境に99.4%から113.9%(14.5ポイント増)となっており,3路線については,このような事故後の需要回復に加え,ダブル・トリプルトラック化により旅客利便の向上及び観光需要の喚起が図られた結果とみられる 〔3-1-5図〕。
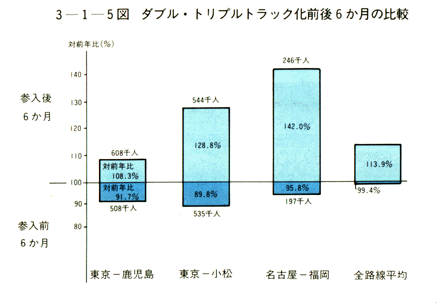
なお,現在は,東京・大阪両空港の空港能力に制約があるため,両空港発着路線のダブル・トリプルトラック化は困難となっているが,63年7月に東京国際空港の沖合展開第一期工事が終了し,発着枠も増える予定であるので,その際にはダブル・トリプルトラック化の推進等も含め発着枠の適切な活用を図っていくこととしている。また,中小航空企業の経営の安定化と利用者利便の向上の趣旨から南西航空の那覇-松山線及びエアーニッポンの福岡-鹿児島線の開設を認めている。
(2) 日本航空の完全民営化
(完全民営化までの経緯)
日本航空株式会社は,戦後我が国の民間航空が立ち後れていたなかで,我が国が速やかに自主的な国際航空運送事業を開始するために28年に政府の出資を得て設立された特殊法人である。同社は今日まで国際線及び国内幹線における定期航空運送事業を経営してきたが,同社設立時から今日までの間に航空輸送は著しい発展を遂げ,我が国航空企業も大きく成長し,その経営基盤も強化された。この結果,同社は世界有数の航空企業となり,特殊法人としての同社の設立目的はおおむね達成されたとみられるに至った。
こうした状況に対応し,運輸政策審議会及び臨時行政改革推進審議会の答申等を踏まえ,政府は61年12月30日,「日本航空株式会社の自主的かつ責任ある経営体制を図るとともに,航空企業間の競争条件の均等化を図るため,特殊法人たる日本航空株式会社を昭和62年度において廃生し,完全民営化することとし,所要の法律案を今国会に提出する。」旨の閣議決定を行った。
この閣議決定に従い,62年3月,第108回国会に日本航空株式会社法を廃止する等の法律案が提出され,第109回国会において9月4日に成立した。日本航空は11月17日に臨時株主総会を開いて定款を変更し,翌日の11月18日に同法は施行された。
(完全民営化の内容)
日本航空株式会社法を廃止する等の法律案の概要は,①日本航空株式会社法を廃止すること,②航空法の一部を改正して,定期航空運送事業者について外国人等の株式取得による免許の失効を防止するための規定を整備すること等である。
これにより,従来の日本航空への政府出資,社債発行限度の特例,債務保証等の助成がなくなる一方,役員人事,社債の発行,定款の変更等についての運輸大臣の認可等の規制もなくなることとなる。
また,政府保有株式については,62年度に売却することとして売却収入を予算計上している。
なお,完全民営化後は日本航空の長期債務について政府保証等もなくなるため資金調達手段が緊要な課題となっていたが,62年度予算において,日本航空も含め,我が国航空企業を対象に競争促進の下において航空機材の円滑な導入を図るため,開銀及び輸銀による長期・低利の航空機購入融資制度が新たに創設された。
(3) 航空運賃問題への対応
(航空運賃問題懇談会の開催)
最近,国際航空運賃の分野においては急激な円高傾向に伴う方向別格差等が,また,国内航空運賃については割引制度のあり方等が問題とされている。さらに,競争促進政策における航空運賃のあり方等航空運賃に関する検討課題が多いことから,航空運賃全般について問題点の検討を行うため,61年11月から航空局において,学識経験者等の参加による航空運賃問題懇談会が開催され,62年9月に報告書がまとめられた。運輸省は今後,当該報告書の趣旨に沿って個別運賃問題に対応していくこととしているが,報告書の主要な内容とこれに対する対応は以下のとおりである。
(国内航空運賃)
① 今後の国内旅客運賃の在り方としては,遠距離逓減を基本としつつ路線距離,使用機材,需要の動向等を勘案し,同じような態様の路線については,同じレベルの運賃が適用されるような整合性のある運賃体系をめざすべきである。このような調整は,通常,全路線について調整を図りうる運賃改定の機会に逐次行うことが適切である。北海道方面について,運賃が割高となっている路線(特に東京-釧路,帯広,旭川,女満別)については,59年の経路の短縮に係るコスト分に限ってでも運賃の見直しを早急に検討することが適切である。
② 割引運賃については,弾力的に導入していくこととし,需要の季節波動や曜日波動に合わせた割引,個人向け,小グループ向けの割引制度の拡充を図ることが適当である。
(国際航空運賃の方向別格差の是正)
① 国際航空運賃は発地国通貨建てで設定されているが,60年以降の円高により,相手国発運賃を円換算した額が日本発運賃に対し相対的に安くなってきた。このいわゆる「方向別格差」の現象は,変動相場制のもとでは不可避的なものであるが,今後とも大幅な方向別格差が長期間にわたって生じる場合には,企業の経営状況にも配慮しつつ格差の縮小に努めるべきである。
航空企業間の運賃清算等に用いられているIATAレート(1FCU=1ドル=296円)の問題については,国際航空運賃設定の基準として用いられているため割高になっているとの誤解を招く原因となっているので,制度の見直しのため,運輸省の強力な指導によりこれを推進していく必要がある。
② 国際航空輸送については,今後個人旅行の割合が増えるものと見込まれること等に配慮して個人向け割引運賃の拡充等を検討すべきである。
(運輸省の対応)
① 運輸省はこの報告を受け,北海道道東方面の運賃の引き下げを航空企業に対し指導したところ,道東4路線についてルート短縮に伴う見直しとして各路線1,000円の値下げが12月下旬より実施されることとなった。また,国内線について女性グループ,単身赴任者等を対象とする割引が導入されることとなった。
② 国際線の方向別格差の縮小については62年7月に太平洋線における日本発普通往復運賃の7.4%値下げ,10月には欧州線において個人旅客がバックキャビン(従来の団体席)を利用して安く旅行できる制度を導入したのに引き続き,東南アジア線等についても格差の縮小措置が具体的に検討されている。また,ハワイ向けに回数割引,小人数割弓1等が導入された。
③ IATAレートに関しては,(i)運賃計算単位として,FCUを廃止し米ドル実勢レートを用いる,(ii)各国の通貨変動をSDR(特別引出権)で監視し,IATA本部から方向別格差是正の勧告を行う等を内容とする制度の見直しが航空企業間で合意(IATA協定;64年7月1日実施予定)され,各国政府に認可申請がなされているところである。
|