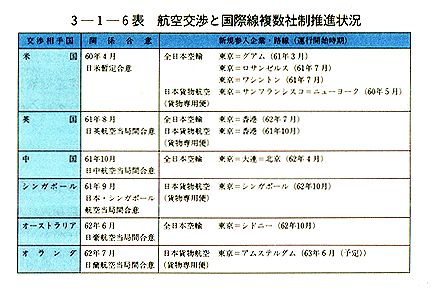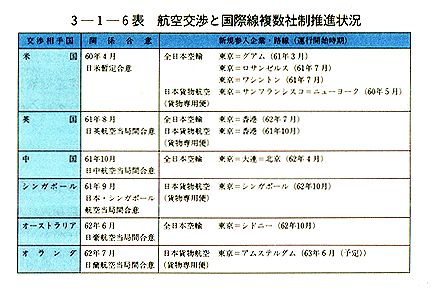|
3 航空交渉の推進
(1) 我が国の国際航空政策
(国際航空の枠組)
現在の国際航空関係の枠組みは,1944年に採択された国際民間航空条約(シカゴ条約)にその基礎を置いている。この枠組みの下では,原則として,国際定期航空運送業務は関係二国間の航空協定に基づいて運営され,二国間に提供される定期航空サービスの路線輸送力,運賃等については双方の国の同意が必要とされるほか,国際不定期航空運送業務は,発着国の政府の規則に従って実施されることとなっている。このため,世界の国際航空輸送量の80%以上を占める定期航空業務は二国間の航空交渉を通じて展開されているほか,近年では,チャーター輸送の発達,各国のチャーター政策の相違等の理由から,航空交渉において不定期航空輸送の問題を取り扱うケースも多くなっている。
(我が国の航空交渉の基本目標)
世界各国の航空交渉に当たっての基本方針は,米国等自由化を標榜する国から,路線輸送力等についての秩序を重視する伝統的な政策をとる国まで多種多様であるが,いずれの国も利用者利便の向上という観点のほかに,自国企業の競争力,地理的条件,観光政策との兼ね合い等といった要素を勘案して,自国の利益を確保するという観点から航空交渉を推進しているのが現状である。
このような環境のもとで,我が国としては,機会均等という航空協定の基本的原則に従って,輸送需要に適合した輸送力の供給を確保することにより,我が国をめぐる国際的な人的交流及び物的流通の促進に向けて努力することを航空交渉の基本目標としている。特に,人的交流の促進については,運輸省として,概ね5年間で日本人海外旅行者を倍増する計画(海外旅行倍増計画)を推進することとしており,この計画を達成するための施策の一環としても,交渉体制を一層強化するとともに,方面別の輸送需要をきめ細かく分析し,各国との交渉を通じ,需要に十分対応できる輸送力の整備を図っていく必要がある。
また,61年6月の運輸政策審議会答申を踏まえ,我が国航空企業全体としての国際競争力,相手国との間の航空政策の調整等に配慮しつつ,わが国航空企業による国際線の複数社制を推進することが新たな交渉課題となった。
(2) 我が国をめぐる国際航空の最近の動き
(航空交渉と航空協定新規締結に向けての動き)
このような観点から,過去一年間(61年9月-62年8月)に,我が国と航空協定を締結している国38か国のうち15か国との間で26回にわたり,我が国航空企業による国際線の複数社制の推進,新規地点の追加,増便取極め等航空関係の拡充を中心に協議が行われ,利用者利便の向上に向けて航空交渉が推進された。
また,我が国の航空市場としての価値の高さから,我が国に対し航空協定締結の申し入れを行っている国は,62年8月現在で39か国にものぼっているが,このうち,オーストリアとの間で,航空協定締結のための第一回の予備的協議が62年8月に開催されたほか,62年6月の橋本運輸大臣のネパール訪問の際に,同国のバンディ観光大臣との間で,航空協定締結のための予備的協議を開始することが合意されるなど,新規の航空協定締結に向けて新しい動きがあったことが注目される。
(日米航空交渉の推進)
日米間においては,航空権益の総合的均衡を図るべく今日まで30年にも及ぶ航空協議が重ねられてきており,その間改善された点は多く,最近でも,60年4月の暫定合意(外交文書の署名・交換は同年5月),61年7月の日本貨物航空の増便に関する了解等により両国間の航空権益の均衡化に前進をみたところであるが,なお是正すべき点が残されている。現在,61年9月に再開された包括的協定改定交渉を継続しているところであるが,今後とも引き続き,双方の航空権益の総合的均衡に向けて交渉を推進していく必要がある。
(国際線複数社制の推進〉
60年の日米暫定合意に基づき,同年5月より,日本貨物航空が貨物専用便の分野における2社目の本邦企業として米国への乗り入れを開始した。この暫定合意は,旅客便の分野においても複数杜の参入を可能とする枠組みとなっており,これが一つの契機ともなり,運輸政策審議会答申(60年12月の中間答申及び61年6月の最終答申)において,我が国航空企業による国際線複数社制の推進という新しい方針が示された。これを踏まえ,日米間において,60年の暫定合意に基づき,全日本空輸が61年3月よりグァムへ,61年7月よりロサンゼルス及びワシントンD.C.へ乗り入れを開始した。
このような状況のなかで,英国との間において61年8月の日英航空当局間合意に基づき日本貨物航空及び全日本空輸がそれぞれ東京=香港路線に参入したほか,中国との関係においても61年10月の日中航空当局間合意により全日本空輸の北京及び大連への乗り入れが実現した。
さらに,シンガポール,オーストラリアとの間で我が国企業の複数社体制が実現したほか,オランダとの間の合意において,複数の本邦航空企業の乗り入れが確保された 〔3−1−6表〕。また,ニュージーランド,タイ,西独,北欧三国等との間で,我が国とこれらの国との航空協定上複数社の参入が認められることが確認されている。
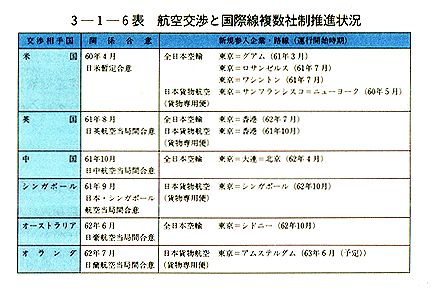
このように,国際線複数社制の推進については,これまでにも一定の成果をあげてきているが,今後も諸外国との航空交渉において,従来からの基本目標に加え,本邦企業全体としての国際競争力の確保に配慮するとともに,相手国との間で航空政策の調整を行う等航空関係全般について配慮しつつ,我が国の複数の航空企業による国際航空路線の運営を可能とする枠組みの形成に向けて諸般の施策を推進する必要がある。
|