|
2 基幹空港の整備
ア 空港建設の進捗状況
このため,59年10月に設立された関西国際空港株式会社は,漁業補償及び環境アセスメント手続きを終え,61年12月2日に飛行場の設置許可,62年1月23日に公有水面埋立免許を得て,62年1月27日,建設工事に着手した。現在,海底の地盤改良工事を含む護岸工事,埋立区域の地盤改良工事及び空港連絡橋工事を行っているところである。
イ 空港計画の概要
なお,関西国際空港の全体構想は,4,000mの主滑走路2本,3,400mの補助滑走路1本,面積約1,200ha,年間離着陸回数約26万回となっている。
ウ 関西国際空港関連施設の整備
空港連絡鉄道(仮称)については,阪和線日根野駅から空港間は関西国際空港株式会社が,南海本線泉佐野駅から空港対岸間は南海電鉄株式会社がそれぞれ建設を行い,日根野駅から空港間は西日本旅客鉄道株式会社が,泉佐野駅から空港間は南海電鉄株式会社がそれぞれ運営を行うこととし,62年11月7日,各社から鉄道事業法に基づく免許の申請がなされた。
エ 今後の進め方
関西国際空港の建設及び運営に際しては,民活会社としての創意工夫を凝らすとともに,環境保全に十分留意し,地元の理解と協力を得つつ進めていくこととしている。
ア 現況と早期完成の必要性
新東京国際空港の現供用施設は既に相当の混雑を呈し,特に旅客ターミナルビルは既に容量をオーバーし,滑走路,エプロン等も60年代半ばには処理能力の限界に達する見込みである。 新東京国際空港には,現在我が国も含め34か国43社の定期航空会社が乗り入れており,新たに39か国から乗り入れ希望があるが,このままでは,今後乗り入れを制限せざるを得なくなり新たな国際摩擦を引き起こしかねない状況となっている。このため,今後とも増大する航空需要に対応するとともに,国際摩擦を回避するためにも,残る2本の滑走路と第二旅客ターミナル等を早期に整備する必要がある 〔3-2-2図〕。
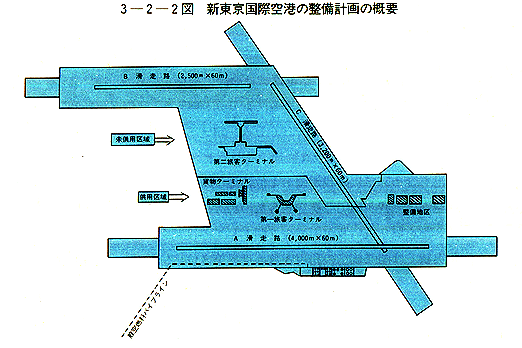
イ 本格工事の推進
しかしながら新東京国際空港は,現在周辺地域にとって不可欠の存在として地元に定着し,特に62年春以降,過激派の暴力排除を求める決議も多数の市町村で行われるなど,空港の早期完成,暴力行為の排除に関する地元の気運は著しく盛り上がっている。 61年11月に閣議決定された,第5次空港整備五箇年計画に基づき新東京国際空港の65年度概成をめざし,新東京国際空港公団では,61年11月以降,警備当局の協力を得て過激派の違法な妨害活動を排除しつつ,将来のエプロン地区注)において本格的な盛土工事に着手した。さらに,空港公団の既取得用地のなかで構内道路,駐車場の整備等可能な工事を着実に進めているところである。
ウ 65年度概成を達成するための課題
(ア) 未買収用地の取得
(イ) 保安警備対策の強化
ア 事業の経緯
本事業は,本空港の首都圏における国内航空交通の中心としての機能を将来にわたって確保するとともに,航空機騒音問題の解決を図るため,東京都が実施している羽田沖廃棄物埋立地を活用し,現空港を沖合に展開するものである。 運輸省では,58年2月,東京国際空港整備基本計画を決定し,その後,航空法に基づく飛行場の施設変更の手続き,東京都条例に準じた環境影響評価の手続きを経て59年1月に工事に着手した。
イ 計画の概要
空港へのアクセスとしては,鉄道については東京モノレールが新ターミナルまで延伸する計画であり,将来的には京浜急行の新ターミナル乗入れも計画されている。道路については,建設中の湾崖道路との取付け,環状8号線の延伸が予定されている 〔3-2-3図〕。
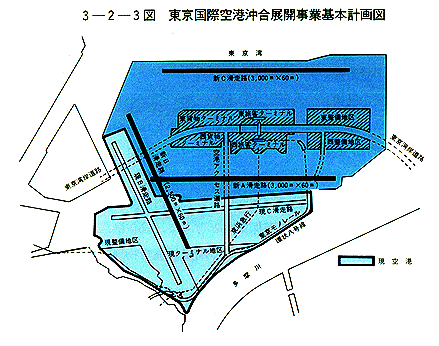
ウ 事業の進捗状況と今後の見通し
〔第1期〕 新A滑走路の供用 〔第2期〕 西側ターミナルの供用 〔第3期〕 新B滑走路,新C滑走路及び東側ターミナルの供用 このうち,第1期については,63年7月に供用開始ができる見通しとなっている。第1期においては,現状の2本の滑走路に加え新A滑走路及び関係保安施設を整備することにより,滑走路処理能力は,現在より年間2万回程度,1日当たり50回程度増加することができるものと見込まれているが,具体の増便については,段階的に行われる。 さらに63年度からは,引続き第2期事業を推進してゆくこととしているが,不等沈下等の対策のため地盤改良や基礎工事に第1期の事業以上に慎重な対応を迫られており,供用開始時期は当初予定より2年程度遅れ67年度後半となる見通しである。
|