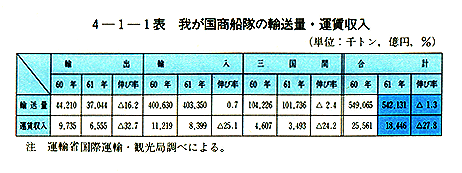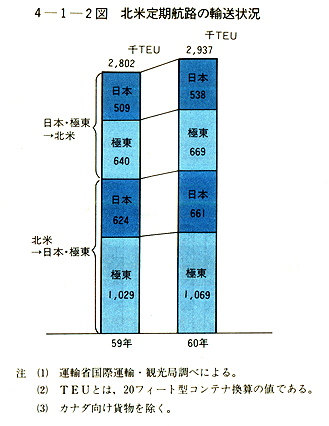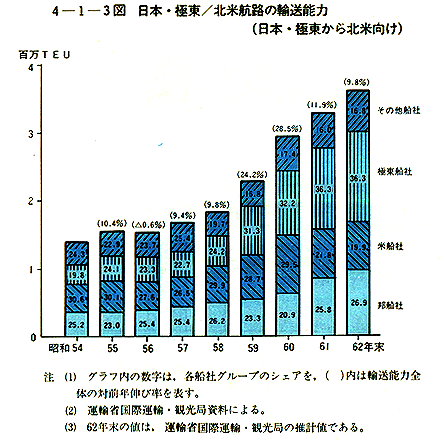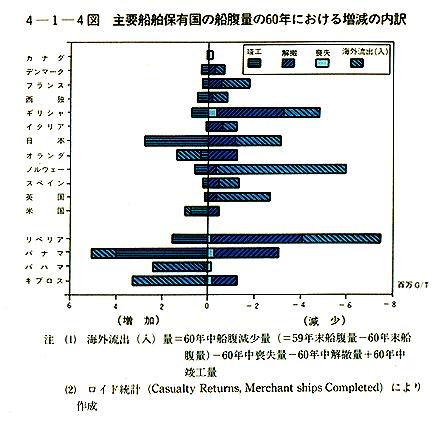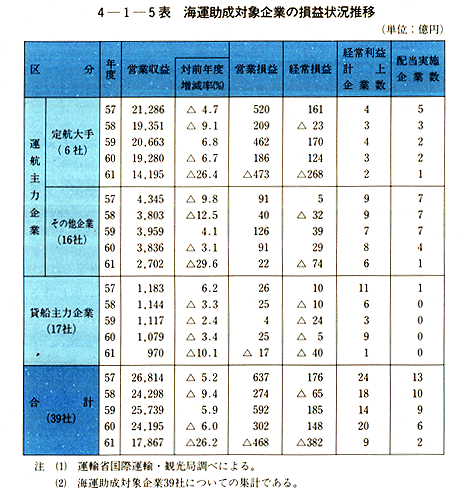|
1 国際海運環境の変化と海運不況の深刻化
(1) 我が国海運をとりまく環境の変化
ア 運賃収入は大幅減
昭和61年の我が国商船隊の活動をみると,輸送量が対前年比13%減の約5億4,200万トンと微減にとどまったのに対し,運賃収入は,各部門での収入の目減りにより対前年比27.8%減の約1兆8,400億円と,輸送量の減を大幅に上回る運賃収入の減少となった 〔4-1-1表〕。
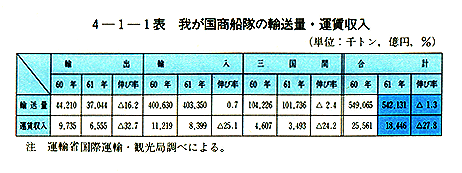
これは,60年秋以来の急速かつ大幅な円高の影響に加えて,近年の集荷競争の激化に伴う運賃水準の低下によるものである。
イ 北米定期航路の現況
なかでも,日本・極東と北米(米国,カナダ〉を結ぶ北米定期航路においては,我が国海運企業は極めて厳しい状況に置かれている。
(北米航路は一大市場を形成)
北米航路は,日本・アジアNICsから北米への製品輸出のルートとして重要な意義を有しており,各船社の輸送体制も同航路を重視する傾向にある 〔4-1-2図〕。このため,同航路は高い成長率(57~60年の輸送能力の平均伸び率19.5%)を達成しつつ世界最大の航路となるに至っている 〔4-1-3図〕。
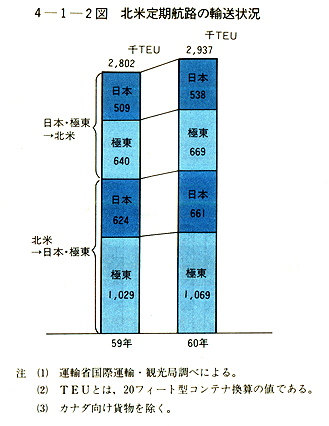
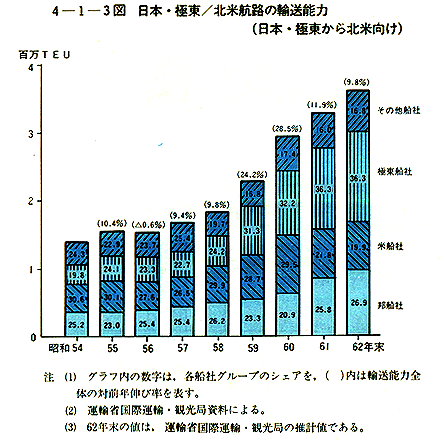
(アジアNICsの台頭と極東貨の比重の増大)
特に最近においては,円高の影響により日本からの輸出が伸び悩んだ反面,アジアNICsへの水平分業が進展したため,極東貨の比重が高まっている(第1章第2節参照〉。邦船社も極東貨への取組みを強化しつつあり,59年には邦船社による日本貨物対極東貨物の比率がTEU(20フィート型コンテナ換算)ベースで71:29であったものが,61年には63:37となっている。
(新海運法により集荷競争が激化)
しかし,同航路は,参入船社が多く,供給過剰傾向にあり,本来運賃調整機能を果たすべき海運同盟の結束力が弱かったがさらに,59年制定の米国新海運法は,同盟メンバーがメンバーのままで同盟運賃以外の低い運賃を設定することを認めたこと及び大口荷主に対する割引運賃制度の導入を認めたことから,集荷競争が激化し,運賃水準が急激に低下することとなった。
(悪化する邦船社の採算〉
北米航路全体の荷動きは堅調であったが,運賃水準の低迷,円高による国際競争力の低下に加え,極東貨についての集荷体制の整備の遅れ等もあって,邦船社の航路採算は悪化している。同航路に参入している邦船6社の61年度航路損益は約690億円の赤字となっており,前年度に比べ約140億円赤字幅が拡大した。
(変化する事業環境への対応)
このように,北米定期航路においては各社とも厳しい経営を余儀なくされているが,同航路の今後のあり方を検討するに当たっては,為替相場の変動といった外部経済環境の変化はもちろんのこと,①米国産業の構造の現状から,日本・極東-北米間の貿易ルートとしての同航路は,将来的にも規模,成長性等の点で有望であること,②極東市場は,従来の日本中心型から,日本・台湾の二極構造,さらには日本・アジアNICs・ASEAN諸国の三極構造へと多極化,複雑化していくことが予想され,船社サイドにおいても,今後とも一層の減量・合理化を進めるとともに,こうした市場構造の変化に対応した事業展開を行う必要があること,③米国内陸部への鉄道との複合一貫輸送は,コンテナの二段積みが可能な列車であるDST(ダブル・スタック・トレイン)の導入後急速に進展しており,今後は,米国内貨物の取扱体制も含めた効率的な複合一貫輸送体制の強化拡充がますます重要となっていくものと考えられること,等にも留意しなければならない。
ウ 船舶保有形態の変化
(フラッギング・アウトが先進国で問題化)
近年の海運不況の下で,コスト減にまる国際競争力の維持を図るため,先進国海運の便宜置籍船への依存度が特に高まっているといわれている。特に,最近は,もともと先進国に登録されていた船舶を便宜置籍国に登録替えする動きが活発化し始めており,船舶の海外流出(フラッギング・アウト)による自国籍船の急激な減少が欧州諸国において問題となってきている 〔4-1-4図〕。
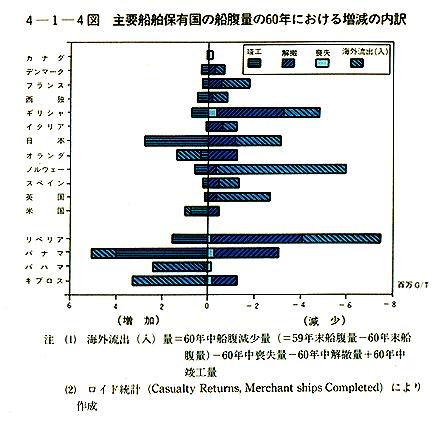
(新たな船舶置籍制度〉
フラッギング・アウト急増への新たな対応として,近時,「オフショア船籍」等の新たな船舶置籍制度が注目を集めている。
「オフショア船籍」は,一般に,本国から独立した一定の自治権を認められた自治領等に,便宜置籍制度類似の船舶置籍制度を設けるものである。現在,英領マン島,仏領ケルゲレン諸島,蘭領アンティル諸島に開設されており,これ以外にもオフショア船籍の開設を検討する国がある。
一方,ノルウェーにおいては,本国から離れた自治領等ではなく,本国そのもの(ベルゲン市)に新制度に基づく船籍を設置しうる,「ノルウェー国際船舶登録制度(NIS)」が62年7月から導入された。
このような新たな船舶置籍制度については,海運をめぐる国際的動向の一つとして,我が国としても引き続き関心を払っていく必要がある。
(2) 外航海運助成対象企業の経営状況
(経営状況は大幅に悪化〉
61年度の海運助成対象企業39社の損益状況は,三部門(定期船,不定期船,油送船)の同時不況に加え,60年秋以来の円高が進行したため,全企業の営業収益は,1兆7,867億円と対前年度比6,328億円(26.2%)の大幅減収となり,営業損益では468億円の損失を生ずるに至った 〔4-1-5表〕。
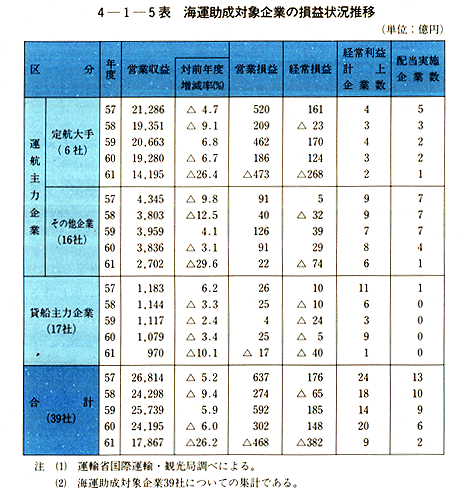
(1円円高で14.3億円の営業差損)
外航海運業は,営業費用のドル建て比率よりも営業収益のドル建て比率がかなり高いため,円高の影響を受けやすい収支構造となっている。
61年度において,海運助成対象企業39社についてみると,ドル建て収益がドル建て費用より14.3億ドル超過しているので,この超過分が1円円高になると14.3億円の営業上の為替差損を生じることとなる。
(61年度は60年度に比べ960億円の円高差損)
61年度の平均レートが60年度の実績と同じレートであったと仮定して試算すると,61年度の営業損益は約490億円の黒字であるが、実績では約468億円の赤字であるから,円高の影響により960億円程度収支が悪化したと推計される。
62年度についてドル建て収益・費用が61年度のそれと同額であるとし,円の対ドル相場が140円で推移すると仮定した場合の試算では,39社合計で更に310億円程度の営業上の差損が発生するものと推計される。
(為替変動対策への取組みが必要)
急激な円高では機敏に対処することが難しく,また,為替相場の予測が困難なこと等から,外航海運企業においては,為替変動対策に苦慮しているのが実情であるが,今後の為替変動の影響をできる限り回避するために,為替リスクヘッジ方策や費用面でのドル建て化の推進など,種々の方策に真剣に取り組む必要がある。
(ドル表示でみた定航大手6社の営業収益・費用)
円高が海運企業の経営に与える影響をドル表示でみた営業収益・費用からみると,61年度の収益が前年度に比べて3億6,500万ドル(4.3%)増加したのに対し,費用は対前年度比6億9,500万ドル(8.3%)増加している。損益悪化の主因は,円高により収入の伸びを大幅に上回って費用が増加したことであると考えられ,運航規模1単位当たりのコストの大幅な上昇により各企業の国際競争力低下を招来している結果となっている。
(思い切ったコスト削減策を)
このような考察からすれば,長期的な円高ドル安の定着に対する対策としては,この増加した費用をいかに減量・合理化等で削減するかということにつきるといわねばならない。即ち,収入面での円建て化が現実的には困難な場合が多いこと,ドル建ての運賃市況の回復が見込み難いことからすれば,企業としては,思い切ったコスト削減策を講じる必要が出てこよう。
|