|
2 外航海運の再構築に係る諸問題
ア 海運造船合理化審議会中間報告
しかし,その後,急速かつ大幅な円高の進行等我が国海運企業をめぐる諸情勢の大幅な変化が生じたため,船員雇用問題への対応を含む何らかの緊急対策が必要との認識のもとに,同審議会海運対策部会小委員会において審議の末,61年12月,以下のような中間報告が取りまとめられ,緊急対策が提言された。
① 船員雇用問題と対策
このため,海運企業としては,まず,海上職域,企業内他部門等での船員吸収に努力するとともに,これらの措置によっても吸収しえない船員については,円滑な調整を行いつつ陸転を図るべきである。 船員の陸転に当たっては,海上労働の特殊性等の諸事情にかんがみ,当面の措置として,海上職域を一定条件で確保しつつ併せて陸転の準備をさせることが、いわゆる軟着陸を図るための現実的方策といえ,そのため,海運労使による努力及び国の所要の支援が必要である。
② その他
・利子補給繰延べ問題についての早急かつ適切な措置 ・我が国商船隊の構成,規模その他海運の再構築の問題についての検討
イ 海運企業における経営の減量・合理化の状況
海運助成対象企業39社について,海陸従業員数及び社船隻数の推移をみると, 〔4-1-6表〕のとおりであり,海運企業の船隊,要員の大幅な合理化が進展しているものの,前述の円高の進展,北米定期航路での競争激化等によって,さらに厳しい減量・合理化をせざるを得ない状況にある。
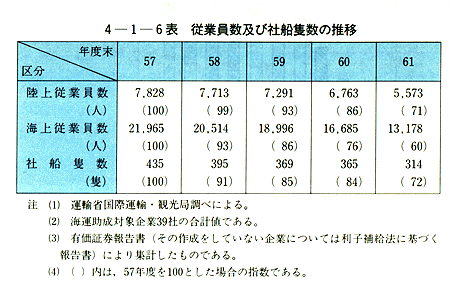
このため,労使の合意に基づく緊急雇用対策が62年4月からスタートし,雇用開発促進機構の設立等により,いわゆる軟着陸を図るための努力が行われている。
ウ 解撤促進対策の推進
日本船の解撤の状況は 〔4-1-7図〕のとおりであり,61年の解撤船腹量は前年に比べて倍増した。しかし,係船量はなお相当の水準にあり,減速航行等係船以前の船腹需給の調整も考えれば,依然日本船は船腹過剰状態にあり,引き続き船腹解撤促進を図る必要がある。
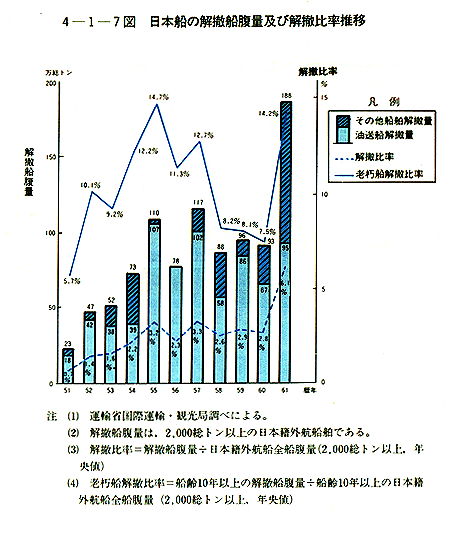
(解撤法の施行状況)
エ 利子補給金繰延べ問題への対応
62年3月に外航船舶建造融資利子補給臨時措置法が改正され,日本開発銀行による利子猶予制度が創設された。これにより,57年度以降利子補給金の一部の支給が繰り延べられてきた海運会社にとって,実質上法律で定められた利子補給金の支給期限内に支給を受けたのと同等の効果を受けることとなり,利子補給金の支給繰延べ問題は,実質的に解決されることとなった。
天然資源に恵まれず,四面を海に囲まれた貿易立国である我が国は,主要資源のほとんどを海外に依存しており,我が国関係海上荷動き量は世界海上荷動き量の約20%となっている。このような状況にある我が国にとって,エネルギー,資源や工業製品の安定輸送を確保していくことは,その経済社会の発展を図る上から極めて重要であり,我が国外航海運の果たすべき役割は極めて重要である。
|