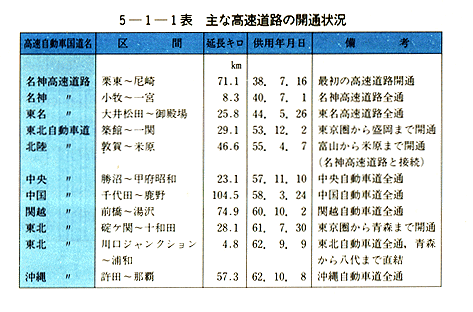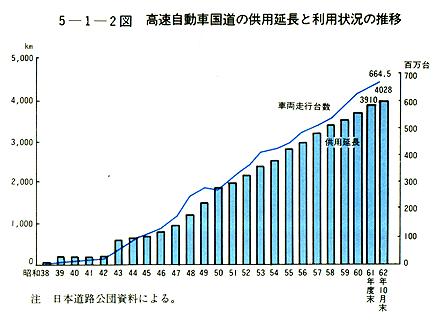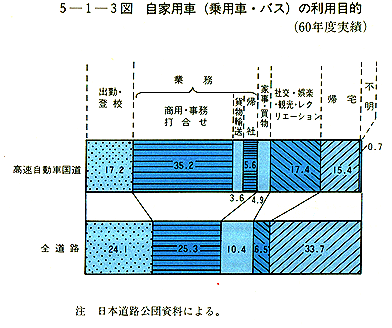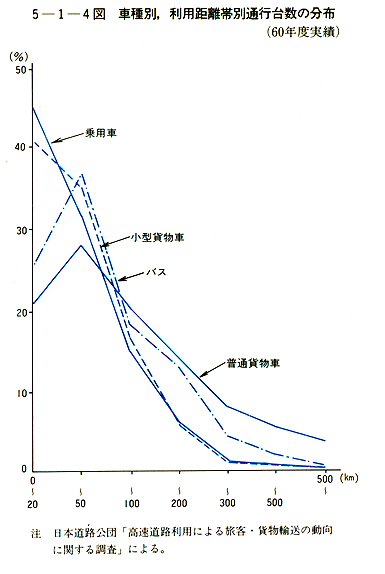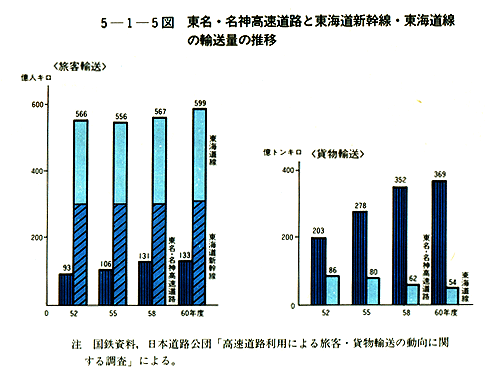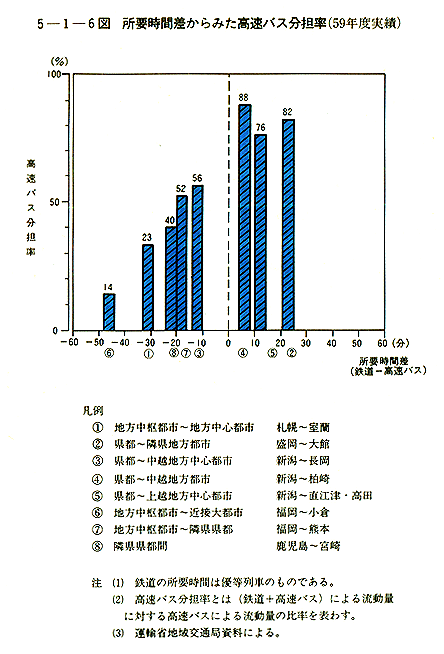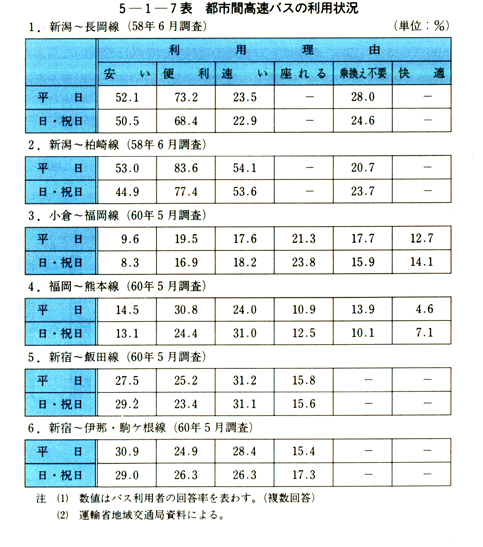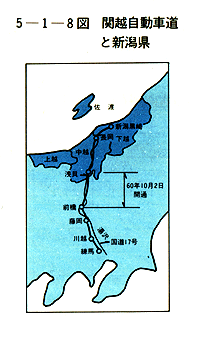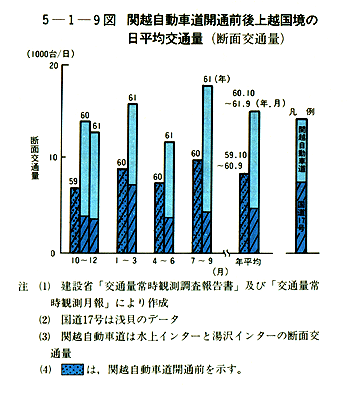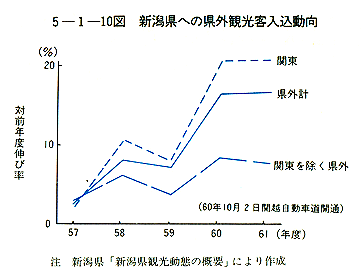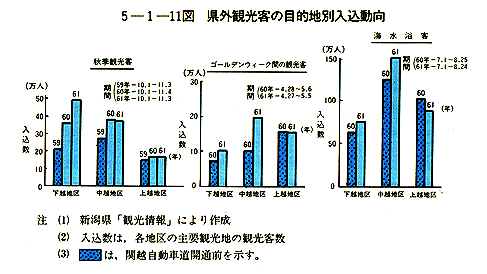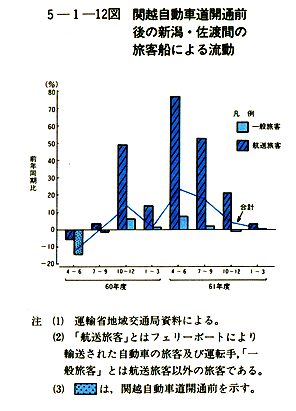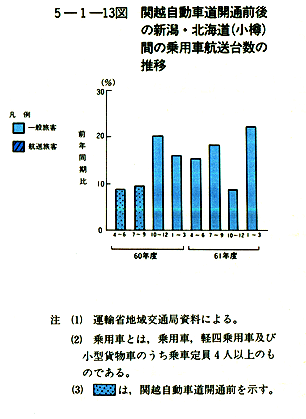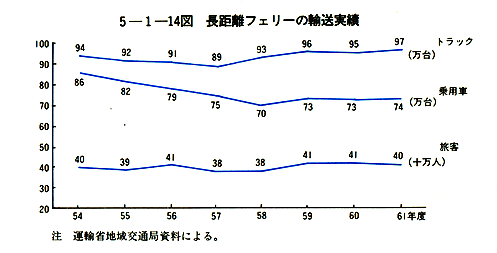|
1 幹線交通網の整備の状況
(1) 幹線鉄道
(主要プロジェクトの現状)
幹線鉄道に係る主要なプロジェクトの現状についてみると,次のとおりである。
① 新幹線鉄道については,国土の総合的かつ普遍的開発に重要な役割を果たすものとして従来よりその整備が進められてきたが,第四次全国総合開発計画においても長期構想として「全国新幹線鉄道整備法に基づく既定計画路線を基本としつつ,社会経済の動向,新たな鉄道事業体制への移行の成果,あるいは技術の進歩等を見極めながら対処する。」と位置づけられている。このうち整備5新幹線(北海道,東北(盛岡・青森間),北陸,九州(鹿児島ルート,長崎ルート))については,国土の均衡ある発展,地域格差の是正に資するものとして,その建設が望まれているが,この問題については,昭和60年8月政府・与党間の申合せにより設置された「整備新幹線財源問題等検討委員会」において財源問題等の着工の前提条件について検討を行っているところであり,その結論を得て適切に対処することとしている。これらの着工の前提条件の検討に当たっては,国鉄改革の趣旨を踏まえ適切に対応していくことが必要である。また,東北新幹線東京・上野間については,現在,新幹線鉄道保有機構において建設が進められている。
なお62年9月には,旅客会社が建設主体とされている東北及び九州の新幹線鉄道の建設に関する事業を日本鉄道建設公団が引き継ぎ,同公団が整備新幹線の建設を一元的に行い得るようにするための法的措置が講じられたところである。
また,日本鉄道建設公団については,54年の閣議決定により,「青函トンネルの本体工事が完了した時点において他との統合等を図る。」とされてきたところであるが,国鉄の分割・民営化等の情勢の変化を踏まえ同公団の在り方を見直した結果,同公団については大規模工事の円滑な実施に資するよう,その存続を図る旨の閣議決定(62年1月30日)が行われた。
② 青函トンネルについては,日本鉄道建設公団が46年に,本工事に着手し,約16年の歳月を経て間もなく完成を迎えようとしているものであり,63年3月13日からは北海道旅客会社が在来線の運行を行う予定となっている。
なお,同トンネルについては,国鉄再建監理委員会の「国鉄改革に関する意見」を踏まえて,国鉄改革関連法により,その資本費については列車の運行を行う旅客鉄道会社に負担させずに,債務整理等の組織である日本国有鉄道清算事業団において処理することとしている。
③ 本州四国連絡橋鉄道の児島-坂出ルート(本四備讃線)についても本州四国連絡橋公団が53年に建設に着手し,完成を迎えようとしているものであり,63年4月10日から四国及び西日本旅客会社が全線にわたって在来線の運行を行う予定となっている。なお,児島-坂出ルート(本四備讃線)のうち茶屋町・児島間については63年3月20日から部分開業する予定である。
また,その資本費についても「国鉄改革に関する意見」を踏まえて,国鉄改革関連法により,日本国有鉄道清算事業団において処理することとしている。
さらに,本四備讃線の整備にあわせて進められてきた四国側の予讃本線高松・観音寺間及び土讃本線多度津・琴平間の電化工事も62年10月までに完成した。
(2) 空港
(三大プロジェクトの推進)
第3章で詳述したとおり,国際及び国内航空輸送の増大に対処するため,関西国際空港の整備,新東京国際空港の整備及び東京国際空港の沖合展開のいわゆる三大プロジェクトを第5次空港整備五箇年計画の最重点課題として推進している。
① 関西国際空港の整備については,関西国際空港株式会社において,飛行場の設置許可及び公有水面埋立免許を得て,62年1月27日に着工し,67年度末開港を目途に鋭意,建設工事を進めている。
② 新東京国際空港の整備については,65年度空港概成に向けて,61年11月から将来のエプロン地区において本格的な盛土工事に着手する等,既に取得済の用地の中で可能な工事を鋭意進めている。
③ 東京国際空港の沖合展開については,全体工程を3期に分けて行うこととしており,63年7月の新A滑走路の供用開始を目途とする第1期事業を順調に進めている。
(ジェット化等の進展)
40年代以降航空機のジェット化・大型化に対応した空港の整備を推進してきており,ジェット化率は50年3月の24%(定期的輸送の行われている68空港中16)から62年8月の52%(同79空港中41)へと著しい進展をみた。また,このうち2,500m以上の滑走路を有する大型ジェット機就航可能な空港数は17(ジェット化空港の41%)となっている。
(3) 高速道路・高速バス路線
(高速道路の整備)
高速自動車国道は,38年7月に名神高速道路の尼崎〜栗東間71kmが開通して以来年々整備が進み,61年度には10区間188kmが供用され,61年度末現在で3,910km(対前年度末比5.1%増)が供用されている。
62年9月に東北自動車道と首都高速道路とが接続したことにより,青森から熊本県八代までの約2,000kmが自動車専用道路で直結するなど国土の背骨となる縦貫道が概成しており,62年10月には,供用区間の総延長は4,028kmとなった 〔5−1−1表〕。
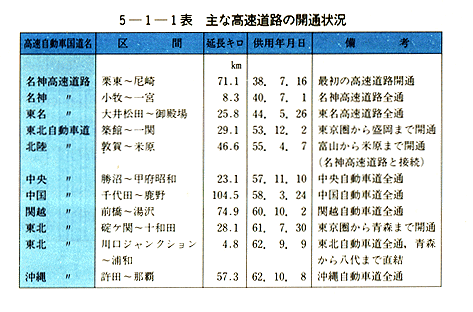
第四次全国総合開発計画においては,長期構想として約1万4,000kmの高規格幹線道路網の整備が提唱されており,これを受けて,国土開発幹線自動車道建設法の一部を改正し,国土開発幹線自動車道の既定予定路線7,600kmに,新たに3,92Okmを追加した。
(高速道路の利用状況)
このような高速自動車国道の整備の進展に伴い,高速自動車国道を利用する自動車数も,38年度の500万台から61年度には6億6,445万台へと飛躍的に増加した 〔5−1−2図〕。
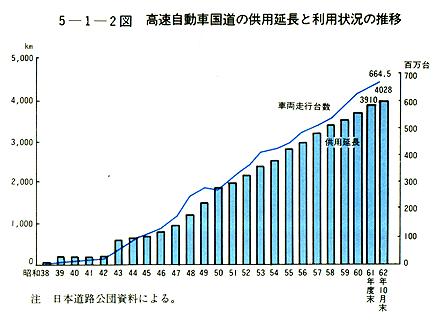
現在の高速自動車国道の利用状況は,車種別では,乗用車41.9%,バス1.7%,貨物車(小型貨物車及び普通貨物車〉56.3%(走行台キロベース)となっている。道路全体の場合に比べ貨物車の割合が高く,なかでも東名(66.7%),名神(62.6%),中層(60.4%)の各高速自動車国道では貨物車の割合が高い。
自家用車(乗用車及びバス)の利用目的では,商用・事務打合せを中心とする業務の割合が最も高く,40%以上を占めており,観光・レジャーは17.4%である。道路全体の場合に比べ,業務及び観光・レジャーの比率が高く,出勤・登校,帰宅,家事・買物のような日常生活に関連したものは少ない 〔5−1−3図〕。
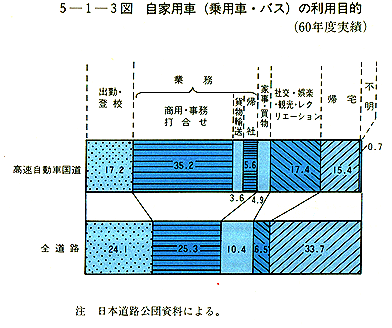
利用距離は,平均では乗用車41.1km,バス65.1km,貨物車63.0kmである。乗用車は,約半数が20km以下の利用で,100km以下が90%以上を占めている。一方,普通貨物自動車は,100kmを超えるものが30%以上あり,乗用車に比べ中長距離輸送にも利用されている 〔5−1−4図〕。
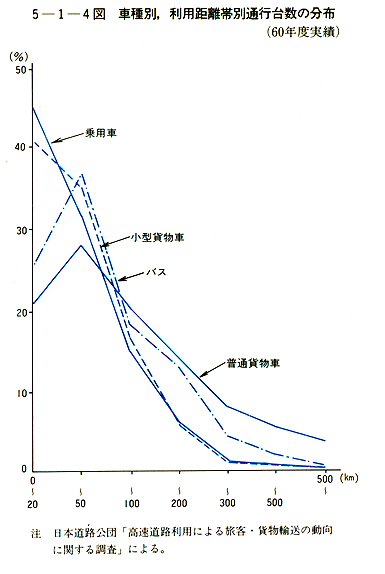
このような利用状況を,東名及び名神高速道路と東海道新幹線及び東海道線について最近の10年間の動きでみてみると,旅客については,東名及び名神高速道路の輸送量は増加傾向にあるが,58年度から60年度にかけては伸び率は低下している。また,東海道新幹線及び東海道線も伸び率は低いものの増加傾向を示しており,絶対量(人キロベース)では東海道新幹線及び東海道線の方がはるかに大きく,中長距離輸送の分野での鉄道の優位性を示している。
なお,貨物については,東名及び名神高速道路の輸送量は大きく増加し,東海道線の輸送量は減少傾向にある。また,絶対量(トンキロベース)も東名及び名神高速道路の方がはるかに大きい 〔5−1−5図〕。
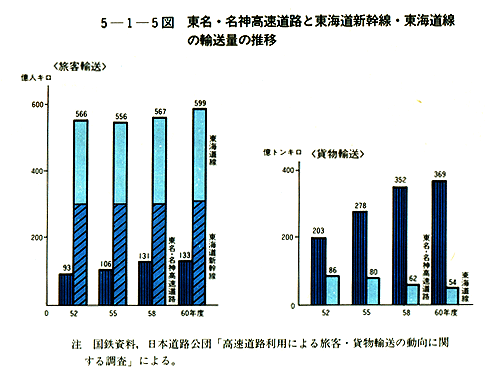
(高速バスの利用状況)
高速道路の利用が高まるなかで,高速バス(運行系統キロのおおむね1/2以上で高速道路を用いる路線バス)の伸長も著しく,その輸送人員は61年度において対前年度比16.7%増の3,798万人となっている。
また,路線網は61年度において66社302系統あり,そのキロ程は24,904km,1日当たり運行回数は2,204回となっている。
このように,高速バスが順調な発展を示しているのは,運賃が割安であること,利便性が高いこと等の理由によるものと考えられる。例えば,高速性について,鉄道と競争関係にある路線の所要時間差からみた高速バス輸送量シェアをみると, 〔5−1−6図〕のとおりである。一般的に高速バスは鉄道(優等列車)より安い運賃設定がなされている場合が多いが,それに加えて高速性も優位となっている路線(新潟-柏崎等)では8割〜9割のシェアを占めている。このほか高速バスの選択理由についてみてみると, 〔5−1−7表〕のとおり,「速い」,「安い」といった高速性,経済性指向のほかに,「便利である(目的地まで近い,待ち時間が少ない,荷物をたくさん持ち込める等)」,「座れる」といった利便性,快適性指向も比較的高いことがうかがえる。
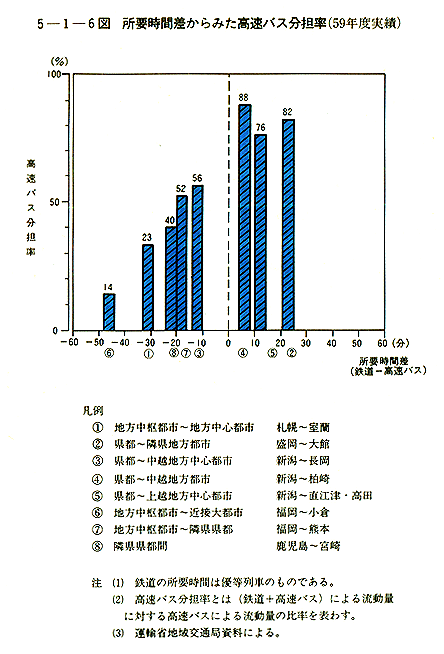
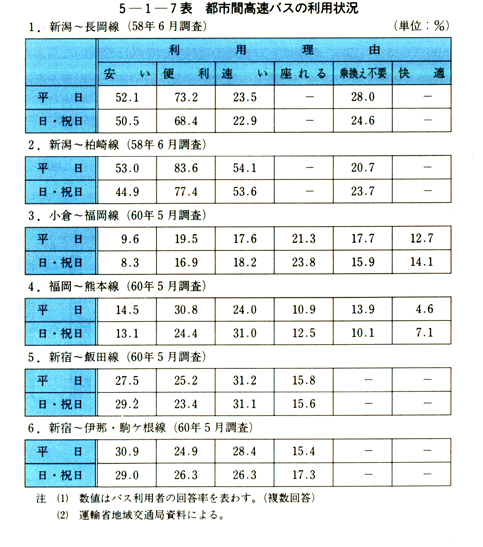
(関越自動車道開通にみる高速道路整備の効果)
上越国境山岳地帯を越えるには,従来国道17号しかなかったが,これとほぼ平行に走っている関越自動車道(東京〜新潟)が60年10月2日,関越トンネルを含む前橋〜湯沢間の開通で全線開通したことにより 〔5−1−8図〕,新潟県と首都圏の道路交通条件は飛躍的に高められ,入込観光客の増加や交通量の増大が産業,経済等にも影響を及ぼしている。そこで,関越自動車道開通によって新潟県境の交通量や入込観光客がどのように変わったかをみてみる。
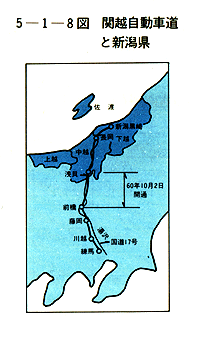
関越自動車道開通前後の群馬県・新潟県境における断面交通量をみると 〔5−1−9図〕,開通後の国道17号の県境付近(浅貝)と関越自動車道の交通量を合わせたものが,開通前の国道17号の同地点の交通量と比較して,開通直後の60年10〜12月期では2.1倍になり,その後も開通前と比べ1.7〜1.9倍で推移し,県境での自動車による交流は活発になった。また,開通に伴い新潟市内と東京都内が高速バスで結ばれ,60年度は開通後半年間で,21,000人,61年度は107,000人の輸送があった。
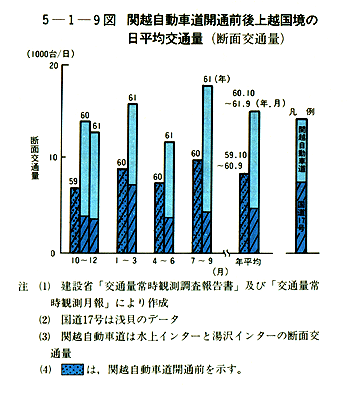
一方,新潟県への入込観光客の動向をみると,県外観光客の入込状況は 〔5−1−10図〕に示すとおりで,関越自動車全通の影響のでる60年度,61年度は,60年3月の上越新幹線上野開業もあり,関東地方からの入込客が大幅に伸びている。また,県外観光客を主な観光シーズンで目的地別にみると 〔5−1−11図〕,関越自動車道の沿線にあたる中越地区で開通後の入込客が急増,新潟市のある下越地区でも増加したが,富山県に近い上越地区では入込客が相対的に伸び悩み県外観光客への影響の大きさを知ることができる。
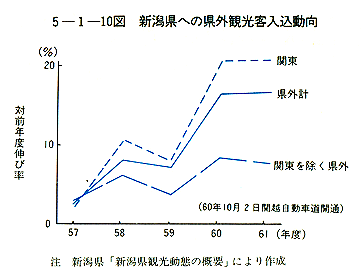
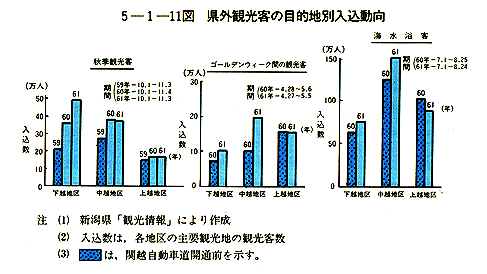
さらに,新潟・佐渡間の旅客船による流動をみると 〔5−1−12図〕,関越自動車道開通後は旅客輸送の伸びが拡大し,なかでも航送旅客の伸びは大きく,自動車による交流が増えていることがわかる。また,新潟・北海道(小樽)間の乗用車航送台数も,関越自動車道開通後に増加がみられる 〔5−1−13図〕。
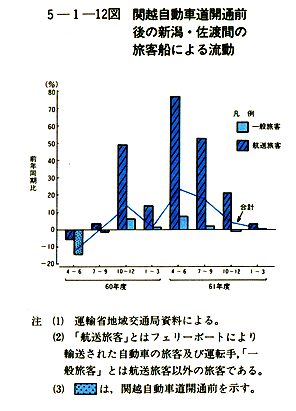
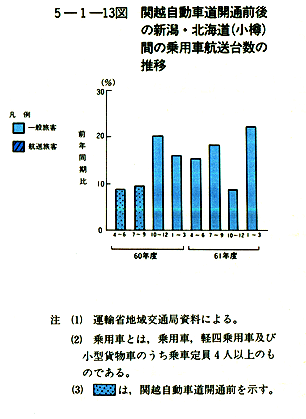
(4) 長距離フェリー
(長距離フェリーの輸送活動等)
長距離フェリーは,陸上のバイパス的機能を有するため幹線交通の一翼を担っており,現在,13事業者により20航路において船舶48隻(47万総トン)をもって運航されている。最近の輸送実績は, 〔5−1−14図〕のとおりであり,旅客,自動車ともほぼ横ばいの傾向を続けている。
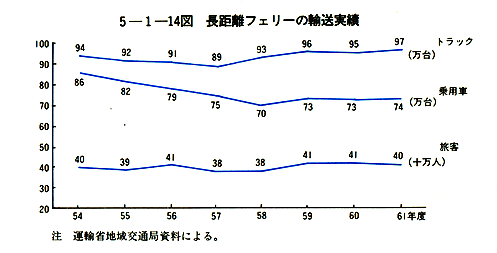
なお,現在の就航船舶の大部分は40年代に建造されたものであり,近年代替建造の時期を迎えているが,代替建造に当たっては,資金調達,利用者の長期的なニーズに適合した船型の選択,旧船の処分方法等について適切に対処していかなければならず,重要な課題となっている。
|