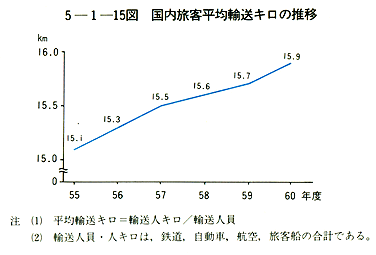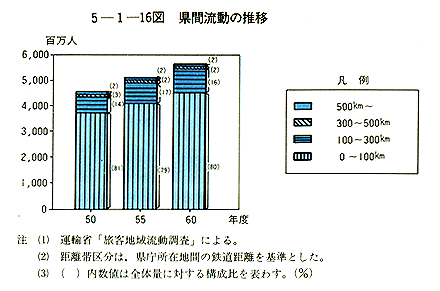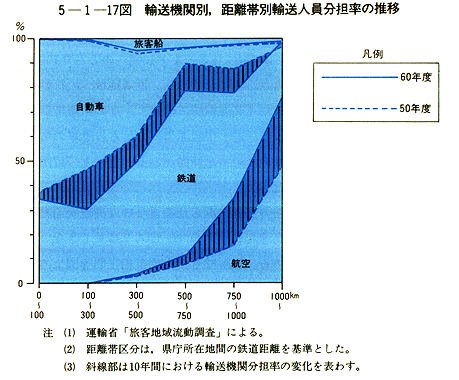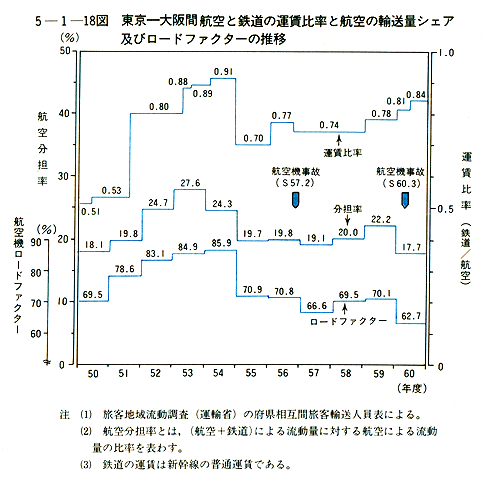|
2 幹線交通網の整備の方向
(1) 行動圏の拡大
最近の国民生活の多様化等に伴い,国内における人々の行動範囲は拡大する方向にある。
例えば,旅客輸送人キロを旅客輸送人員で割った平均輸送キロの推移をみると,55年度から60年度までの年平均伸び率は1.0%となっている 〔5−1−15図〕。
また,県間流動量(人員ベース〉においては,県内流動量に比べ絶対量は小さいものの,全流動に占めるシェアは着実に増大しており(50年度9.2%→60年度10.5%:「旅客地域流動調査」による。),県という枠を越えた交流が増加してきていることがわかる。
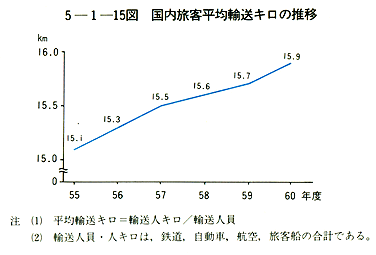
県間流動量を距離帯別にみると, 〔5−1−16図〕のとおり100km〜300km帯,0〜100km帯が大きく増加しており,近隣地域への行動範囲の拡大がうかがわれる。また,交通機関に着目し,その距離帯別分担率を全流動量についてみると,近・中距離帯における自動車の増加,長距離帯における航空の増加といった傾向がある 〔5−1−17図〕。
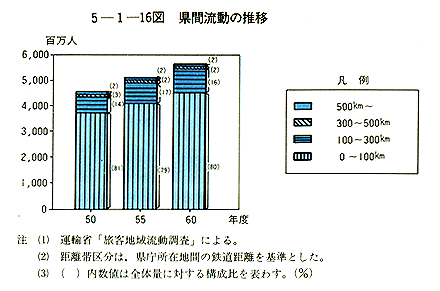
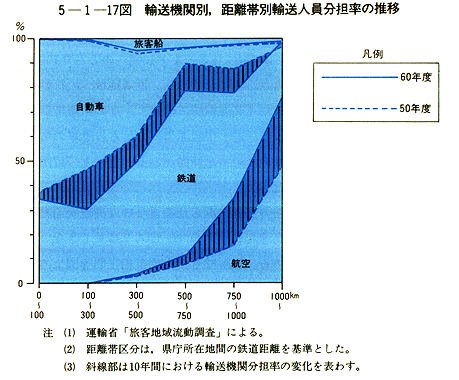
(2) 高速交通機関の競争状況
空港,新幹線高速道路の整備にみられるように,高速交通網の整備は着実に進んでおり,高速交通機関のサービスを享受できない空白地帯も序々に解消しつつある。なかでも,大都市相互間等国土の主軸に沿った移動においては,複数の高速交通機関が利用可能となっている。
例えば,東京-大阪間旅客の交通機関の利用状況をみると,60年度実績では鉄道利用が約80%を占め,航空利用が20%程度,高速バス利用が0.5%程度となっている。
また,過去10年間のデータで航空と鉄道の利用状況をみると,年度によってある程度の変動がみられる。 〔5−1−18図〕は東京-大阪間旅客流動における航空の分担率及びロードファクターと鉄道,航空の運賃比との変動を表したものであるが,運賃比,分担率,ロードファクターは連動していることがうかがわれる。このことから,東京-大阪間のような複数の交通機関が存在する区間における旅客の交通機関選択には,いくつかの要因が存在するものの,運賃の変動もその要因の1つであることがうかがえる。
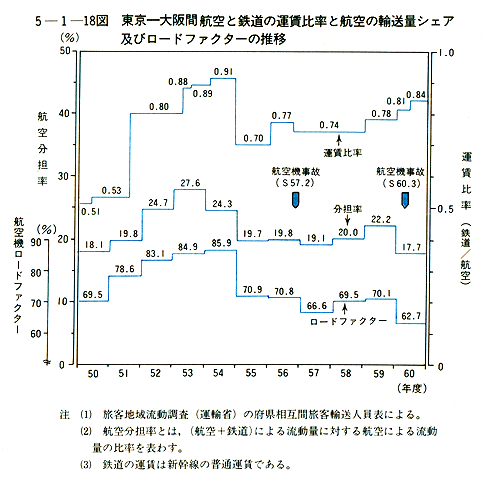
なお,この10年間には57年と60年の2度,大きな航空機事故が起きているが,この年はともに航空分担率及びロードファクターとも低下しており,航空機事故も利用者の交通機関選択に影響を及ぼしているものと考えられる。
(3) 幹線交通網整備の方向
今後とも進む人々の行動圏拡大に伴う交通需要の増加,量・質両面にわたる国民の交通に対するニーズに対応して,適切な競争と利用者の自由な選択を通して,各交通機関の特性が生かされるような幹線交通網の整備を進めていく必要があるが,その長期的目標としては以下の2点があげられる。
① 高速交通サービスの地域間格差を解消し,全国土にわたってできるだけ一日交通圏を拡大するという観点から,地方都市から複数の高速交通機関へのアクセス時間を概ね1時間以内とすること
② 地域間相互依存関係拡大に伴い,交通網の安定性の確保,利便性の向上等が重要となることから,複数ルート,複数交通機関による多重交通網の形成を図ること
しかしながら,その整備にあたっては今後とも財政,空間等の制約の強まりが予想されるので,投資の重点化,効率化を図りつつ,各高速交通機関の特性に応じて長期的な視点から順次選択的に高速交通施設の整備を進めていくとともに,これら高速交通施設と一体となって機能し,その質を高める在来鉄道の列車設定の適正化等フィーダー・アクセス機能の充実を図る必要がある。
|