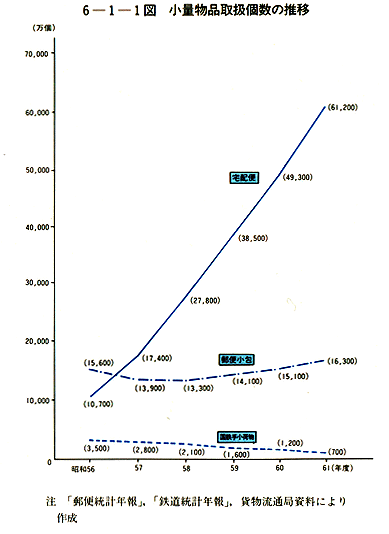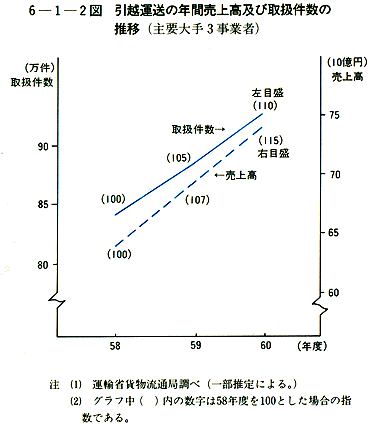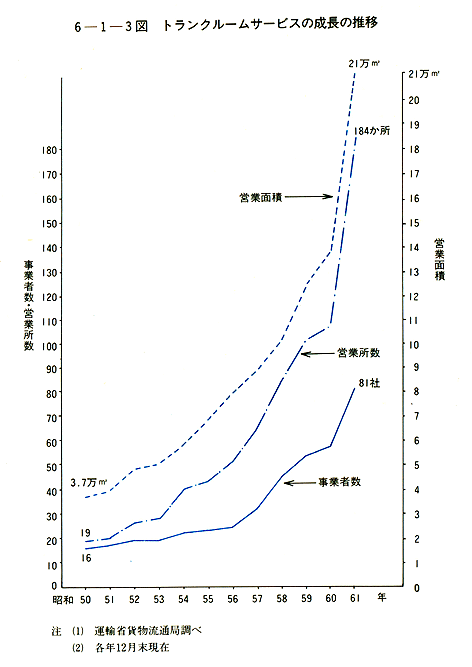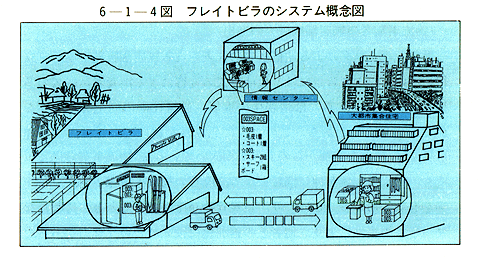|
1 消費者物流の進展と消費者保護のための施策
(消費者物流の進展の背景)
荷主が不特定多数の消費者である消費者物流については,宅配便.引越運送,トランクルーム等を中心にその伸長に著しいものがある。
消費者物流が進展しているのは,一般消費者の潜在的需要があったことに加え,産業構造の変化等に伴い物流の量的拡大が伸び悩んだために,物流事業者が新たな市場開拓に迫られたことと,消費生活の質的向上に伴い,多少の支出は伴っても,利便性・快適性といった高度の物流サービスを要求するようになってきたことが合致したためであると考えられる。
ところで,こうした消費者物流は,荷主がいわば「物流の素人」であることを考えると,その利益保護を図ることが重要となってくる。従って,行政施策についても,企業荷主向けに設定されている運賃・料金制度,約款等を,一般消費者の立場を保護し,かつ一般消費者にわかりやすいものにするための方策が中心となっている。
(1) 宅配便
(拡大を続ける宅配便)
宅配便は,近年成長の一途をたどっており,宅配便全事業者40便153社の昭和61年度における取扱個数は,対前年度比約1億2,000万個増加(対前年度比24.2%増)の約6億1,200万個に達している 〔6-1-1図〕。この成長は,小口・軽量輸送ニーズの高まりもさることながら,宅配便事業者が,①わかりやすい運賃設定,②取次店網の拡大による利便性の高まり,③貨物追跡システムの導入に代表される情報化による確実性の高まり,④自動仕分機の導入等による配送の迅速化等,利
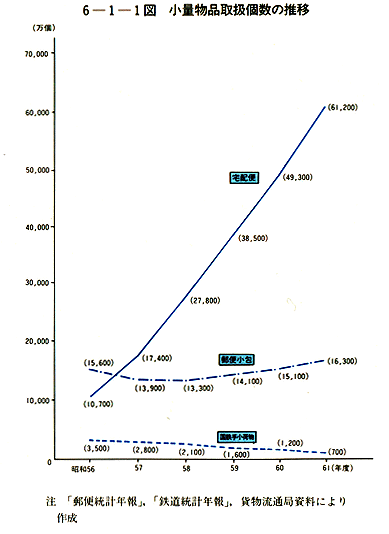
(宅配便の新たな展開)
宅配便は,ゴルフ・スキー用具の輸送はもとより,地方名産品の産地直送,保冷輸送などにも事業範囲を拡大し,多様化・高度化する消費者ニーズへの積極的な対応を図っている。さらに,最近登場した書籍宅配のように,宅配便の進展のなかで形成された全国的な集配体制や貨物追跡システムの活用による消費者サービスも,宅配便の新たな展開として注目されているところである。
(宅配便に係る行政施策)
宅配便に係る消費者保護施策としては,58年7月に整備された宅配便運賃制度と,60年9月に制定された標準宅配便約款がある。
また,運輸省は,62年6月に,一度に定数量以上の貨物の運送を行う場合に割引轟を実施する宅配便の数量割引制度を導入した。これは,まとまった数量の荷物の運送を委託される場合,一個当たりの集荷コストが小さくなることを理由としたものであるが,導入の背景としては,一般消費者を対象とする輸送サービスとして始まった宅配便が,最近は,デパート配送をはじめとする商業物流にも利用されるようになり,一度にまとまった荷物の運送を委託されるケースが生じてきたことが挙げられる。
(2) 引越運送
(引越運送サービスの新たな展開)
現在,トラック運送事業者による引越運送は,転勤・入学時の移動や家屋の建て替えに伴う人口移動の増加により,年々その件数が増加している 〔6-1-2図〕。また,主として家具・家財の大型化に伴って引越作業が消費者の手に負えなくなってきたこと,引越事業者が不用品の処理,冷暖房器具の取付け,取外し等各種付帯サービスの展開に努めてきたこと等を背景として,引越サービスの高付加価値化傾向も強まっている。
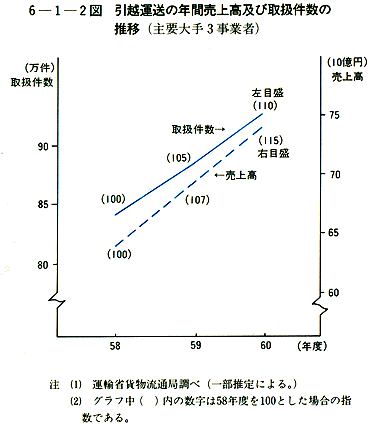
消費者が煩雑な作業を自ら行うことを避け,有料であってもサービス産業に委ねるという最近の生活意識の変化を勘案すると,トラック輸送を核とする引越産業は,付帯サービスの一層の拡大を図ることにより,今後も順調に成長していくものと考えられる。
(引越運送に係る消費者保護対策)
このような状況にかんがみ,運輸省は,付帯サービスのウェイトの高まりや内容の多様化に伴い複雑化する引越運送を,利用者にとってわかりやすく,かつ,安心できるものとし,利用者と運送事業者間のトラブルを防止するため,61年10月に標準引越運送・取扱約款を制定するとともに,引越運賃料金制度を整備し,中央及び地方における研修会の実施により事業者に対する周知徹底を図った上で,これらを62年3月から実施に移しているところである。また,これらに併せて引越運送から生ずる苦情処理体制も整備され,引越運送の事前相談・苦情処理が,全日本トラック協会及び各都道府県トラック協会の輸送相談窓口で無料で行われている。
(3) トランクルームサービス
近年の大都市圏における住宅事情の悪化や事務所スペースの不足,高価品の普及,海外赴任の増加等を背景に,一般消費者及び一般企業を対象として,家財,衣類,美術品,毛皮,書類,磁気テープ等の小口の非商品の保管を行ういわゆるトランクルームサービスが,首都圏を中心に急速な進展をみせている。
このような状況の下で,トランクルームサービスの消費者保護施策の一環として,61年5月に標準トランクルームサービス約款が制定され,同年8月から実施された。
この約款制定を受けて,トランクルームサービスの普及が一層促進されており,その実態は 〔6-1-3図〕のとおりである。
今後は,トランクルームサービスの一層の定着を図るため,わかりやすい料金体系の設定について検討するとともに,設備水準の向上等についても取り組んでいく必要がある。
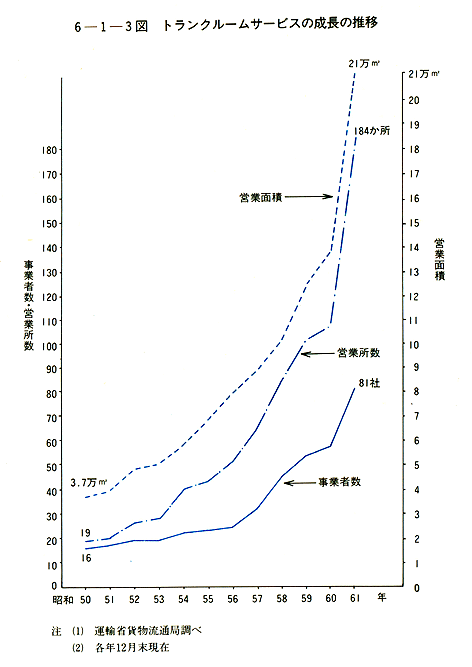
(4) 無店舗販売
(物流事業者の無店舗販売への進脚)
近年,カタログによる通信販売に代表される無店舗販売市場が急成長している。この背景には,生活様式の変容による消費者ニーズの多様化・個性化,さらには情報化の進展通信技術の向上等,様々な面での環境変化がある。このように急成長を続けている無店舗販売市場には,様々な業種からの参入が相次いでいるが,物流事業者にとっても,物流量全体が伸び悩むなかで,既存の物流・情報ネットワーク等を有効活用することにより,新規貨物が確保できるとともに新たなサービスの提供により,他者との差別化に役立つという魅力があるため,無店舗販売業者と提携したり,あるいは自社で参入するなどの積極的な対応が目立っている。
(産地直送宅配便と地域振興)
こうした物流事業者の無店舗販売への進出のうち,産地直送宅配便が特に注目されている。これは各地方の特産品を物流事業者のネットワークと情報システムを利用して,新たな流通ルートにのせようとするものであるが,物流事業者にとっては,物流需要の創造になるとともに,企業イメージの高揚にもつながる。
一方,出荷側の産地にとっては,マーケット開拓とともに特産品の宣伝になり,地域振興にもつながるものと期待されている。例えば大量出荷への対応と品質管理の徹底の必要性から産地に専用の加工場ができ,地域の活性化につながった事例も報告されている。
(無店舗販売進出についての問題点)
このように無店舗販売への進出は,物流事業者にとって多くの利点があると思われるが,一方,無店舗販売に本格的に進出する場合,物流事業と全く異なる業務分野であるため,新たな経営リスクを負うことにも注意しなければならない。
具体的には,受注した量の商品を確保出来なかったり,商品が売れ残ったりすることもあることや,運転手が営業活動を併せて行うことには限界があるため,専門の営業担当者の確保が必要となるといった問題点も指摘されている。物流事業者としては,このような問題点を踏まえ,精致な見通しと明確な経営戦略に従った対応をする必要がある。
(5) フレイトビラ構想
首都圏をはじめとする大都市において,住宅問題が大きな課題となっている状況にかんがみ,住宅内の当面使用しない荷物を宅配便システムなどにより過疎地域等外部に建設する保管庫に預け入れ,必要に応じて取り寄せるというニューサービスを実現し,もって,住空間の拡大を図ることを目的とする「フレイトビラ構想」が提案されている 〔6-1-4図〕。
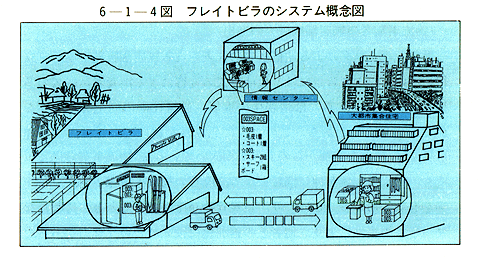
この構想の実現可能性を高め、構想の具体化を推進していくため,フレイトビラに対するニーズの有無建設運営主体のあり方,サービスの内容などについて検討する場として,関係業界,地方公共団体,一般消費者の代表を含む有識者からなるフレイトビラ構想研究会が設置されている。
同研究会は,62年8月にフレイトビラの実験事業の実施を提言する旨の中間報告をまとめた。運輸省では,この中間報告を受け,関係者の協力を得つつフレイトビラの実験事業を実施していく予定である。
フレイトビラ構想については,この実験事業の結果を踏まえ,同構想の実現に向けての具体的整備方策を確立していくこととしている。
|