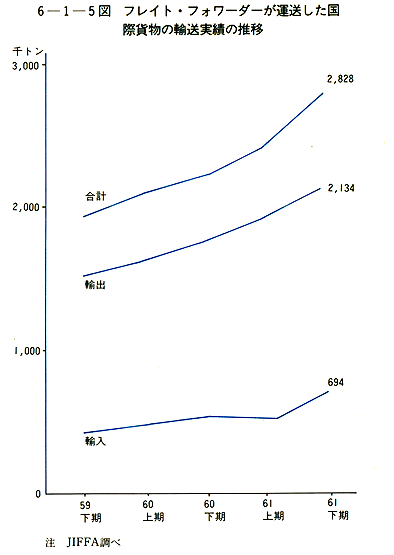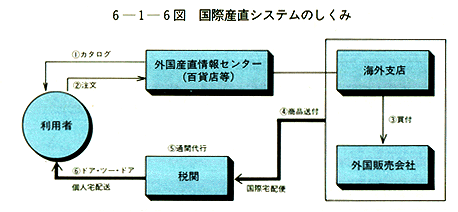|
2 国際物流対策の推進
(1) 国際複合一貫輸送の推進
(国際複合一貫輸送の進展)
近年,国際物流の分野においては,一人の運送人が船舶鉄道,航空機トラックといった輸送機関を組み合せて一貫した責任と運賃で貨物を輸送する国際複合一貫輸送が進展している。
国際複合一貫輸送は,船社,航空会社といった幹線部分に実運送手段を有している者にも提供が可能ではあるが,実運送手段を持たない利用運送人であるフレイト・フォワーダーの活躍する余地が大きい。これは,フレイト・フォワーダーの国際複合一貫輸送が,①自らは輸送手段を持たないという立場を生かして多様なルートを形成できる,②荷主にとって全体の経費の削減につながる付帯サービスを提供することができる,③ドア・ツー・ドアのキメ細かいサービスが提供できる等の利点があるためであり,その輸送量も増加傾向を示している 〔6-1-5図〕。フレイト・フォワーダーの61年のシェアは,日本発米国向け海上貨物を例にとると,全体の10%弱と推定されている。具体的な輸送ルートとしては,欧州航路のバイパスとして定著しているシベリア鉄道経由欧州・中近東向け一貫輸送(シベリア・ランドブリッジと呼ばれる。),主として欧州向けに海上運送と航空運送を組み合わせた一貫輸送(シー・アンド・エアと呼ばれる。)及び米国,欧州,韓国,中国,アフリカといった地域の内陸までの一貫輸送がある。このうち,シー・アンポ・エアは,日本から北米西岸(バンクーバー,シアトル,ロサンゼルス),東南アジア贋港,シンガポール,バンコク),ソ連(ウラジオストク)までをそれぞれ海上輸送し,以降を航空輸送するもので,日本発欧州向けの海上輸送や航空輸送の輸送実績の伸び率が鈍化しているのに比較して,著しい伸びを示しており,61年実績で前年比7割増の約29,000トン(欧州向けのみ)という調査結果もある。これは,迅速な輸送が求められる一方で,円高等の影響により荷主のコスト意識が層高まっていることを反映して,航空輸送と海上輸送の中間の需要を満たす輸送形態の選択が増加していることの現れと考えられる。ところで,日本発欧州向けの航空貨物の輸送量は80,000トン程度(61年実績)といわれている。シー・アンド・エアの貨物が,主に航空貨物からシフトしており,両者の貨物が似通っていることを考えると,両者を合わせた市場全体に占めるシー・アンド・エアの割合は約27%となり,無視できないものとなっている。
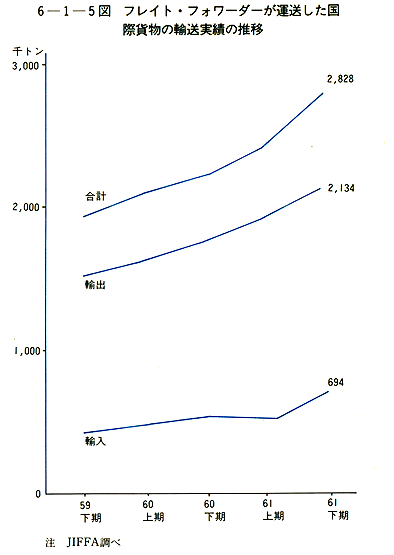
なお,船杜も,自社航路に内陸輸送を組み合わせて提供する試みを見せており,特に,米国においては,DST(ダブルスタック・トレイン:コンテナ二段積み専用則車)を導入するといった動きが自立つ。
(フレイト・フォワーダーの活動基盤整備)
国際複合一貫輸送の担い手であるフレイト・フォワーダーについては,航空フォワーダーに関しては免許制がとられているものの,特に多様なルートを形成している海上のフレイト・フォワーダーに関して参入規制がないこと,運送人としての歴史が浅いことなどの理由により,信用力が不十分であることや責任内容にばらつきがあるため取引に円滑さを欠くことがある。
こうした状況にかんがみ,60年9月に公益法人化された(社)日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会(JIFFA)を通じて,標準的な約款の検討,国際的知識やノウハウを有する人材の育成,情報システムの整備等の方策を進めている。特に,標準的な約款の制定については,学識経験者等からなる検討委員会を設け,検討を行っているところである。
(2) 国際宅配便と国際産直システム
(国際宅配便の進展)
国内においては,トラック等による宅配便の成長が著しいが,近年,国際貨物輸送の分野においても,航空機を利用して小口貨物や書類をドア・ツー・ドアで輸送する国際宅配便が急速に伸びている。国際宅配便は,運賃水準が相対的に高いにもかかわらず幅広い需要に支えられて発展しているが,これは,①ドア・ツー・ドアの輸送を一貫して引き受けるパック商品である,②所要時間が短く,かつ到着時間が正確である,③分かりやすく利用しやすい通し運賃制度である等の点が,近年の高度化・多様化する国際ビジネス活動のニーズに適合したためであると考えられる。
国際宅配便の61年度実績は,取扱件数で約500万件,取扱重量で約6,100トン(日本発ベース)となっている。また,国際航空貨物全体に占める割合は売上げベースで約7%となっている。
(協会の設立と本格的実態調査)
こうした状況にかんがみ,国際宅配便を,多様化する利用者ニーズに対応した高度の輸送サービスとして健全に育成していくため,61年8月,日本国際宅配便協会(IAA)が設立されており,同協会を通じて必要な行政施策が講じられている。
また,62年度においては,正確に把握されていない同事業の状況について,本格的実態調査を行うとともに,利用者の保護を図る観点から国際宅配便約款の望ましいあり方等について検討を進めている。
(国際産直システムによる偶人輸入の推進)
ところで,貿易収支の是正,内需振興の観点から,輸入の促進を図ることが緊要の課題となっているが,運輸省でも,国際宅配便を利用した個人輸入システム国際産直システム)を構築することを関係事業者に提唱し,その推進を図ってきた。この国際産直システムとは,国際宅配便事業者と大手デパート等とをタイアップさせ,個人輸入の手続きをすべて代行し,海外の商品を国際宅配便によりドア・ツー・ドアで届けるというもので,個人輸入を安全確実に,迅速に,簡単に行えるようにしたシステムである 〔6-1-6図〕。
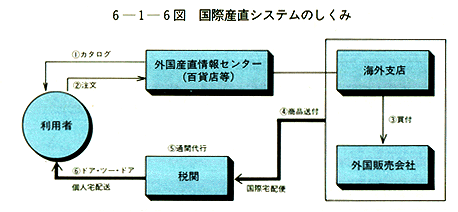
こうした呼びかけに対応して,民間の数事業者がこれに賛同し,数次にわたる実験輸入を行うなど事業化への努力を重ねたうえで,62年3月以降5店舗において,順次,同システムとしての外国産直情報センターが開設されており,今後も数事業者が開設することを検討している状況にある。個人輸入については,消費者,物流業界とも関心が高いため,国民生活の国際化の進展に対応して,今後とも,同システムを普及させ,その内容の充実を図っていきたいと考えている。
|