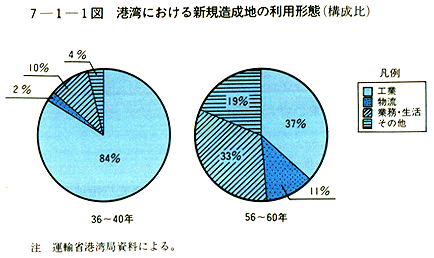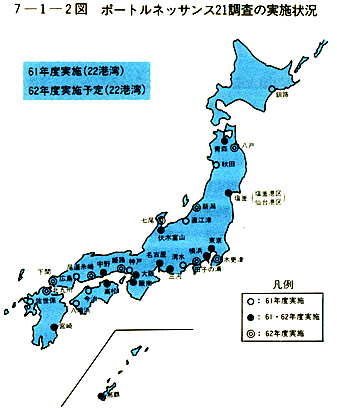|
1 高度化・多様化する要請に対応した臨海部空間整備
(1) 総合的港湾空間整備の進展
(求められる総合的港湾空間の整備)
港湾は,交通,産業,生活等の諸活動を支える活力基盤であるとともに,人々が働き,憩う空間である。港湾に対する要請は,高度成長期においては物流機能と工業機能の拡充が中心であったが,国際化,情報化,都市化が進展するなかで,21世紀に向けてその内容も高度化・多様化している。
こうした変化を背景に運輸省が新たな長期港湾整備政策として昭和60年5月に策定した「21世紀への港湾」においては,物流,産業に係る多様な機能を整備し,その高度化・高質化を図るとともに,生活に係る諸機能を積極的に導入し,これら3つの空間が調和よく組み合わされ,全体として高度な機能が発揮できる「総合的港湾空間の創造」を今後の港湾整備の目標の1つとした。
港湾空間は港湾区域(海域)とその埋立地及び港湾活動と密接に関連する隣接周辺地域(陸域)とからなる空間である。この港湾空間の土地利用形態は時代の要請によって変化してきている。これを港湾において新規に造成される埋立地の土地利用比率でみると 〔7-1-1図〕,高度成長期には工業への利用が8割以上占め,業務・生活関連は1割程度にしかすぎなかったが,近年は,工業が4割程度で,業務・生活関連が3割に達している。総合的港湾空間の整備とは,こうした動きをとらえ,各種施策を講ずることにより,三つの空間の比率が適正に組み合わされることをめざしたものである。
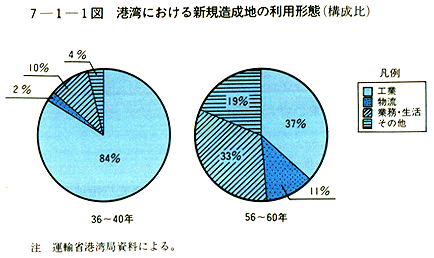
(第7次港湾整備五箇年計画の推進と諸制度の充実)
「21世紀への港湾」のめざした方向を実現するため,61年度を初年度とする第7次港湾整備五箇年計画を,総投資額4兆4,000億円(内港湾整備事業費2兆5,500億円〉で策定し,62年度は5,732億円の事業費で港湾整備事業を推進している。
総合的港湾空間形成のためには,港湾整備事業に加えて,多様な施設を民間活力を活用して積極的に整備していく必要がある。このため,61年度に日本開発銀行等からの出融資制度を「港湾機能総合整備事業」として創設し,また「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法」(以下「民活法」という。)の制定を行った。また,62年度には「民間都市開発の推進に関する特別措置法」(以下「民都市法という。),総合保養地域整備法」(以下「リゾート法」という。)の制定,民活法の一部改正を行うなど港湾における民活施策の充実を図った。こうした諸制度の確立によって大都市圏,地方圏を通じ各地域で様々なプロジェクトが進行しつつあり,総合的港湾空間の整備は多様な形で着実な進展をみせている。
(2) 活力ある港湾空間の再生
(港湾再開発の推進)
古くから整備が行われて,利用がなされてきた内港地区等においては,港湾施設の老朽化,陳腐化が顕在化しつつある。これら内港地区の再開発を進め,港湾の活性化を図って行くことが重要な課題となっている。このため,総合的港湾空間の創造を推進するための制度として「ポートルネッサンス21」を61年度に創設した 〔7-1-2図〕。「ポートルネッサンス21」は,港湾管理者が策定する基本計画に基づき各種事業制度を組み合わせ,官民一体となって総合的に事業を実施するものである。基本計画策定のための調査は,61年度22港で実施し,62年度も22港で実施中である。今後,これらの地域においては,調査結果に基づき多様な機能を導入することによって,物流地区,商業業務地区,レクリエーション地区あるいは市民に開かれた親水地区といった活力と潤いのある地区としての再開発が図られることとなる。
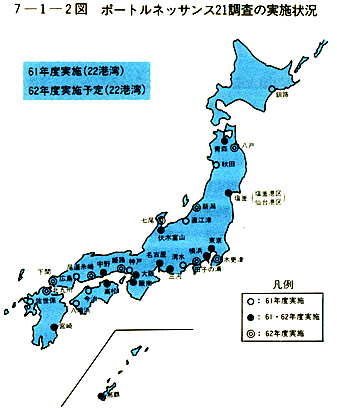
(臨海部の活性化の推進)
臨海部においては,産業構造の転換等によって用地の遊休化が生じ,地域活力の低下がみられるところがある。こうした臨海部用地については水際線を活用しつつその土地利用転換を進め,地域の活性化を図るとともに,併せて水際線を積極的に市民に開放することが求められている。
(3) 港湾の開発,利用及び保全等に関する基本方針の改訂
運輸省は,「21世紀への港湾」で示した港湾整備の方向を,各港の港湾計画等に反映させるため,49年7月に策定した「港湾の開発,利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」を改訂することとしている。基本方針は,港湾整備に関する基本的理念について,交通体系の整備,国土の適正な利用及び均衡ある発展等を考慮しつつ,港湾法第3条の2の規定に基づき運輸大臣が定めるものであり,今後の港湾の整備は新たな基本方針に基づき展開されることとなる。改訂の要点は以下のとおりである。
① 高度な物流空間,多様で高質な産業空間,豊かな生活空間を形成するとともに,全体として高度な機能を発揮できる総合的な港湾空間の創造を図る。
② 多極分散型の国土造りが求めちれているなかで,複数の港湾が一体的に機能し,また,海上交通網ばかりではなく情報や,空や陸の交通を通じ港湾相互の連けいの強化を図る。
③ 港湾業務のための情報・中枢機能,国際交流や貿易振興のための機能,また,港湾を利用する人に豊かな環境やきめ細かいサービスを提供できる機能の充実強化を図る。
④ 外貿コンテナ船の地方港への寄港,内航コンテナ船等による内貿雑貨輸送のネットワーク形成を図る。
⑤ 市民生活における親水機能としての水辺空間の回復,海洋生レクリエーション需要への対応等潤いのある生活環境の創造を図る。
⑥ 水面貯木場造船所跡地等の効率的利用や土地利用の弾力的利用,内港地区等における港湾の再開発,並びに,人工島,静穏海域の創出による新たな利用空間の開発を行う。
(4) 東京湾の総合的,計画的な開発・利用の推進
大都市地域においては,残された貴重な開発空間として臨海部が注目されている。特に,近年,諸機能の集中が著しい東京を抱える東京湾においては,東京臨海部の再開発構想,大小様々な人工島構想等,数多くの大規模プロジェクトが各界から提言されており,新たな要請に対応した東京湾域全体の利用計画の策定が必要となっている。
これまで,運輸省は,東京湾全体を一つの広域港湾としてとらえ,総合的な空間利用計画として「東京湾港湾計画の基本構想」(以下「基本構想」という。)を過去2回にわたり策定し,湾内各港の港湾計画の指針としてきた。しかしながら,前述の基本方針で示したような,様々な港湾機能の展開が湾内各港で求められており,これに対応するため,61年度より基本構想の改訂作業に着手し,関係港湾管理者の意見を踏まえて,62年3月にその中間報告を取りまとめた。現在,これを骨格として62年度中に成案を得るべく検討を進めている。今後は,新たな基本構想を指針として,東京湾諸港の港湾計画が改訂される予定である。
なかでも,東京港の港湾計画については,その改訂作業の一環として61年度より運輸省と東京都が共同でポートルネッサンス21調査を実施しており,この調査の結果を受けて,東京都は内港地区の物流機能の沖合展開と客船埠頭を中心とした潤いのある水辺空間の創出,13号地テレポートを中心とする副都心開発等を内容とする基本的な方向を示した。
|