|
1 物流の高度化に対応した港湾の整備
第4次全国総合開発計画においては,交流ネットワーク構想の推進を図るため,国際交流拠点を形成するとともに,貨物輸送の輸送時間の短縮にあわせ,輸送に要する時間が正確で,予定輸送の可能な圏域を全国へ拡大することをめざしている。海上輸送の分野でも物流の高度化を図るため,効率的な物流サービスの全国的普及をめざした海上輸送網の整備が必要となっている。
国際海上輸送におけるコンテナ化は著しく進展しており 〔7−2−1図〕,コンテナ貨物量は50年以降年平均約11%で増加し,61年には約8,025万トンに達している。また,定期コンテナ船の寄港数も55年の12港から,62年8月には19港に達しており,全国的なコンテナターミナルの整備が進展している。
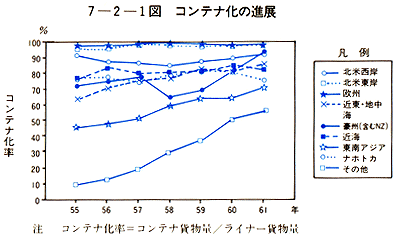
近年の特徴として,アジアNICs等との貨物量の急増に伴い,中進国船社が台頭しており,船社への専用貸付を原則とした埠頭公社等のコンテナターミナルの整備のほか,中小の船社の利用が可能な公共的なコンテナターミナルの整備が要請されている。
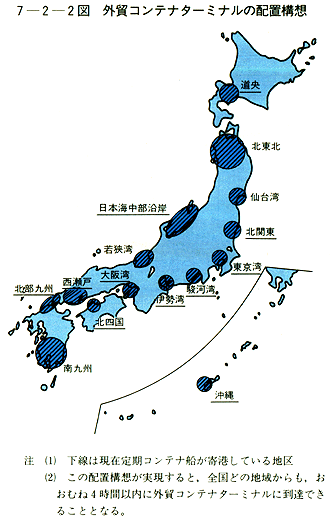
このため62年度は,三大湾では東京港,神戸港等5港で大型コンテナターミナルの整備を推進しており,また地方では博多港,那覇港において公共コンテナターミナルの整備を新規に着手している。
国内輸送においても,近年,製品の軽薄短小化の傾向に伴い雑貨輸送が着実に増大しており,これに伴い内航コンテナ船,RO/RO船(Rol1 on Roll off船),フェリー等によるユニットロード輸送が全国的に展開しつつある 〔7−2−3図〕。
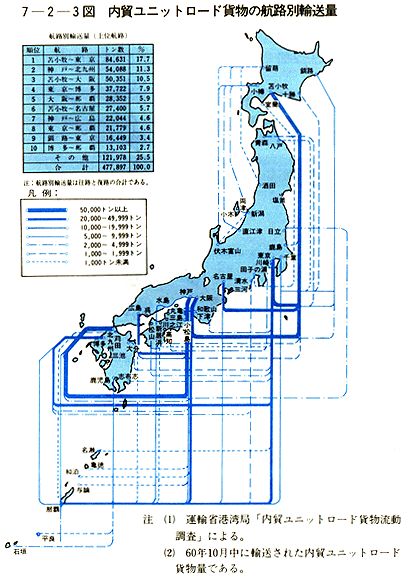
このため,高速内貿雑貨輸送のネットワークの形成をめざし,三大湾等の内貿の基幹となる港湾をはじめ,その他の地域においても隣接港湾との機能分担,背後圏の広さ,ユニットロード貨物注)の取扱実績,高速道路へのアクセス等を考慮した内貿拠点港湾を重点的に整備している。
コンテナ貨物等の増大に伴う港湾関連車両の大型化や陸上輸送の広域化等に対応し臨港交通施設の整備の要請が高まっている。また市街地における港湾関連車両と一般車両とのふくそうや,埠頭間の貨物輸送の大幅な迂回など港湾貨物の円滑な流動を妨げる問題も生じている。このため,港湾背後の幹線道路網と直結する,あるいは,埠頭間の連絡を強化するための幹線臨港道路の整備を推進している。
社会の国際化,情報化の進展に対応し,港湾においても物流の高度化のための港湾情報システムの整備や各種情報関連産業の受け皿としての空間形成が求められている。このため,横浜港等4港で港湾情報システムが整備されており東京港,堺泉北港等において導入が検討されている。さらに,大阪港において共同溝等の情報・通信基盤の整備に新規着手している。
|