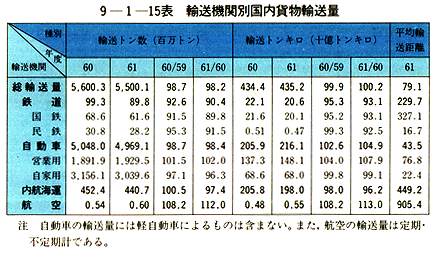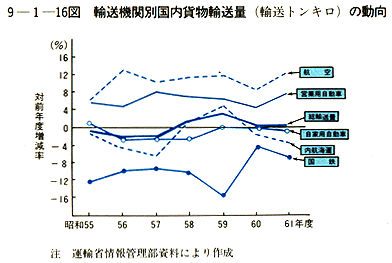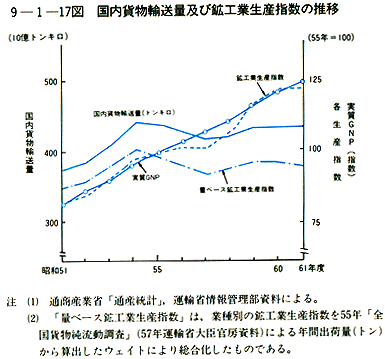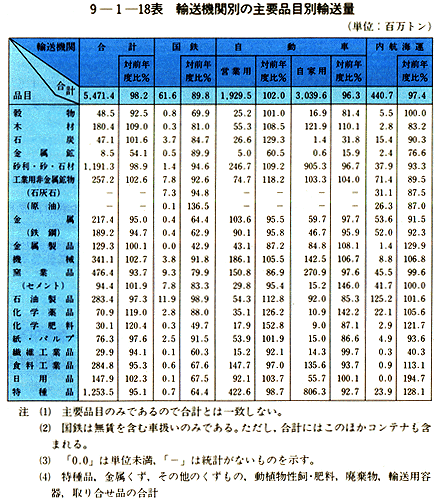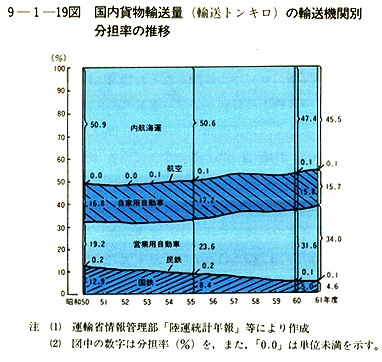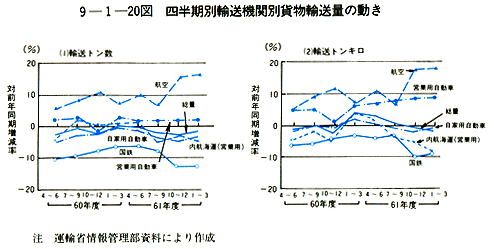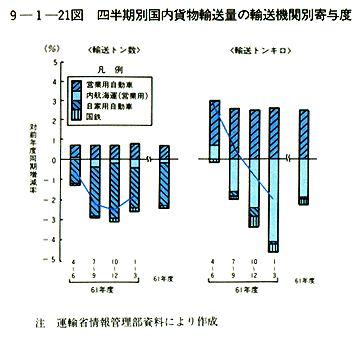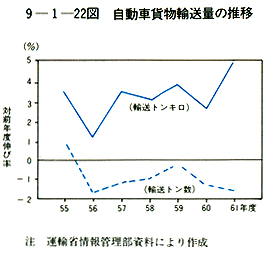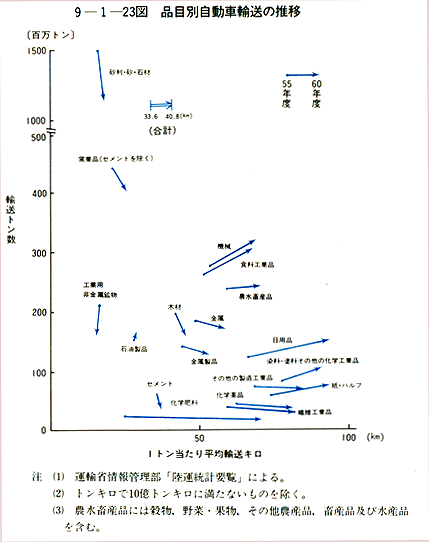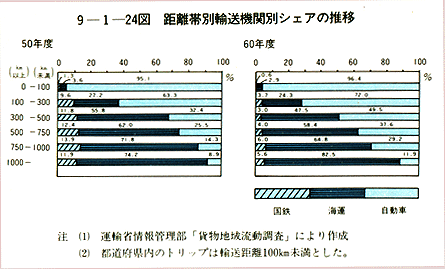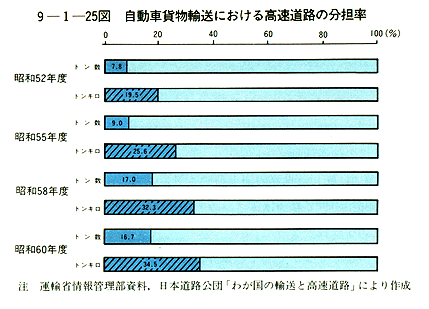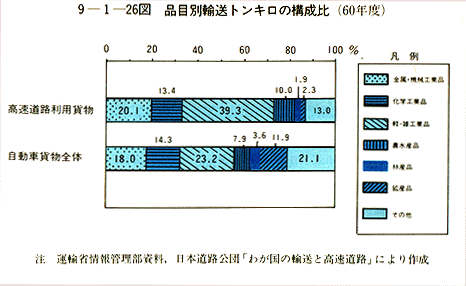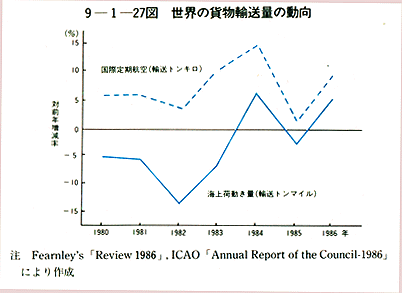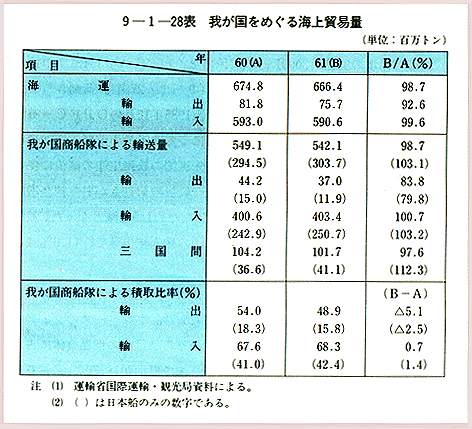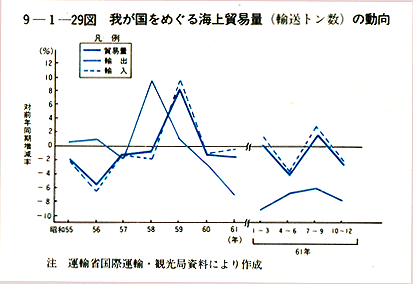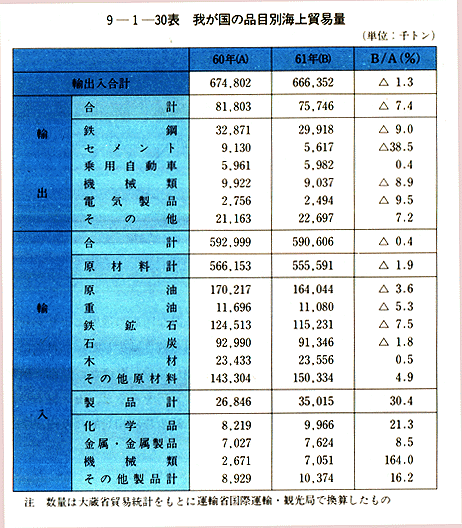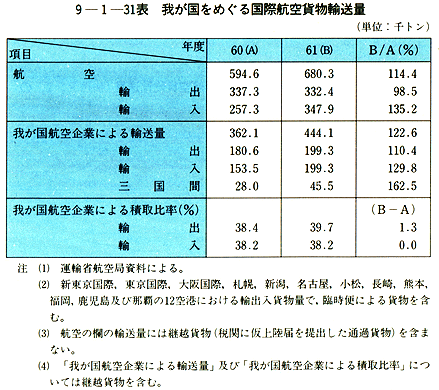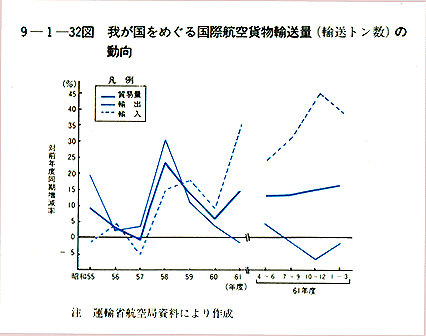|
2 貨物輸送の動向
(1) 国内輸送活動
ア 61年度の概況
(伸び悩む国内貨物輸送)
61度の我が国経済は,個人消費及び住宅建設が着実に増加したものの,急激な円高・ドル安の進行により輸出が弱含みで推移し設備投資の伸びも鈍化したため,実質経済成長率は2.6%(60年度4.2%)にとどまった。
このようななかで61年度の国内貨物輸送の動向をみると, 〔9−1−15表〕のとおり,総輸送トン数は,55億トン,対前年度比(以下同じ。)1.8%減と56年度以降6年連続して減少し,総輸送トンキロは,4,352億トンキロ,0.2%増とほぼ横ばいであった。
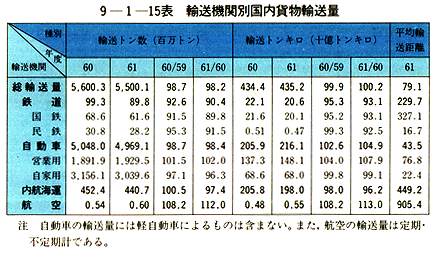
61年度の特徴としては,貨物輸送が伸び悩むなかで,営業用自動車及び航空が増加率を伸ばす一方,鉄道の減少率が大きくなり内航海運についても停滞する等,輸送機関別の明暗が顕著になったこと 〔9−1−16図〕,輸送機関別分担率(トンキロ)において昨年度初めて内航海運と肩を並べるに至った自動車が内航海運を上回ったこと等が挙げられる。
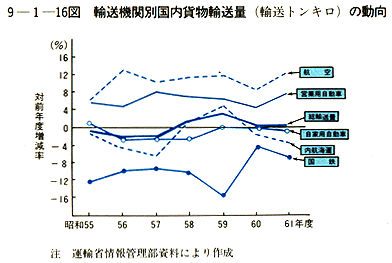
このような国内貨物輸送の伸び悩みの要因としては,経済のサービス化の進展や,それに伴う「モノ」以外のサービスに対する欲求の高まりによる消費生活のサービス化,第2次産業における知識集約的・高付加価値的産業の成長等による軽薄短小化の進展等が考えられる。このため実質GNPが伸びているにもかかわらず,鉱工業生産が量ベースで停滞し,貨物出荷量も伸び悩んでいる 〔9−1−17図〕。
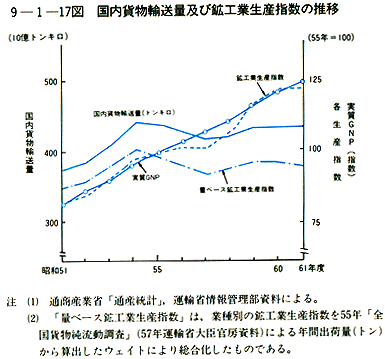
イ 輸送機関別輸送動向
(大幅な減少となった国鉄)
輸送機関別にみると,国鉄は,61年11月に車扱の運転本数の大幅な削減等のダイヤ改正を行ったため,コンテナは増加(輸送トン数3.2%増)したものの車扱が減少(同13.0%減)し,全体としては輸送トン数が10.2%減,輸送トンキロで6.9%減と大幅な減少となった。品目別(トン数ベース,以下同じ。)にみても 〔9−1−18表〕,原油を除く全ての品目で減少しており,そのうち,セメント,石炭等で減少が目立っている。
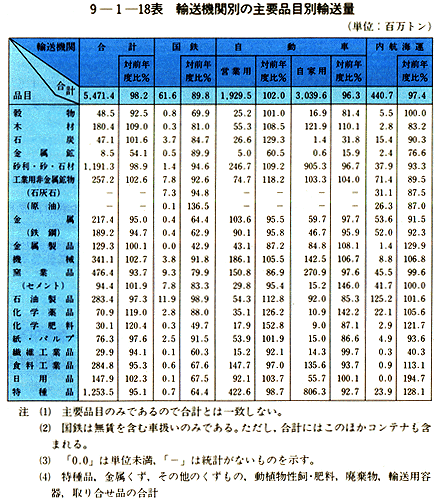
かつて国鉄は国内貨物輸送の基幹的輸送機関として,我が国経済の発展に大きく寄与してきたが,産業構造の変化,各種交通機関との競争が展開されるなかで物流ニーズに即応した輸送サービス提供のための輸送体制の変革に立ち遅れ,貨物輸送量は45年度の624億トンキロをピークに逐年減少を続けた。
国内貨物輸送に占めるシェアでも61年度トンキロベースで4.6%となってその幕を閉じ,62年度より民営会社として新たなスタートを切った。
(営業用で増加,自家用で減少する自動車)
自動車は,輸送トン数で1.6%減と6年連続の減少となったが,輸送トンキロでは4.9%増と増加を続けている。このうち営業用自動車鮭,輸送トン数で2.0%増,輸送トンキロで7.9%増となった。品目別では,砂利・砂・石材,機械等が増加し,窯業品,金属製品等が減少した。一方,自家用自動車は,輸送トン数で3.7%減,輸送トンキロでも0.9%減となった。品目別では,木材,機械等が増加し,砂利・砂・石材,特種品等が減少した。営業用が増加し,自家用が減少するという傾向が56年度以降続いているが,これは高度化するニーズに対応する自家用車による配送の限界,積載効率・実働率の低さからくるコスト高等の問題点を解決するために,営業用車利用への転換が進みつつあることが背景と思われる。
また,宅配便は,物流ニーズの小口高頻度化や利用者ニーズに適合したサービスにより,取扱個数で24.2%増と前年度に比べ伸び率は減少したものの依然高成長を続けている。
(輸送トンも減少に転じた内航海運)
内観海運は,輸送トン数が2.6%減と減少に転じ,輸送トンキロは3.8%減と前年度に引き続き減少した。品目別では,化学薬品,特種品等が増加し,粗鋼の生産量が7.1%の減少となる等,重厚長大産業の低迷を反映し鉄鋼,石灰石,原油等が減少した。
(好調が続く航空)
航空は輸送トン数で12.0%増,輸送トンキロでも13.0%増と増加を続けている。このうち,幹線は輸送トン数で11.3%増,輸送トンキロで11.8%増,ローカル線はそれぞれ13.4%増,16.2%増であった。国内航空貨物の品目別シェア(重量ベース)をみると機械部品が19.0%と大きく,以下書類・印刷物(14.1%),水産品(13.6%),衣類(7.9%),野菜(7.6%)等となっている(運輸省航空局資料による。)。
(普通倉庫は伸び悩み,冷蔵倉庫は増加)
次に営業倉庫の取扱量をみると,普通倉庫(1〜3類倉庫〉の入庫量は0.8%増の1億3,541万トンで前年度(2.8%増)と比べ伸び率が鈍化した。品目別では,金属製品・機械食料工業品等が増加している。一方,平均月末在庫量は0.1%増の1,881万トンと前年度(4.6%増)と比べ伸び率は縮小し,年間回転数は7.20回(前年度7.15回)と高水準となった。
また,冷蔵倉庫については,入庫量は6.9%増(前年度3.8%増)の1,184万トンと増加し,品目別では,冷凍水産物,畜産物等が増加している。一方,平均月末在庫量は,6.4%増(前年度3.5%増)の216万トンと増加し,年間回転数は5.49回(前年度5.47回)となった。
(分担率で内航海運を上回った自動車)
以上のような輸送動向により,61年度の輸送機関別国内貨物輸送トンキロの分担率は,鉄道は前年度に比べ0.4ポイント減の4.7%(うち,国鉄は0.4ポイント減の4.6%),自動車は2.3ポイント増の49.7%(うち,営業用は2.4ポイント増の34.0%,自家用は0.1ポイント減の15.7%),内航海運は1.9ポイント減の45.5%となり,昨年度初めて内航海運と肩を並べるに至った自動車が内航海運を上回る結果となった 〔9−1−19図〕。
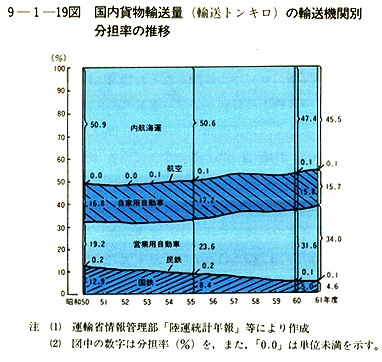
(四半期別の輸送動向)
さらに,四半期別の輸送動向を輸送量と輸送機関別寄与度の推移でみると 〔9−1−20図〕, 〔9−1−21図〕のとおりである。国鉄は61年11月のダイヤ改正で車扱の運転本数を大幅に削減したために,60年度から縮小傾向にあった輸送トン数輸送トンキロの減少率が61年10〜12月期には再び拡大し,62年1〜3月期には輸送トン数が前年同期比12.8%減輸送トンキロが同9.0%減となった。
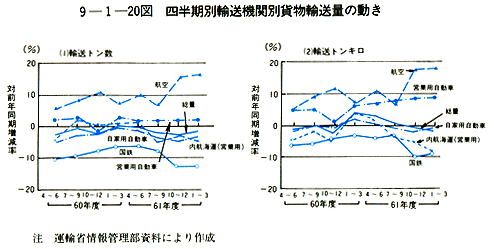
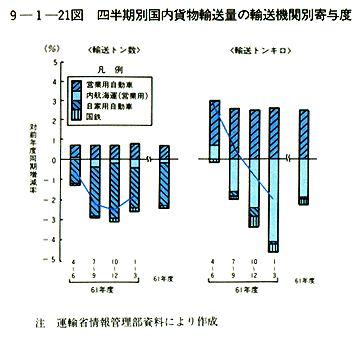
自動車は輸送トン数が61年度の対前年同期比で年度を通じて減少傾向が続いたが,輸送トンキロではいずれの四半期とも前年を上回った。これを営業用自動車についてみると,輸送トン数は年度を通じて対前年同期比2%前後の安定した伸びとなりており,輸送トンキロでも61年1〜3月期以降5期連続で伸び率が増加するなど好調に推移している。品目別では,年度前半は砂利・砂・石材,機械等が,後半は工業用非金属鉱物,廃棄物等がそれぞれ輸送トン数の増加に寄与した。一方,自家用自動車は年度後半に廃棄物の輸送量が減少したこと等により輸送トン数の減少率が拡大した。
内航海運(営業用)は,粗鋼の生産量が61年7〜9月期に対前年同期比7.9%減と大きく落ち込んだことや石炭の生産量が減少(2.9%減)に転じたこと等により輸送トン数,輸送トンキロとも61年7〜9月期に対前年同期比で減少に転じた。また,年度後半も原油の輸入量が対前年同期比で7.0%減少(年度前半は同0.6%増)したこと等により,輸送トン数輸送トンキロともに減少が続いている。
航空は,60年度に輸送トン数輸送トンキロともに伸び率が一けた台と鈍化していたが,61年度後半になると再び増勢が強まり,62年1〜3月期には,対前年同期比で輸送トン数が16.1%増,輸送トンキロが17.8%増と高い伸びになっている。
ウ 輸送距離を伸ばす自動車貨物輸送
(トンで減少,トンキロで増加する自動車貨物輸送)
61年度の自動車輸送量は,輸送トンキロの分担率で内航海運を上回り,全輸送量の半分を占めようとしている。しかし,輸送トンキロの伸びに対し,最近のトンベースの輸送量は低迷する傾向にあり 〔9−1−22図〕,したがって1トン当たりの平均輸送距離の伸びが著しい。この平均輸送距離と輸送トン数の推移(55年度〜60年度)を品目別に示したのが 〔9−1−23図〕であるが,これによると,ほとんどすべての品目で平均輸送距離が伸びている。このうち,機械,食料工業品,日用品等は,輸送トン数,平均輸送距離ともに大きく伸びており,輸送トンキロの増加に寄与している。また,輸送トン数はあまり変化はないが,化学工業品(肥料,薬品,その他),紙・パルプ,繊維工業品等を中心に平均輸送距離が大きく伸びており,高速道路網の整備に伴う事業所の分散等を背景に,製造工業品の輸送サービスエリアの拡大がうかがえる。
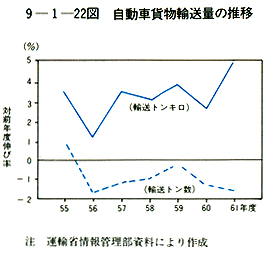
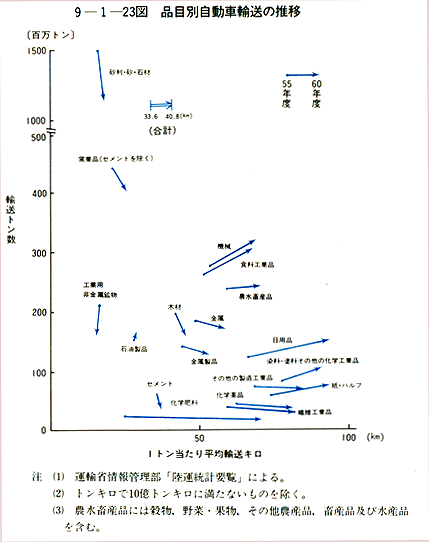
一方,公共投資の抑制等を背景に,砂利・砂・石材,窯業品,木材等の建設関連貨物を中心に輸送トン数の落込みが自立ち,最近の輸送トン数低迷の要因となっている。
(長距離化する自動車貨物輸送)
このような自動車貨物の長距離化は,他の輸送機関からの貨物の転移によっても進んでいる。 〔9−1−24図〕は,距離帯別に,国鉄,海運,自動車の輸送トン数シェアを,50年度と60年度で比較したものであるが,自動車は,0〜100km帯で圧倒的なシェアを保っているほか,すべての距離帯でシェアを伸ばしているが,特に従来から海運が中心で,鉄道も優位を占める300〜1,000kmあたりの距離帯での進出が目立っている。
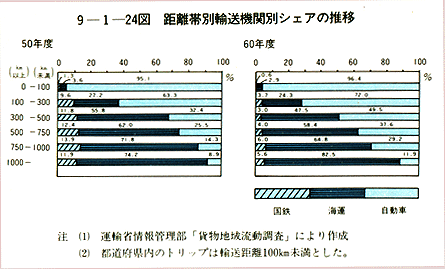
(自動車貨物輸送における高速道路の役割)
我が国の高速道路(高速自動車国道)は年々整備が進み,61年度末には開通延長は,3,910kmに達している。これに伴い貨物輸送に果たす高速道路の役割も大きくなっており,高速道路利用の貨物輸送量は,自動車貨物輸送量(トンキロベース)全体の約3分の1を占めるに至っている 〔9−1−25図〕。また品目別にみると,高速道路では,軽・雑工業品,金属・機械工業品等の工業製品輸送の割合が高くなっている 〔9−1−26図〕。
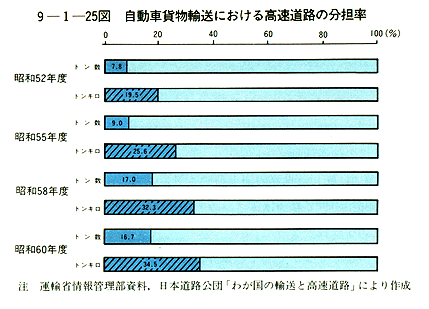
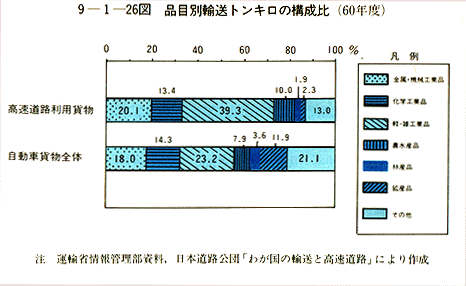
エ 軽自動車による貨物輸送の実態
61年度の調査によると,軽自動車による貨物輸送量は,輸送トン数で1億7,058万トン,輸送トンキロは25億4,854万トンキロであり,これは全貨物輸送量(軽自動車による輸送を除く。)の輸送トン数で3.1%,輸送トンキロでは0.6%にあたる。
(2) 国際輸送活動
ア 世界の輸送活動
(増加に転じた世界の海上荷動き量)
1986年の世界経済はアメリカの前年に続く緩慢な経済成長等により低調な成長となった。
このようななかで86年の世界の海上荷動き量は乾貨物が減少したものの,原油の荷動き量の大幅な増加により,トンベースで対前年比2.1%増の33億6,200万トン,トンマイルベースで5.4%増の13兆7,650億トンマイルと増加に転じた 〔9−1−27図〕。荷動き(トンベース)を品目別にみると,原油は,1985年12月のOPEC(石油輸出国機構)総会以来の価格の急落による欧米での消費の増加等により,7.9%増となった。鉄鉱石は,先進国の鉄鋼生産の減少に伴い対前年度比5.3%減となり,石炭は,一般炭の荷動きが引き続き増加したものの,原料炭の荷動きが減少したため1.5%減となった。穀物は,世界的な豊作により,穀物輸入国の輸入減少等で,11.6%減と2年連続の減少となった。
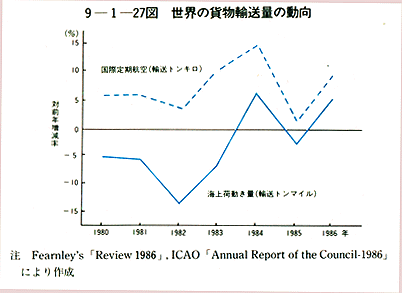
なお,世界における我が国輸出入貨物の海上荷動きは,トンマイルベースのシェアで2.1ポイント減の25.7%,トンベースのシェアで0.7ポイント減の19.8%となった。このうち品目別の世界全体に占める我が国のシェアは,トンマイルベースで原油が18.7%,鉄鉱石が45.4%,石炭が32.2%,穀物が27.5%であった。
(世界の航空貨物量は増加)
1986年の世界の航空貨物輸送量(定期航空)は,322億トンキロ,対前年比9.5%増と増加した 〔9−1−27図〕。このうち,我が国のシェアはICAO(国際民間航空機関)加盟156か国中アメリカに次いで第2位の9.7%(前年は9.0%)と増加した。
イ 我が国をめぐる輸送活動
(我が国の海上貿易量は輸出入ともに減少)
61年(暦年)の外航海運による我が国の国際貨物輸送量(トンベース)は輸出入とも減少し,全体で対前年比1.3%減となった 〔9−1−28表〕, 〔9−1−29図〕。
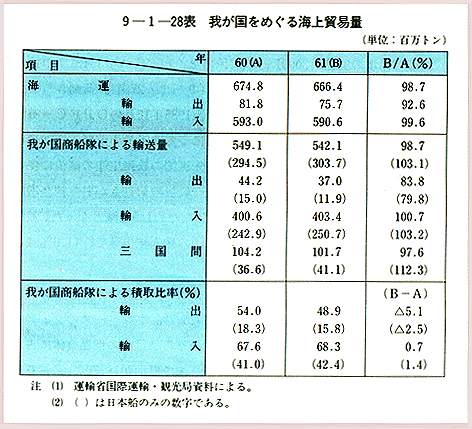
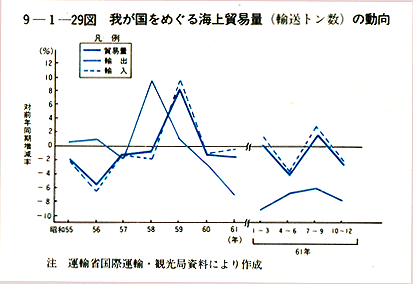
これを輸出入別にみると,輸出は急激な円高の進展により,対前年比7.4%減の7,600万トンと前年に引き続き減少した。品目別にみると,セメントが前年に引き続き大幅に減少したほか,鉄鋼,機械類,電気製品等が減少した。地域別シェアをみると,セメントの輸出の減少により中東のシェアが大きく減少し,相対的に欧州,アジアのシェアが増加した。
一方,輸入は,対前年比0.4%減の5億9,100万トンとなった。品目別にみると,国内の素材型関連産業の生産低迷を反映して,原油及び鉄鉱石が前年に引き続き減少したほか,石炭も減少に転じた。地域別シェアをみると,アジア及び欧州のシェアが高まり,太洋州及び北米のシェアが減少した。
こうしたなかで,輸入数量(トンベース)に占める割合は小さいが,機械類等を中心に製品輸入は大幅に増加している 〔9−1−30表〕。
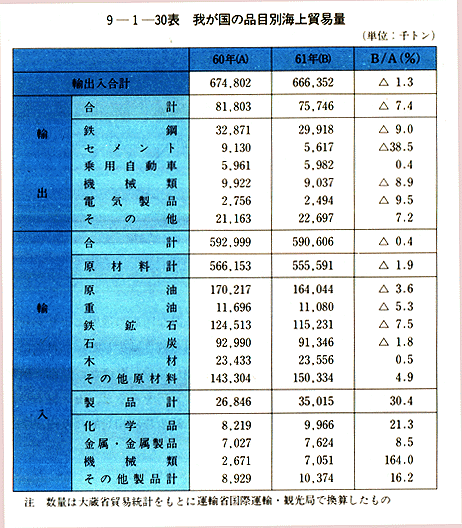
(減少した我が国商船隊による輸送量)
61年の我が国商船隊(外国用船を含む。)の輸送量をみると,対前年比1.3%減の5億4,200万トンとなった。輸出は,コンテナ船,在来定期船,不定期船の輸送量が前年に引き続いて減少したため,対前年比16.2%減の3,700万トンとなった。輸入は不定期船輸送量が鉄鉱石輸入の落ち込みにより減少したものの,油送船輸送量が増加したことに加えてコンテナ船輸送量も事務用機器を中心に増加したため,対前年比0.7%増の4億300万トンとなった。
この結果,我が国商船隊の積取比率は輸出が5.1ポイント減の48.9%となり,輸入は0.7ポイント増の68.3%となった(このうち,日本船の輸送量をみると,輸出は対前年比20.2%の減少,輸入は32%の増加に転じ,積取比率は輸出が2.5ポイント減の15.8%,輸入は1.4ポイント増の42.4%となった。)。
なお,三国間輸送は,極東〜北米航路を中心としてコンテナ船輸送量が大幅に増加したものの,海送船輸送量が減少したため,対前年比2.4%減の1億200万トンと減少に転じた。
(輸出は減少,輸入は増加した国際航空)
61年度の国際航空による我が国の貨物輸送量(継越貨物を除く。)をみると 〔9−1−31表〕, 〔9−1−32図〕,輸出はトンベースで対前年度比1.5%減の33万トン,ドルベースでは同28.3%増の242億ドルと,60年9月以降の急激な円高の影響等によりトンベースでは減少に転じたにもかかわらず,ドルベースでは大幅な伸びとなった。品目別(ドルベース)ではテープレコーダー,衣類等が減少し,事務用機器,熱電子管・半導体等が増加した。また路線別(トンベース)にみると,対前年度比で太平洋線及びモスクワ経由欧州線が減少し,他の路線では増加している。
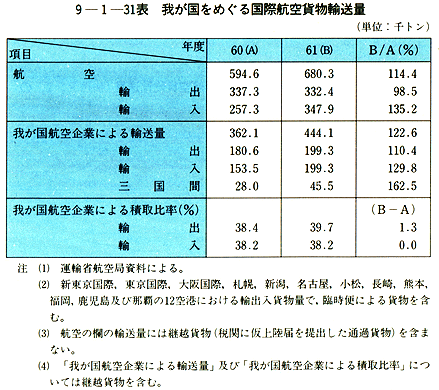
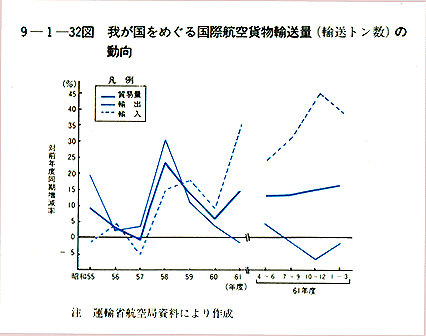
一方,輸入はトンベースで対前年度比35.2%増の35万トン,ドルベースでは同52.3%増の270億ドルと大幅に伸び,トンベース,ドルベースとも輸出を上回った。品目別(ドルベース)では食料品,化学製品,機械機器等が増加した。また路線別(トンベース)にみても,モスクワ経由欧州線の対前年度比65.9%増を最高にすべての路線で増加している。
我が国航空企業による輸送量(トンベース,継越貨物を含む。)をみると,輸出は対前年度比10.4%増,輸入も29.8%増となり,積取比率は,前年度に比べ輸出が1.3ポイント増の39.7%,輸入は横ばいの38.2%となった。
さらに四半期別の輸送動向をみると,トンベースで伸び悩んでいた輸出が,61年7〜9月期の対前年同期比で減少に転じ,逆に輸入は61年10〜12月期には同45.0%増と大幅に増加する等,円高による明暗を分けた。
以上のような輸送動向により,61年度の我が国貿易に占める航空貨物の割合(ドルベース)は輸出で11.3%,輸入で21.5%となり輸出入総額で60年度より3.3ポイント上昇の15.0%となった。
(大幅に拡大した運輸関係貿易外収支赤字/
運輸関係貿易外収支(運輸収支と旅行収支の合計)の動向をみると,61年度は95億6,800万ドルの赤字となり,赤字幅が30億3,600万ドル拡大した。このうち,旅行収支(63億6,300万ドルの赤字)の赤字幅は大幅に拡大し,海運収支(20億1,100万ドルの赤字)及び航空収支(9億5,800万ドルの赤字)も赤字幅を拡大した。
|