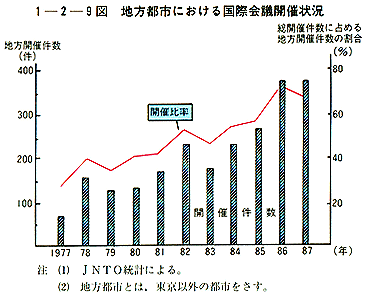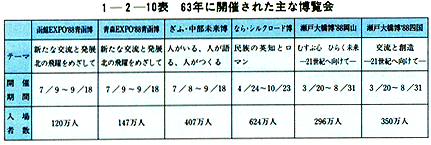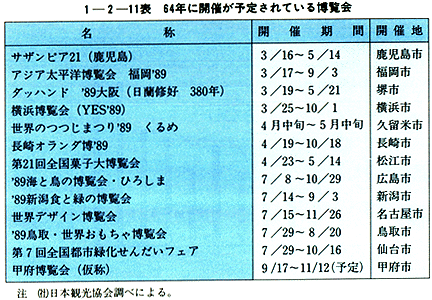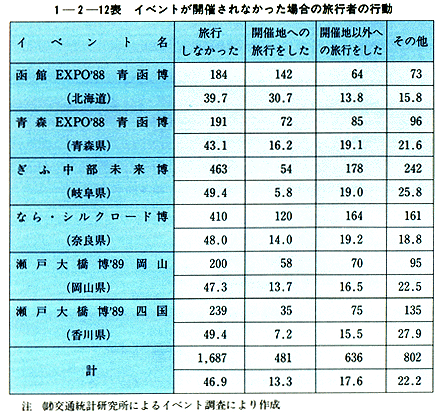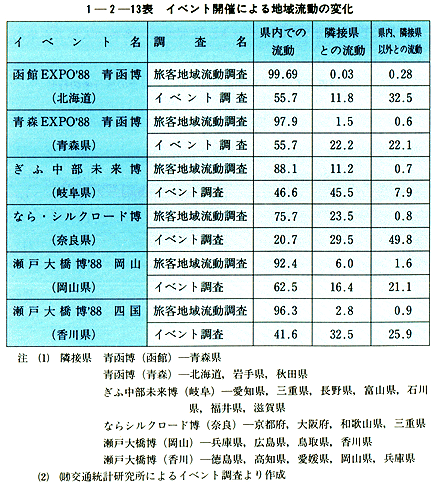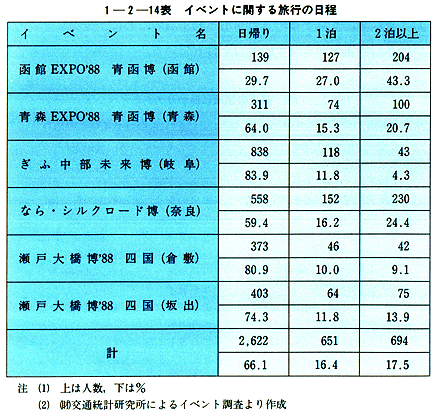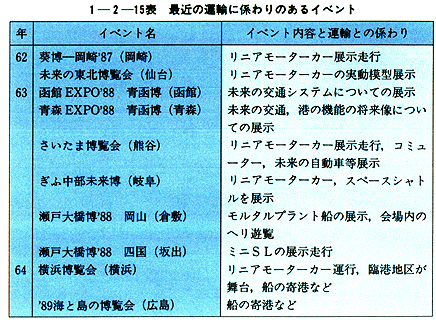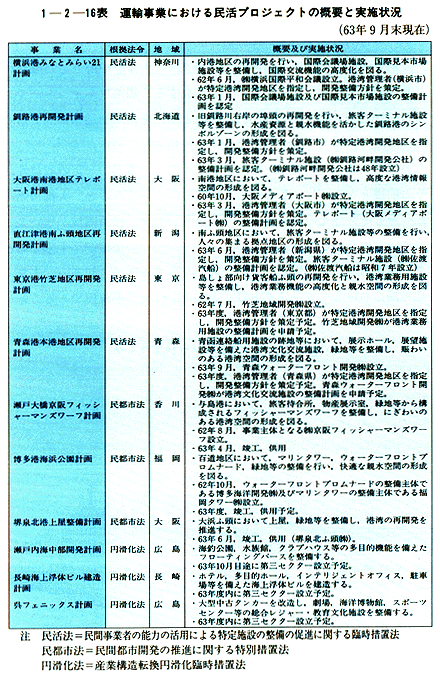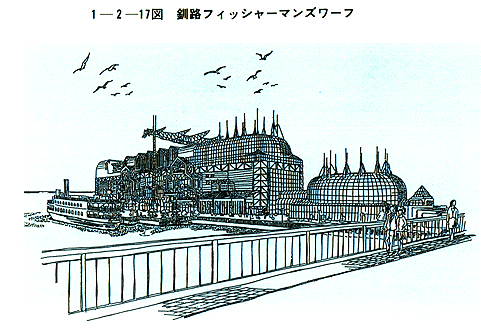|
2 地域の振興と暮らしの充実
(1) 急がれる地域の振興
(積極的な地域の活性化の必要性)
東京圏への一極集中が進展する一方で,地方の活力の低下が懸念されている。特に,産業構造調整の進展に伴い,農業や重厚長大型産業が相対的に縮小する一方,今後は都市型産業が発展していくと見込まれており,これを放置すれば東京圏への一極集中と地域経済の停滞が一層強まるおそれがあることから,積極的な地域活性化施策の展開が求められている。
(イ) 地域活性化を推進するに当たっての視点
地域の活性化を図るに当たっては,まず,東京圏に過度に集中している諸機能を分散し,多極分散型国土の形成を図るための受け皿としての基盤づくりが必要である。その際,今後成長の見込まれる都市型産業の波及力を有効に活用するとの観点から,都市型産業の発展が期待できる中枢都市等を核とした広域経済圏の戦略的な育成が重要となることにかんがみ,広域経済圏内における幹線交通ネットワークや,経済圏相互の交流を促進する高速交通ネットワークの形成が必要となるほか,国際化の流れに対応して,地域が直接世界と交流しうる体制作りも必要となろう。
また,地域の魅力を高め,定住の促進を図ることを必要である。高速交通ネットワークは,大都市の情報や文化活動に対する地方からのアクセスとしても重要な機能を果たすと考えられる。また,地域交通ネットワークの維持整備は,日常生活の基盤として必要不可欠であり,さらに,地域の経済力そのものを高めるために,雇用機会の増大や所得の拡大等を図るための産業の振興も重要である。他方,地域特性を活かした観光の振興や,多数の人々が集まるという交流機能を有する鉄道駅,空港,港湾などのターミナルを活用した地域の活性化,イベントの振興等は,地域住民にとっての地域の魅力度を高めるのみならず,地域内,地域間の交流を深め,国民の自由時間活動の充実にも資することとなろう。
(2) 地域の振興と交通ネットワーク
(ア) 交流の基盤となる幹線交通ネットワーク
幹線交通ネットワークは,多極分散型国土を形成するに当たっての骨格として,地域経済社会の均衡ある発展の基盤となるのみならず,国民生活の面でも,所得と自由時間の増大等に伴う幅広い交流活動の拡大を支える重要な役割を果たしている。
(a) 航空ネットワークの整備
航空は,特に,高速交通ネットワークによる全国一日交通圏を形成するうえで重要な役割を担っている。しかしながら,効率的な航空路線網を形成する上で,東京国際空港及び大阪国際空港の処理能力が大きなネックとなっていることにかんがみ,東京国際空港の沖合展開事業,関西国際空港の整備を鋭意推進するとともに,就航機材のジェット化,大型化に対応するため,地方空港の滑走路の延長,新設等を進めているところである。また,国内航空路線網について,61年7月の東京-鹿児島線のトリプル化を皮切りに,逐次ダブル・トリプルトラック化を図ってきているが,今後とも航空企業間の競争促進を通じ,路線網の拡大を図っていくこととしている。
(b) 鉄道ネットワークの整備
鉄道は,63年3月の青函トンネル,同年4月の瀬戸大橋の開業により,北海道,本州,四国,九州が1本のレールで結ばれた。これにより,ネットワークはさらに充実したものとなり,インターブロック交流圏の形成に対する期待が高まっているのをはじめ,地域間交流の活性化に大きな役割を果たすことが期待される。今後は,鉄道の有する特性を十分に発揮し,交流可能圏の拡大に資するため,軌道の改良や高性能車両の導入等により在来線の高速化を進めるとともに,新幹線と在来線が一体となった広域的な鉄道のネットワークの形成が必要である。JR各社は,逐次都市間の所要時間短縮を図っており,例えば,上野-富山間は,従来3時間49分かかっていたのが,63年3月のダイヤ改正により3時間26分に短縮された。また,これまでにない試みとして,山形と福島間の在来線を大改良し,新幹線と直通運転を行う幹線鉄道活性化事業を63年度から進めている。
なお,整備新幹線については政府・与党により設置された「整備新幹線建設促進検討委員会」において検討中である(第4章第1節1.(1)(ア)参照)。
(c) 高速バスネットワークの整備
一方,主に都市間旅客輸送において,近年著しい伸長を見せ,全国的なネットワークを形成しつつあるのが高速バスである。これは,高速道路の整備が進捗していること,運賃レベル,所要時間,サービス等の要素において高速バスが他の交通機関に対し一定の競争力を有していることがその要因と考えられる。東京-弘前間の夜行便等の長距離便が設定され,快適な車両の導入とも相まって人気が高まっているとともに,盛岡-弘前間,福岡-熊本間のように地方の主要都市間を結ぶ路線や主要空港等から周辺の主要都市への路線が設定されており,これらは上記のような高速バスの競争力を発揮した例といえよう。
(d) 既存のネットワークの効率的活用
このように,幹線交通ネットワークは着実に充実しつつあるが,今後は,国民のニーズの高度化,多様化に応えながら,一層の高度化,快適化等のサービス向上や幹線へのアクセスの改善,きめ細かなダイヤの設定等,既存のネットワークをさらに効率的に活用するための施策の充実が求められている。
(イ) 地域住民の生活基盤としての地域交通ネットワーク
地方圏においては,住生活の面では大都市ほどの切実な問題はないものの,日常生活を支える交通についてみると,地方中枢都市等においても大都市と同様の交通混雑の問題を抱えており,他方,農山村地域等においては,公共交通機関の維持すら困難な状況にあることから,豊かな地域社会を形成する上でも大きなネックとなっている。従って,地域の実状に即した交通ネットワークの維持整備は,地域の活性化を図るための重要な前提である。
(a) 地方中枢都市等における交通体系の整備
地方中枢都市においては,人口・産業活動の集積に伴い大量の通勤・通学輸送需要や業務交通が発生しており,道路の混雑が都市機能の円滑な発揮の妨げとなっているため,定時性,大量性等で信頼度の高い鉄軌道系の公共交通機関の整備が進められている。62年7月には仙台市で地下鉄が開業したほか,広島市では,市を南北に縦断する新交通システムが計画されており,これらは,今後の地域経済の発展の基盤としての役割を果たしていくことが期待されている。
また,地域の実状に応じ,既存の鉄道,バス等の交通機関を活性化することも重要であり,そのためには,ソフト面での施設を充実させることにより,既存の交通機関のサービス水準の向上を図ることが必要である。例えば,鉄道のダイヤを地域密着型に改善し住民の足としての機能を高めたり,地方都市のバスの活性化を図るため,都市新バスシステムの導入等により,バスの走行環境の改善と利用者サービスの向上を図っている。
(b) 中小都市,農山漁村等における公共交通の維持
一方,地方の中小都市や農山漁村では,過疎化の進行や,マイカーの普及等により,地方の中小民鉄やバスは輸送需要が減少し,事業者は苦しい経営を強いられている。地域住民の足の確保にとってこれら公共交通機関は欠かせないものになっており,事業者は運営の合理化を進める等の経営改善努力を講じているが,国も事業者の自助努力では維持し得ない路線について,地方自治体とも協力して助成措置を講じている。
(c) コミューター航空の育成
また,コミューター航空をはじめとする地域航空を導入しようとする動きが各地にみられる。地域航空は,地域に密着した輸送を行うものであること等の性格を有することから,その整備に当たっては地域の関係者,運航に当たる事業者がそれぞれの地域の特性に応じた航空輸送について自ら工夫し,検討していくことが基本的に重要であるが,国も航空の新たな可能性を拓くものとしてこれを支援することが必要である。このような考え方のもと,コミューター空港及び公共用ヘリポートの整備に対する無利子貸付制度等の助成措置が創設され,現在,地域航空の整備が推進されている。
しかし,我が国初の本格的都市間コミューター航空である大分〜広島〜松山間の輸送実績の低迷にみられるように,コミューター航空には輸送需要の確保等の課題があり,地域航空を一層展開していくためには,地域の開発との連携等を図っていくことが必要である。
(3) 地域の特性を活かした地域振興
地域の振興を図るためには,産業の振興により雇用の確保や所得の増大を図るとともに,地域内,地域間の交流活動の活発化を通じて魅力ある地域づくりを行い,地域への定住を図ることが必要である。その際,地域においては,いわゆる地域格差が地域特性の一面であることを認識し,地域の実情に応じた独創的なまちづくり・むらづくりを展開していくことが必要である。
運輸省は,後述するように,観光の振興,ターミナルを活用した地域の振興等ハード・ソフト両面にわたる地域振興のための諸施策を推進している。
これらの施策の効果的な活用による地域の活性化は,地域経済への波及効果をもたらすのみならず,国民の広汎な交流の促進を通じ,豊かな国民生活を築くことにも資することとなろう。
(ア) 観光の振興
観光は,国民一人一人の幅広い交流を通じ,国民が地域を理解し,体験する絶好の機会であり,また,消費機会の増大を通じ,地域経済にも大きな波及効果を有するものである。従って,観光の振興を図ることは,地域振興の観点からも多くの期待が寄せられている。
運輸省としては,このような期待に応え,国内観光及びインバウンドに係る国際観光の振興を総合的に推進するための「90年代観光振興行動計画(TAP90's)(P.99参照)を策定し,観光立県推進会議の開催等を通じて,具体的な観光振興施策を推進することとしており,また,施設整備の面では,リゾート地域,家族旅行村及び国際交流村の整備等を推進している。
(イ) ターミナルを活用した地域の振興
鉄道駅,空港,港湾などのターナミルは,本来的に多数の人々の集散という交流機能を通じて,地域の活性化に資するという特性を有している。
(a) 鉄道駅については,従来からこれを拠点としたまちづくりが行われてきている。今後は,音楽などの文化活動の場として鉄道の駅の持つ交流機能の活用を図るほか,鉄道の駅そのものについても高度利用を図りながら,必要に応じ駅付近の国鉄清算事業団用地の有効活用を図りつつ,周辺地区と整合性のとれた地域開発を行い,駅周辺の魅力を増大させることが求められている。
(b) 空港は,地域開発にとって重要な役割を果たしてきており,今後,空港を核とした地域づくりが期待される。
また,近年では新たに既存空港へのアクセス確保のほか,地域交通の整備の観点からのコミューター空港・ヘリポートの整備に対する期待が高まってきており,これに十分応えていく必要がある。
さらに,外国の例にみられるように,空港は,路線の集中が当該空港の利便性を高め,それが一層の路線集中や空港自体の国際化をもたらすという特性を顕著に有しており,この特性を活用した地域の活性化方策についても検討する必要があろう。
(c) 港湾は,近年では物流空間,産業空間としての役割に加え,都市住民と海との触れ合いの場としてアメニティ豊かな空間を形成するポテンシャルが注目されるようになっている。これを踏まえ,港湾においては,「ポートルネッサッス21」プロジェクトなど民間活力を活用した総合的な港湾空間の創造が行われつつあり,今後ともこれを一層強力に推進する必要がある。さらに,用地需要に対応しながら,海洋性レクリエーション活動などの進展に対応して静穏海域を確保するため,民間活力を活用しつつ開放性の海域で埋立地を造成する「沖合人工島整備事業」や,海上浮体施設を活用したウォーターフロント空間の形成などの新たな施策を推進していくことも必要であろう。
(d) 高速道路は,その全国的なネットワークの整備が進むにつれ,インターチェンジ周辺において,高速道路を活用した全国的な物流ネットワークが形成されつつある。今後,このようなインターチェンジ周辺を,情報機能や商流機能なども併せもった物流拠点として整備することにより,地域の活性化を図っていくことも検討していく必要がある。
(ウ) 地方の国際化の促進
わが国は,今後本格的な国際化の時代を迎え,世界に開かれ,世界とともに歩む国土づくりを進めることが強く求められている。このようななかで,全国各地域がそれぞれの特性を活かした,国際交流機能を分担することにより,地域の活性化を図るとともに,国際社会と共存する地域社会を築くことが必要になる。その意味において,国際的な会議,展示会などを開催するコンベンション・シティを地方圏に育成していくことは,近年の本格的な国際化の進展のなかで,地域の国際交流機能の分担とその活性化の極めて効果的である。現に近年の顕著な動向として,国際コンベンション開催の地方分散が進展している 〔1−2−9図〕。これは,国際コンベンション振興のもつ多大な意義にかんがみ,近年各地方都市が都市全体でコンベンションの誘致等に積極的に取り組み始めたことによるものである。
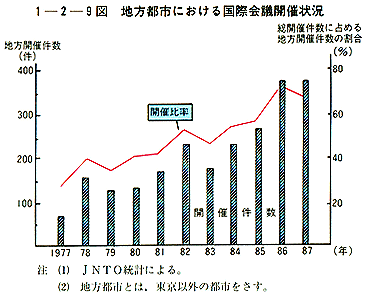
運輸省としては,国際コンベンション・シティ構想(P.106参照)及び国際会議場施設の整備を推進しているほか,利用者利便の向上,観光の振興,臨空型産業の展開,国際交流機能の整備等を図る見地から,空港及び港湾の国際化,国際観光モデル地区の整備等の施策を通じ,地方の国際化を支援していく考えである。
(エ) イベントと地域振興
イベントは,地域特性を活かした独自の活動の場を提供することにより,地域の産業,文化や住民意識を向上させ,大都市に依存しない個性的で活力ある地域の形成の契機となるものであり,「お祭り空間」としてそれまでにはなかった人や物の交流が生まれたり,新たな消費需要を生じさせて,様々な面で地域の産業の活性化に大きく寄与している。近年このようなイベントのもつ地域経済社会への波及効果の大きさに注目が集まり,文化,歴史,科学など各種の広範なテーマのもとに,全国各地で多くのイベントが開催され,多数の入場者を集めている 〔1−2−10表〕, 〔1−2−11表〕。
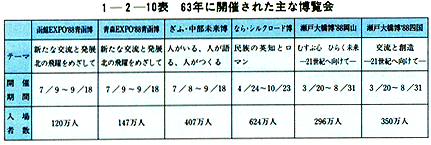
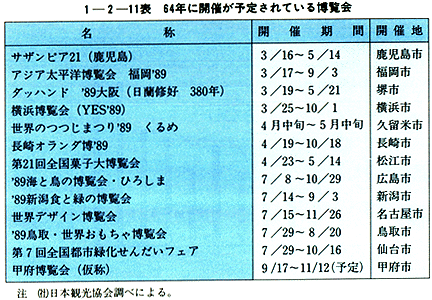
63年8月に運輸省の協力により運輸関係調査機関が青函博覧会(函館),同(青森),ぎふ中部未来博覧会,ならシルクロード博覧会,瀬戸大橋博覧会(児島),同(坂出)の6会場で行ったイベント入場者に対するアンケート調査(以下「イベント調査」という。)によると,「博覧会がなかったら旅行しなかった」という人が半数近くもおり,博覧会そのものが新規の旅行需要の発掘にかなりの効果があったことがうかがえる 〔1−2−12表〕。また,博覧会入場者がどういう地域から来ているかをみると,例えば,なら・シルクロード博のケースのように地域旅客流動調査では4分の1弱しかなかった県外との流動が,イベント調査では8割を占めているなど,通常に比べ遠方の地域からの人の流れもかなり発生していることがわかる 〔1−2−13表〕。
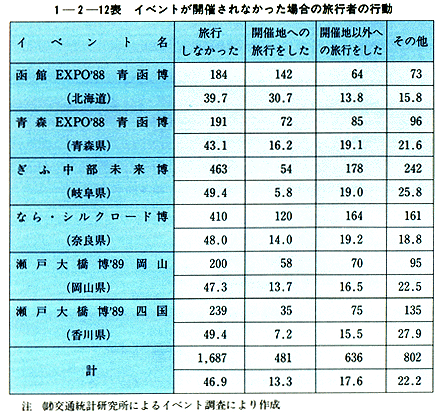
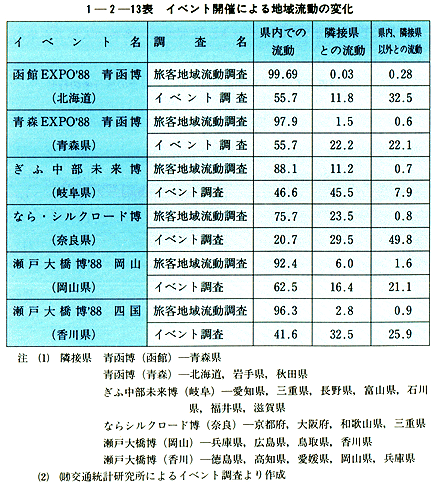
さらに,イベント調査により入場者の旅行日程をみると,多少のばらつきはあるものの,博覧会の入場者の7割近くが日帰りとなっている一方で,宿泊者も多数にのぼっており,ホテル等の観光事業もイベントによる恩恵を受けていることがうかがえる 〔1−2−14表〕。
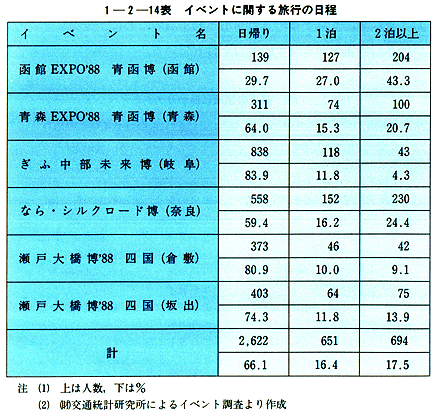
イベントの地域振興に対する効果は,パビリオン等の会場施設の建設費,人件費,広告費等のイベントの運営費,入場料,飲食代,土産品購入等直接的なものから,上記のような新規の旅行・宿泊等の運輸関連需要の創出に伴う間接的なものまで,さまざまな波及過程を通じて生じている。このような点で,運輸産業そのものにもイベントは大きな利益をもたらすものといえる。
ところで,イベントを成功させるとの観点から,このような一定期間内に大量に発生する人の流れを円滑にするため,交通機関の側では,臨時便の増発などの対応策を講じているが,開催者側でも,最寄りの駅から会場までの間,入場者をピストン輸送するための特別バスを運行するほか,6割を占める自家用車利用者のために十分な駐車場のスペースの確保を図るなどの努力を行っている。
また,運輸関係の施設そのものが,イベントのテーマになっていたり,演出の盛り上げに貢献している点も見のがせない 〔1−2−15表〕。例えば,港湾はイベント空間としての恰好の条件を備えている。観光船や帆船等の寄港に際した催し物や,全国各地において毎年開かれている港まつり等,港に関するイベントが数多く存在しているのも,その海と陸,人と物との結節点である交流拠点としての港湾がその基盤として有効であることを示している。一方,63年の青函トンネルと瀬戸大橋の開通は,日本列島を1つに結ぶ交通ネットワークの完成という面からとらえることも重要であるが,各々の地において開通を記念したイベントが開かれ,交通ネットワークに対する市民の啓蒙と地域意識の向上に一役買っていることも注目できよう。
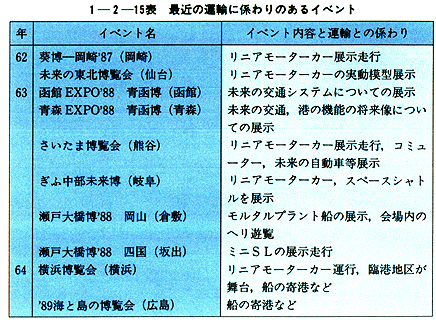
イベントに対して運輸省としては,61年から主要港湾都市の持ち回り方式(北九州,神戸,名古屋,横浜等)の「海の祭典」も含め,各地の港まつりに代表されるように,題材,場の提供といった支援の他,大量の人の流れを円滑にさばくため,輸送面での増強対策や観光業を通じた広報・宣伝活動の支援等多様な施策を推進している。
ところで,近年ではイベントに対する期待の高まりから,全国各地でイベントの開催が相次ぎ,テーマや出典内容が似通っていたり,開催時期が重複したりするといったケースがみられ,採算割れの事態に陥るものもあるといわれている。今後は地域の特色を活かしたイベントの個性づくりやPR対策,アクセスの確保等の対策を入念に講ずる必要があろう。
(4) 民間活力の活用による地域おこし
地域振興の基盤となるリゾート施設,国際交流の基盤施設等の諸施設や港湾におけるアメニティー豊かな空間の形成等を促進するためには,財源の確保や整備・運営主体のあり方等についての工夫が必要である。
その際,現下の厳しい財政事情を踏まえつつ,一方で,地域住民の多様なニーズに対応した効率的な施設の整備・運営を確保していくためには,民間活力を積極的に活用することが重要である。
運輸省においては,従来より民間の経営能力,効率性等を事業運営に導入する観点から国鉄の分割・民営化や日本航空(株)の完全民営化を図ったり,民間の資金・ノウハウ・技術等を導入しつつ内需の拡大と効率的な施設整備を進める観点から株式会社方式による関西国際空港の整備を進める等,民間活力を積極的に活用してきたところであるが,近年においては,行政の各般にわたって民間活力を活用する見地から,さまざまな制度面の整備が行われている。
すなわち,61年には「民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(民活法)」が制定され,経済社会の基盤の充実に資するような新しい施設(特定施設)の整備を民間事業者の能力を活用して促進するための税制,財政投融資等の支援措置が確立され,その後も逐次特定施設の追加が行われており,63年度は,当省関係では国際市民交流基盤施設,港湾文化交流施設,臨海部活性化施設,物流高度化基盤施設及び大灘難肺鉄道新線多目的旅客ターミナル施設の5施設が特定施設となっている。また,62年には「民間都市開発の推進に関する特別措置法」,「総合保養地域整備法(リゾート法)」が制定されるなど制度の充実が図られてきており,さらに,同年にはNTT株式の売払収入を活用した無利子貸付制度も創設された。
これらの制度の充実に伴い,全国で民活プロジェクトが進みつつある 〔1−2−16表〕。民活法関係のプロジェクトとしては,大都市圏においては,「横浜みなとみらい21計画」に基づく国際会議場・国際見本市場,「テクノポート大阪計画」に基づくテレポートの整備がすでに事業化されているほか,JR西日本の片町線と福知山線を結ぶ関西高速鉄道の多目的旅客ターミナル施設の63年度着工が検討されている。また,地方圏においては,釧路港に旅客ターミナルを中心とした賑わいと潤いのあるウォーターフロントを形成する「釧路フィッシャーマンズワーフ計画」 〔1−2−17図〕,佐渡と本州を結ぶ交通結節点である直江津港の旅客ターミナルの整備が事業化されている。
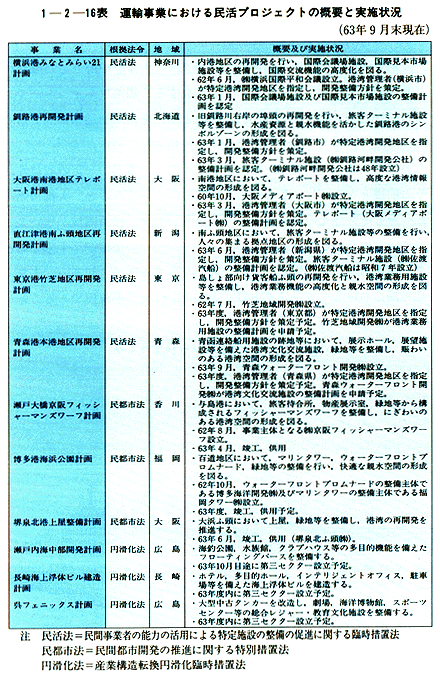
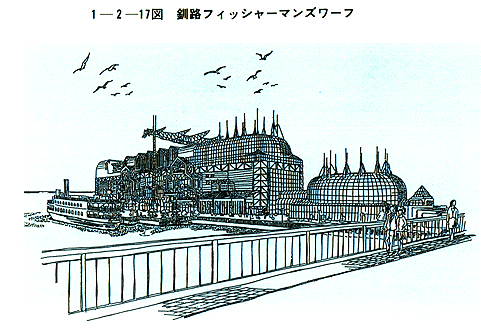
各種の事業に民間資金を導入するためには,事業の一定の収益性がその前提となる。しかしながら,地方圏についてみると,大都市圏に比べそもそも地元の民間の資本力が小さいこと,経済圏域が狭いこと等により事業の収益性が厳しいこと,ノウハウの蓄積が不十分であること等から事業化に至るまでに長期間を要するケースが多い。また,地方圏におけるプロジェクトは,大都市圏に比べ小規模であることが多く,一定の事業規模をインセンティブの付与の要件としている場合については,その要件に達しないケースも出てきている。
このように,地方圏における民間活力の活用については,さまざまな課題があることにかんがみ,NTT株式の売払収入を活用した無利子貸付制度の融資比率については,大都市圏の近郊整備区域が37.5%,既成市街地が25%であるのに対し,大都市圏以外では50%と格差が設けられた。さらに,63年6月に公布・施行された「多極分散型国土形成促進法」に基づく振興拠点地域におてい整備される民活法の特定施設については,税制の優遇措置の要件である事業規模の下限が10億円から5億円に緩和されており,これらにより民間活力の活用による地域振興の一層の展開が期待されるところである。
(5) 今後における地域振興施策の展開
運輸は,本来的に,交流を促進するという機能を通じ,地域振興に大きな役割を果たすことができると考えられる。特に,この交流を促進するという機能と,施設整備というハード面の施設を組み合わせることにより,その効果が相乗的に高まることが期待される。
このような観点から,運輸省においては63年度より,小樽市において「歴史的港湾都市のズーム・アップ事業」を展開している。これは,長い歴史を有する港湾都市における古い建築物等の潜在的な観光資源 〔1−2−18図〕に着目し,交通関係事業者の集客ノウハウの活用というソフト面の施策と,港湾環境整備というハード面の施策を組み合わせて,関係者の総力を結集して観光の振興を通じた港湾都市全体の活性化を図ろうとする新しい試みである。これにより小樽市の活性化が成功すれば,小樽市と同様の条件を備えた全国の他の港湾都市の活性化を図ることができると期待されるのみならず,今後の新しい地域振興施策展開上の1つのモデルケースとなるものと考えられる。

|