|
3 自由時間の充実と世界に開かれた社会に向けて
(ア) 観光レクリエーション活動の促進
こうした状況のなかで,最近の観光に係る状況についてみると,国内観光については,国民の自由時間の増大や自由時間活動に対する関心の高まり,観光の基盤となる高速交通体系の整備等を反映して量的にも着実な伸びを示すとともに,質的にも高度化,多様化の傾向が見られる。一方,国際観光については,円高等の影響もあって,特に日本人海外旅行者数の伸びが著しくなっている。 運輸省では,このような国民の観光レクリエーション活動の動向に対応し,国民の観光に対する期待に応えるため,62年9月に,日本人海外旅行の促進を図るための「海外旅行倍増計画(テン・ミリオン計画)」を,また,63年4月には,国内観光及びインバウンドに係る国際観光を振興するための「90年代観光振興行動計画(TAP90'S)」をそれぞれ策定し,観光レクリエーション活動の促進を図るための施策を総合的,計画的に推進することとしているところである。また,63年7月には,「Marine'99計画」を策定し,海洋性レクリエーション活動の振興を図るための施策を総合的,計画的に推進することとしているところである。
(イ) 90年代観光振興行動計画(TAP90's)等の推進
(a) 90年代観光振興行動計画(TAP90's)の策定
この行動計画は,中央及び各地方ごとに有識者からなる「観光立県推進会議」を開催し,観光振興に関する具体的施策を提言し,実行に移そうとするものであり,観光の振興による地域の活性化と地方の国際化をめざして,官民協調して「観光立県推進運動」を展開しようとするものである 〔1-2-19図〕。
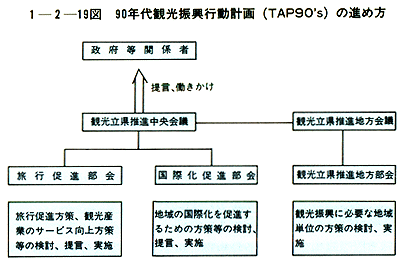
観光立県推進会議の中央会議及び地方会議においては,今後以下のような施策につき検討する。
(i) 旅行促進のための施策
(ii) 地方の国際化のための施策
なお,観光立県推進地方会議は,64年においては4月頃に熊本県及び長崎県を,6月頃に山形県及び宮城県をそれぞれ対象地域として開催することとしている。
(b) 観光振興のための具体的施策
(i) リゾート地域の整備等観光基盤施設の整備
ゆとりのある国民生活の実現,地域振興施策の展開,内需拡大等の政策課題に対応して広く国民が余暇を利用して滞在しつつスポーツ,レクリエーション,教養文化活動等の多様な活動を行うことができるリゾート地域を整備することが必要となっている。 このため,62年10月には「総合保養地域整備法」(いわゆるリゾート法)に基づき,リゾート地域の整備に関する基本的な事項等を定めた基本方針が告示されたところである。リゾート地域の整備については,三重,宮崎及び福島の三県の基本構想を63年7月に,兵庫及び栃木の二県の基本構想を10月に,また新潟県の基本構想を12月にそれぞれ承認したところであり,今後は承認された基本構想に基づき県を中心として整備を推進していくことになるが,運輸省としても,リゾート法に基づき,周辺の既存観光地との調和やその積極的活用により地域全体の活性化を図りつつ,魅力あるリゾート地域の整備を推進することとしている。 (国際市民交流基盤施設の整備) 我が国の国際的地位の高まりの中で,我が国において積極的な国際交流活動を展開し,諸外国との相互理解を増進していくことが必要となっている。 このため,63年6月に民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(以下「民活法」という。)の一部が改正され,新たに「国際市民交流基盤施設」が追加され,これにより施設の整備を行う民間事業者に対し税制・財投等の支援措置を講じることとなった。 「国際市民交流基盤施設」とは,我が国又は外国の経済・社会・技術等を効果的に紹介するための一群の施設のことであり,市民レベルにおける国際化の促進に資する交流拠点を形成し,国際相互理解の増進及び地域経済の活性化を図ることを目的とするものである。 (家族旅行村の整備) 家族旅行村は,国民の観光レクリエーション需要に対応して家族が恵まれた自然の中で手軽に利用できるキャンプ場,ピクニック緑地,スポーツレクリエーション施設,簡易宿泊施設等を整備するもので,現在26地区において供用が開始され,12地区において整備が行われている 〔1-2-20図〕, 〔1-2-21図〕。
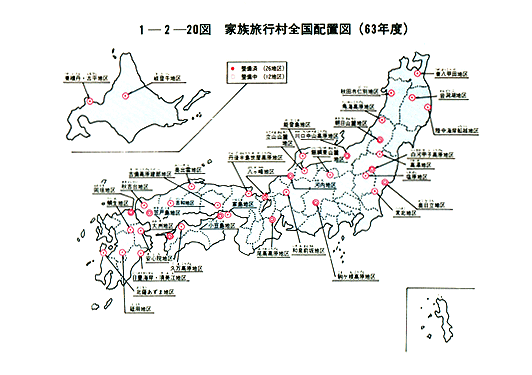
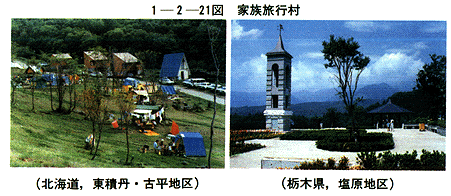
(ii) 国際観光モデル地区整備等外国人訪日促進施策の推進
外国人の訪日を促進することは対日理解の増進につながるのみならず,地方への外国人の訪問を促進することは当該地方の国際化にも寄与するものであることから,運輸省としても,外国人の訪日促進,とりわけ,地方への訪問を促進するため,以下のような施策を推進している。 (国際観光モデル地区の整備等) 国際観光モデル地区構想は,海外に紹介し得る観光資源を有する観光地であって,外客受入体制の整備に熱心な地域を国際観光モデル地区として指定し,外客が安心して一人歩きすることのできる環境づくりを進めることにより,当該地域への外客の来訪を促進し,もって,地方の国際化,国際的相互理解の増進等に寄与しようというものである。 運輸省では,61年3月に15地区を第1次指定し,次いで62年6月には18地区を第2次指定した。さらに,同年10月及び63年3月に3地区を追加指定した(合計34道県36地区, 〔1-2-22図〕)。
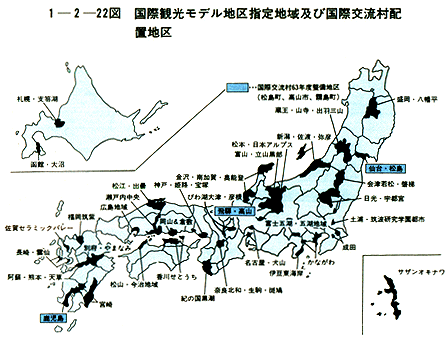
国際観光モデル地区においては,地方公共団体等が中心となって整備実施計画を策定し,これに沿った整備を進めることとしているが,運輸省では,国際観光振興会等と連携して,「i」案内所注1),総合案内板,各種標識等の整備,パンフレットの充実,善意通訳注2),ホームビジット注3)の普及等の事業を推進している。
(iii) コンベンションの振興
コンベンションの振興は,①人的交流による国際相互理解の推進,②関連施設の整備や消費機会の増大による内需の拡大,③地域経済の活性化,地方都市の国際化への寄与等,多大な意義を有するものである。 我が国では,コンベンションに対する取組みの歴史が浅いこと等から,誘致体制の未整備,関連施設の不足,人材やノウハウの不足などの多くの問題点を抱えており,国際会議開催実績を国際比較すると, 〔1-2-23図〕のとおり,我が国は欧米諸国に比べ,大きく立ち遅れているばかりか,都市別に見れば,バンコク,シンガポールといったアジアの諸都市に対しても立ち遅れが見られる状況にある。
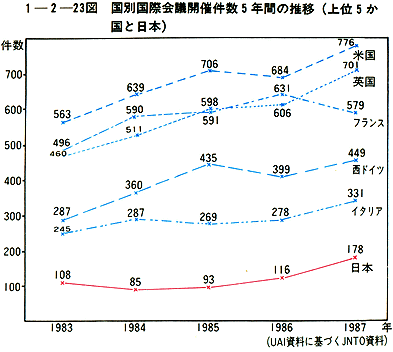
このような状況のなかで,地方自治体においては,近時,コンベンションの誘致,開催に積極的に取り組むようになってきており,この結果,コンベンションの開催地も地方へ広がりをみせるようになってきている。
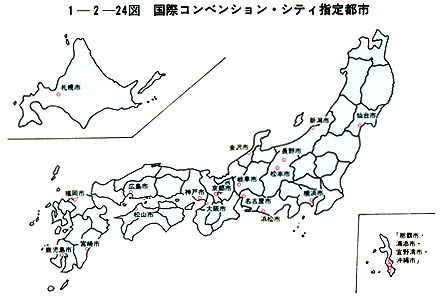
これらの諸都市に対しては,①国際観光振興会の海外宣伝事務所を通しての諸外国への宣伝,②海外コンベンション・トレードショーへの参加及び海外巡回セミナの実施,③コンベンションは開催決定権者の招へい等による国際コンベンションの誘致,④コンベンション研修会の開催,⑤コンベンション・ミッションの派遣等の支援措置を講じることとしている。
(iv) 観光情報提供体制の整備
このような状況に対応して,高度情報化社会の進展に対応した観光情報システムを充実していく必要があり,このため,(社)日本観光協会,(特)国際観光振興会等の観光関係団体が中心となって,国内観光地情報,訪日外客のための情報等の収集体制の整備を進めており,このようにして収集された情報を運輸機関,宿泊機関,旅行業者等のシステムとの連携により効率的に提供するシステムの整備を図るなど,引き続き高度情報化社会の進展に対応した観光情報システムを充実していくこととしている。
(v) 旅行者保護施策
さらに,63年3月には警察庁,都道府県,旅行業協会等の協力を得て「いい旅しよう'88」キャンペーンを展開し,①旅行者に対する登録業者の利用の呼びかけ及び旅行者保護のための営業保証金の供託制度等の周知,②無登録業者に対する監視体制の整備,③登録業者に対する立入検査等,旅行業法の遵守の総点検を行い,また無登録業者の取締りのため,警察との連携を一層強化するなど,旅行業法の遵守を徹底し旅行者保護の一層の充実を図っている。
(ウ) 海外旅行倍増計画(テン・ミリオン計画)の推進
(a) 海外旅行倍増計画の策定及び見直し
運輸省は関係省庁の協力を求めつつ,66年までに日本人海外旅行者数を1,000万人の水準に乗せることをめざす「海外旅行倍増計画」を62年9月に策定した。さらに,各方面からの提言等を取り入れつつ,日本人の海外での安全対策や長期連続休暇取得運動の充実等を図るため63年7月に所要の改正を行い,国民の海外旅行を促進するための施策を強力に推進している。 (日本人海外旅行の状況) 本計画の実現に向けての官民一体となった活動に,折からの円高に伴う海外旅行の割安感の浸透とも相まって,62年の出国日本人数は対前年比23.8%増の683万人に達した。しかしながら,これを対人口比でみると,依然として我が国では年間国民の5.6%しか海外旅行をしておらず,他の先進国に比べて極めて低い水準となっており,同じ太平洋にあるオストラリアの約10%(61年)と比べても半分に過ぎない 〔1-2-25図〕。
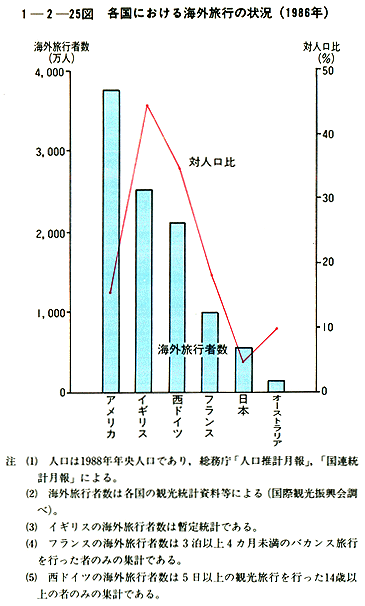
(計画の具体的実施状況)
① 海外旅行促進キャンペーン等の実施
② 海外における日本人観光客の受入環境の改善
③ 海外旅行促進の環境整備
④ 航空輸送の整備
⑤ 外航客船旅行の振興
(b) 海外旅行者安全対策等の検討
(c) 海外旅行促進フォーラムの活動
(ア) 国際交流の促進
海外旅行の促進を図ることは,国際的な相互理解の増進,国民の国際感覚のかん養などといった意義のほかに,諸外国の経済振興,我が国及び相手国の国際収支のバランス改善への寄与等の効果をも有するものであり,今後,相互依存関係の深まる国際社会において我が国の安定的な存立を確保するためには極めて重要になってきている。このような観点から,「市場アクセス改善のためのアクション・プログラムの骨格」や「世界とともに生きる日本-経済運営五箇年計画」においても,日本人海外旅行の促進等を図るべきことが盛り込まれている。 また,外国人旅行者受入体制の整備により,我が国を訪れた外国人旅行者が主体的に日本の姿を見聞きし,日本人との触れ合いの機会を持つことができるような環境を整えることも,国際的な相互理解の増進,地方の国際化にとって重要である。 運輸省では,「海外旅行倍増計画」及び「90年代観光振興行動計画」に従って,日本人の海外旅行及び外国人の訪日の促進のための施策を総合的,計画的に実施することとしているが,海外旅行促進フォーラムの試算により「海外旅行倍増計画」の国際収支面での効果を見てみると, 〔1-2-26表〕のとおり66年には265億ドル以上が諸外国に還元されることが見込まれている。
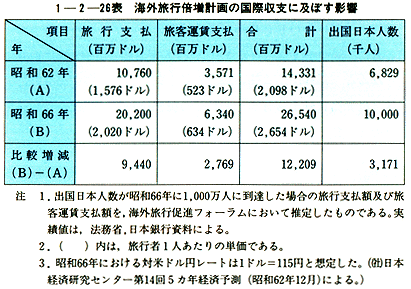
〔1-2-27表〕は先進諸国のなかで貿易収支が黒字である日本と西ドイツの貿易収支と旅行収支を比較したものである。西ドイツでは,貿易黒字の還元に旅行収支の赤字が大きく貢献していることがわかるが,我が国においても同様に,その貢献する割合が高まってきている。
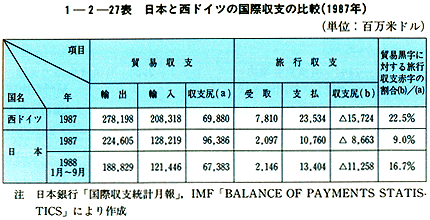
各国が外国からの旅行者の受入れに力をいれるなか,この計画が他国に例をみないアウトバウンド施策であることから,WTO(世界観光機関)やOECD等の国際機関において大きな反響を呼ぶとともに,エコノミスト(イギリス),人民日報(中国)等に取り上げられるなど諸外国から強い関心が示されており,観光の分野における「世界に貢献する日本」としての役割に対し,各国から強い期待が寄せられている。
(イ) 国際協力の拡充
(a) 多様化する経済協力要請
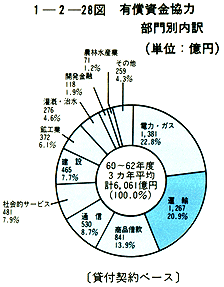
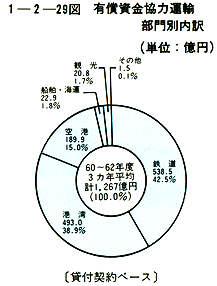
加えて,最近は,新たに施設を整備するだけでなく,既存施設の近代化,効率化等即効的な協力や施設の管理・運営等ソフト面での協力要請も多くなり,また,観光や気象等,分野も多様化するなど,我が国に対してより質の高い協力が要請されている。
(b) 運輸分野における経済協力の動向
62年度は,新たに協力を開始した中国の鄭州・宝鶏間鉄道電化計画,タイの観光開発計画,パキスタンの港湾浚渫船計画等を含め,17件に対し総額1,049億円に及ぶ円借款の交換公文が締結された。また,無償資金協力としては,スリランカの自動車整備工訓練センター建設計画,パキスタンの船員養成学校機材整備計画,スーダンの燃料輸送網整備計画等12件に対し総額85億円の供与の交換公文が締結された。 (技術協力) 運輸省は,中国の北京首都空港施設地区拡張計画インドのニューデリー駅近代化計画,カルカッタ・ハルディア港開発計画等62年度において新たに調査に着手したものを含め合計43件について国際協力事業団を通じてフィージビリティ・スタディ又はマスタープランの作成を行う開発調査を行った。また,同事業団を通じ,30の国及び国際機関に対し長期110名,短期145名の専門家を派遣し,64の国及び地域から359名の研修員を受け入れるとともに,開発途上国の人材育成に寄与するため,中国鉄道管理学院等6件のプロジェクト方式技術協力注)を実施した。 また,同事業団を通じ,62年度に鉄道車両の保守・管理等の専門家チームをインドネシアに,さらに63年度にはバスの保守・管理等の専門家チームをフィリピンにそれぞれ派遣して,既に円借款等により供与された鉄道車両やバスに対して,メインテナンスの現場指導を行いつつ技術移転を図る,いわゆるリハビリテーション協力を実施している。このような協力は,開発途上国の技術水準の一層の向上に寄与するものであるので,我が国の経済協力の質的向上を図るため積極的に推進していく必要がある。 (観光協力) 観光地の開発,受け入れ体制の整備等観光分野における協力は,開発途上国にとって外貨の獲得,雇用の増大に直接つながるばかりでなく,我が国にとっても,これらの協力に伴って生ずる海外への観光客の増大が,国際収支の黒字の減少にも寄与するものであるので,積極的に推進していく必要がある。62年度には,諸外国からの観光開発に対する協力要請に対処するため,(財)国際観光開発研究センターに委託して南太平洋地域開発基礎調査を実施したほか,国際協力事業団を通じてギリシャ観光振興計画調査等,観光開発・振興を図るための調査を実施した。 また,ESCAP主催の観光政策・振興方策に関するセミナーが,運輸省の全面的な支援の下に63年10月に開催され,13か国14人の参加を得て,各国の観光開発・振興の方策や我が国が発表した海外旅行倍増計画(テン・ミリオン計画)等について情報交換が行われるとともに,我が国の観光関連の現場視察等を行った。 特に開発途上国の観光開発には,官民一体となった協力が不可欠であり,運輸省としても今後それぞれのノウ・ハウを活用して適切な観光協力を推進していくこととしている。
(c) 協力関係が緊密化する中国・インド
(中国) 我が国と中国との間の運輸分野における協力は,近年ますます緊密化している。円借款については,中国は61年度交換公文ベースで我が国にとって第一の円借款受取国となって以来その地位を保っており,既往の円借款供与額の過半は鉄道及び港湾の運輸分野で占められている。さらに,従来からの第1次,第2次円借款に引き続き,第3次円借款を65年度から6年間にわたり42案件,総額8,100億円を供与することが決定されており,今後とも運輸分野での協力を積極的に推進していく必要がある。技術協力についても,運輸分野が専門家派遣及び研修員受入れの大きな柱の一つとなっている。 さらに,運輸分野における閣僚レベルでの交流が盛んに行われており,また,鉄道分野における日中協力を円滑に実施するため中国鉄道部との間に日中鉄道協力実務者協議が,港湾,海運等の分野での意見交換を行うため,中国交通部との間に日中運輸交通実務者協議が,それぞれ毎年1回開催されている。この他,中国の運輸関係の研究者を我が国に招へいし,研修を実施するとともに意見交換を行った。 こうした意見交換の場を通じて,中国との運輸分野の国際協力をさらに推進していくこととしている。 (インド) インドに対する運輸分野における協力は,従来円借款及び研修生受入れを中心に行われてきたが,61年度に鉄道近代化計画を対象として開発調査が開始されるに至り,引き続き63年度にはニューデリー駅近代化計画調査及びカルカッタ・ハルディア港開発計画調査が実施される等,資金・技術の両面で緊密化している。また,新たな円借款の対象分野として,ビハール州等における仏跡観光基盤整備事業に対する円借款が供与されることとなった。 インドにおいては運輸分野の近代化を推進中で,日本に対する期待も大きいことから,運輸分野全般の国際協力を,より一層推進していくこととしている。
(d) 経済協力に関する啓蒙
運輸省は「国際協力の日」にあたり,運輸経済協力の中でも重要な分野の一つである鉄道について,今後の経済協力のあり方を探るため,中国,タイから鉄道関係の要人を招へいし,63年10月6日「経済発展と鉄道の役割」のテーマの下に「運輸経済協力シンポジウム」を開催し,各国の鉄道分野における現状と問題点及び我が国の鉄道協力のあり方について活発な意見交換を行った。 今後とも,あらゆる機会を通じて運輸分野の経済協力についての啓蒙を図っていくこととしている。
(e) 運輸経済協力の一層の推進
我が国の国際的地位の向上と影響力の増大に伴い,国際社会に対し積極的貢献を行うことは,我が国の果たすべき重要な責務となっており,このため,63年6月には政府開発援助の第4次中期目標として,63年から67年までの5か年での実績総額を500億ドル以上とするよう努めるとともに,質的改善を図ることが決定された。 運輸基盤施設の整備は,開発途上国の経済社会発展にとって不可欠であり,従来にも増して運輸分野の国際協力を積極的に推進していく必要がある。また,運輸分野は,施設整備のみならず,適切な運営・管理等が極めて重要であり,運輸省としては今後このような観点から,一層効果的な協力のあり方を探っていくこととしている。 (輸送安全対策協力の推進) 最近,開発途上国において輸送機関に係る大事故が相次いでいるが,輸送の安全性の確保は,開発途上国の発展に重要であるばかりでなく,人命の保護という緊急の課題であることから,ハード・ソフト両面にわたる安全性の向上策を早急に講ずる必要がある。 我が国は,過去において輸送機関に係る多くの事故の苦い経験を踏まえて輸送安全対策を講じてきており,運輸省としては,今後これらの知見・経験を踏まえて,開発途上国のニーズに対応しつつ,輸送の安全性の向上を図るための協力を積極的に行っていく必要がある。
(f) 気象に係る国際協力
また,近年,オゾン層の破壊,砂漠化,二酸化炭素等の温室効果気体の濃度増加による地球の温暖化などの全地球的な環境問題に対しては,世界気象機関が中心となって推進している世界気候計画や,世界気象機関・国連環境計画の「気候変動に関する政府間パネル」等によって国際的な取り組みが推進されており,気象庁はこれらに対し積極的に参加・協力をしている。
(g) 国際科学技術協力
すなわち,63年度には,6月に従来の日米科学技術協力協定に代わり,新しい協定が締結された。 この新協定では,日本の科学技術が,今やアメリカと等しく,世界の最高水準に達したとの認識から,日本がアメリカの科学者の受け入れを促進するよう努めるとともに,知的所有権の保護及び安全保障上の守秘について規定された。 また,10月には,日伊科学技術協力を推進するべく,日伊科学技術協力協定が締結された。 こうした動きを受けて,科学技術会議は,63年度科学技術振興に関する重点指針の中で「外国人研究者の受入れ促進等国際的に開かれた研究体制の整備に努めるとともに,多様な国際協力及び研究者,情報の交流を促進する。」ことを重点事項として取り上げている。 運輸関係の技術は,例えば,船舶,航空管制,気象等,世界中で使用されており,また,技術開発の成果が国際基準や国際ネットワークの中に反映されることが多いことなどに加え,我が国が世界に貢献できる余地が多く,国際的な研究協力の意義が特に大きい分野である。 このため,運輸省においては,磁気浮上式鉄道,海洋開発及び気象観測等の分野を中心に,国際的な科学技術協力を積極的に進めているところである。 運輸省が関係している国際科学技術協力の案件は, 〔1-2-30図〕に示すように年々増加しており,現在では,12か国,71テーマ(63年8月末)に及んでいる。
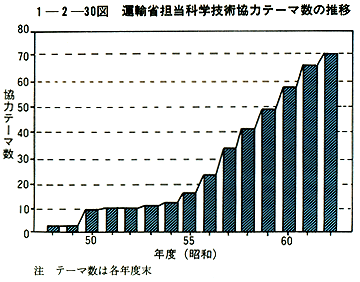
しかしながら,こうした協力案件の中には,情報交換の段階に留まり,研究者の交流等による十分な協力が必ずしも実施できていないものもある。今後は,協力案件の増加のみならず,その質的な充実も含めて協力の推進を図っていくことが望まれている。
(ウ) 対外経済対策の推進
(a) 大型公共事業等への外国企業参入問題
その措置の概要は,①関西国際空港及び同様の民間事業主体が実施するその他の大型プロジェクトに関し,62年11月4日付で通報した措置の実施を見守る。②東京国際空港(羽田)沖合展開第3期工事,新広島空港,横浜みなとみらい21等を含む7つの大型公共事業について,我が国の調達制度に外国企業が習熟することを目的として,調達手続上の特例措置を講じる。③上記7プロジェクトに関連する特定の民間及び第三セクター事業主体に対し,内外無差別な調達方針の採用等の措置を取るように勧奨する。④今回の措置に関して,日米両政府間においてモニタリングの会合を開く。⑤2年後に本措置が所期の目的に役立っているか否かについて日米両政府間においてレビューの会合を開くとなっている。 我が国は,その後,外国企業の建設市場へのアクセスを容易にするため,政府,民間ともこれらの措置を誠実に実施しており,米国も63年9月6日に開催されたモニタリングの会合において評価しているところである。 運輸省所管プロジェクトでは,まず,関西国際空港プロジェクトで通報した措置の発注手続が実施に移され,同手続の適用第1号である気象海象観測データ処理用ミニコンピュータの調達において米国系企業が落札している。同プロジェクト発足以降の関西国際空港株式会社及び同社からの受注企業による外国企業からの調達実績は,63年10月31日現在,約65億円に達している。公共事業関係では,発注機関へのコンタクトポイントの設置,対象プロジェクトのマスタープランの公表等を行った。また,民間及び第三セクターの関係でも,羽田空港西側旅客ターミナルビルについてコンタクトポイントの設置,マスタープラン等の説明会の開催(39社の外国企業を含む185社が参加),エレベータ等の応募要領書の内外企業への頒布等,外国企業のアクセスを容易にする努力が行われている。 運輸省としては,今後とも所管のプロジェクトへの外国企業のアクセスを容易にする努力を行っていくこととしている。
(b) 自動車基準・認証制度の国際化の推進
さらに,基準の国際化に必要な政府の諸活動を支援するため,国からの補助金等により62年10月に「自動車基準認証国際化研究センター(JASIC)」を設立,63年3月には同センター・ジュネーブ事務所を開設し,国際基準作成のための試験研究,情報の収集,ECE・WP29等の国際会議への参画等の活動を行うなど基準の国際化への貢献を図っている。 一方,二国間等においても,関係政府機関及び業界との会合を通じて基準の国際化を進めており,日欧間については,61年12月に行われた日・EC閣僚会議に基づき,62年2月及び6月に日・EC自動車専門家会合を開催している。その後も関係者との会合を重ね,これら会合の結果を踏まえつつ,基準の国際化を進めているところである。 HR
注1) 外客向け観光案内所
|