|
3 瀬戸大橋供用後の旅客,貨物,観光の動向
瀬戸大橋は,人の流れ,物の流れに大きく変化をもたらし,開通後の状況は各交通機関ごとに明暗が分かれている。
(瀬戸大橋の自動車利用は予想外の低調,航空は大阪線に打撃,JRは好調)
(ア) 瀬戸大橋通行量
これを車種別にみると,普通車が76.6%と大半を占めており,大型車が8.4%,軽自動車等が8.3%,特大車が6.7%となっている 〔2−2−5図〕。
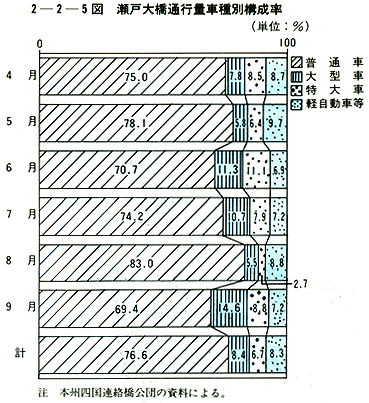
(イ) JR旅客(瀬戸大橋線)
瀬戸大橋線開通から9月までの輸送実績は594万人(1日平均3万4,000人)で,前年の宇高連絡船による実績194万人(1日平均1万1,000人)の3.1倍と好調であった。 これは瀬戸大橋効果による観光ブームや,瀬戸大橋博覧会(四国・岡山両会場)の開催による観光客等の増加に加え,マイカーによる瀬戸大橋の通行料金に比べJRの運賃が割安なことから,人気が高まっていると考えられる。 特に,快速マリンライナーの人気が高く,1列車平均588人の利用実績となっている 〔2−2−6図〕, 〔2−2−7図〕。

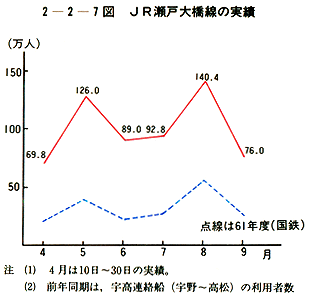
(ウ) 瀬戸大橋特急線バス
これには,4系統1日22往復が運行されているが,4系統とも好調であり,瀬戸大橋開通から9月までの輸送実績は22万7,612人,1車平均でも29人となっている。 中でも,岡山〜高松(1日5往復,1車平均36人)と岡山〜琴平(1日4往復,1車平均36人)の2系統が特に好調となっている 〔2−2−8表〕。
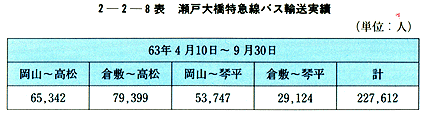
(エ) 航空旅客
しかし,大阪〜四国線(100万4,617人)については,対前年同期比90%と落ち込んでおり,このうち特に大阪〜高松については同72%となり,大きく影響を受けていると考えられる。 これは,JRとのアクセス,待ち時間を含めた所要時分に大差がなく,運賃が相対的に高いことが要因となっているものと考えられる 〔2−2−9図〕, 〔2−2−10表〕。
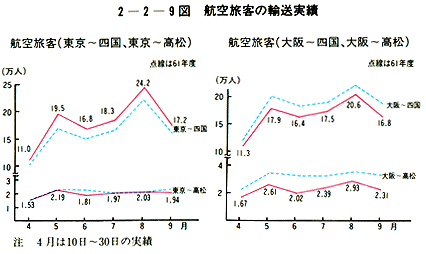
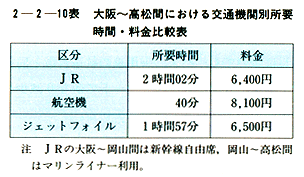
(オ) フェリー・旅客船
輸送人員についても,バス,乗用車の航送台数と同様,中国〜西讃,宇野〜高松,阪神〜香川の3ルートでかなり減少しているが,阪神〜淡路については順調に推移している。 また,神戸・大阪〜高松ルートのジェットフォイルについては,航空旅客と同様,利用客がかなりJRに転移したものと考えられる 〔2−2−11図〕。
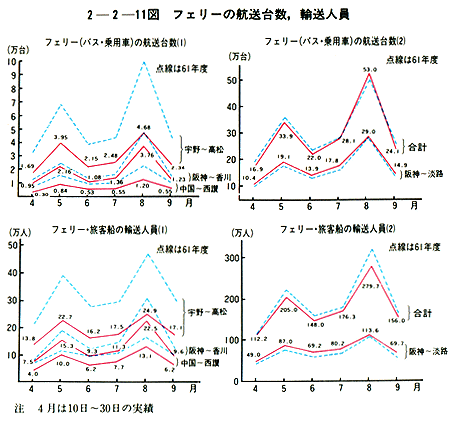
(トラックの瀬戸大橋利用は模様眺め,JRコンテナ好調,フェリーは瀬戸大橋直下航路のみ大打撃)
(ア) トラック
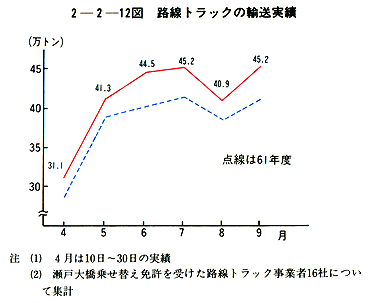
このうち,瀬戸大橋経由分は,当初予定の乗せ替え量(約3万トン)の7割程度となっており,フェリーから瀬戸大橋への切り替えは,現在のところ模様眺めの傾向にある。
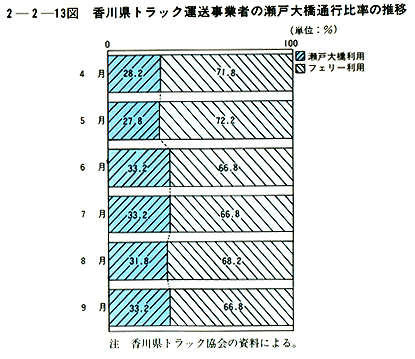
また,四国各県のトラック運送事業協同組合に加盟しているトラック運送事業者の別納割引利用による瀬戸大橋運行状況をみても,1日当たりの利用台数は4月以降,徐々に増加傾向にある。
(イ) JR貨物
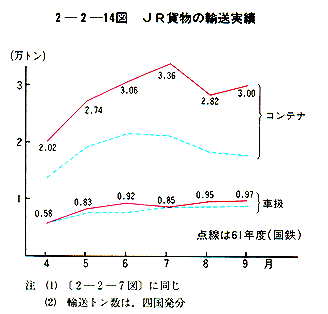
なお,四国発の主要なコンテナ貨物は,新聞巻取紙,化学繊維,清涼飲料水,肥料,タバコ等である。
(ウ) 航空貨物
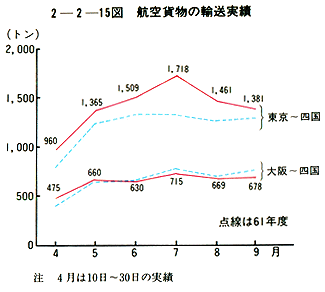
(エ) フェリー利用トラック
しかしながら,この比率は4月以降漸新傾向が続き,7月には93.9%と最低を記録し,8月には下げ止まったものの9月には94.4%と再び減少傾向にあり,徐々にフェリーから大橋利用へと移行する兆しを見せている。 なお,ルート別にみると,瀬戸大橋直下の中国〜西讃が対前年同期比で66%と大きく影響を受けているが,全体的には瀬戸大橋の影響はあまり受けていない現状にある 〔2−2−16図〕。
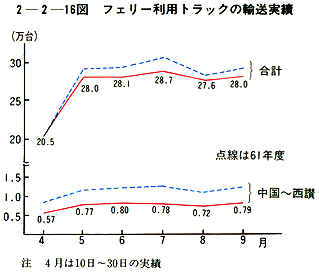
(オ) 物流施設
(瀬戸内観光は大盛況)
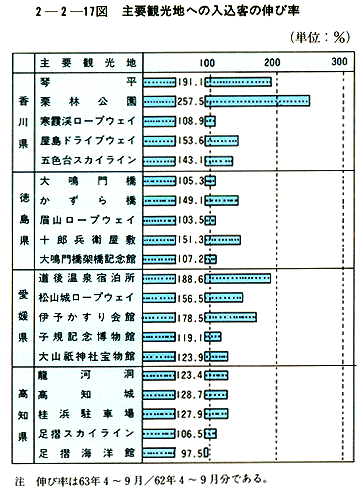
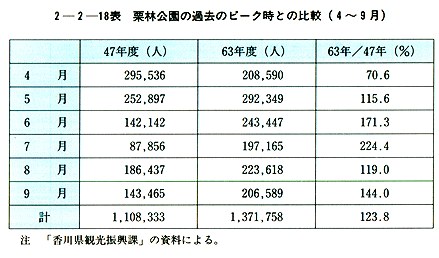
また,県別にみると,瀬戸大橋のある香川県や道後温泉を抱えた愛媛県の伸びが大きい。
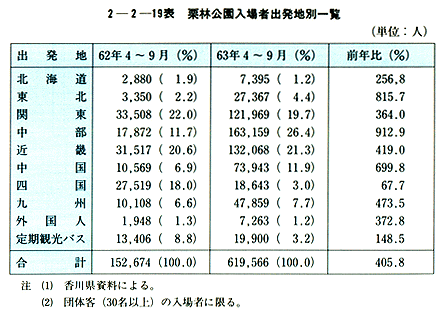
また,主要な登録ホテル,旅館の宿泊者数(63年4月〜6月)をみても,前年同期に比べ60%以上増加している。
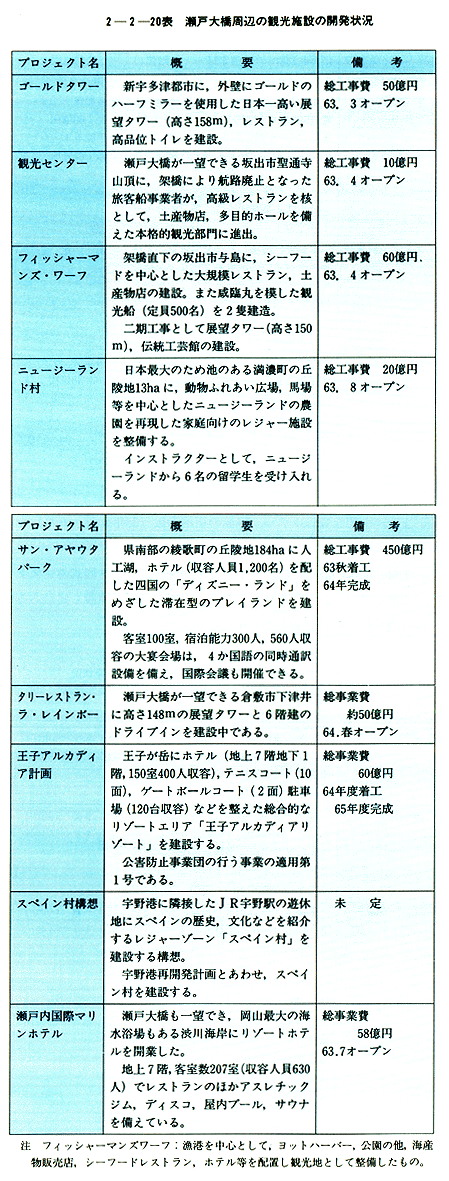
さらに,瀬戸大橋を周遊する観光船が人気を呼んでおり,輸送人員も急増している 〔2−2−21表〕。
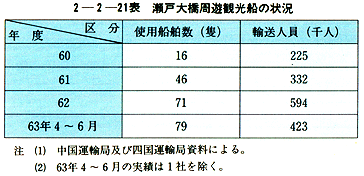
|