|
1 保有台数の動向
我が国の保有自動車台数は,昭和40年度の812万3,000台から60年度末の4,824万1,000台と約6倍の急激な増加を示したが,なかでも自家用自動車は,40年度末の172万7,000台から60年度末の2,559万5,000台と,この20年間で約15倍という極めて大きな伸びを示している 〔4−3−1表〕。また,軽四輪自動車も,40年度末の189万4,000台から60年度末には1,088万7,000台と約6倍の増加を示している。
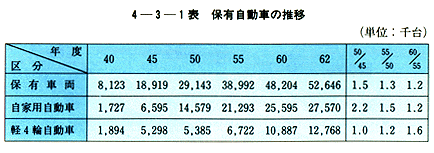
自家用乗用車の増加を地域別にみると,世帯当りの台数(普及率)には,地域差があり,大都市圏を除く地域において普及が進んだことが明らかである 〔4−3−2図〕。また60年度末において,茨城県,富山県,福井県,山梨県,長野県,岐阜県での普及率は1.0/世帯であり,群馬県,栃木県では1.1/世帯に達しており,これらの地域では全般的に複数保有世帯化が進んでいると考えられる。
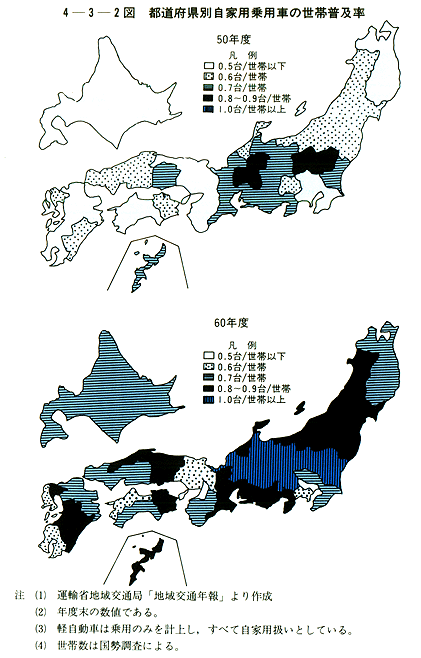
30年代後半に始まったモータリゼーションもあり,自家用乗用車の保有台数は,近年,安定化傾向にある。今後,保有台数の動向を左右する要因は,複数保有世帯の動向にあると考えられる。二人以上の普通世帯における自家用乗用車の世帯保有率は,62年で68.6%と2/3を超えており,複数保有帯では,17.3%と乗用車保有世帯の1/4に達している。その伸び率をみると,世帯保有率が47年-52年が1.52倍,52年-57年が1.21倍,57年-62年が1.16倍と減少傾向にある方,複数保有率も同2.33倍,1.79倍,1.53倍と減少傾向にあるが,その伸び率は世帯保有率よりも高くなっている 〔4−3−3図〕。自家用乗用車保有世帯の今後の増車意向そのものも年々増加しており,62年で自家用乗用車保有世帯の8.6%が事情が許せば増車を希望している 〔4−3−4図〕。自家用乗用車に対する根強い志向性を考えると,地方部のみならず,既に都市部にも波及している複数保有世帯が,今後どこまで増加するかが大きな問題であるが,これは,保管場所の確保,公共交通機関の整備状況,道路混雑の解消等の交通政策に大きく影響されるものと考えられる。
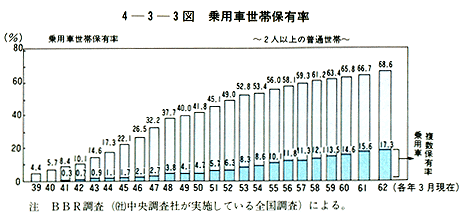
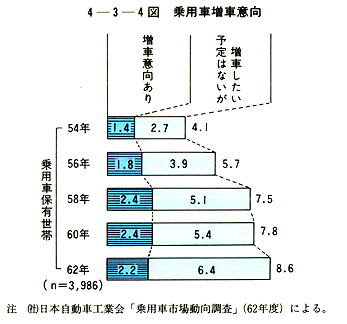
|