|
4 利用形態の多様化
自家用車の保有状況,利用状況は,公共交通機関の整備状況,道路整備状況,道路混雑状況等地域の特性に応じて多様な形態が見られるため,以下では三地域の自家用車保有世帯を対象として63年7月に運輸関係調査機関が行ったアンケート調査に基づいて,地域別に多様化している自家用車の利用形態の一端を示す。対象とした地区は,横浜市(大都市)の郊外部,仙台市(地方中核都市)の郊外部,宮城県牡鹿町(過疎地域)である。横浜地区は郊外鉄道駅を中心とした計画的市街地であり,仙台地区は地下鉄の郊外駅を中心として計画的市街地であり,牡鹿町は市町村代替バスが走る漁業を中心とした過疎地である。
自家用車保有世帯のうち,2台以上保有している複数保有世帯の割合は,横浜地区で10%,仙台地区で25%,牡鹿地区で40%,3台以上保有している世帯は各々1%,2%,8%であり,公共交通機関が不便な過疎地域のみならず,都市郊外部でも既に複数保有が普及していることを示している 〔4−3−11図〕。
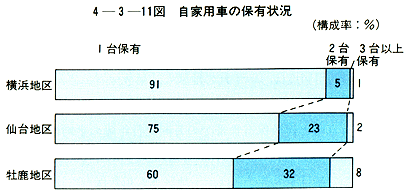
単数保有世帯での平日の利用目的は,横浜地区では買物が40%,通勤が29%であるのに対し,仙台地区と牡鹿地区では通勤が50%程度を占め,買物は20%以下となっており,都市部では地方部に比べて通勤以外の私事目的で利用する傾向が高く,この傾向は複数保有の場合にもほぼ当てはまる 〔4−3−12表〕。
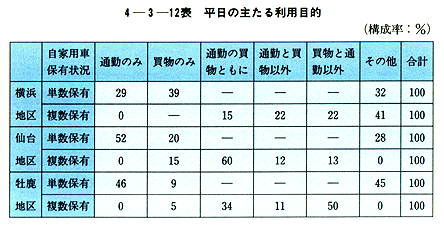
平日の利用頻度は,いずれの地域も,単数保有・複数保有にかかわらず,毎日利用する割合が最も高く,おおむね50%を上回っている。単数保有世帯と複数保有世帯での月間走行距離の平均は横浜地区570km,750km,仙台地区720km,730km,牡鹿町640km,600kmとなっているが,ここで注目すべきことは,三地区とも単数保有に比べて複数保有の利用頻度,走行距離がそれほど減少していないことである。
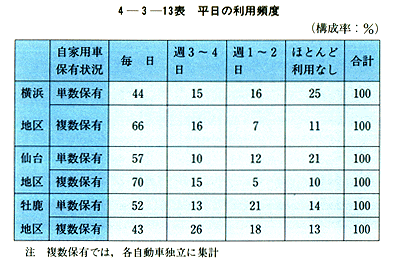
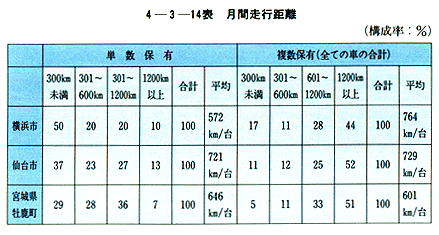
自家用車を利用する割合は,公共交通機関の整備状況,道路整備状況駐車場確保の容易度等を反映して,横浜地区で低く,仙台地区,牡鹿地区で高くなっている。例えば,出勤時の自家用車利用は横浜地区31%,仙台地区63%,牡鹿地区58%となっており,このうち鉄道駅までの端末交通手段としての利用,すなわちパーク・アンド・ライド(P&R),キス・アンド・ライド(K&R)注)は横浜地区と仙台地区とでみられる 〔4−3−15表〕。
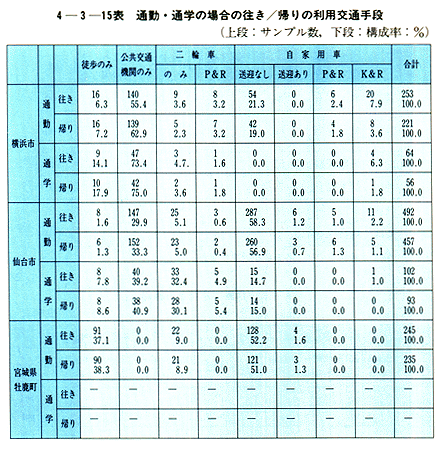
大都市圏全域でみると,端末交通手段としては近年,二輪車の増加が著しく,自家用車の利用は横ばい状態に見えるが 〔4−3−16表〕,都市郊外部ではかなりの利用が見られる地域もある。一例をあげれば,常磐線沿線地域では端末交通手段利用者のうちK&Rは23%,P&Rは5%を占めている。K&Rが高くなっているのは,鉄道駅周辺に駐車場を必要としない,また家族が自家用車を利用できる等の利点があるためと考えられる 〔4−3−17図〕。
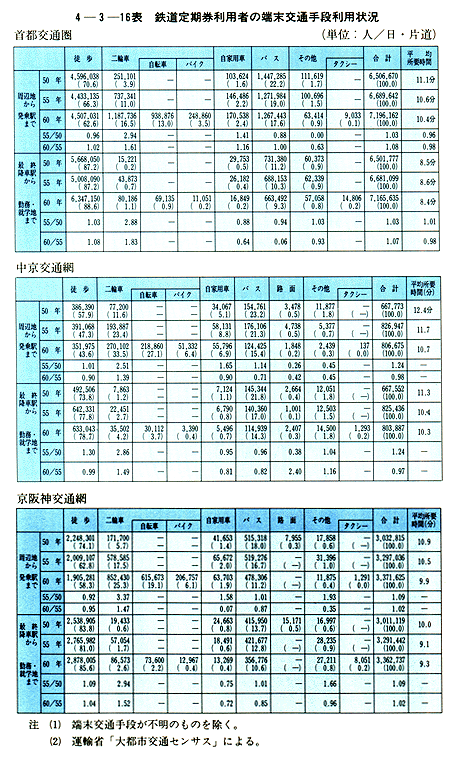
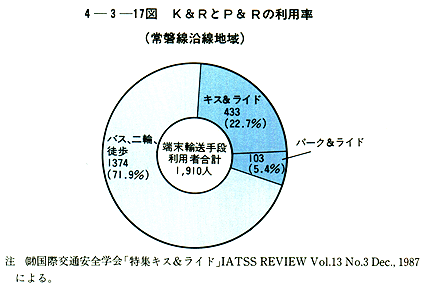
K&Rには送り型と迎え型があるが,迎え型K&Rの選考理由は“所要時間が短い”(22.6%)“雨天のため”(14.8%)を理由とする人が多いが,“バス本数が少ない”“終バスが早い”“バス路線がない”というバスの問題を指摘する人も15.7%にのぼり,“タクシーは費用がかかる”“タクシーはかなり待たされる”というタクシーの問題点を指摘する人も10%にのぼっている。なお,送り型K&Rについても同様の理由が指摘されている 〔4−3−18表〕。
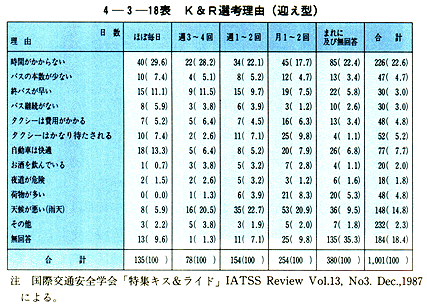
P&R,K&Rは,公共交通機関と自家用車を組み合わせて,個人の欲求にあった交通サービスを作り上げていく移動方法である。自家用車の普及,女性・老人ドライバーの増加,高齢化社会の到来,鉄道駅からの遠隔地での住宅立地の増加,より快適な交通に対する欲求等は端末交通における自家用車の役割を,一層大きいものにすると考えられる。
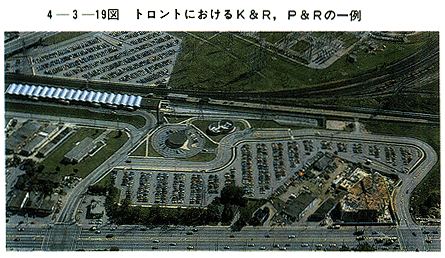
都市間交通で自家用車のみを利用する旅行は,三地区とも過半数を超えているが,公共交通機関を利用した旅行の場合も7割以上が空港,新幹線駅,在来線駅,高速バス停までの端末交通手段として自家用車を利用しており,都市間交通での自家用車利用の比重は極めて高いと考えられる 〔4−3−20図〕, 〔4−3−21表〕。このとき,K&Rは4割以上に上っており,P&Rは横浜地区,仙台地区で高くなっている 〔4−3−22表〕。
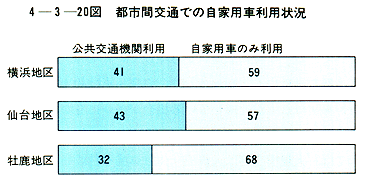
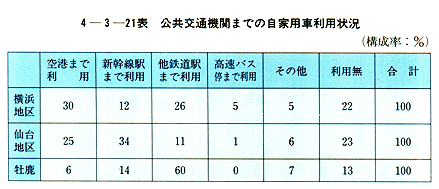
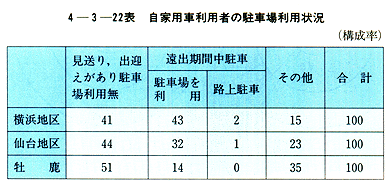
〔4−3−23図〕は,空港(名古屋,小松,宮崎),新幹線駅(郡山,岡山,小倉)への航空利用者,新幹線利用者のアクセス交通手段を示したものである。航空は鉄道駅から離れている場合が多く,その最終手段は当然自動車中心となっており,自家用車は約4割にのぼる。また,新幹線駅は鉄道が近隣している場合が多いにもかかわらず,最終交通手段として自家用自動車が14%も占めている。
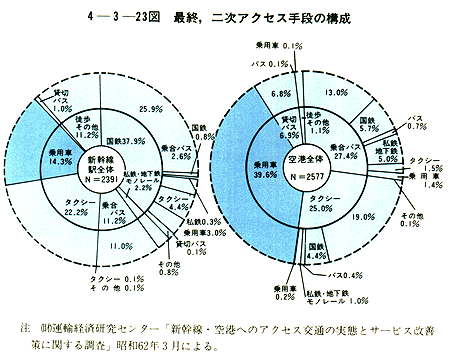
欧米では,大規模空港は大規模立体駐車場を付設しているところが多い。それに対し日本では,箱崎の地下駐車場及び首都高速道路の高架下駐車場において,成田空港の利用者に対して割引料金を適用している。
|