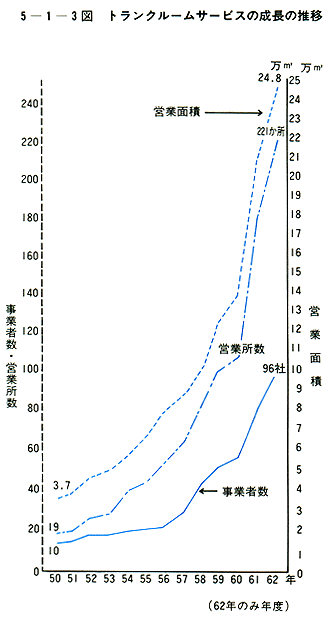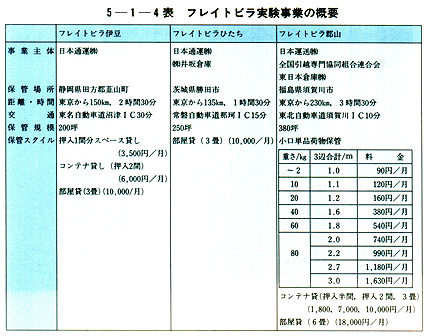|
2 消費者ニーズの変化に伴う物流の変化
(1) 宅配便
(8億個にせまる宅配便)
(ア) 拡大を続ける宅配便
宅配便は,近年成長の一途をたどっており,宅配便全事業者39便153社の62年度における取扱個数は,対前年度比約1億5,000万個増加(対前年度比24.5%増)の約7億6,200万個に達している。この成長は,小口・軽量輸送ニーズの高まりもさることながら,宅配便事業者が,①わかりやすい運賃設定,②取次店網の拡大による利便性の高まり,③貨物追跡システムの導入に代表される情報化による確実性の高まり,④自動仕分機の導入等による配送の迅速化等,利用者ニーズに適合したサービスの提供に努めていることによるものである。さらに,最近は新たなサービスの開拓や商業物流への展開が行なわれており,最近の取り扱い個数の伸びは,こうした新たな需要の掘り起こしが大きく寄与しているものと考えられる。
(イ) 宅配便の新たな展開
宅配便は,ゴルフ・スキー用具の輸送はもとより,地方名産品の産地直送,保冷輸送などにも事業範囲を拡大し,多様化・高度化する消費者ニーズへの対応を図っている。さらに,最近登場した書籍宅配のように,宅配便の進展のなかで形成された全国的な集配体制や貨物追跡システムの活用による消費者サービスも,宅配便の新たな展開として注目されているところである。
(ウ) 宅配便に係る行政施策
宅配便については,58年7月に宅配便運賃制度,60年9月に標準宅配便約款が整備されたほか各事業者における苦情処理体制,各トラック協会における苦情相談窓口の充実等が図られている。標準宅配便約款は,契約内容・損害賠償責任を明確化すること等により消費者保護を図ったものである。
また,62年6月には,一度に一定数量以上の貨物の運送を行う場合に割引を実施する宅配便の数量割引制度の導入も行われた。これは,まとまった数量の荷物の運送を委託される場合,一個当たりの集荷コストが小さくなることを理由としたものであるが,宅配便が,デパート配送をはじめとする商業物流にも利用されるようになり,一度にまとまった荷物の運送を委託されるケースが生じてきたことが導入の背景である。
(2) 引越運送
(引越も手軽に)
(ア) 引越運送サービスの新たな展開
現在,トラック運送事業者による引越運送は,転勤・入学時の移動や家屋の建て替えに伴う人口移動の増加により,年々その件数が増加している。また,主として家具・家財の大型化に伴って引越作業が消費者の手に負えなくなってきたこと,引越事業者が不用品の処理,冷暖房器具の取付け,取外し等各種付帯サービスの展開に努めてきたこと等を背景として,引越サービスの高付加価値化傾向も強まっている。
消費者が煩雑な作業を自ら行うことを避け,有料であってもサービス産業に委ねるという最近の生活意識の変化を勘案すると,トラック輸送を核とする引越産業は,付帯サービスの一層の拡大を図ることにより,今後も順調に成長していくものと考えられる。
(イ) 引越輸送に係る消費者保護対策
このような状況にかんがみ,運輸省は,付帯サービスのウェイトの高まりや内容の多様化に伴い複雑化する引越輸送を,利用者にとってわかりやすく,かつ,安心できるものとし,利用者と運送事業者間のトラブルを防止するため,61年10月に契約内容,損害賠償責任の明確化等を内容とする標準引越運送・取扱約款を制定するとともに,引越運賃料金制度を整備し,中央及び地方における研修会の実施により事業者に対する周知徹底を図った上で,これらを62年3月から実施に移しているところである。また,これらに併せて引越運送から生ずる苦情処理体制も整備され,引越運送の事前相談・苦情処理が,全日本トラック協会及び各都道府県トラック協会の輸送相談窓口で無料で行われている。
(3) トランクルームサービス
(書類と磁気テープが大半)
近年の大都市圏における住宅事情の悪化や事務所スペースの不足,高価品の普及,海外赴任の増加等を背景に,一般消費者及び一般企業を対象として,家財,衣類,美術品,毛皮,書類,磁気テープ等の小口の非商品の保管を行ういわゆるトランクルームサービスが,首都圏を中心に急速な進展をみせている。
このような状況の下で,トランクルームサービスの利用者保護施策の一環として,61年5月に標準トランクルームサービス約款が制定され,同年8月から実施された。これにより対象貨物が明確にされるとともに,損害についての挙証責任を倉庫事業者に課す等,寄託者保護が図られた。
この約款制定を受けて,トランクルームサービスの普及が順調に推進されており,次のような点が特徴として挙げられる。
(ア) トランクルームサービスは,61年度に大幅な増加を示したが,62年度においても,事業者数,営業所数及び営業面積とも前年度に比して約20%程度の増加と,引き続き順調な伸びをみせている。営業所は東京,大阪を中心にほとんどの都道府県に設置されており,全国で200箇所を超えるに至った。
(イ) 設備の面では,磁気テープ,毛皮,美術骨董品等に対して高度の保管サービスを提供することが可能な定温・定湿倉庫が営業面積の50%を占め,引き続き増加傾向をみせているのに対し,常温・常湿倉庫の面積は伸び悩んでいる。
(ウ) 年間入庫件数も,約11万件,対前年比15.9%増と堅調に推移している。これを品目別に見ると,「磁気テープ」,「書類」及び「家財」がトランクルームサービスを利用する「ベスト3」であり,これらで全体の9割近く占めている。
(エ) トランクルームサービスの利用者は,企業が約80%,個人が約20%と推定されるが,企業からの寄託が大宗を占める「書類」,「磁気テープ」については,この4年間で取扱件数が56%の増加と顕著な伸びを示しており,今後とも,企業からの保管需要は旺盛に推移すると見込まれる。最近では,「書類」「磁気テープ」等の企業からの寄託物品の保管を専門に行う倉庫事業者も相当数みられるようになってきている。
(オ) 個人からの寄託が大宗を占める「家財」,「衣類」,「ピアノ」等については,年度により若干の増減はあるものの,この4年間の取扱件数の伸び率は41%であり,各種目についての一般家庭からの根強い保管需要があることをうかがわせる。
なお,営業面積等の推移については 〔5-1-3図〕のとおりである。
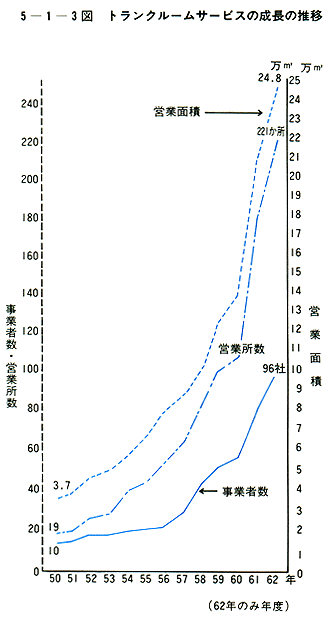
今後は,トランクルームサービスの一層の定着を図るため,わかりやすい料金体系の設定について検討するとともに,設備水準の向上等についても取り組んでいく必要がある。
(4) フレイトビラ
(実験事業スタート)
フレイトビラとは,大都市に居住する一般家庭等における当面使用しない家庭用品等を対象に安価な保管サービスを提供するねらいとして,大都市周辺等に立地する倉庫と,宅配便等の輸送システムとを組合せた消費者物流システムである。
運輸省では,63年4月より倉庫業者及びトラック事業者の協力を得つつ実験事業を実施している 〔5-1-4表〕。
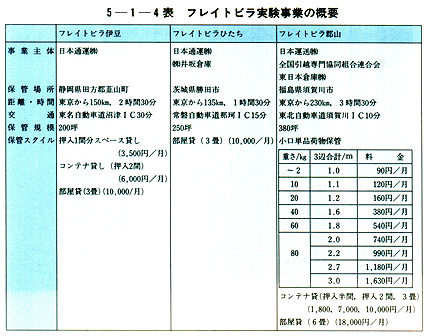
これまでの利用状況は各フレイトビラによりばらつきはあるもののおおむね良好である。現在,フレイトビラ利用者からサービス改善事項,実験事業者から事業収支結果,一般消費者からフレイトビラに対する要望等についてのデータを収集するとともに,保管庫が立地している現地の地方公共団体から,フレイトビラを活用した地域振興策の提示を求めているところである。
今後,これらデータについて分析調査を行い,本格的な事業着手が円滑に行われるよう,①物流事業者がフレイトビラ事業を健全に運営していくための指針,②フレイトビラのサービス水準を一定以上に保持するための優良フレイトビラ事業者の推薦,③クレーム・トラブル処理を円滑にするなどのためのフレイトビラ利用約款,④フレイトビラ事業者の収支改善のための国の支援措置等について,総合的整備運営方策を検討していく予定である。
|