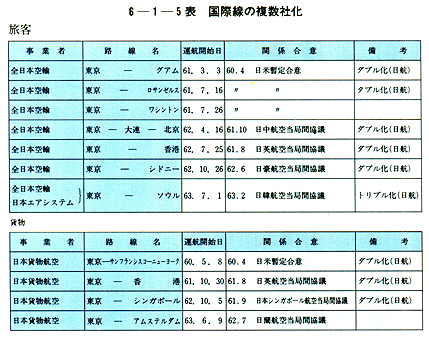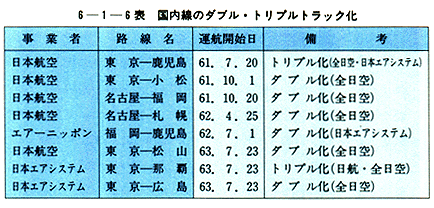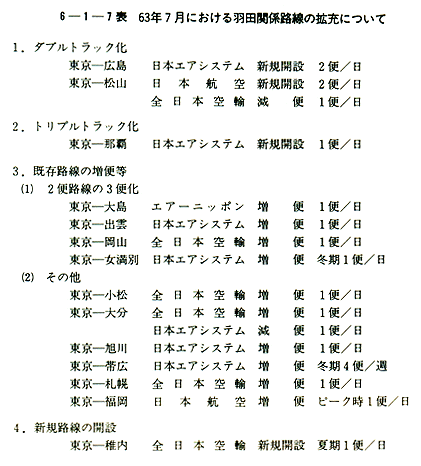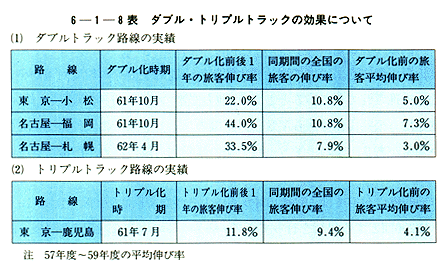|
2 競争促進施策の積極的推進
(1) 競争促進施策の推進状況
(新たな路線展開等)
現在,我が国においては,61年6月の運輸政策審議会の答申「今後の航空企業の運営体制の在り方について」の趣旨に沿って安全運航の確保を基本としつつ,航空企業間の競争促進を通じて利用者利便の向上を図るため,国際線の複数社化及び国内線のダブル・トリプルトラック化を推進することとし,積極的に新路線の開設及び増便を行っている。さらに63年7月に東京国際空港の新A滑走路の供用が開始されたことに伴い,同空港発着便の増便等が行われた。
なお,日本航空株式会社については,競争条件の均等化及び同社の自主的かつ責任ある経営体制の確立のため,62年9月の「日本航空株式会社法を廃止する等の法律」の公布(同年11月施行)及び同年12月の政府保有株式の売却により,完全民営化が実施された。
(ア) 国際線の複数社化
国際線においては61年より,全日本空輸が東京からグアム,ロサンゼルス,ワシントン,大連・北京,香港,シドニーへと国際定期路線を次々に開設し,さらに63年7月にはソウルへも新路線を開設した。また日本エアシステムは61年9月以降チャーター便の運航を開始し国際線への進出を果たしたが,さらに国際定期路線進出に備え,社名を63年4月に東亜国内航空から日本エアシステムへと改め,7月には同社にとっては初の国際定期路線である東京-ソウル線を開設した。この結果,東京-ソウル線は我が国航空会社間においても3社による競争が実施されている 〔6−1−5表〕。
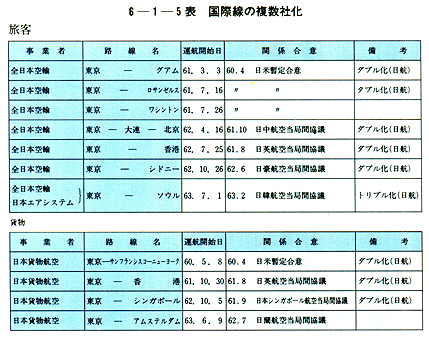
貨物についても,日本貨物航空が61年より東京-香港,シンガポール線を開設し,63年6月にはアムステルダム線を開設したことにより,複数社化が進められている。
(イ) 国内線のダブル・トリプルトラック化
国内線についてはダブル・トリプルトラック化の路線需要量の基準を,それぞれ,ダブルトラック化については年間需要70万人以上,ただし札幌,東京(羽田成田),名古屋,大阪,福岡,鹿児島及び那覇の各空港間を結ぶ路線にあっては年間需要30万人以上,トリプルトラック化については,年間需要100万人以上と定め,この基準に沿って競争促進を図っている。61年以降,束京-鹿児島線のトリプルトラック化,東京-小松線,名古屋-福岡線,名古屋-札幌線のダブルトラック化が実施された 〔6−1−6表〕。
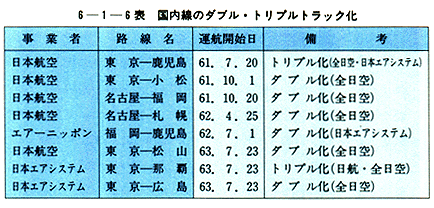
このような,競争促進施策の推進には,航空企業による新たな路線の展開,増便等が必要であるが,現在,新東京国際空港,東京国際空港,大阪国際空港の空港処理能力は限界に達しつつある。
このような状況を抜本的に改めるため,現在,三大空港プロジェクトが進められているが,このうち,東京国際空港の新A滑走路の供用が開始されたことにより,東京国際空港発着の路線の新設・増便が可能となった。具体的には,東京-那覇線について日本エアシステムが参入しトリプルトラック化が実施され,また,東京-広島線について日本エアシステムが参入し,東京-松山線について日本航空が参入し,それぞれダブルトラック化が実施された。さらに,併せて東京-稚内線の新規開設のほか,必要な路線についての増便が実施された 〔6−1−7表〕。
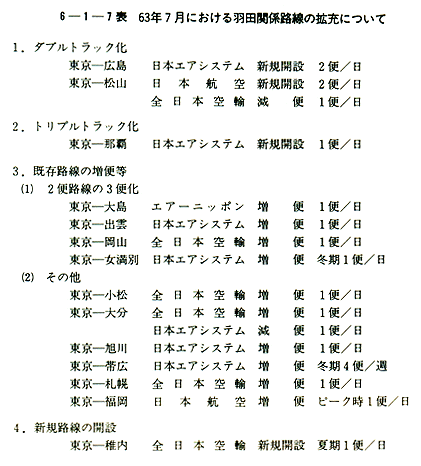
(2) 競争促進施策の効果
(需要の大幅な増加)
(ア) 国際線の複数社化による効果
競争促進導入が図られ,複数社化が実施された国際線について,実際に複数社化によって需要がどのように変化したのかを実数値で見てみると,62年7月に全日本空輸が新たに参入したことにより複数社化された東京-香港線においては,我が国航空企業全体の旅客輸送実績は複数社化される前の1年と複数社化後の1年の輸送実績を比較してみると,輸送実績は54万人から71万人へと31.2%の伸びであり,我が国航空企業の積み取りシェアも36.2%から39.3%へと高まり,複数社化による我が国航空企業の躍進がうかがえる。
(イ) 国内線のダブル・トリプルトラック化による効果
また,国内線についても競争促進導入による需要の変化を実績値で見てみると,例えば61年10月にダブルトラック化された東京-小松線においては,ダブルトラック前の同路線の年平均旅客輸送伸び率は5%であったが,ダブルトラック化前1年の旅客輸送実績に比べたダブルトラック化後1年の輸送実績は22%の伸びをみせ,さらに同期間中の全国の航空利用旅客輸送実績の伸び(10.8%増)をも大きく上回っている 〔6−1−8表〕。
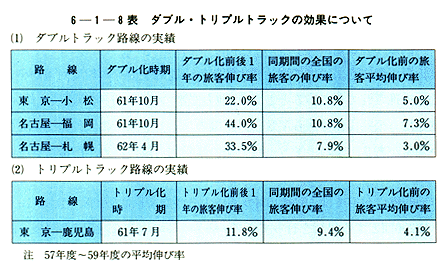
(3) 中小航空企業の路線展開
(地域のために)
我が国の中小航空企業は,地域住民の利便の確保のため,採算性の悪い路線を数多く運航しているが,そのなかでも地域住民の生活上必要不可欠な離島路線については,不採算であっても運航を維持することが強く求められている。このためこれらの中小航空企業については,経営の安定化と利用者利便の向上を図るため,経営基盤の強化に資するような路線展開を積極的に認めてきており,62年以降,エアーニッポンについては全日本空輸からの路線移管による福岡-小松線の開設が行われ,また日本エアシステムの一社体制であった福岡-鹿児島線への参入も行われた。さらに南西航空については沖縄から本土への路線,那覇-松山線及び那覇-岡山線の開設が行われた。
|