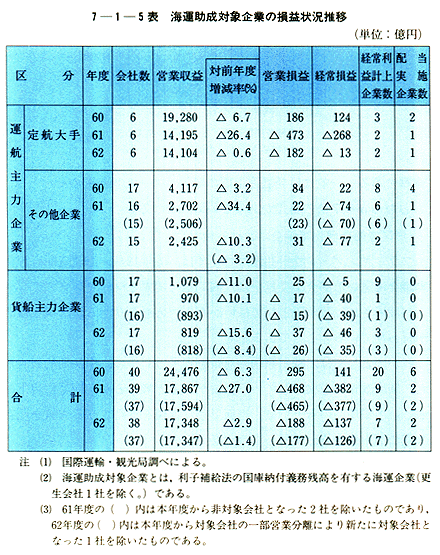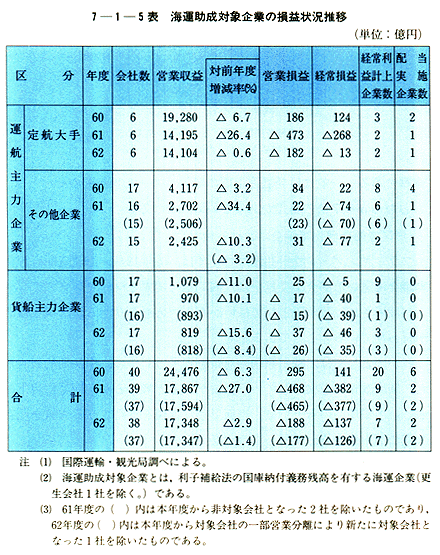|
3 62年度海運助成対象企業の経営状況
(1) 損益状況
(苦境続く経営状況)
62年度の海運助成対象企業38社の損益状況は 〔7−1−5表〕のとおりであり,営業収益が1兆7,348億円と前年度を下回り,海運集約がなされた39年度以降最悪を記録した前年度に引き続き,営業損益段階でも損失(188億円)を計上する厳しい状況となっている。
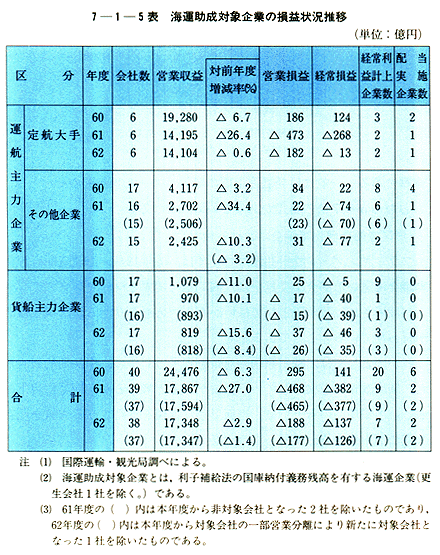
このような厳しい経営状況に至ったのは,主として円高によるものと考えられ,営業収益の推移をみると,60年度後半に始まった円高の影響を受け,59年度を頂点に,以後円高の進行と同一の歩調で減少している。
不経済船の処分,要員合理化による船舶経費の減少等営業費用を減少させる要因もあり,前年度と比較し,営業損失・経常損失において赤字幅を縮小しているものの,依然としていずれも損失を計上する厳しい状況は変わらず,その結果,配当実施会社は前年度同様38社中わずか2社にとどまっている。
63年度は,いずれの企業も経営全般にわたる減量・合理化対策の一層の強化に迫られており,このような対策と経営の活性化をさらに推進することにより,経営基盤の強化が望まれる状況となっている。
(2) 円高の海運企業経営への影響
(円高による収支悪化が300億円)
外航海運業は,営業収益,営業費用ともに特にドル建ての比率が高いが,ドル建て収益がドル建て費用よりも多いため,円高の影響を受けやすい収支構造となっている。62年度において,海運助成対象企業38社の収支構造についてみると,ドル建ての収益がドル建て費用より13.2億ドル超過しているので,1円円高になると13.2億円の営業上の為替差損を生じることとなる。
62年度の平均レートが61年度の実績と同じレートであったと仮定して試算すると,62年度の営業損益は約111億円の黒字となるが,実績では,約188億円の赤字となっており,円高の影響により約300億円程度収支が悪化したと推計される。
外航海運企業は,為替リスクのヘッジ対策に真剣に取り組む必要があり,先物為替予約の活用といった面のみならず,費用面でのドル建て化の推進や,外貨建て債務への切替え等を取り入れていく必要があると考えられる。
|