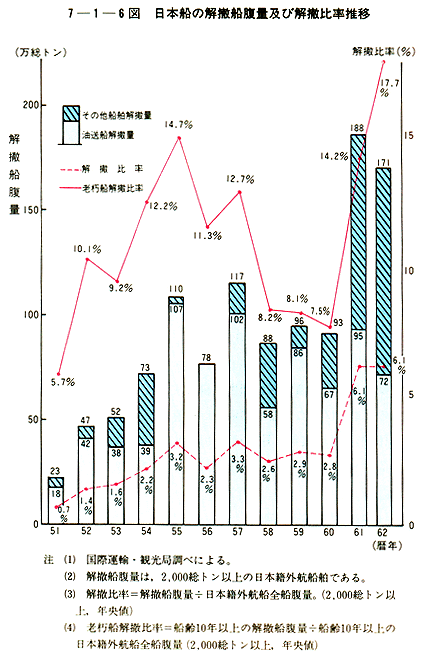|
4 外航海運企業経営改善対策の推進
(1) 海運企業における経営の減量・合理化等の状況
(船隊・要員を中心とした合理化等の進展)
海運助成対象企業38社についてみると,従業員数は,近年大幅に縮減され(62年度末従業員数対58年度末比率,海上48%,陸上72%),社船についても,62年度中に延べ105隻(うち解撤23隻,海外生き船売船63隻)が処分される等,海運企業の船隊要員の合理化が進展している。特に62年度においては,労使合意に基づく緊急雇用対策(62年4月より2年間)の中で大幅な減少が見られた。
さらに,海運企業はそれぞれの企業の実情に応じ,費用全般にわたる節減対策を実施する一方,経営の安定化や船員の新たな職域開拓に資するため,海運以外の分野に事業の多角化を図るなど,経営基盤の強化に努めている。
政府としても,このような企業努力が早急に成果をあげうるよう環境整備を図っていく必要がある。
(2) 利子補給金繰延べの解消
現行の外航船舶建造融資利子補給については,国の厳しい財政事情により,57年度以降やむなく利子補給金の一部の支給を後年度に繰り延べる措置をとってきた。これに対し,円高の進行等により海運企業が厳しい経営状況にあることにかんがみ,62年度においては日本開発銀行の62年4月以降の利子補給金相当額の利子支払猶予制度等を創設し,さらに62年度第2次補正予算措置として,62年度において支給を後年度に繰り延べていた開銀及び市中銀行に対する利子補給金(開銀分については利子猶予措置の対象となる以前のもの)を全額追加支給することとした。以上の措置によって,利子補給金支給繰延べは完全に解消されることとなった。
(3) 解撤促進対策の推進
(ア) 日本船の解撤状況
(62年の解撤船腹量は前年に引き続き高水準)
62年の日本船の解撤船腹量は,171万総トンと,日本籍外航船腹量の6%に達しており,61年に引き続き高水準となったが,年後半には解撤のペースが落ちてきている 〔7−1−6図〕。
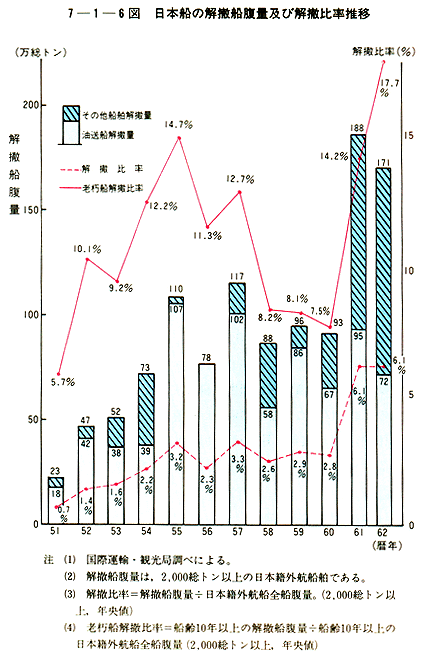
(イ) 解撤法の施行状況
(既存の解撤対象船種の状況)
我が国においては,61年6月に特定外航船舶解撤促進臨時措置法を制定し,公的債務保証制度を創設することにより,余剰船舶の解撤の促進を図ることとしている。既存の解撤対象6船種の解撤目標量(60年7月〜64年6月)合計520万総トンに対して,解撤量実績(60年7月〜62年12月)は,317万総トン(目標達成率61%)となっている。
(自動車専用船の追加)
62年10月には,新たに自動車専用船を解撤対象船種に追加指定し,解撤目標量(61年7月〜64年6月〉として40万総トンを設定した。
|