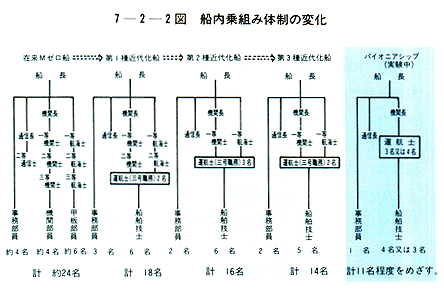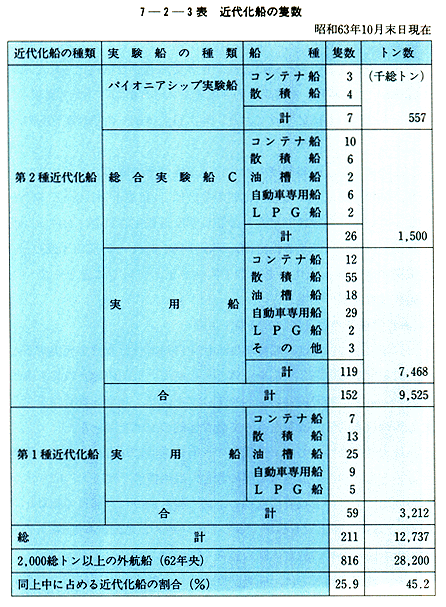|
2 船員制度の近代化と船員教育体制の充実
(1) 船員制度の近代化
(近代化実験の進展)
(ア) 実験の推進
船員制度の近代化は,近年の船舶の技術革新の進展に対応した新しい船内職務体制を確立する 〔7−2−2図〕とともに,乗組員を少数精鋭化することにより,厳しい海運情勢の下で日本人船員の職域の確保を図ることを目的とし,52年以来,船内職務の実態及び諸外国の船員制度についての調査が進められ,これを踏まえて,54年からは,実際に運航されている船舶を用いて,船員制度近代化委員会の下で作成された新しい船内就労体制の試案について,その実行の可能性及び妥当性を検証するための実験を行ってきている。
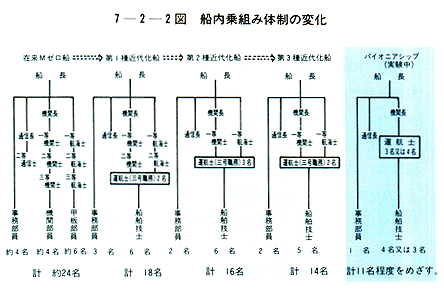
58年4月には,その第一段階の実験結果を受け,甲板部,機関部両部の職務を行う運航士及び船舶技士の制度を導入し,乗組員18名で運航する近代化船の乗組み体制( 〔7−2−2図〕第1種近代化船)が法制度化された。
その後,引き続き,自動衝突予防援助装置等のさらに進んだ設備を備えた近代化船において,第二段階の実験が進められ,61年4月には,その実験結果を受けて乗組員16名体制で運航する新しいタイプの近代化船に対する乗組み体制( 〔7−2−2図〕第2種近代船)が法制度化された。
さらに,61年7月からは,船橋で機関をコントロールできる等一層設備の充実した近代化船において,自動化設備等を充分に活用した,より効率的な就労体制の確立をめざし,第三段階の実験が進められ,63年6月には船員制度近代化委員会においてその実験結果のとりまとめが行われ,それを受けて,63年12月に乗組員14名で運航する新しいタイプの近代化船に対する乗組み体制( 〔7−2−2図〕第3種近代化船)が法制度化された。
(イ) パイオニアシップ実験と今後の近代化
また,62年10月から円高等の急激な情勢の変化の対応して,早急に船員制度の近代化を一層推進する必要があるとの観点から,第三段階の実験と並行して,船橋ウイングに設置された機関の遠隔操縦装置及び操舵装置,その他船内作業が効率的に行えるように配慮した設備を備えた近代化船により,世界で最も少数精鋭化された乗組み体制(11名程度)の確立をめざす実験(パイオニアシップ実験 〔7−2−2図〕)が開始されており,順次11名体制への移行が図られつつある。
このように,船員制度の近代化は着実にその成果をあげてきており,63年10月末現在の近代化船の隻数は計211隻 〔7−2−3表〕となっている。今後は63年6月の船員制度近代化委員会における「船員制度近代化に関する提言(第三次)」を踏まえ,一等航海士及び一等機関士の共通技能化等をめざす実験を進めていくこととしている。
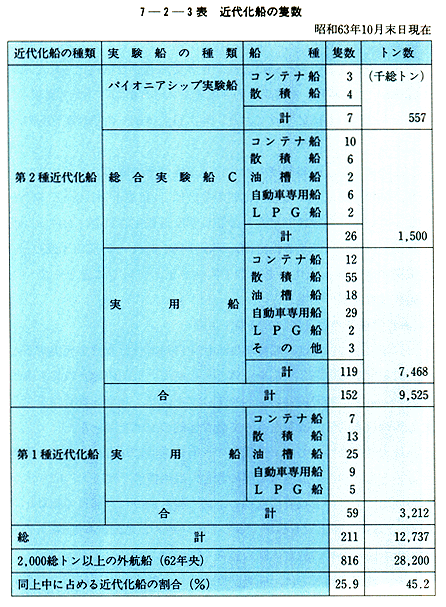
(2) 船員教育体制の充実
(海員学校等の教育体制の整備・再編)
海員学校については,船員制度近代化に対応した教育を充実するため,61年度から中卒3年制を主体とした航海・機関の総合教育を実施するとともに,教育内容のレベルアップを図り,高卒同等資格を付与する等の抜本的学制改革を行って教育体制の整備を図った。
海技大学校については,近代化の一層の進展に対応した教育を実施するとともに昨今の海運水産界の厳しい雇用情勢を踏まえ,62年度から短期間で上級の海技資格取得のための科を新設し,部員の職員化の促進,さらには陸上でも活用できる訓練コースを充実する等,船員の職域拡大を図るための教育体制の整備を図った。
また,航海訓練所では,船員制度近代化に対応した運航士教育を59年度から実施し,63年9月に新人教育では初の運航士が誕生することとなった。
|