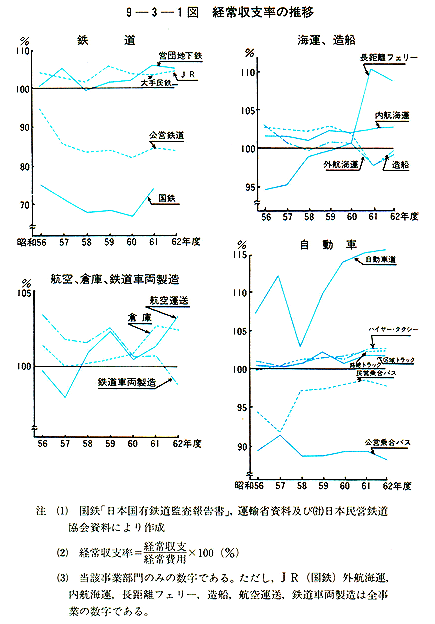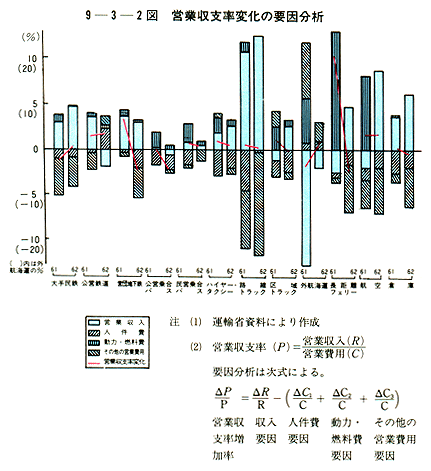|
2 運輸事業の収支状況
運輸事業における経常収支率の状況をみると, 〔9−3−1図〕のとおり,鉄道車両製造は大幅に悪化しており,公営鉄道,公営乗合バス,民営乗合バスも低迷が続き,長距離フェリー,営団地下鉄も収支率は下降しているが,その他は横ばいもしくは改善傾向にあるといえる。
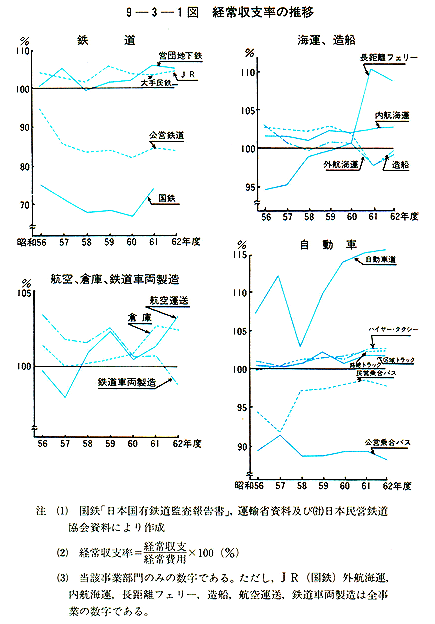
(1) 鉄道部門
(JRは好調,その他は前年並み)
JR(旅客会社6社,貨物会社1社)は,きめ細かなダイヤ設定,魅力ある企画商品の開発,駅,車両の改良,美化等に向けての経営努力のほか,我が国全体の景気回復による輸送量の増加から,収入面は順調に推移した。一方,費用面においては,契約単価の見直し等の経費節減努力,動力費の軽減,人件費負担の軽減等により,全体として経費の節減が図られた。この結果,経常収支率は104.2%となり,おおむね順調に推移したと思われる。
大手民鉄(14社)は,営業費用が人件費,減価償却費等の諸経費の増加により4.3%増となったものの,営業収入も輸送量の微増及び運賃改定(6社)により4.8%増となり,営業・経常両損益とも黒字を維持した。
中小民鉄(90社)は,燃料費等の減少により営業費用は2.3%減となったが,営業収入も3.3%減となり,全体としては依然として苦しい経営状態が続いている。
公営鉄道(12社)は,62年7月に開業した仙台市地下鉄を除いて比較すると,営業費用が人件費等の増加により3.9%増となったものの,営業収入が5.2%増となったため,営業損益は黒字を維持した。しかしながら,支払利息等が増加したため,経常損失は増加し,依然として大きな赤字を計上している。
営団地下鉄は,有楽町線(和光市〜営団成増)開業等による利用者の増加により営業収入は3.7%増となった。しかしながら,人件費及び有楽町線(同)開業に伴う減価償却費等の増加から,営業費用も5.6%増加した。この結果,営業利益は3.4%減となり,経常損益は黒字を維持しているものの,経常収支率は降下している。
(2) 自動車部門
(バスを除いて堅調に推移)
民営乗合バス(42社)は,営業収入がわずかに増加したが,営業費用も減価償却費等が増加したため,営業・経常両損益は大幅に悪化した。
公営乗合バス(33社)は,営業収入が0.7%減,営業費用が人件費等の増加により1.9%増となり,営業・経常両収支率は悪化し,依然として大きな赤字を計上している。
ハイヤー・タクシー(55社)は,燃料費の減少等もあって,営業収入の伸びが営業費用の伸びをわずかながら上回り,経常収支率は前年度とほぼ同水準となった。
路線トラック(50社)は,輸送需要の増加に伴い営業収入は14.1%増となったが,傭車費の増加等により営業費用も14.0%増となり,経常収支率はわずかながら上昇した。
区域トラック(40社)は,営業収入が2.6%増加したものの,営業費用も2.7%増となり,経常収支率は前年度と同水準となった。
自動車道(26社)は,営業収入の増加(4.8%増)を営業費用の増加(6.9%増)を上回り,営業利益は1.1%減となったが,営業外損失が減少(10.5%減)したため経常利益は6.5%増加し,黒字を拡大した。
(3) 海運業,造船部門
(外航海運,造船業は,引き続き厳しい経営状況)
外航海運(助成対象38社)は,営業収入が円高による目減り等により減少したが,営業費用も,燃料油価格の上昇等による運航費の増加があったものの,不経済船の処分,人員合理化による船舶経費の減少及び円高による借船料の目減りにより減少した。その結果,営業・経常両損益は赤字幅を縮小したが,依然として厳しい経営状況となっている。
内航海運(356社)は,営業収入・費用とも1.0%増加し,経常収支率はわずかながら増加した。
長距離フェリー(13社)は,新船投入及び内需拡大等により輸送量が増加し,営業収入は5.1%増となったが,営業費用も燃料費が安定的に推移したものの,新船投入に伴う減価償却費等の増加により7.7%増となり,営業利益は12.1%減,経常利益も9.6%減となった。経常収支率は引き続き黒字で推移しているが,当期未処理損失も316億円を計上しており,依然として苦しい経営状態を余儀なくされている事業者もある。
造船(主要9社)は,売上の大幅減少により,営業収入は8.4%減となったが,営業費用も経費削減の企業努力,合理化の効果及び採算割れのない注文のみ受注するという,いわゆる選別受注の成果により10.5%減となり営業損益は黒字に転じ,経常収支率も改善の兆しをみせた。しかしながら,依然として経常損益は赤字を計上しており,今後とも厳しい状況が続くと思われる。
(4)その他
(航空運送は順調に回復)
航空運送(主要3社)は,便数及び路線の拡大により営業費用は7.5%増となったものの,堅調な需要の増加により営業収入も9.5%増となり,営業・経常両損益ともに黒字を拡大し,初めて3社そろって8%配当を行った。しかしながら,売上高利益率は3.4%にすぎず,現行運賃を維持している経営状況である。
倉庫(15社)は,営業費用が6.9%増,営業収入が6.8%増となり,経常収支率はわずかながら下降した。
鉄道車両製造(主要3社)は,円高時代に外貨建てで受注した輸出車両の大量出荷等により営業費用が増加したため,私鉄向け車両の大量出荷による営業収入の増加にもかかわらず,営業損益は赤字を計上した。また,61年度に営業外収入として計上された多額の有価証券売却益が,62年度は少額であったため,経常損益も赤字に転落した。
鉄道車両・同部分品等の需要は,長期にわたりその多くを日本国有鉄道が占めてきたが,58年以降は国鉄再建のための設備投資抑制の影響を受け,国鉄の需要が著しく減少してきたが,最近ではJRの経営も軌道に乗り,63年度の鉄道車両等の生産見通しは明るさを取り戻しつつあるといえる。一方,海外市場は,61年度及び62年度は手持ち受注の米国向け電車等を中心に比較的好調な生産実績を維持したが,63年度以降は,円高現象が定着しつつある中で,他の輸出国との競争激化により厳しい状況で推移するものと見込まれている。
ホテル(40社)は,円高の影響により外国人宿泊客は減少したものの,国内旅行の増加に伴う日本人宿泊客が増加したこと等により営業収入は増加(1.8%増)し,営業費用が減少(0.2%減)したため,営業利益は25.9%増,経常利益も25.2%増と黒字を拡大した。
一般旅行(大手10社)は,海外旅行者の増加等により営業収入が6.4%増加したものの,営業費用も8.0%増加したため,営業利益は20.9%減と黒字を縮小した。しかしながら,営業外費用が28.9%減となったため,営業外利益は大幅な増加となり,経常利益は3.3%減少したにとどまった。
(動力・燃料費の減少が改善要因)
次に62年度の各事業の収支状況を営業収入及び営業費用(人件費,動力・燃料費,及びその他費用)の伸び率の変化でみると 〔9−3−2図〕のとおりであり,営業収支率の変化の下降が,収支率の悪化を示すとは一概にいえないが,長距離フェリー,営団地下鉄,公営バスが大きく落ち込み,区域トラック,倉庫もマイナスとなったが,全体的には前年度に引き続き改善傾向にあるといえる。
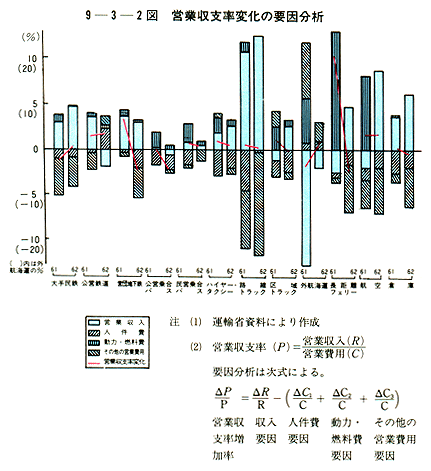
収入面をみると,公営鉄道,外航海運でマイナスの要因となっているのを除き収支率の改善に寄与しており,輸送需要の回復基調がうかがえる。一方,費用面をみると,人件費は人員削減の進んでいる外航海運等の数業種を除き,マイナス要因として作用した。また,動力・燃料費は,前年度に引き続く円高・原油安の影響により,ほとんどの業種に対してわずかではあるがプラスに寄与した。
62年度の運輸事業における経営状況は,以上のとおり営業収入の伸びが目立ち,流動的な要因である動力・燃料費も低価格で安定したため,おおむね収支は改善の傾向を維持したといえる。今後は,我が国経済の急速な景気拡大とともに大幅な収入の増加をめざしながら,かつ固定的性格の強い人件費をできるだけ抑制する等,営業費用の縮減努力が望まれる。そして,動力・燃料費に大きな影響を与える円レート,原油価格の動きに注目しながら,多岐・多様にわたる利用者ニーズに対応したサービスの提供等を図り,より一層営業収入を増加に導くための努力が期待される。
|