|
3 生産性の動向
50年度からの生産性等の動向をみると,以下のとおりである。まず,輸送機関別物的労働生産性(従業員一人当たりの輸送量)をみると 〔9−3−3図〕のとおりであり,輸送量が減少傾向にあった国鉄は,55年度以降人員の合理化が進んだことにより生産性は上昇を続けた。62年度については,国鉄がJRに移行したため,61年度までの国鉄とは不連続になるが,仮にJRを国鉄時代と同様の扱いをして評価した場合,62年度も上昇を続けている。大手民鉄は,人員の合理化と輸送量の増加により,ゆるやかな上昇を続けている。乗合バスは,着実に人員削減を進めているが輸送量の減少が大きく,61年度も生産性は若干低下した。ハイヤー・タクシーは,従業員数,輸送量とも前年並で,61年度の生産性は前年と同水準であった。内航海運は,人員の合理化が進んだ反面,輸送量が増加したため,62年度の生産性は3年ぶりに上昇した。航空は,輸送量,人員とも増加しているが,輸送量の伸びが人員の伸びを上回っているため,生産性は62年度も上昇している。
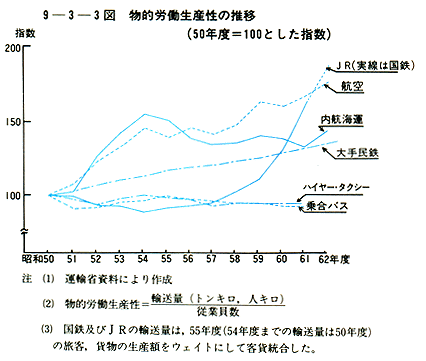
次に,付加価値ベースによる労働生産性(従業員一人当たりの付加価値額)を大蔵省「法人企業統計年報」でみると, 〔9−3−4図〕のように推移しており,運輸・通信業全体としては全産業と同様の生産性を示して順調に推移しており,陸運業も付加価値が着実に増加していることから,生産性は安定した上昇を続けている。水運業は,人員の合理化よりも付加価値減少の割合が大きく生産性は下降していたが,62年度は付加価値額が上昇したため,4年ぶりに生産性は上向いた。
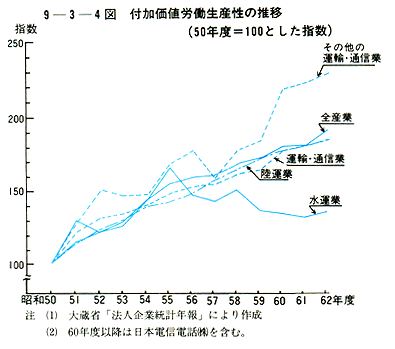
また,業種別の輸送原価(単位輸送量当たりの営業費用)の推移をみると, 〔9−3−5図〕のとおりであり,乗合バスは,輸送量は減少しているが営業費用は増加しており,輸送原価は大きな上昇を続けている。
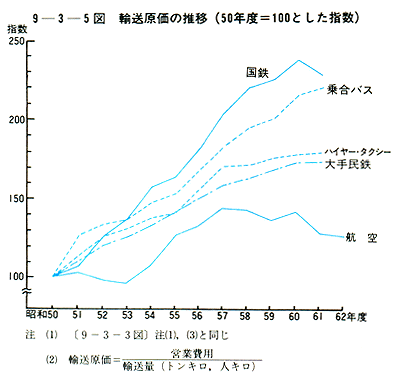
ハイヤー・タクシーは,輸送量,営業費用とも大きな変化はなく,大手民鉄は,輸送量と営業費用がともに増加しているため,どちらも最近5年間は大幅な上昇がみられない。また,航空は,2年連続して低下している。
|