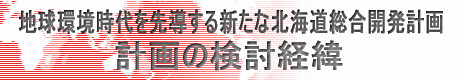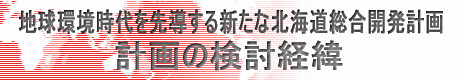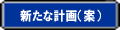
平成20年5月8日に開催された国土審議会第11回北海道開発分科会において、「地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発計画(案)」が取りまとめられ、答申がなされました。
 答申文 答申文
 新たな北海道総合開発計画(案)のPDFファイルはこちらをご覧ください 新たな北海道総合開発計画(案)のPDFファイルはこちらをご覧ください
 |
 |
地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発計画(案)の構成 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 ご覧になりたい部分をクリックすると、本文へ移動します ご覧になりたい部分をクリックすると、本文へ移動します
 |
 |
地球環境時代を先導する新たな北海道総合開発計画(案) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
第1章 計画策定の意義
第1節 北海道開発の経緯
(北海道開発の歴史)
我が国は、北海道の豊富な資源や広大な国土を利用し、国全体の安定と発展に寄与することを目的として、明治2年の開拓使設置以降、特別な開発政策の下、計画的に北海道開発を進めてきた。特に、北海道開発法(昭和25年法律第126号)の制定後は、同法に基づきこれまで6期にわたり北海道総合開発計画を策定し、我が国経済の復興や食料の増産、人口や産業の適正配置など、その時々の国の課題の解決に寄与することを目的に、積極的な開発を行ってきた。
この結果、明治2年に約5万8千人だった人口は、1世紀余りの開発の歴史の中で五百数十万人に達し、道内総生産は約20兆円となるなど、今日の北海道は、フィンランド、アイルランドなど欧州の一国に相当する規模の地域経済社会を形成するに至っている。また、食料の供給や観光・保養の主要な拠点として我が国全体の安定と発展に大きく寄与する地域となっている。
(第6期北海道総合開発計画の経緯)
1990年代後半の北海道においては、農林水産業、鉄鋼業などの基幹産業が低迷し、これに代わる産業の成長が遅れていたことに加え、金融機関の破綻等により地域経済が動揺し、経済の体質改善と重点的・効率的な基盤整備が喫緊の課題となっていた。このような状況の下で、北海道における産業振興、社会資本整備等を総合的に展開するための指針と施策の内容を示す第6期北海道総合開発計画を平成10年4月に閣議決定し、おおむね平成19年度までを計画期間として施策を推進してきた。
当該計画期間中には、産学官の連携により進められた「北海道産業クラスター創造プロジェクト」が実績を上げるとともに、東アジア地域からの観光客やオーストラリアからのスキー客など、来道外国人観光客が3倍以上に増加するといった成果が見られた。これらは、北海道の成功事例と呼べる新たな成長の芽である。
平成9年度にマイナス成長に転じた道内総生産は、経済対策による下支え等もあって、計画期間中に次第に持ち直した。ただし、その回復の動きは全国に比べ弱く、雇用情勢については、他地域と比べ長く低迷が続いている。人口も、平成9年の570万人を頂点に減少に転じ、全国よりも少子高齢化が進行するなど、厳しい状況が続いている。さらに、産炭地などかつてその存立の基盤となっていた産業を失った地域における新たな地域づくりの課題も顕在化している。
また、計画に基づく施策の推進に当たっては、関係者の連携・協働による事業効果の一層の発揮、重点化・効率化や、北海道の実情に即した先駆的・実験的取組の拡充が課題となっている。
第2節 新たな北海道総合開発計画の意義
北海道開発の基本的な意義は、北海道の資源・特性を活かして、国の課題の解決に貢献するところにある。
現在、東アジア地域の急速な経済成長、地球環境問題の深刻化とエネルギー資源の逼迫に対して、本格的な人口減少・少子高齢化を迎える我が国経済社会がどのように対処していくのかが問われている。
こうした時代の潮流の大転換期にあって、北海道は、我が国の経済社会づくりを先導する役割を担っていかなければならない。
北海道は、様々な経済社会活動を可能とするゆとりある空間と、21世紀に最も重要な要素となる自然環境も十分に保持している。こうした特徴的な資源・特性を活かして、我が国の持続可能な経済社会づくりに貢献することが重要となっている。
北海道では、明治以降の開発の歴史の中で、新しい課題に進んで挑戦するフロンティア精神が培われてきた。
我が国経済社会が大きな転換期を迎え、国民の間に将来への不安や閉塞感が増している今こそ、北海道は、新たな時代の先駆者としてフロンティア精神を発揮し、豊かな経済社会づくりのための先駆的・実験的な取組に挑戦していく。ここに、北海道開発の新たな意義がある。
このような北海道開発を推進するためには、国、地方公共団体、住民、NPO、企業等の各主体の連携により施策の総合性を発揮するための戦略的取組を描くことが必要である。国から地方へ、官から民への流れの中で、各主体はそれぞれの役割分担と責任を自覚しつつ、北海道の地域特性を踏まえた将来の豊かな社会づくりのためにビジョンを共有し、同じ方向性の下に各自の取組を進めていくことが重要である。北海道洞爺湖サミットが開催され我が国が地球環境問題等に関して国際社会でリーダーシップを発揮しようとする今、北海道における持続可能な開発をいかにして進め、我が国の課題の解決にいかに貢献するかについてのビジョンとして、この計画を策定する。

第2章 計画の目標
第1節 我が国をめぐる環境変化と国家的課題
(グローバル化の進展)
人、物、資金、技術、情報などの国境を越えた移動がかつて無いほど迅速かつ容易になり、世界的な競争が激しさを増している。また、WTO(世界貿易機関)体制の下、EPA(経済連携協定)等の交渉が各国間で進められるなど、世界経済の自由化に向けた動きが一層活発になっている。
特に、東アジア地域の急速な経済成長と産業構造高度化の中で、我が国を含めた東アジア地域全体での生産ネットワークの構築や経済連携の動きが活発化している。我が国の貿易相手も、1980年代には輸出先の6割弱を欧米が占めていたが、2003年には、中国を始めとするアジア地域がこれを上回るに至っている。このような中で、我が国の地域経済社会が東アジア地域の急速な成長をどのように取り込み自らの成長の糧とするかが課題となっている。
また、世界経済の自由化の動きが強まる中で、国内農業の持続的な発展や食料安全保障の確保が課題となっている。
(生存基盤そのものを脅かす地球環境問題)
世界における温室効果ガスの排出量は、現状では自然界の吸収量の2倍を超えており、地球温暖化による異常気象の頻発、農業への打撃、災害の激化など人類の経済社会活動に対する様々な悪影響が危惧されている。
また、今後、東アジア地域等の急速な経済成長に伴い、環境負荷の更なる増大が懸念されるとともに、国際的なエネルギー資源の獲得競争が激化するおそれがある。
さらに、環境負荷の増大により、地球の長い歴史の中ではぐくまれてきた生物多様性が大幅に失われ、生態系のバランスが崩れつつある。
このような地球環境問題の深刻化により、人類の生存基盤が掘り崩され、経済社会の持続的な発展に支障を来す懸念がある。我が国が世界における持続可能な経済社会の形成を先導していくとともに、美しい国土を継承していくことが課題となっている。
(かつて経験したことの無い規模の人口減少と急速な少子高齢化)
少子化の進行により、我が国は、今後本格的な人口減少社会を迎える。総人口は、2004年の1億2,779万人を頂点に減少局面に入り、21世紀中盤には1億人を割り込むものと見込まれている。また、2005年に20%程度であった高齢化率は、2050年には40%弱まで上昇すると推計されている。
人口減少により地域社会の過疎化が進行し、活力の低下が懸念されるとともに、保健・福祉などの行政サービスや、地域の共同体そのものの維持さえ困難な状況が生じることも懸念され、人口減少が国の衰退につながらない地域づくりが課題となっている。
第2節 北海道の資源・特性
北海道の気候は、夏は欧州並みに冷涼、冬は積雪寒冷である。北海道には広大な土地、良質で豊富な水、広大な農地、豊かな漁場、我が国の4分の1近くを占める森林等の豊かな資源がある。我が国の湿地のうち8割以上が北海道に位置するなどアジアの中でも特徴的で豊かな北国らしい自然環境と、美しく明瞭な四季の風景がある。風力、バイオマス天然ガス田などの環境負荷の少ないエネルギー源も豊富に存在する。
北海道は、我が国の国土面積の22%を占め、日本列島の最北端に位置し、日本海、オホーツク海及び太平洋の三つの海に面し、長い海岸線を有している。ロシア極東地域に隣接するとともに、北米及び東アジアとの結節点に位置している。
人口密度は全国平均の5分の1であり、都市間距離が長く、各地域の拠点となる都市に集積された都市機能を周辺の広い地域で利用する広域分散型社会が形成されている。
北海道では、古くからアイヌの人々が、自然とのかかわりの中で、独自の伝統や文化をはぐくんできた。また、明治以降の開発の歴史の中で、国内外の人々を受容する社会的開放性が培われるとともに、各種技術・基盤が蓄積されてきた。
第3節 今後の北海道開発の戦略的目標
北海道の資源・特性を活かして我が国が直面する課題の解決に貢献していくとともに、地域の活力ある発展を図るため、この計画では、「アジアに輝く北の拠点~開かれた競争力ある北海道の実現」、「森と水の豊かな北の大地~持続可能で美しい北海道の実現」及び「地域力ある北の広域分散型社会~多様で個性ある地域から成る北海道の実現」を戦略的目標として掲げ、多様な主体の連携・協働によって、効果的に計画を推進する。
1.アジアに輝く北の拠点~開かれた競争力ある北海道の実現
北海道の美しく豊かな自然環境や冷涼な気候は、国内のみならずアジアにおいても特徴的なものであり、この異質性が生み出す魅力が強みとなる食関連・観光産業は、広く東アジア市場においても競争力を確保し得る。東アジア地域の急速な成長を地域経済発展の好機ととらえ、これらの産業を核としつつ、東アジアや世界と競争し得る成長期待産業等の育成及びこれに向けた戦略的な条件整備を進めるとともに、基盤となる食料供給力の強化を進める。
これにより、開かれた競争力ある北海道の実現を目指す。
2.森と水の豊かな北の大地~持続可能で美しい北海道の実現
環境・気候変動問題を主要テーマの一つとする北海道洞爺湖サミットを契機として、北海道の豊かな自然環境の保全・再生に取り組み、国民共通の資産として将来にわたって着実に継承していくとともに、地域の自然を最大限に活用し、美しい四季の風景等を保全・創出していくことにより、雄大な自然の恵みを体感できる北海道づくりを進める。
また、北海道に豊富に存在する自然エネルギー源など地域資源を活用した低炭素社会、循環型社会の構築に向けた先駆的な取組により、環境と経済が調和した地域社会の形成を進める。
これにより、持続可能で美しい北海道の実現を目指す。
3.地域力ある北の広域分散型社会~多様で個性ある地域から成る北海道の実現
北海道内の各地域において、高品質な農水産品を内外に供給する地域、世界的に価値ある自然資源を保全し観光に貢献する地域、東アジア地域への玄関口として生産・物流の拠点となる地域など、優れた特色ある地域資源を活かした地域づくりを進める。
これらの地域の発展の基盤として、札幌を中心とする都市圏の機能により北海道全体を牽引するとともに、地方都市圏と周辺の人口低密度地域から成る広域的な生活圏において、都市機能の維持と、交流・連携の強化を進め、人口減少・少子高齢化に対応した地域社会モデルを構築する。
これにより、多様で個性ある地域から成る北海道の実現を目指す。

第3章 計画推進の基本方針
第1節 計画の期間
この計画の期間は、21世紀前半期を展望しつつ、2008(平成20)年度からおおむね2017(平成29)年度までとする。
第2節 計画の主要施策
前章第3節に掲げる戦略的目標を達成するための主要施策は、次のとおりとし、これらを総合的に推進する。
第1の戦略的目標である「アジアに輝く北の拠点~開かれた競争力ある北海道の実現」のため、グローバルな競争力ある自立的安定経済を実現する施策として、食料供給力の強化と食にかかわる産業の高付加価値化・競争力強化、国際競争力の高い魅力ある観光地づくりに向けた観光の振興、東アジアと共に成長する産業群の形成に取り組む。
第2の戦略的目標である「森と水の豊かな北の大地~持続可能で美しい北海道の実現」のため、地球環境時代を先導し自然と共生する持続可能な地域社会を形成する施策に取り組む。
第3の戦略的目標である「地域力ある北の広域分散型社会~多様で個性ある地域から成る北海道の実現」のため、魅力と活力ある北国の地域づくり・まちづくりを図る施策に取り組む。
また、3つの戦略的目標を達成するための横断的な主要施策として、内外の交流を支えるネットワークとモビリティの向上を図る施策、安全・安心な国土づくりを図る施策に取り組む。
第3節 計画の進め方
1.多様な連携・協働
北海道が、時代の大転換期を乗り切り、21世紀における我が国の経済社会づくりを先導していくためには、国、地方公共団体、住民、NPO、企業等の各主体が、自主性と創意工夫の下に、特色ある地域資源の有効活用に向けて、その力を結集していくことが必要である。
北海道の資源・特性を最大限に活かして東アジアを始め内外の諸地域との交流・連携を進め、地域全体の成長力を高めていくとともに、北海道内の各地域が、それぞれの地域資源を活かして多様で個性的な発展を遂げていくことが重要である。
また、地域において、国と地方公共団体が中心となって必要な調整を行い、地域の発展に向けた各種事業・施策等について連携・協働を図るとともに、多様な民間主体と行政とが一体となった取組を展開することにより、相乗的な効果を発現させることが重要である。
さらに、道州制へ向けた先行的取組である道州制特区の仕組みを適切に活用し、地域の自主性・裁量性を高める取組を推進する。
2.新たな時代を見据えた投資の重点化
厳しい財政状況の中において、21世紀前半期の我が国経済社会を持続可能なものとしていくためには、これまでの開発基盤の蓄積を活かしつつ、社会資本整備重点計画等に即して、公共投資の重点化・効率化を図ることにより、社会資本の整備効果を早期かつ十分に発現させ、関連する民間投資を誘発させていくことが必要である。
このため、主要施策ごとに、特に重点的、総合的、先行的に実施することが適切な施策を明らかにして、計画の効果的な推進に努めるものとし、施策の推進に当たっては、時々の情勢変化を勘案して、柔軟かつ機動的な対応を図る。
また、事業の迅速化、汎用品の積極的使用、地域の実情に合った規格の設定やPFI等民間資金・能力を活用する社会資本整備手法の推進など、総合的なコスト縮減に向けた取組の充実を図る。
さらに、今後、老朽化した社会資本ストックの急速な増加が想定される。既存のストックをできる限り有効に活用していくため、総合的な資産管理手法の導入によるライフサイクルコストの最小化、点検から補修に至る管理の高度化による既存ストックの長寿命化など、計画的・効率的な維持・管理や更新の取組を強化するとともに、そのための費用をできる限り節約し、これから必要となる新たな社会資本整備に的確に対応していく。
3.新たな北海道イニシアティブの発揮
この計画の推進に当たり、各主体は、内外との積極的な交流・連携を通じて不断に地域の資源・特性を再認識しつつ、その総力を結集して、豊かな特色ある経済社会の形成に向けた先駆的・実験的な取組を実施していくことが重要である。
北海道の優れた資源・特性を活かし、全国画一ではないローカルスタンダード導入による、北海道固有の課題に対する独自の取組(北海道スタンダード)や、我が国経済社会の変化に応じた制度設計のフロンティアとなる、他地域にも共通する課題に対する北海道の特性を活かした先駆的・実験的取組を、我が国の経済社会づくりを先導する新たな北海道イニシアティブとして、積極的に推進する。

第4章 計画の主要施策
第1節 グローバルな競争力ある自立的安定経済の実現
開かれた競争力ある北海道の実現に向けて、東アジア地域の急速な成長を地域経済発展の好機ととらえ、北海道の資源・特性を活用することが重要である。
我が国の食料安全保障を将来にわたって支えていくため、北海道の食料供給力を強化し、食の供給基地としての役割を一層高めていくことが必要である。
また、食にかかわる産業の高付加価値化や個性豊かな観光地づくりに取り組むとともに、競争力ある産業群の形成を図っていくことが必要である。
これにより、自立的・安定的に成長し得る活力ある地域経済を確立することが重要である。
1.食料供給力の強化と食にかかわる産業の高付加価値化・競争力強化
世界人口の増加、東アジア地域の経済発展等により、今後、世界の食料需要が大幅に増加すると見込まれる。また、食料供給面では、水資源の開発余地の減少、塩害や砂漠化、さらには地球温暖化による影響等の不安定要因が存在することから、今後、世界の食料需給が逼迫する可能性がある。
このような中、我が国の食料自給率は、主要先進国の中で最も低い水準となっている。さらに、農水産業従事者の減少や高齢化等による労働力の脆弱化、耕作放棄地の増加、水産資源の減少等の影響により国内の食料供給力の低下が懸念されている。
このため、食料安全保障の観点から、食料自給率の向上に向けて国内農水産物の消費拡大を促進しつつ、食料供給力の強化を図ることが必要であり、最大の食料供給力を有している北海道の農水産業が果たす役割は、今後一層重要性を増すこととなる。
一方、食の安全や高品質な農水産物に対する国内及び東アジア地域を中心とする国外の需要が拡大している。
このため、生産・加工・流通等の食にかかわる産業において、食品の安全を確保した上で、高付加価値化を図り、海外の農水産物や食品にも対抗し得るように競争力を強化し、あわせて、輸出促進を図ることが重要である。
(1) 食料供給力の強化
(農産物の供給力強化)
良好な営農条件を備えた農地・農業用水の確保を図りつつ更なる生産性の向上に努めるとともに、持続的・効率的な農業経営の確立を進めることにより、農産物の供給力を一層強化することが必要である。
このため、安定的な作物生産を可能とする農業水利施設等の計画的な更新整備、暗渠排水や土層改良等のほ場整備及び低コストな農業生産を可能とするほ場の大区画化や、担い手への農地の利用集積等を推進する。
特に、水田地帯においては、水管理の省力化を可能とする施設整備等を推進する。畑地帯においては、作物の品質や収量の向上に資する畑地かんがいや排水改良等を推進する。酪農地帯においては、草地・飼料畑の整備等を推進するとともに、コントラクターやTMRセンター等経営支援組織の育成・強化を促進する。
加えて、直播に向いた水稲品種や耐冷性・耐病性・収益性が高い品種の開発、低コストな生産技術及び未利用有機性資源の飼料化技術の開発等を促進する。
また、地域農業の維持・発展につながる法人化等の効率的な経営体の育成・確保及び多様な人材の円滑な新規就農を促進する。
さらに、施設野菜・園芸や肉牛の導入等による経営の複合化及び農家等による農産物加工・直売や農家民宿、農家レストラン等の起業による経営の多角化へ向けた取組等を促進する。
(水産物の供給力強化)
漁場環境が悪化傾向にある北海道周辺水域の資源生産力の向上を図り、消費者に対し鮮度が良く安全な水産物を安定的に供給するとともに、資源状況に見合った持続可能な漁業生産構造を確立することにより、水産物の供給力を強化することが必要である。
このため、TAC(漁獲可能量)制度やTAE(漁獲努力可能量)制度の適切な運用や漁業者自らによる漁獲規制による資源の回復・管理及び種苗放流等による栽培漁業の取組、産卵・生育環境となる藻場・干潟等の漁場の整備を促進する。
また、漁港における水産物の衛生管理の高度化等を推進するとともに、産地市場の統廃合や市場機能の強化を促進する。
さらに、省エネ・省人型の代船取得や低コストの操業・生産体制等による漁船漁業の構造改革及び収入の変動による影響を緩和する経営安定対策への取組を促進する。
(2) 食の安全の確保
安全な農水産物の生産や、農水産物・加工食品の品質管理の高度化等を通じ、生産段階から食卓まで一貫した食の安全を確保することが重要である。
このため、農業生産や食品加工の現場段階において、GAP(農業生産工程管理手法)やHACCP(危害分析・重要管理点方式)の導入及び流通段階における衛生管理施設の整備等、食品の安全確保へ向けた取組を促進する。
(3) 食にかかわる産業の高付加価値化・競争力強化
農水産物・加工食品の品質向上のための生産・加工技術の開発等、食にかかわる産業の各段階で高付加価値化を進めるとともに、コスト縮減、消費者ニーズに適合した食品の供給、消費者への訴求力の強化等に取り組むことにより、海外市場も視野に入れて競争力を強化することが必要である。
このため、生産段階において、冷涼な気候を活かして農薬の使用量を抑え、家畜排せつ物等の有機性資源を活用した有機農業を始めとする環境保全型農業の取組や、食味向上のための品種改良や新技術の開発等を促進する。
流通・加工段階においても、電子タグ等を活用した出荷・物流システムの導入、産地直送など多様な流通経路の構築、マーケティングによる消費者ニーズの把握及びこれらを踏まえた新技術の活用等による多様な食品の開発・普及の取組を促進する。
また、地域のイメージとの関連付けによる相乗効果の発現や北海道ならではの農水産物の利用等による新たな食のブランドの確立へ向けた取組とともに、地域産業の活性化につながる地産地消の推進等、消費者と生産者等の結びつきの強化に向けた取組を促進する。
さらに、東アジア地域等への農水産物・加工食品の輸出促進へ向け、情報の収集及び発信、海外市場開拓機能の形成等、販路の拡大を支援する。

2.国際競争力の高い魅力ある観光地づくりに向けた観光の振興
北海道には、豊かな自然環境、さわやかな夏や雪・流氷が見られる冬など温暖な地域とは異なった気候風土がある。また、こうした自然や気候風土がはぐくんだ個性ある景観や歴史・文化、安全で高品質な農水産物等、アジアの中でも特徴的で、魅力的な観光資源を有している。これらを活用して、国内はもとより、東アジア地域を始め海外との観光交流の拡大を図ることが重要である。
また、北海道における観光は、食にかかわる産業を始め他の産業分野の雇用を創出するなど波及効果が大きいことから、地域経済を先導する産業としての役割が期待されている。
なお、旅行者ニーズの多様化、観光分野での国際競争・地域間競争の激化等観光をめぐる諸情勢に著しい変化が生じており、これらに適切に対処する必要がある。
(1) 国際競争力の高い魅力ある観光地づくり
北海道は、アジアの中でも特徴的な自然環境等を有しており、地域それぞれが持つ資源・特性を活かして、旅行者ニーズの多様化等に対応した、国際的にも個性豊かな観光地づくりを進める必要がある。
このため、自然環境の保全や適正な利用を図るための取組とともに、優れた自然の風景地、良好な景観、温泉等国内外の観光客にとって魅力となる観光資源の保護、育成及び開発を推進する。あわせて、観光客の滞在や行動に伴う環境負荷を低減させる取組を推進する。
また、地域住民やNPO、企業といった地域の様々な主体が行政と連携し、美しい景観づくり、活力ある地域づくり、魅力ある観光空間づくりを行う「シーニックバイウェイ北海道」など地域が主体となった取組を促進する。
特に、北海道を訪れる外国人観光客に人気が高い自然観賞、冬のイベントやスポーツを目的とする体験型観光、観光客と地域のより深い交流を実現する長期滞在型観光や客船クルーズ旅行等ゆとりのある観光を推進するため、良質なサービスの提供や関連する施設の整備を進める。また、広域周遊型観光を促進するため、複数の地域が広域的に連携して行う観光資源のネットワーク化や情報発信の取組を促進する。
北海道への外国人観光客の誘致を図るため、特に、2008(平成20)年の北海道洞爺湖サミットの開催等を活用し、北海道の魅力を戦略的に発信する。さらに、国際会議や国際的な規模で開催される行事の誘致を促進し、情報発信の機会の充実を図るとともに、国際交流を推進する。
観光を始め多様な形での交流を拡大するには、来訪者を暖かく迎え、外国人や高齢者等が容易かつ円滑に旅行できるような観光地づくりを進めることが必要である。特に、外国人観光客に対しては、言葉の壁を取り除くことが重要である。
このため、北海道を訪れる人々に対する地域の案内や魅力の紹介、通訳等のサービスを担うガイドの確保・育成に向けた取組を促進するとともに、情報通信技術を活用した観光に関する情報の提供を推進する。また、外国語対応が可能な観光案内所、宿泊施設等旅行に関連する施設、さらに多言語表記や図記号を利用した案内表示の整備を推進する。
加えて、旅行に関連する施設のバリアフリー化を推進するとともに、ユニバーサルデザインに配慮した観光地の整備や旅行商品の開発を促進する。
(2) 地域経済を先導する観光産業の振興
北海道における観光産業の更なる発展のためには、地域の特徴的な資源・特性を活かし、食や健康といった内外の人々の嗜好・ニーズと観光を組み合わせ、地域の活性化に向けた相乗効果をより一層追求することが重要である。
このため、豊かな自然環境と農林水産業を始めとする地場の産業を組み合わせたグリーンツーリズム、マリンツーリズム、ヘルスツーリズムといったニューツーリズムの創出・普及を、産学官が連携して促進する。また、地域資源を利用したその地ならではの産品の開発・販売やこれらの活用を促進する。
さらに、地域の観光産業の中核を担うリーダーや接遇に携わる人材を始めとする観光産業の従事者、多様な主体が参画する観光地づくりをマネジメントする人材等の確保・育成と能力の向上を促進する。その際、観光関係人材の育成に取り組む大学等との連携を促進する。

3.東アジアと共に成長する産業群の形成
グローバル化の進展と東アジア地域の急速な成長は、我が国にとって市場拡大の好機である。北海道が地理的特性、固有の資源、培われた技術、各種基盤等を最大限に活用し、東アジアと共に成長していく産業群の育成を図ることが重要である。
このため、既存産業集積や技術的蓄積など地域の強みを活かした産業の育成を図るとともに、物流機能の強化や人材の育成などの条件整備を図ることが必要である。
(1) 地理的優位性を活かした産業立地の促進
北海道は、北米と東アジアとを結ぶ線上に位置し、ロシア極東地域にも隣接している。また、日本海側と太平洋側のそれぞれに港湾を有し、その間に空港や工業団地などの基盤の集積が存在している。これらの地理的優位性を活かし、北米及び東アジア各地域との一層迅速で円滑かつ低廉な物流を推進することで、東アジア地域の成長と活力を取り込んでいく産業群の形成を図ることが重要である。
このため、苫小牧港、石狩湾新港、新千歳空港などの国際物流機能の強化を図るとともに、既存の産業集積を活用した生産拠点の形成を促進する。また、素形材産業などの基盤技術に関する産業の育成や地場企業の技術力の向上を進め、加工組立型産業の集積を促進する。これにより、国際物流・交流拠点と生産拠点とが一体となった相乗効果の発揮を目指す。
苫小牧東部地域は、これらの港湾や空港に近接し、広大かつ自然環境にも恵まれた、開発可能性の高い貴重な空間である。関係機関の緊密な連携の下、自動車関連産業、リサイクル産業など既存立地分野の一層の集積を促進する。また、バイオ燃料関連産業等の新たな産業の育成、自然エネルギー源を活用した大規模農産物貯蔵施設の整備と高品質な農水産物の輸出、国際物流関連企業の誘致を促進し、国際総合物流ターミナルの形成を図るなど、東アジア地域を視野に入れた取組を戦略的に推進する。あわせて、他の土地利用についても検討しつつ、当該地域の開発を推進する。
(2) 強みを活かした産業の育成
(IT、バイオ、環境・エネルギー関連等成長が期待される産業の育成)
これまで「北海道産業クラスター創造プロジェクト」として産学官が一体となって育成してきたIT、バイオ産業は、大学発ベンチャーの誕生や研究拠点、インキュベート拠点の形成など、産業としての地域的優位性を発揮しつつある。このような好条件を活かし、両産業を国際競争力を有する産業として成長させるとともに、これらの分野の技術革新は他の産業に幅広く影響を及ぼすことから、域内での技術移転を積極的に進め、道内産業全体の底上げをもたらすことが重要である。
また、環境・エネルギー関連の技術は、資源の再生利用やエネルギー源の多様化等の観点から、北海道において集積を進めることが必要である。東アジア地域の急速な経済発展がもたらすエネルギー需要や環境負荷の増大から、これらの技術を利用するビジネスチャンスも拡大している。
このため、IT、バイオ産業については、企業と大学・研究機関等の連携の下に先端的な研究を実施するとともに、研究開発型企業の誘致、コーディネート人材・組織の確保・充実を進め、一層の知的資産の集積と活用を促進し、新事業・新産業の創出を推進する。特に、こうした産学官のネットワークや新たな技術を活用し、農水産業や食品加工業の生産効率、安全性、品質の向上に向けた取組を進め、食にかかわる産業の高付加価値化を推進する。
また、風力、バイオマス等の自然エネルギーや水素エネルギーといった、北海道において優位性のあるクリーンエネルギーに関連する技術や、リサイクル関連産業を始めとする環境ビジネスに関連する技術について、産学官連携による研究開発や事業化・企業化を促進する。
(森林資源を活かした産業の育成)
木材の需要が、品質及び性能の明確な製品を大量かつ安定的に求める構造に変化している中、北海道においては、利用拡大が期待されるカラマツ人工林の多くが主伐期を迎えつつあるなど利用可能な人工林資源は増加している。こうした状況から、木材産業において、市場のニーズに対応した品質及び性能の明確な付加価値の高い製品の生産を拡大し、安定的かつ低コストで供給することにより、道産材の競争力強化を図ることが必要である。
このため、合板、集成材等の製品を低コストで生産するための高次加工施設を整備するとともに、製材工場については連携や協業化等による規模拡大を図るための取組等を促進する。また、計画的な伐採や植栽等により森林資源を保全しつつ、施業の集約化及び低コストかつ高効率な施業のための作業システムの整備等木材の安定供給体制の整備を促進する。
(3) 産業育成に向けての条件整備
人口が減少していく中、北海道が活力ある地域として発展するためには、発展を支える人材を育成すること、北海道内の資金を道内の有効な投資に結びつけることが必要である。
このため、高度な技術を有する人材を育成する大学、試験研究機関などの集積、産学官・企業間の連携の強化による地域の知の拠点の活性化を促進する。また、内外の能力ある人々が北海道において研究開発活動を展開、継続し得る環境づくりを進める。
さらに、若年層の流出は発展の基盤の喪失につながることから、職業能力開発や地域における就業情報の提供など、若年層が北海道で活躍できる雇用環境の整備を促進する。
加えて、域外市場への販路拡大、地域資源を活用した新たな取組の掘り起こしや地域資源のブランド化等に向けた地域一体の取組を促進する。

第2節 地球環境時代を先導し自然と共生する持続可能な地域社会の形成
持続可能で美しい北海道の実現に向けて、北海道の豊かな自然環境の価値を維持し向上させることが必要である。生物多様性の損失など自然環境の変化、天然資源の減少、地球温暖化といった地球規模での環境問題が深刻化しており、国民の自然に対するニーズが多様化している中でこれらの問題に対応し持続可能な社会を構築していくことが重要である。
また、環境負荷の少ないエネルギー利用は、北海道の気候、地形、社会的特性を活かせる有利な分野であり、北海道に豊富に存在する自然エネルギー源を活かし、エネルギー問題の解決や地球温暖化対策について先導的な役割を果たすことが必要である。
(1) 自然共生社会の形成
(良好な自然環境の保全)
北海道の豊かな自然環境は、我が国にとってかけがえの無いものであり、これを次世代に引き継ぎ、恵まれた自然と共生する社会を形成するためには、多様な野生生物の生息・生育環境の保全・再生・創出、水環境の保全・改善等を進め、生態系ネットワークの形成を図る必要がある。
このため、世界自然遺産の知床及びその周辺地域、釧路湿原・サロベツ原野に代表されるラムサール条約湿地、自然公園などの自然環境の保全・再生を推進する。貴重な動植物の生息等に適した優れた自然環境を有する森林については、その機能を持続的に発揮させるように保全・管理を推進する。さらに、多様な動植物の生息・生育環境の確保を図るため、多自然川づくりを始め、河川や湿原、藻場、干潟、汽水域等の海域・沿岸域の良好な環境の保全・再生を推進する。
また、水生生物の生息環境に配慮した海岸・港湾・漁港整備、野生生物の移動経路を確保した道路整備、生物多様性の保全を重視した農林水産業の推進など、豊かな生態系との共生を目指す。
水質や河川流量等の水環境の保全・改善や土砂移動の阻害の改善等については、流域圏における健全な水循環系の構築や、山地から海岸までの一貫した総合的な土砂管理の取組を推進する。流域からの汚濁負荷を低減するため、下水道・浄化槽・農業集落排水施設の整備等の生活排水対策、畜産経営等における水質汚濁防止対策を、計画的・効率的に促進する。特に、河川・湖沼における水質悪化の進んだ閉鎖性水域等において、流域における汚濁負荷削減対策と一体となって、導水・底泥浚渫等の水質浄化対策を推進するとともに、水質悪化の進んだ港湾やその周辺海域において、浚渫・覆砂等による海域環境の改善を促進する。
(北海道らしい個性的な景観、自然とのふれあい空間の形成)
北海道においては、都府県とは異なる歴史的・社会的条件が豊かな自然環境と相まって特徴的な景観が形成されている。これを継承するとともに、自然とのふれあいの場をつくり、人と自然とのつながりを保っていくことが必要である。
このため、北海道の農村特有の良好な景観の形成を促進するとともに、農村の豊かな自然環境の保全・再生に向けた活動を支援する。また、湿地の保全・再生、多自然川づくり、防雪林や道路敷地における緑化等の取組を推進する。都市部については、まちづくりや河川整備等が一体となって水と緑の連続性を確保することにより、水と緑あふれる都市空間の形成を推進する。
また、北海道の自然環境の魅力を活用し、内外の人々の保養・交流空間や自然とのふれあい空間を提供するため、都市公園や水辺・海辺、フットパス等の整備を推進する。
(豊かな自然をはぐくむ意識の醸成)
北海道の豊かな自然を次世代に継承するためには、国、地方公共団体、住民、NPO、企業等の多様な主体が協働して環境保全活動に取り組むことが必要であり、環境保全に係る教育や情報提供を通じて、豊かな自然をはぐくむ意識を醸成することが重要である。
このため、学校、地域、社会等幅広い場において環境教育を実施する。また、環境教育を担う人材の育成や人材認定等事業の登録制度の運用、効果的な環境教育プログラムの整備、環境に関する正確な情報を入手できるインターネット等を活用した情報提供の体制を充実する。
(自然とのかかわりが深いアイヌ文化の振興等)
アイヌの伝統や文化が置かれている状況を踏まえると、アイヌ文化の振興等を図るための施策を推進することが必要である。
このため、自然とのかかわりの中で育まれてきたアイヌ文化を総合的に伝承していくアイヌの伝統的生活空間(イオル)の再生を支援するとともに、アイヌ語やアイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する普及啓発、アイヌに関する総合的かつ実践的な研究を支援する。
(重視すべき機能に応じた森林づくりの推進)
森林の有する様々な多面的機能を持続的に発揮させるためには、重視すべき機能に応じた望ましい森林の姿として、水土保全林、森林と人との共生林及び資源の循環利用林に区分し、それぞれの森林について重視すべき機能に応じた望ましい森林の姿へ誘導することが必要である。
このため、林業・木材産業の構造改革と木材利用の推進による間伐等の採算性の向上、森林整備・保全の担い手の確保・育成と山村地域の活性化及び森林所有者のみならず都市住民・企業等幅広い主体による森林づくりの推進に取り組む「美しい森林づくり推進国民運動」の展開により、着実な間伐の実施や、針広混交林化、長伐期化等の多様で健全な森林づくりを推進する。
(2) 循環型社会の形成
資源採取、生産、流通、消費、廃棄などの経済社会活動の全段階を通じて、新たに採取する資源をできる限り少なく、また、環境負荷をできる限り少なくするため、3R(廃棄物等の発生抑制(リデュースReduce)、循環資源の再利用(リユースReuse)及び再生利用(リサイクルRecycle))の推進により、循環型社会の形成を図る必要がある。
特に北海道では、全国平均と比較して1人当たり廃棄物排出量が多く、廃棄物の直接埋立処分の割合が高いことに加え、リサイクル率が低くなっており、循環型社会の形成に向けた取組を一層加速する必要がある。
このため、リデュース・リユースについては、老朽化した公共施設の適切な維持管理や改良整備等により施設機能を適切に維持し、ライフサイクルコストの縮減及び施設の長寿命化を推進する。良質な住宅ストックを長く大切に使う社会の実現のため、耐久性に優れ生活様式等の変化に柔軟に対応できる住宅・建築物の普及や、住宅等の履歴情報システムの構築を促進する。
また、リサイクルについては、下水熱等都市部における廃熱、家畜ふん尿・下水汚泥からのバイオガスの回収など未利用・廃棄物系バイオマスの有効活用を中心とした再生利用を図るとともに、最終処分場も含めた廃棄物処理施設の整備を促進する。また、総合静脈物流拠点港(リサイクルポート)の整備等を通じた効率的な静脈物流ネットワークの構築を推進する。
さらに、国等の行政機関は、事業ごとの特性や必要とされる機能の確保、コスト等に留意しつつ、率先して環境物品等の調達を推進する。また、建設工事のゼロエミッション化に向け、公共事業の実施に伴う発生土砂の有効活用などを推進する。さらに、循環型社会の形成を図るためには、人々の意識と行動の変化が不可欠であることを踏まえ、環境教育等を通じた意識啓発を推進する。
(3) 低炭素社会の形成
(地球環境負荷の少ないエネルギーの利活用促進)
地球温暖化問題が顕在化する中、生活の豊かさの実感と、二酸化炭素排出削減が同時に達成できる低炭素社会の実現に向けた取組を進めることが急務となっている。
北海道は、風力、太陽光、雪氷冷熱、バイオマスなどのクリーンエネルギー源が豊富に存在しており、これらの資源を活用して、環境負荷の少ないエネルギーを積極的に導入することで、二酸化炭素排出量の削減を図り、地球環境負荷の低減に向けた先駆的・先導的な役割を果たす必要がある。
このため、原子力や天然ガス、自然エネルギー源等の利用によりエネルギー源の多様化を推進する。特に、クリーンエネルギーの地産地消の観点から、その先導的な利用を推進する。
また、資源作物や未利用・廃棄物系バイオマスからのバイオエタノール、バイオディーゼル燃料の生成などに必要な技術の開発及びその積極的な利用を推進するとともに、これらを新たな地域産業の核とする地域社会の活性化を推進する。
(効率的なエネルギー消費社会の実現)
積雪寒冷、広域分散型社会といった北海道の特性にかんがみ、熱のカスケード利用や効率的な交通システムの整備等を進め、エネルギー消費効率の高い地域社会を形成していく必要がある。
このため、民生部門については、住宅・建築物におけるエネルギーの効率的な利用に資する技術や設備の導入等を促進するとともに、都市部における地域熱供給や熱電併給(コージェネレーション)の導入を促進する。
また、運輸部門については、低公害車の導入、エコドライブ(環境負荷の軽減に配慮した自動車使用)の推進、市街地における渋滞対策、高規格幹線道路の利用促進、情報通信技術を活用した道路交通情報等の提供の充実、貨物の発着地に近い港湾の利用による陸送距離の短縮等を通じた効率的で環境にやさしい物流体系の構築(グリーン物流の推進)、公共交通の利用促進、船舶のアイドリングストップなど、環境負荷の少ない交通体系の構築を推進する。
(温室効果ガス吸収源対策の推進)
森林は、その成長の過程で二酸化炭素を吸収し、長期に貯蔵することが可能であるとともに、木材は、カーボンニュートラルという特性を有していることから、木材利用を通じた森林整備・保全を進めることが重要である。
このため、間伐等の適切な森林の整備・保全等を推進するとともに、国民一人一人の行動を促す観点から、地域住民、NPO等との協働による国民参加の森林づくり等の取組を推進する。また、道路、河川の緑化や公園、港湾緑地の整備等を推進する。
さらに、住宅や公共部門等への木材の利用の拡大や、林地残材等の未利用木質バイオマスの利用の拡大を支援する。

第3節 魅力と活力ある北国の地域づくり・まちづくり
多様で個性ある地域から成る北海道を実現するためには、医療、福祉、教育、情報、商業など地域の暮らしを支える都市機能を広域的な生活圏において維持し、各地域の特性を最大限活かした魅力と活力ある地域社会を形成していくことが必要である。
また、都市における機能の強化や人口低密度地域における地場産業の育成、二地域居住といった新たな居住形態の創造など、活力ある地域社会モデルへの取組を進めることが必要である。
(1) 広域的な生活圏の形成と交流・連携強化
広域分散型社会である北海道において活力ある地域社会を形成していくためには、地域経済や暮らしにおけるつながりを持つ6つの広域的な生活圏を単位とし、圏域全体で暮らしや経済を支えていくことが必要である。
このため、それぞれの広域的な生活圏の拠点となる都市に集積された都市機能を維持・高度化しつつ、都市間で相互に機能が補完されるようなアクセス強化を推進する。
特に、札幌市を中心とする都市圏には北海道内で最も高度な都市機能が集積しており、広域的な生活圏の拠点都市としての役割に加えて、北海道全体の経済社会を牽引していく役割が重要である。このため、都市圏の国際的な魅力を高め、諸外国を含む他地域との交流を発展させる取組を推進する。また、北海道全体を対象とする高次の都市機能が維持増進されるよう、高度な知的資本の集積、産学官・企業間の連携の強化、文化芸術活動の振興など拠点性の向上を図るとともに、これを支える土地の高度利用、都市構造の再編等を推進する。
多様で個性ある広域的な生活圏の形成に向けて、圏域内外の様々な連携が相乗効果を生み出すよう、交通・情報・人的ネットワークの強化を推進し、全国、世界との直接的な交流を促進させる。
また、「国土の国民的経営」による地域づくりという考え方に立ち、美しく豊かな国土を国民全体として支えるとともに、後世代に継承していくため、民間を始めとする多様な主体による開かれた地域づくりの実践等を図り、活力ある地域社会のモデルとなる先駆的な取組を推進する。
(2) 都市における機能の強化と魅力の向上
(集約型都市構造への移行)
人口減少・少子高齢化を迎える中で、活力ある地域経済社会を維持していくため、今後目指していくべきものと考えられる集約型都市構造への移行を基本とした各種施策を進めていくことが必要である。
このため、まちなか居住の推進や都市機能の集約化により拠点でのにぎわいづくりを進める。また、除雪費低減など都市経営コストを抑制するため、郊外部における土地利用規制等による都市機能の適正配置を図る。集約拠点となり得る主要駅周辺の低未利用地等では、都市機能の効率を高める街区の再編や基盤施設の一体的整備を推進し、集約拠点へつながる公共交通ネットワークや、道路ネットワークの強化などを推進する。
(都市の魅力・活力の向上)
地域の歴史、産業等を地域の誇りとして再認識し、これを観光資源として活かすなど、地域主導の個性あるまちづくりを進めることにより、都市の魅力・活力を向上し、活発で多様な交流を推進する必要がある。
このため、文化財や産業遺産の保存・活用、美しいまちなみ景観の形成等を促進するとともに、地域からの情報発信・交流機能を高める観光情報センター等の施設整備や、にぎわいを創出するイベントの実施、観光資源の発掘等を促進する。このような活動は、住民、企業、行政の協働により地域が一体となって行われることが重要であり、地域の協働によるまちづくりの展開を促進する。
また、住民が安心して働き、活き活きと暮らしていけるよう、安全・安心で良質な住宅を適時・適切に選択できる住宅市場の形成及び住宅のセーフティネットの構築、上下水道の整備等を促進する。
(冬も暮らしやすい生活環境の創造)
北海道の積雪寒冷な気候は、地域経済や暮らしの障害となっている面もあることから、快適な冬の生活環境づくりを目指した施策の推進が必要である。
このため、北方型住宅に代表される高断熱・高気密住宅の性能向上のための仕様や工法等の開発と、一層の普及を促進する。また、冬でも暖かい共用廊下等を設置するなど克雪型の集合住宅の普及や、堆雪空間としての活用に配慮した都市公園、融雪槽等の整備を促進する。
また、冬でも快適な歩行空間の確保を図るため、駅周辺部や公共施設周辺等において、冬期を考慮した歩行空間のバリアフリー化や地下を利用した歩行者用通路等の整備を推進するとともに、地域住民等との協働により、転倒事故を防止するための取組等を推進する。
さらに、冬の余暇活動の場として、スキー場の活性化等を図るとともに、屋内遊戯施設、体育館、冬季スポーツ施設を備えた都市公園の整備を推進する。
(ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたまちづくり)
高齢者や障害者等を含めたすべての者の社会参加による活力ある社会を実現するため、ユニバーサルデザインの考え方を踏まえたまちづくりを進める必要がある。
このため、公共交通機関、建築物、道路、公園等のバリアフリー化を推進するとともに、意識啓発や交流の場の提供による心のバリアフリー化を推進する。
また、安心して子どもを生み育てられる環境を確保するため、家族向け賃貸住宅や子育て支援施設の充実及び歩いて行ける身近な緑地の保全や都市公園の整備を促進する。
さらに、障害者が施設から地域へ居住の場を移し、社会参加の機会を広げ、様々な人々との交流を深めるための活動を支援する。
(3) 人口低密度地域における活力ある地域社会モデルへの取組
主として農林水産業が営まれている人口低密度地域では、人口減少等の進行により、地域社会の活力や社会的サービスの低下が懸念されている。
こうした地域においては、恵まれた環境、良好な生産基盤及びこれらの下で展開される生産活動と結び付き形成されてきた美しい景観等、地域資源の適切な保全を図りながら、その魅力や特性を最大限利用し、都市との交流の拡大等を通じた地域社会の活力の維持向上を図る必要がある。
このため、生産者と地域住民による地域資源の保全・活用に係る共同活動等の実践、地域資源を活用した内発型の地場産業の育成を促進する。また、グリーンツーリズム、マリンツーリズム等を促進するとともに、企業やNPO等による森林整備・保全活動や森林体験学習及び森林セラピーの取組等を促進する。
さらに、地域の内外の多様な主体による連携・協働により、質の高い生産環境の整備、モビリティの確保、長期滞在、二地域居住、冬期集住にも対応した暮らしやすい生活環境の整備、地域資源を活かした観光等の推進を行う、活力ある地域社会モデルの構築を図る。
(4) 多様で個性的な北国の地域づくり
広大な北海道は、一つの同質的な地域ではなく、気候、人口、産業、歴史、文化等が異なる多様で個性的な地域から成り立っており、それぞれの地域資源を活かして独自性のある発展を遂げていくことが必要である。また、地域の成長力を高めていくためには、東アジアを始め内外の諸地域との交流・連携を進めていくことが必要である。
このため、地域における行政・民間の多様な主体は、地域の将来像の実現に向けて、適切な役割分担の下、ハード・ソフトの両面にわたる多様な連携・協働を推進する。また、交通ネットワークなど交流基盤の整備を推進するとともに、北海道と隣接する東北地方やサハリン州などとの交流を始め、内外の諸地域との交流を促進する。
なお、我が国固有の領土である北方領土では、戦後60年以上を経た今もなおロシアによる不法占拠が続いている。根室市等の北方領土隣接地域は、かつて行政的にも経済的にも北方領土と一体の社会経済圏を形成して発展した地域であるが、北方領土問題が未解決であることから、戦後はその望ましい地域社会としての発展が阻害されてきた。また、当該地域は、北方領土元居住者が多数居住する北方領土返還要求運動の拠点である。
このため、安定振興対策を計画的に推進するとともに、旅券・ビザなしで実施される四島交流や国民世論の啓発活動の一層の充実などにより、北方領土の早期返還の実現に向けた環境整備を推進する。

第4節 内外の交流を支えるネットワークとモビリティの向上
この計画の戦略的目標を達成するため、前述の主要施策の展開と併せて、道内外の拠点を結び経済活動を支えるネットワークの強化とモビリティの向上を図るとともに、広域分散型社会に対応した地域交通・情報通信基盤の形成や、積雪寒冷な気候に対応した冬期交通の確保を図ることにより、活力ある地域経済社会の基盤を整備していくことが必要である。
(1) 国内外に開かれた広域交通ネットワークの構築
(高速交通ネットワークの強化)
広域分散型社会を形成している北海道において、交通機関が相互に連携・連続した利便性の高い高速交通ネットワークの形成を図るため、高規格幹線道路を始めとする基幹的なネットワークの整備を推進するとともに、内外との交流基盤である新幹線、空港の整備を推進する。
高規格幹線道路を始めとする基幹ネットワークについては、今後の具体的な道路整備の姿を示す中期的な計画に即して、主要都市間を連絡する規格の高い道路、拠点的な空港・港湾へのアクセス道路や国際競争力確保のための道路などに重点をおいて効率的な整備を推進する。
北海道新幹線については、平成16年12月の政府・与党申合せ「整備新幹線の取扱いについて」に基づき、着工区間の着実な整備を進めるとともに、それ以外の整備計画区間である新函館・札幌間について所要の事業を進める。
航空については、海外との玄関口となる新千歳空港において国際空港機能の向上を推進する。また、その他の道内各空港についても、東アジア地域等との交流が緊密化・高頻度化していることを踏まえ、必要な国際空港機能の向上を図る。さらに、国内外の航空路線網の充実を支援するとともに、国際競争力の強化や空港背後地域の地域競争力強化、空港利用者の利便増進を図るための空港機能の高質化を推進する。
(国際競争力を高めるための物流ネットワーク機能の強化)
北海道は、北米と東アジアを結ぶ線上に位置し、ロシア極東地域にも隣接している。また、シベリアランドブリッジを通じて欧州と結ぶことも可能である。このような地理的優位性を活かして、北海道における国際物流の一大拠点の形成を図るため、苫小牧港の国際海上コンテナや新千歳空港の国際航空貨物の輸送に係る機能強化を推進するとともに、港湾手続の統一化・簡素化等港湾サービスの一層の向上、国際複合一貫輸送等の新たな輸送手段の確立を促進する。
また、北海道の基幹産業である農業、製紙業等の競争力を強化するため、飼肥料や原材料の輸送コスト低減に資する多目的国際ターミナルの整備を推進する。
さらに、港湾・空港や道内各地の物流拠点・生産拠点と高規格幹線道路とのアクセスを強化するほか、国際標準コンテナ車が支障無く通行できる幹線道路ネットワークを構築する。
一方、国内物流においても、本州と北海道を結ぶフェリー、RORO船航路による輸送効率の高い国内物流の促進を図るため、内貿複合一貫輸送機能の維持・向上を推進する。
(2) 地域交通・情報通信基盤の形成
(バランスの取れたまちなか交通体系の実現)
将来の望ましい都市・地域像の実現に向け、徒歩、自転車、自動車、公共交通がバランスの取れた交通体系を構築することが必要である。
このため、地域公共交通の活性化や再生、交通結節点や歩行者空間、自転車走行環境の整備を推進することにより、高齢者、通学者等の日常生活におけるモビリティを確保する。また、広域分散型社会である北海道では自動車が交通手段の主役となっていることを踏まえ、渋滞の解消に向けた踏切対策、都心部へのアクセスの改善等を推進する。さらに、これらのハード・ソフト両面からなる総合的な交通施策を関係者が一体となり、戦略的に推進する。
(地域の実情に即したモビリティの確保)
北海道における地域公共交通は、高度に人口が集積した都市部を除き、バス交通が主役であるが、利用者の減少等による運行本数の減少や収益構造の悪化などにより、その維持が厳しい状況にある。
地域の実情に即したモビリティを確保するため、市町村、公共交通事業者、地域住民等の地域の関係者が協働して主体的な取組を行うことが必要であり、コミュニティバスやデマンド型乗合タクシーの導入等、地域公共交通の活性化・再生を図るための取組を促進する。
また、新たな公共交通として、観光資源としても期待されるDMV(デュアル・モード・ビークル)の実用化に向けた取組等を促進する。
離島交通については、本土への安定的なアクセスを確保するため、航路・航空路の維持及び防波堤等の整備を推進する。
人口減少下において、多様化する地域や交通利用者のニーズにきめ細やかに対応し、効率的・効果的にモビリティの向上を図っていくためには、行政だけでなく地域や交通利用者も含めた多様な主体の発意や活動を活かすことが重要である。このため、「シーニックバイウェイ北海道」の取組から得られた知見を基に、地域の発意、地域資源、既存ストックを最大限活用した地域課題の解決、交通基盤施設の整備やその利活用を推進する。
(情報通信体系の整備と利活用の促進)
国内、世界との交流や、広い北海道内の交流等、広域的な交流の強化に向けて、情報通信の利活用は、活力ある地域社会の形成のため必要不可欠である。とりわけ、高品質な食料を供給する農山漁村や優れた自然を有する観光地など人口低密度地域において、競争力ある地域産業の振興や地域社会の活力維持を図るため、情報通信体系の充実を推進していく必要がある。
このため、光ファイバ網や無線アクセスシステム等の情報通信体系の整備を推進するとともに、情報通信技術を利活用した公共サービスの高度化・効率化等を推進する。
(3) 冬期交通の信頼性向上
冬期における道路交通は、積雪や路面凍結に起因する都市部の渋滞、地吹雪や雪崩等による通行止めの発生など多くの問題を抱えている。これらの問題を克服し、安全で信頼性の高い道路交通を確保するため、効率的な除排雪の実施、雪崩防止施設や防雪林等の整備、堆雪幅の確保、凍結路面対策等を推進する。
また、航空輸送の定時性・安定性を確保するため、ILSの双方向化や滑走路の改良、除雪体制の強化等を推進する。

第5節 安全・安心な国土づくり
安全・安心の確保なくして国民の生活や経済社会の安定は図れない。地震、水害等の災害から国民の生命や財産を守ること、交通の安全確保など、安全・安心の確保は、国の最も重要な責務の一つであるとともに、経済社会活動の基盤である。北海道は、水害による被害額が全国でも有数であるとともに、多数存在する活動的な火山による災害、日本海溝・千島海溝等で発生する地震災害等の危険性が高く、自然災害に対していまだ脆弱な地域である。さらに、地球温暖化に伴う気候変動等による集中豪雨等の増加や海面上昇等、災害リスクの増大が懸念される。このため、安全・安心な国土づくりを着実に推進する必要がある。
(1) 頻発する自然災害に備える防災対策の推進
(根幹的な防災対策の推進)
自然災害が頻発し、災害リスクの増大が懸念されている状況にかんがみ、水害に対し、堤防、洪水調節施設等の根幹的な治水施設等の整備、近年被災した河川における再度災害を防止する対策等の治水対策、下水道による浸水対策を重点的に推進する。
集中豪雨や火山の噴火等により発生する土砂災害に対し、人命等を守るための土砂災害対策を推進する。特に、住民等の避難路、避難場所の確保、災害時要援護者の安全確保等のための対策を重点的に推進する。また、噴火等により機能が損なわれた場合、経済社会への影響が極めて大きい中枢的交通基盤等の保全を推進するとともに、代替機能確保のための対策を推進する。
長大な海岸線を持つ北海道における津波、高潮、波浪等による被害から海岸を防護する総合的な海岸保全を推進する。
道路について、異常気象時通行規制区間等における岩盤斜面対策等の防災対策を優先して推進し、道路密度の低い北海道において信頼性の高い道路ネットワークの構築を図る。
山地災害を防止するため、計画的な保安林の配備を推進するとともに、近年の災害の発生形態の変化を踏まえ、山地災害危険地区の的確な把握等を図りつつ、国有林と民有林を通じた計画的な事業の実施等により効果的な治山施設の設置等を推進する。
農地、農業用施設を災害から守るため、地すべりの防止等の防災対策を推進する。
災害などによる大規模な断水は国民生活に大きな影響を与えることから、災害時にも安定的な水道用水の供給ができるよう、水道施設の整備を促進する。
(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震等、地震・津波に備えた防災対策の推進)
北海道では、釧路沖地震、北海道南西沖地震、十勝沖地震等、近年においても大規模な地震が発生していること、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定があったこと等を踏まえ、防災関係機関、NPO、企業、地域住民が連携した地震・津波防災対策を推進する必要がある。
このため、避難場所の整備、地震・津波情報の早期提供、緊急地震速報の利活用等を推進する。また、救急・救命、避難、緊急物資輸送等を確保するための緊急輸送道路の橋梁の耐震補強、港湾における耐震強化岸壁を配備した臨海部防災拠点の整備、空港・漁港施設や河川構造物、海岸保全施設の耐震強化を推進するとともに、被害軽減のための河川、港湾、海岸における津波対策等を推進する。さらに、避難路や緊急輸送道路沿道等の住宅・建築物の倒壊等による被害軽減を図るため、住宅・建築物の耐震化を促進する。
(豪雪対策及び積雪寒冷地域における防災対策の推進)
豪雪等による国民生活や経済社会活動への影響を緩和するため、豪雪時の情報連絡本部設置など除排雪における関係機関の連携等を強化する。また、冬期の地震・津波発生時等においては、避難路の積雪や凍結によって避難が困難となることが予想されるため、避難路の除雪・防雪・凍雪害防止対策の強化推進、冬期を想定した避難訓練実施等、積雪寒冷地域の特性を考慮した防災対策を推進する。
(2) ハード・ソフト一体となった総合的な防災・減災対策の推進
(地域防災力を向上させる取組の推進)
安全・安心の確保には、災害が発生した場合においても国民生活や経済社会活動に深刻な影響を生じさせないよう、施設整備等のハード対策と併せ、防災情報の高度化、防災関係機関の災害情報伝達体制の整備等、被害の軽減を図るソフト対策を一体的に進めることが重要である。また、高齢化等の経済社会の変化に伴い、地域防災力の低下等も懸念されていることから、地域住民や企業を含めた自助、共助、公助のバランスの取れた地域防災力の再構築など、総合的な防災・減災対策を講じることが必要である。
このため、迅速かつ円滑な災害対応を行うため、防災情報の高度化、防災情報共有体制の整備、防災情報伝達基盤の強化を推進するとともに、現地での速やかな応急対策実施や復旧活動支援のため、被災地への緊急物資輸送等を確保するための体制整備、災害対策用機械の効率的運用、防災資機材の適正配備など、防災関係機関の連携強化を推進する。
また、市町村による洪水、津波、高潮、土砂災害、火山災害等の各種ハザードマップの作成・普及に対する支援、職員の防災技術向上のための講習会の実施等、地方公共団体の防災力向上を支援する取組を推進する。
さらに、NPO等との協働による防災教材の作成・普及等、地域における防災教育活動を推進するとともに、防災関係機関と地域住民が参加する防災訓練の実施など、地域との協働による防災対策の取組を推進する。
(災害に強いまちづくりの推進)
地域に根付いた防災・減災対策を実施するためには、まちづくりや住まい方等を含め、関係する様々な主体が相互に連携し、総合的に取り組む必要がある。
このため、土砂災害警戒区域等の指定、特定開発行為の制限促進等、災害の危険度を考慮した計画的な土地利用に努めるとともに、防災拠点となる公園・緑地、避難路、防災ステーション等の整備を推進する。また、堤防、遊水地等の整備とまちづくり・地域振興施策とを連携させるなど、災害に強いまちづくりを推進する。
(多様な災害・事故等に対応する体制の強化)
油流出事故に伴う海洋汚染の拡大を防ぐための体制の整備、国際交流の窓口である港湾・空港を始めとする重要施設、公共交通機関等におけるテロ対策の強化など、多様な災害・事故の被害軽減やテロの未然防止に向けた取組を推進する。
(大規模災害時等、非常時の業務執行体制の確保)
国、地方公共団体は、災害・事故発生時の対応のみならず、広く住民生活にかかわる重要な業務を遂行する責任を負っている。また、我が国の経済社会活動に深刻な影響を及ぼす大規模災害が発生した場合、被災地の速やかな復旧・復興には、周辺地域のみならず全国的な視点を持った支援が必要である。
このため、災害・事故の経済社会活動への影響を最小限にするため、官民それぞれの立場から非常時における業務執行体制確保のための取組を推進するとともに、広域的な支援体制確立のための取組を推進する。
(3) 道路交通事故等の無い社会を目指した交通安全対策の推進
北海道の交通事故死者数は、毎年高い水準で推移しており、安全な道路交通環境の整備が必要である。このため、道路網の体系的整備と併せ、事故データの客観的な分析に基づき、事故の発生割合の高い区間において集中的な事故対策を推進するとともに、人優先の安全・安心な歩行空間の確保を推進する。
また、情報通信技術を活用した道路情報提供や冬期道路管理の高度化等を推進するほか、積雪寒冷地域における道路交通の安全確保や郊外部における重大事故などの北海道特有の交通課題に関する研究開発を推進する。
港湾内の静穏度向上等により海上交通の安全性・安定性の向上を図るため、防波堤を始めとする外郭施設や航路、泊地等の水域施設の整備を推進する。
航空輸送における安全・安心を確保するため、道内各空港における基本施設や航空保安施設等の機能を保持するための更新・改良等を着実に推進する。
付記
施策の推進に当たっては、「政策の企画立案→実施→評価→改善」というマネジメントサイクルに沿って政策評価を積極的に進め、主要施策、期間等について弾力的運用又は必要に応じた見直しを図るとともに、計画策定からおおむね5年後に計画の総合的な点検を行う。また、道州制の導入など内外の変革を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを図るものとする。
なお、特殊な条件下に置かれている北方領土をめぐる状況が変化した場合には、この計画の改定を行い、開発の基本方向を改めて示すこととする。

|