新しい海難審判制度について
海難審判法は、昭和23年の施行以来、時代の流れとともに数度の改正を経てきましたが、近年の多様化・複雑化する陸・海・空の事故を踏まえ、運輸安全のより一層の確保が求められていることから、事故の再発防止機能の向上に向け、平成20年10月、「運輸安全委員会」と「海難審判所」が設置されることになりました。
「海難審判所」は、海事に関する豊富な知識・経験を有する審判官による海難審判を通じて海技免許等の所有者に対し懲戒処分を行い、もって海上交通の安全確保に努めていきます。
「海難審判所」は、海事に関する豊富な知識・経験を有する審判官による海難審判を通じて海技免許等の所有者に対し懲戒処分を行い、もって海上交通の安全確保に努めていきます。
組織改編のポイント
海難の原因究明機能を「運輸安全委員会」に移行し、「海難審判所」は海技免許等の所有者に対する懲戒処分を行います。
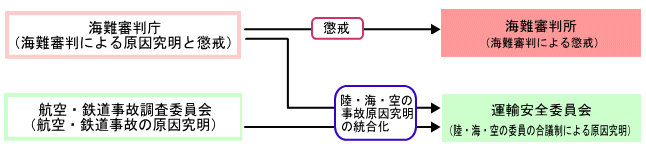
二審制から一審制に改め、東京の「海難審判所」では重大な海難を、「地方海難審判所」においてはそれ以外の海難を取り扱います。
重大な海難とは...
- 旅客のうちに、死亡者若しくは行方不明者又は2人以上の重傷者が発生したもの
- 5人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの
- 火災又は爆発により運航不能となったもの
- 油等の流出により環境に重大な影響を及ぼしたもの
- 次に掲げる船舶が全損となったもの
- 人の運送をする事業の用に供する13人以上の旅客定員を有する船舶
- 物の運送をする事業の用に供する総トン数300トン以上の船舶
- 総トン数100トン以上の漁船
- 前各号に掲げるもののほか、特に重大な社会的影響を及ぼしたと海難審判所長が認めたもの
