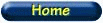主要なタンカー油流出事故について
主要なタンカー油流出事故について


平成12年7月
海上技術安全局安全基準課安全評価室
-
| 年 |
船名 |
旗国 |
汚染被害国 |
流出量
(トン) |
事故
内容 |
| 1967 |
トリー・キャニオン |
リベリア |
英・仏 |
119,000 |
座礁 |
| 1972 |
シー・スター |
韓国 |
オマーン |
120,000 |
衝突 |
| 1976 |
ウルキオラ |
スペイン |
スペイン |
100,000 |
座礁 |
| 1977 |
ハワイアン・パトリオット |
リベリア |
米国 |
95,000 |
破損 |
| 1978 |
アモコ・カディス |
リベリア |
仏 |
223,000 |
座礁 |
| 1979 |
アトランティック・エンプレス |
ギリシア |
トリニダード・トバゴ |
287,000 |
衝突 |
| 1979 |
インデペンデンタ |
ルーマニア |
トルコ |
95,000 |
衝突 |
| 1983 |
カストロ・デ・ベルバー |
スペイン |
南アフリカ |
252,000 |
火災 |
| 1988 |
オデッセイ |
ギリシア |
カナダ |
132,000 |
破損 |
| 1989 |
エクソン・バルディス |
米国 |
米国 |
37,000 |
座礁 |
| 1991 |
ABTサマー |
リベリア |
アンゴラ |
260,000 |
火災 |
| 1993 |
ブレア |
リベリア |
英 |
85,000 |
座礁 |
| 1996 |
シー・エンプレス |
リベリア |
英 |
72,000 |
座礁 |
| 1997 |
ナホトカ |
ロシア |
日本 |
6,200 |
破損 |
| 1999 |
エリカ |
マルタ |
仏 |
10,000+ |
破損 |
- 注)流出量はITOPF資料等による。ナホトカの流出量は海底沈没部分の貨物油を含まない。
 1.トリー・キャニオン(Torrey Canyon)
1.トリー・キャニオン(Torrey Canyon)
- リベリア籍の大型タンカー・トリーキャニオン号(118,285dwt)はクウエートで原油を満載し、英国(ミルフォードヘイブン)に向けて航行中、1967年3月18日に、英国南西部のシリー島とランズエンドの間の浅瀬に座礁した。
- 貨物油は直ちに壊れたタンクから流れ出した。離礁作業が難航し、3月26日に2つに折損した。油の流出が続き、英国政府は船内に残った4万トンの原油を燃焼させるために本船を爆破することを命じた。爆撃は3月30日まで続き、本船は沈没した。流出した油は119,000トンに及び、英国の南西部とフランスの北部沿岸部を深刻な被害を及ぼした。
- 事故の原因は、予定されたコースを変えて航行した船長にあるとされている。この事故を契機として、国際海事機関(IMO)において、タンカー事故時の油流出量の抑制策が検討され、1973年に海洋汚染防止条約(MARPOL)が締結された。
 2.シー・スター(Sea Star)
2.シー・スター(Sea Star)
- 韓国籍の大型タンカー・シー・スター号(120,300dwt、船齢4年)は12万トンのサウジ原油を積み航行中、ブラジル籍のタンカー・オルタ・バルボーサ(Horta Barbosa)(116、750dwt)とオマーン湾において1972年12月19日に衝突した。オルタ・バルボーサ号はアデンからイラクに向けてバラスト航海中であった。シー・スター号は大火災を起こし、乗組員12名が死亡した。舷側の破口部から流出した原油で海面も火炎に包まれた。オルタ・バルボーサ号も直ぐに延焼したが、36名の乗組員は無事退船した。シー・スター号の残りの乗組員29名も救助された。シー・スター号は激しく爆発、炎上を続けた後、12月24日に沈没した。
 3.ウルキオラ(Urquiola)
3.ウルキオラ(Urquiola)
- スペイン籍の大型タンカー・ウルキオラ号(111,225dwt)は11万トンのサウジ原油を積載し、揚げ荷のためスペイン北西部のコルーニャ港に入港中、1976年5月12日、船底を損傷した。積荷が船底部から流出し、火災爆発の危険があるため、港外への移動を命じられたが、再度船底を損傷し、港への2つの進入航路の間に座礁した。本船は50度傾き、積荷が噴出した。2時間後に船首部が爆発し、船長は死亡した。
- 黒い煙が港を覆い、流れ出た原油はスペインの北西部沿岸に拡散した。半没状態となった本船は激しく燃焼し、爆発による突風により周囲の窓が割れた。5月14日、本船は2つに折損した。
 4.ハワイアン・パトリオット(Hawaiian Patriot)
4.ハワイアン・パトリオット(Hawaiian Patriot)
- リベリア籍の大型タンカー・ハワイアンパトリオット号(99,447dwt、船齢12年)は95,000トンのブルネイ原油を積載して、ハワイに向けて嵐のなかを航行中、1977年2月23日、ホノルルの西330マイルの地点で船体に長さ30メートルのクラックを生じた。17,500トンを超える油が流出し、火災が発生した。大爆発が起き、本船は炎と黒い煙に包まれた。
- 一名が亡くなったが、他の38名の乗組員は海に飛び込み、近くを航行していた貨物船に救助された。本船は燃え続け、2月24日に2つに折損し、沈没した。流出した油は長さ50マイルに達し、海流によって流されたが、幸いハワイ諸島の海岸は汚染から免れた。
 5.アモコ・カディス(Amoco Cadiz)
5.アモコ・カディス(Amoco Cadiz)
- 1978年にリベリア籍のVLCCアモコカディス号(233,690dwt、船齢4年)が操舵装置の故障のため、フランス太平洋岸ブルターニュ半島で座礁し、積荷であった223,000トンのイラン原油全てを流出した。3月16日、荒天中を航行中、フランスの北西部Ushant沖8マイルにおいて操舵装置の故障が起きた。悪天候のため、タグボートの懸命の作業にも関わらず、本船は漂流し、同日遅くPortsall沖に座礁し、翌17日に2つに折損した。流出した原油の帯はリゾート地の砂浜を汚染し、漁業に壊滅的な打撃を与えた。125マイルに及ぶ海岸線が汚染された。
 6.アトランティック・エンプレス(Atlantic Empress)
6.アトランティック・エンプレス(Atlantic Empress)
- ギリシア籍のVLCCアトランティックエンプレス号(292,666 dwt)は、アラブ首長国連邦で積荷し、米国(テキサス)に向けて航行中に、リベリア籍のVLCCエージアン・キャプテン号(Aegean Captain)(210,257 dwt)と、トリニダード・トバゴの北方で1979年7月19日に衝突した。
- 損傷し破口を生じたアトランティックエンプレス号は積み油を大量に流出し、火炎に包まれた。34名の乗組員中、29名が死亡した。エージアン・キャプテン号は右舷船首部に破口し、同じく火炎に包まれたが、36名の乗組員は退船することができた。その積荷(200,499トン)も大量に流出した。エージアン・キャプテン号はカリブ海からシンガポールに向けて航行中であった。
- しばらくの間、両船は組みあった状態で漂流し、火炎に包まれたまま大量の油を流出し続けた。その後、両船は分離したが、その流出油は約25平方マイルにも及んだ。アトランティックエンプレス号は、7月21日にタグボートにより外洋に曳航された後も爆発・炎上を繰り返し、その火炎は上空200メートル近くにまで達したが、8月2日に船尾から沈没した。一方、エージアン・キャプテン号は乗組員が再乗船し、鎮火した。
 7.インデペンデンタ(Independenta)
7.インデペンデンタ(Independenta)
- ルーマニア籍の大型タンカー・インデペンデンタ号(147,631dwt、船齢1年)は1979年11月15日、イスタンブールの沖、ボスポラス海峡への入り口のマルマラ海において、ギリシア籍の一般貨物船エブリアリィ号(Evrialy)(5,298gt)と衝突し、爆発炎上した。事故により、インデペンデンタ号の45名の乗組員中、42名が死亡した。
- 本船はリビアからルーマニアに向けて、95,000トンの原油を積載して航行していた。衝突により、火災・爆発を生じ、エブリアリィ号も延焼した。エブリアリィ号の33名の乗組員は退船に成功した。4マイル離れた地点の窓ガラスが割れる程、爆発の衝撃はすさまじかった。インデペンデンタ号の壊れたタンクから流出した原油はボスポラス海峡を1マイル半にわたって火に包み、他船の航行は停止された。インデペンデンタ号は燃焼と油の流出を続けた後、12月14日に鎮火した。
 8.カストロ・デ・ベルバー(Castillo de Bellver)
8.カストロ・デ・ベルバー(Castillo de Bellver)
- スペイン籍のVLCCカストロ・デ・ベルバー号(271,540dwt)はアラブ首長国連邦からスペインに向け航行中に、1983年8月6日の早朝、ケープタウン(南アフリカ)の北西68マイルの南大西洋上で出火、炎上した。本船と付近の海上は、船体に生じたクラックからの貨物油流出により、周囲は直ちに火の海と化し、36名の乗組員の内3名が亡くなった。
- 本船は、続く2度の大爆発で2つに折れ、流出油は60平方マイルに達したが、南東の風が続いたため、海岸部の汚染は免れた。2つに折れた船体はそれぞれ分かれて漂流したが、船尾部は爆発した後、8月7日に沈没した。船首部は深海域に曳航された後、沈められた。
 9.オデッセイ(Odyssey)
9.オデッセイ(Odyssey)
- リベリア籍のタンカー・オデッセイ号(船齢17年)が、北海原油を積み米国に向けて航行中に、1988年11月10日、北西部大西洋上で悪天候のため、船体が二つに折損し、132,000トンの原油を流出した。
- 船尾部は火災を生じ、当日遅く沈没した。船首部もしばらく漂流した後、沈没した。流出油は厚さ1フィート、幅3マイル、長さ10マイルに達した。27名の乗組員全員が死亡した。
 10.エクソン・バルディス(Exxon Valdez)
10.エクソン・バルディス(Exxon Valdez)
- 1989年3月24日未明、米国エクソン社のVLCCエクソンバルディス号(214,861dwt,船齢3年)がアラスカのプリンス・ウィリアム湾で座礁した。本船は、アラスカ原油約20万トンを満載し、アラスカ州バルディス石油基地からロサンゼルスに向け航行中であった。座礁により、11の貨物油タンクのうち8タンクが、また、5のバラストタンクのうち3タンクが損傷し、事故発生後、数時間の内に船底破口部から原油約4万トンが流出した。この油流出により2,400kmにわたる海岸線が汚染され、米国沿岸での過去最大規模と言われる甚大な海洋汚染を引き起こた。
- この事故を契機として、国際海事機関(IMO)において、事故の再発防止対策が検討され、大規模な油流出事故への国際協力の枠組みを定めたOPRC条約が1990年に締結され、さらに、1992年には海洋汚染防止条約(MARPOL)が改正され、タンカーに二重船殻構造が強制化された。
 11. ABTサマー(ABT Summer)
11. ABTサマー(ABT Summer)
- リベリア籍のVLCC・ABTサマー号(267、810dwt、船齢17年)はイラン原油を満載し、ロッテルダム(オランダ)に向けて航行中に、アフリカ南西部アンゴラ沖900マイルの南大西洋上で1991年5月28日爆発炎上した後、沈没した。32名の乗組員の内、5名が亡くなった。船体は火炎に包まれ、流出した油も激しく炎上した。26万トンの原油が流出し、油面は80平方マイルに及んだ。
 12. ブレア(Braer)
12. ブレア(Braer)
- リベリア籍の大型タンカー・ブレア号(89,730dwt)が、1993年1月に英国北部シェットランド諸島で座礁し、ノルウェー産の軽質原油約84,000トンを流出した。ブレア号はカナダ(ケベック)に向けて航行中であったが、空気管が損傷し、燃料に海水が混入したことにより、機関が停止した。その後、救助活動が行われたが、荒天に災いされ、座礁に至った。
- 事故後、 燃料管の二重化、タンカーへの非常用曳航装置の義務付け等の再発防止策が国際海事機関(IMO)で検討され、1994年に海上人命安全条約(SOLAS)が改正された。
 13. シー・エンプレス(Sea Empress)
13. シー・エンプレス(Sea Empress)
- 1996年2月15日夜、130,018トンの北海原油を積載した、リベリア籍の大型タンカー・シー・エンプレス号(147,273dwt、船齢3年)が、英国南西部のミルフォードヘイブン港外で座礁した。座礁後、直ちに救助作業が開始されたが、荒天に災いされ、救助作業は難航し、漂流・座礁を繰り返した。2月21日深夜にようやく本船を港内の桟橋に着桟させ、船内に残った原油を陸揚げすることができた。
- 最初の座礁で約2,500トンの原油が、更にその後の救助作業の間に69,300トンの原油が流出し、国立公園内を含む約200kmの海岸線が汚染され、自然環境に深刻な打撃を与えた。
 14. ナホトカ(Nakhodka)
14. ナホトカ(Nakhodka)
- 1997年1月2日未明、ロシア船籍のタンカー・ナホトカ号(20000dwt、船齢26年)は、風速約20 m、波高約6mの大時化の状況下、C重油約19,000klを積載し、上海(中国)からペトロパブロフスク(ロシア)向けに航行中、島根県隠岐島沖北北東約106kmの海上において、船体が二つに折損し、船尾部が沈没、船首部は半没状態で漂流した。船長は死亡したが、他の乗組員31名は救命ボートに避難し、救助された。
- この事故により、折損した部分からC重油約6,240klが流出した。また、船首部が約2,800 klを残存したまま、7日午後、福井県三国町に漂着した。流出した油は島根県から秋田県に及ぶ日本海岸に漂着し、甚大な被害をもたらした。
- 事故原因の調査を行った結果、この事故は構造部材の著しい衰耗による「船体強度の大幅な低下」が原因であったため、我が国から国際海事機関(IMO)に旗国検査及びポートステートコントロール(PSC)の強化を提案した。その結果、板厚測定報告書への板厚衰耗限度の記載(1997年に海上人命安全条約を改正)、船体構造の健全性に関するPSCの強化(1999年にIMO総会決議を採択)、検査時における船舶の縦強度評価(2000年秋に海上人命安全条約を改正予定)等の事故再発防止策が採られている。
 15. エリカ(Erika)
15. エリカ(Erika)
- マルタ籍のタンカー・エリカ号(37283dwt、船齢25年)が、1999年12月12日、フランスの北西部ブレスト沖南方60海里を航行中に、荒天のため船体が真っ二つに折損した。折れた船体は共に沈没した。積荷の重油が大量に流出し、観光地として、また牡蠣やムール貝の養殖で有名なブルターニュ半島の400kmに及ぶ海岸に大規模な汚染をもたらした。
- 乗組員26人は全員救助された。エリカ号はダンケルク(仏)からリボルノ(イタリア)へ向け、3万トンの貨物油を積載して航行中であった。事故当時の風速は秒速25m、波高が6〜10mとされ、大時化の状態であった。エリカ号は事故の前日に、異常な傾斜を生じたことから、船長の判断により、ロワール川河口の港に向かっていた。
- 事故後、フランス政府は事故調査を行い、主因は「腐食による強度不足」であるとして、船齢の高いシングルハルタンカー(二重船殻化されていないタンカー)のフェーズアウト促進、ポートステートコントロール(PSC)の強化、船級協会の監督強化等一連の規制強化策を検討している。