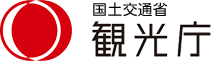髙橋長官会見要旨
最終更新日:2024年3月22日
日時:2024年2月21日(水)16:15~16:42
場所:国土交通省会見室
冒頭発言
(2024年1月の訪日外国人旅行者数について)
(旅行・観光消費動向調査(2023年年間値及び2023年10-12月期速報)の結果について)
- 本年1月の訪日外国人旅行者数等について報告があります。
- 本年1月の訪日外国人旅行者数は、268万8,100人となり、8ヶ月連続で、単月200万人を超えました。
- コロナ前の2019年1月と比べた回復率は、単月で100%となり、4ヶ月連続で単月ではコロナ前の水準を回復しました。
- 本年1月の出国日本人数は、83万8,600人となりました。コロナ前の2019年1月と比べた回復率は、単月で58%となりました。
(旅行・観光消費動向調査(2023年年間値及び2023年10-12月期速報)の結果について)
- 旅行・観光消費動向調査の2023年年間値及び2023年10-12月期の速報について報告します。本調査は日本人の国内旅行を対象としています。
- まず、2023年の年間値について、[1]延べ旅行者数、[2]1人1回当たり旅行支出、[3]この2つを掛け合わせた旅行消費額の順で申し上げます。
- 2023年の日本人国内延べ旅行者数は4億9,733万人、コロナ前の2019年比で84.7%となっています。
- また、日本人国内旅行の1人1回当たり旅行支出は、43,995円、2019年比で17.8%増と、コロナ前を上回る数値となっています。
- 旅行者数と単価を掛け合わせた国内旅行消費額は、21兆8,802億円と推計され、2019年比で99.8%と、コロナ前の水準を回復しました。
- これにより、観光立国推進基本計画における「国内旅行消費額を早期に」20兆円との目標を達成することとなり、国内旅行消費額は、順調に推移していると受け止めています。
- 続いて、昨年の第4四半期の結果について、[1]延べ旅行者数、[2]1人1回あたり旅行支出、[3]この2つを掛け合わせた旅行消費額の順で申し上げます。
- 2023年10-12月期の日本人国内延べ旅行者数は1億2,127万人、2019年同期比で91.3%と、初めて9割台まで回復しました。
- また、日本人国内旅行の1人1回当たり旅行支出は、46,289円、2019年同期比で22.2%増と、2022年第1四半期以降、コロナ前を上回る数値となっています。
- これらを掛け合わせた2023年10-12月期の日本人の国内旅行消費額は、5兆6,135億円、2019年同期比で11.5%増となりました。
質疑応答
(問)本日1月の訪日数が発表されました。能登半島地震の影響を含めて、どのように受け止めているか、改めて所管をお伺いします。
(答)
(問)中国からのインバウンドについては、回復の伸びが十分ではないとの認識を示されていましたが、今回の春節の動向について、どのように分析されているかお聞かせください。
(答)
(問)訪日外国人旅客数は堅調に伸びてきている印象ですが、今年に入ってからの出国日本人数の伸び率は4割減ということで、コロナ後もなかなか回復に至らない状況です。日本人のパスポート取得者数が減っている等、要因はいろいろあると思いますが、今後、出国日本人数を増やしていくための施策として、長官がお考えをお聞かせください。
(答)
(問)日本人の国内旅行の一人当たりの旅行支出単価というのが大幅に増えていると思いますが、その背景は物価の高騰と見られているのか、それとも他の要因があると見られているのか、教えていただきたいです。
(答)
(答)
(答)
- 本年1月の訪日外国人旅行者数は268万8100人と8ヶ月連続で単月200万人を超え、回復率は単月100%と4ヶ月連続でコロナ前の水準を回復していまして、堅調に回復しているものと受け止めています。
- 国・地域別に見ますと、韓国、台湾、豪州では単月の過去最高を更新したほか、主な23市場のうち、アメリカやシンガポールをはじめ10市場が1月として過去最高を記録しました。
- 我が国の観光の重要な柱である北陸地域は、能登半島地震によって甚大な被害や予約のキャンセルなど大変厳しい状況に置かれています。
- 観光庁としてもその復興に全力で取り組んでまいります。
- それ以外の国内の各地域につきましては、東アジア、東南アジアなどで若干のキャンセルがありましたが、その後堅調に回復してきています。
- 日本全体で見た場合には冒頭申し上げたような数字となっています。
- 観光庁としましては、今回の能登半島地震を受け、被災された方々へのご支援に力を尽くすとともに、北陸4県の比較的被害の少なかった地域については、正確な情報発信と訪日プロモーションを実施させていただき、風評対策に取り組んでいるところです。
- 引き続き、被災地域のご意向を丁寧に踏まえながら、北陸地域へのインバウンド誘客にしっかり取り組むとともに、全国的には11モデル地域における高付加価値なインバウンド観光地づくりや、全国各地での特別な体験の創出と世界への発信を進め、限りないポテンシャルを有する地方への誘客を強力に進めてまいります。
(問)中国からのインバウンドについては、回復の伸びが十分ではないとの認識を示されていましたが、今回の春節の動向について、どのように分析されているかお聞かせください。
(答)
- 1月の中国からの訪日者数は約42万人、2019年同月からの回復率は約55%となりました。
- 昨年11月の回復率は約34%であり、昨年12月の回復率は約44%でしたので、一定の回復傾向にあるのではないかと考えています。
- 今回の春節につきましては、その休暇期間が2月9日から始まり、17日に終了したばかりため、現時点において客観的な分析結果あるいは全体的な傾向を申し上げることは困難でありますが、JNTO(日本政府観光局)を通して現地の旅行会社に対し、春節の予約状況について聞き取りを行いました。
- 2019年の同時期とそれぞれ比較した場合、1月の回復率よりも春節期間の回復率の方が高かったと回答したケースが相当程度ありました。
- また、特に春節期間の予約数について、2019年の同時期以上の数と回答したケースも複数ありました。
- また、日系エアラインによりますと、春節期間の航空便の予約率は、それ以外の期間よりも高く、中国の民間旅行会社が実施した市場調査等では、春節旅行の目的地として「日本」や「東京」「大阪」などの日本の都市が上位にランクインしています。
- さらに、実際に春節中に中国から日本にお越しになった旅行者の動向について、各地に聞き取りを行っています。
- 例を申し上げますと、北海道道東では、個人旅行を中心に定期観光バスの利用者も増えるなど、中国からの訪日客がこの時期確実に増えました。
- 青森では、個人旅行者を中心に、昨年よりも明らかに中国からの旅行者が増えました。
- 鬼怒川地域では、祭りの時期に個人旅行客を中心とする中国からの旅行客などが増え、コロナ前水準に戻りつつあるとの回答がありました。
- このようなことをふまえますと、春節期間における中国からの訪日者数について2019年同時期比の回復率は、1月の回復率と同等、あるいはそれ以上の可能性もあるのではないかと考えています。
- また、先ほど申し上げた各地の聞き取りにおいて、例えば、北海道道東では氷結した阿寒湖の湖上トレッキングや、早朝の阿寒湖畔から日の出を見る等、屋外で大自然を満喫するアクティビティが大人気となっているとの回答がありました。
- 青森では、日本食やスキーなどの体験が人気で非常に混雑しているとの回答もあり、従来の買い物に止まらず、新たな魅力や楽しみ方が見出され、訪日旅行に広がりが生まれているところです。
- 他方で、先ほど申し上げたJNTO(日本政府観光局)による聞き取りにおいては、「中国経済全体の停滞が、販売予約に影響を与えている」との回答もありました。
- 現段階では、このように様々な回答や分析があり、引き続きしっかり分析して、来月、皆様に2月の数値をご報告・発表したいと考えています。
(問)訪日外国人旅客数は堅調に伸びてきている印象ですが、今年に入ってからの出国日本人数の伸び率は4割減ということで、コロナ後もなかなか回復に至らない状況です。日本人のパスポート取得者数が減っている等、要因はいろいろあると思いますが、今後、出国日本人数を増やしていくための施策として、長官がお考えをお聞かせください。
(答)
- 出国日本人数を増やしていく、あるいは回復させることにはいろんな役割がありますが、国際相互理解、平和の礎を築くという意味で、非常に重要なことです。
- 観光、国際観光は、相互交流においてバランスの取れたインとアウトが大事だと思っています。
- エアラインのネットワークを張るという意味でも、バランスの取れたインとアウトが大事であることは言うまでもありませんが、意義としても、日本人が外に出ていくということは大事だと思います。
- 特に、若い方々が外国を見て外国の方々と交流する、あるいは日本人の姿を若い感性で語っていただくことは、非常に大事なことです。
- 出国日本人数の回復率は、昨年12月で55%、1月で58%と伸びてきてはいるものの、インバウンドに比べると回復が遅れています。
- 要因の一つとして考えられるのは為替、日本人が外国に行く上で必ずしも有利な局面ではありません。
- 外国にも政府あるいは州等の観光局があり、通常、それぞれの国に呼び込むためのプロモーションを行います。
- そういった相手国の観光局との取組、あるいは、国内旅行業界の事業者等と連携して日本人の出国を後押しするようなプロモーションにより、機運をしっかり醸成していくことがあげられます。
- また、インバウンドも市場ごとマネジメントしているように、アウトバウンドにおいても、相手国との取組やイベント等を一つひとつ積み重ね、マネジメントしていくことが大事です。
- 一例を申し上げると、昨年、斉藤国土交通大臣と駐日大使が、本年を日米観光交流年にしようと署名式を行いまして、これから米国といろんな取り組みをしていきます。
- 例えば、多くの自治体が結んでいる姉妹都市交流をきっかけに行き来する、あるいは、お互いの国民に人気のある「野球」を切り口にして行き来する、そういった取組をさまざまな国々との間でもやっていきたいなと思っています。
- 今はSNSや映像等で、その国や人々の暮らしに触れることができますが、やはり、相手の国に行って実際の生活に触れたり話をすること、リアルな体験によって得られる感激や感動を、若い方々等にしっかり伝えていきたいです。
- 観光、リアルな交流は、決して他の何かに取って代わられるものでも、時代遅れになるものでもありません。
- リアルの交流、感動というものをしっかり若い方々等にお伝えし、修学旅行や教育旅行等の体験を、関係省庁と協力しながらさらに後押ししてまいります。
- また、さまざまな世代・年齢層の交流も、相手国の関係者と連携し進めていきたいと思います。
(問)日本人の国内旅行の一人当たりの旅行支出単価というのが大幅に増えていると思いますが、その背景は物価の高騰と見られているのか、それとも他の要因があると見られているのか、教えていただきたいです。
(答)
- 旅行消費額は、延べ旅行者数と一回当たりの単価を掛け合わせたものですが、これには、国内旅行消費額を早期に20兆円にするという「観光立国推進基本計画」の目標があります。
- 要因について見てまいりますと、国内延べ旅行者数のうち宿泊旅行については、観光・レクリエーション目的の宿泊旅行者数が、2023年全体でコロナ前の98.3%、直近の10-12月期でみると2019年同期比108.0%とコロナ前を上回っており、堅調に回復しています。
- 帰省や出張等を含めた宿泊旅行全体でみても、2023年はコロナ前の90.2%まで回復しています。
- 一方、日帰り旅行については、特に出張目的の旅行者数の回復が遅れており、日帰り旅行全体で、2023年はコロナ前の78.5%にとどまっています。
- また、1人1回当たり旅行支出は、2019年比で17.8%増となり、一昨年、昨年と連続でコロナ前を上回っており、この背景としては、全国旅行支援等による旅行並びに旅先での支出意欲の増加に加え、物価上昇の影響等が考えられます。
- 観光庁としては、観光地・観光産業の高付加価値化を推進するとともに、地域の観光資源を一層魅力的なものに徹底的に磨き上げ、観光資源のさらなる拡大に取り組んでまいります。
(答)
- インバウンドというものには、いろんな意義があるといつも縷々申し上げておりますが、世界の経済成長力を日本国内に呼び込み、日本国内の経済成長あるいは地域経済の活性化の切り札にするということは疑いのない意義であります。
- そのほかにも、国際相互理解の増進、あるいは、日本文化や日本人の精神性等を世界の方々に知っていただくことで、ソフトパワーを高め、国際相互理解の増進に寄与しますし、インバウンドを通して、地域に受け継がれてきた文化や自然への自らの誇りを高めるということも、非常に意義あることだなと思っています。
- そういったことで、インバウンドというものに、予算が充てられることはあるのだと考えます。
- 他方、アウトバウンドというのも、国際相互理解の増進、あるいは日本のソフトパワー向上という意味でも大変意義あることですし、インバウンドを進めていくうえでも、双方バランスよく発展させていくことが理想です。
- 直接アウトバウンドに予算措置を講じることや、具体的にどういったことをすべきかについては、今お答えするのは早いと思いますので、先ほどのご質問にお答えしたような取組をしながら、どうすればアウトバウンドを伸ばしていけるのか、政策面でしっかり考えてまいりたいと思います。
- アウトバウンドは、「国外に行ってみたい」「リアルを見たい・触れてみたい」という掻き立てられるような気持ち、機運を醸成したり、旅行に行きやすい環境を整えていくこと、また諸外国の文化や人の魅力をしっかりお伝えしていくこと等が大事だと思います。
以上