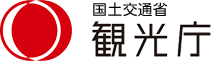髙橋長官会見要旨
最終更新日:2024年3月25日
日時:2024年3月19日(火)16:15~16:33
場所:国土交通省会見室
場所:国土交通省会見室
冒頭発言
(2024年2月の訪日外国人旅行者数)
- 本年2月の訪日外国人旅行者数等について報告があります。
- 本年2月の訪日外国人旅行者数は、278万8,000人となり、2月としては過去最高、9ヶ月連続で、単月200万人を超えました。
- コロナ前の2019年2月と比べた回復率は、単月で107%となり、5ヶ月連続で単月ではコロナ前の水準を回復しました。
- 本年2月の出国日本人数は、97万8,900人となりました。コロナ前の2019年2月と比べた回復率は、単月で64%となりました。
質疑応答
(問)2月の訪日外国人旅行者数について、これまで伸び悩んでいた中国はコロナ前と比べた回復率が63.5%ということで、1月よりもさらに上昇しています。春節の影響もあったと思いますが、どのように評価していらっしゃるか、また中国に対しての今後の見通しをお聞かせください。
(答)
(問)インバウンド全体が回復している中、日本の各地域は宿泊税や入山料の導入など、オーバーツーリズム対策や受入環境整備を実施・検討する動きが広がってきています。長官はこういった各地の取組を、どのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。
(答)
(問)
中国の件ですけれども、団体旅行の解禁からちょうど半年というタイミングですので、もう少しお伺いします。ちょうどその頃、東京電力の福島第1原発の処理水の放出がありましたが、その影響については当時「限定的」と仰っていたかと思いますが、あらためて評価を伺えればと思います。
(答)
(問)
ALPS処理水の件と少し関連してですが、今年3月で東日本大震災から13年が経ちました。被災地にとって産業振興は一つの課題だと思われますが、東北各県では震災遺構を巡る観光ツアーなどを開発したり、観光で何とか被災地の産業を振興しようという動きもあります。特に福島は、処理水のことや原子力災害のことで、未だに誘客が難しい部分もあるかと思いますが、そのあたりについて、観光庁の取組や今後の展望をお聞きかせください。
(答)
(問)「特別な体験の提供等によるインバウンド消費の拡大・質向上推進事業」では113件採択されたかと思いますが、長官から見て期待以上のもの、何か印象に残っているものがあれば教えていただけますか。
(答)
(問)北陸応援割についてお聞きします。一部の自治体からですが、すでに予算が尽きそうだということで、期間の延長や拡充を求める声が上がっています。今後の期間の延長や拡充についての検討如何について、お伺いします。
(答)
(答)
(答)
- 冒頭で申し上げましたが、2月の訪日外国人旅行者数は合計で278万8000人、9ヶ月連続で単月200万人を超えています。
- 2019年同月からの回復率は単月で107%と、5ヵ月連続でコロナ前の水準を回復しており、堅調に回復をしているものと受け止めています。
- 国・地域別に見ますと、単月で過去最高を更新した台湾・ベトナム、また23市場のうちアメリカやシンガポールはじめ19市場で2月として過去最高の値を記録しました。
- お尋ねの中国市場についてですが、2月の訪日者数は約46万人、コロナ前の2019年同月からの回復率は約64%となっており、昨年12月の約44%、1月の約55%から回復傾向が続いているものと承知しています。
- ご指摘の春節についてですが、2月には春節に伴う休暇期間があり、その日数も9日間とコロナ前の2019年の7日間よりも長く、外国旅行がしやすい状況にあったこと等により、このような結果になったものと認識しています。
- 実際、春節中に中国から日本を訪れた旅行者は、例えば、北海道道東においては、氷結した阿寒湖の湖上トレッキングや早朝の阿寒湖畔からの日の出の鑑賞等、屋外で大自然を満喫するアクティビティ体験が大人気と伺っています。
- 従来の買い物にとどまらず、新たな魅力や楽しみ方が見出され、訪日旅行に広がりが出てきたと考えています。
- 中国市場については、昨年から徐々に回復を続け、今回コロナ後に初めて回復率が6割を超えたところですが、他の市場の回復状況と比べますと、まだまだ安定して伸ばしていかなければならない状況にあると考えています。
- 中国市場の回復に影響を与えている要因について、いくつか申し上げたいと思います。
- 引き続き景気動向の影響などにより中国における内需・消費が低下していること、昨今、中国では国内旅行の回復に比べ海外旅行全体の回復が遅れていること、また、中国からの訪日者数に大きな割合を占める若年層が、相対的に国内の景気の影響を受けやすい傾向にあることなども考えられます。
- 日本政府観光局(JNTO)を通して実施した現地旅行会社への聞き取りにおいても、中国市場の伸びに影響を与えている主な要因として、過半数の会社が中国国内の経済の低迷と回答、また一定程度の会社が海外旅行全体の回復の遅れを回答されているところです。
- 観光庁としては、いわゆるインバウンド、中国からの訪日者数のみならず、消費額や宿泊数など様々な観点から総合的に状況を判断することが大切であると考えています。
- 訪日旅行者1人当たりの消費単価を見ますと、昨年10月から12月期における2019年同期間との比較では、全市場では約3割増、中国はこれを上回る6割増となっており、また昨年10月から12月期における中国からの訪日者の平均泊数については、2019年同期間との比較で7.5泊から10.5枠と4割増となっており、これらは明るい材料だと思っています。
- 引き続き、中国からの旅行客の動向あるいは実績を注視するとともに、先ほど申し上げた自然の中でのアクティビティ体験型旅行の他、日本のアニメを初めとするポップカルチャーなどの様々なコンテンツが中国からの旅行者に人気であることもふまえ、こういった魅力や地域の資源を徹底的に磨き上げるとともに、集中的なプロモーションを実施するなど、中国市場の更なる回復に取り組んでまいります。
- 先ほど申し上げましたように、初めてコロナ後に回復が6割を超えたところでありますが、他の市場の回復状況と比べるとまだまだ安定して伸ばしていかなければならない市場だと考えていますので、しっかり取組を続けてまいりたいと考えています。
(問)インバウンド全体が回復している中、日本の各地域は宿泊税や入山料の導入など、オーバーツーリズム対策や受入環境整備を実施・検討する動きが広がってきています。長官はこういった各地の取組を、どのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。
(答)
- 外国人旅行者の受入環境整備、あるいはご指摘いただいたようなオーバーツーリズム対策は、インバウンドをさらに伸ばしていく上で大事な取組だと思っています。
- ご指摘いただいた二つの事項のうち、まず宿泊税については、地域の魅力を高め観光振興を図ること等を目的として地方自治体のご判断において導入されているものと承知しています。
- もう一つご指摘いただいたいわゆる入山料の導入等については、国立公園などにおいて入山時に登山者から徴収する、いわゆる「協力金」や「入域料」というような形で、施設における多言語案内などの充実や、登山道などの維持管理といった受入環境整備に活用すべく、地元の自治体、環境省の管理事務所、観光関係事業者など地域の関係者による協議のもとで実施されてきている例を承知しています。
- こうした取組については、地方自治体のご判断や地域の関係者の協議に基づいて行われるものですが、観光庁では、特に入山時における協力金や入域料などを導入する場合に、地域資源の保全・活用による持続可能な観光を促進する観点から、徴収のためのシステム整備等をご支援の対象としているところです。
- 観光庁としては、こうした取組を通じて、持続可能なあり方での観光地域づくりを実現するために、地域の実情に応じた取組を後押ししてまいりたいと思っています。
(問)
中国の件ですけれども、団体旅行の解禁からちょうど半年というタイミングですので、もう少しお伺いします。ちょうどその頃、東京電力の福島第1原発の処理水の放出がありましたが、その影響については当時「限定的」と仰っていたかと思いますが、あらためて評価を伺えればと思います。
(答)
- ご指摘いただきましたように、昨年の8月10日に、従前禁止をされていた中国から日本への団体旅行が解禁されました。
- 皆さまにこのような機会をいただくたびに、ALPS処理水の放出の影響は限定的であるという受け止めを申し上げていますが、その認識は今でも変わっていません。
- コロナ前の2019年からの回復率は、昨年12月の44%から今年1月に55%、そして2月の64%と、一気に急速な回復とまでは評価いただけないかもしれませんが、着実に中国のお客様をお迎えできつつあるのではないかと思っています。
- 中国からの旅行客の動向や実績をしっかり注視して、地域の資源、あるいはその魅力を徹底的に磨き上げ、プロモーションをしっかり行っていくことで、この回復基調をしっかりと伸ばしていきたいと思っています。
(問)
ALPS処理水の件と少し関連してですが、今年3月で東日本大震災から13年が経ちました。被災地にとって産業振興は一つの課題だと思われますが、東北各県では震災遺構を巡る観光ツアーなどを開発したり、観光で何とか被災地の産業を振興しようという動きもあります。特に福島は、処理水のことや原子力災害のことで、未だに誘客が難しい部分もあるかと思いますが、そのあたりについて、観光庁の取組や今後の展望をお聞きかせください。
(答)
- この3月で東日本大震災の発災から13年を迎えました。
- あらためまして、犠牲になられた方々に哀悼の意を表させていただくと共に被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。
- 今の福島県についてお尋ねをいただきましたので、現状をご報告しようと思います。
- 国内旅行とインバウンドそれぞれ申し上げますと、国内旅行については、令和5年の日本人延べ宿泊者数は概ね震災前の水準となります。
- 96%まで回復をしていますが、震災前からの回復率、あるいは伸び率で見ますと、全国の平均、あるいは東北6県の平均の数字にはまだ届いていません。
- また、インバウンドでは明るい数字を申し上げますと、令和5年の外国人延べ宿泊者数が福島県として過去最高を記録しており、コロナ前との比較では、全国で4番目、東北では最も高い回復率、伸び率となるなど、コロナ後の回復プロセスとしては順調に推移していると受け止めています。
- ただ、震災前からの回復率、伸び率としては、全国の平均、あるいは東北6県の平均の数値にはこちらもまだ届いていません。
- しかしながら、台湾からのお客様の延べ宿泊者数は、福島は震災前の約7倍となっているとともに、本年1月から、福島と台湾を結ぶ週2回往復のチャーター便の運行が開始されるなど、さらに伸ばしていける可能性があると思っています。
- 観光庁としては、このような状況をふまえ、特に福島ならではの取組に対するご支援に力を入れていきたいと思っています。
- 例えば、震災あるいは原発事故の被災地域をフィールドにした学びの旅です。
- ホープツーリズム、これは昨年度に過去最多の約1万8000人の方々が参加されるなど、ポテンシャルの高い事業だと思っています。
- ホープツーリズムを支え、携わっている現地のガイドにお話を聞いてみたところ、ホープツーリズムに参加した学生は、顔つきがまるで別人に変わるそうで、これは、答えが一つでない被災地の大きな課題に対しての探究心の芽生えからくるものだと思います。
- 学生に接するガイドとしても、常に地域のことを勉強し続けなければならないという思いで取り組んでいる、と伺っています。
- こういった交流といいますか、心の通い合い、あるいはその学び、気付きがたくさんあるホープツーリズムの今後の推進のために、旅行関係者を対象としたモニターツアー、あるいはインバウンド向けのガイド育成などを支援してまいりたいと思います。
- また、ALPS処理水の海洋放出による風評対策として実施しているブルーツーリズムについては、引き続き、岩手県から茨城県までの沿岸部において、海の魅力を高める体験型コンテンツの造成、あるいは海浜の高い品質を証明する国際認証の取得などを支援してまいります。
- また、インバウンドについては、最近伸びが著しい台湾、あるいはタイ、ベトナムなどからのお客様を対象とした集中的なプロモーション、あるいは欧米豪に訴求力のある会津磐梯スノーリゾート等の高付加価値化の取組、いわき湯本温泉などの宿泊施設の高付加価値化などに力を入れ、福島の観光振興をしっかり支援、促進してまいりたいと思います。
(問)「特別な体験の提供等によるインバウンド消費の拡大・質向上推進事業」では113件採択されたかと思いますが、長官から見て期待以上のもの、何か印象に残っているものがあれば教えていただけますか。
(答)
- 私が今この場で固有名詞で地域を申し上げることは、心には浮かんでいるものの、やはり控えた方がいいかと思います。
- この事業は、地域としての魅力をいかに特別なものとして、磨き上げていくか、あるいはそれをしっかり説明して体験していただくことが大切です。
- 今回、地方の皆さまから上がってきた申請内容を私も全て拝見しましたが、非常にその趣旨を捉え、地域としての力をつけ、かつもう一段上に伸びていこうという志を感じましたし、そういう意味では、審査員の方々も選考が大変でした。
- これから地方部にインバウンドの大きな流れを作ることが私どもの最大の課題であり、やらなければいけないことだと思います。
- 地方としての自力・底力を磨いていただく上で大変重要な取組であり、それに地域の方々がしっかり応えていただいていることを心強く思いました。
(問)北陸応援割についてお聞きします。一部の自治体からですが、すでに予算が尽きそうだということで、期間の延長や拡充を求める声が上がっています。今後の期間の延長や拡充についての検討如何について、お伺いします。
(答)
- 今般の能登半島地震による風評被害の懸念や影響が出てきたところ、それらを早期に払拭するために、キャンセルによって失われた分の旅行需要を新たに喚起することが、北陸応援割の目的です。
- 北陸新幹線の金沢から敦賀間開通の機会を捉えて、今月16日から北陸応援割を実施しています。
- 大手旅行会社から聞き取りました北陸4県における3月の予約人泊数は、2019年同月比を大きく上回るなど、北陸応援割の政策効果が表れている状況にあると認識しています。
- 一部の宿泊施設では予算の上限に達し、予約を締め切っていると承知していますが、他方、現在も予約を受付けている宿泊施設、あるいは今後、予約受付を開始する宿泊施設もあります。
- 引き続き、北陸応援割の予算を活用し、旅行需要の喚起が図られることを期待しています。
- もう一つ、地域の皆さまへの大変強力な応援団として、今月15日から日本観光振興協会を中心とした民間事業者、航空会社、鉄道会社などによる割引運賃のPRなど、関係者が足並みを揃えた観光キャンペーン始まりました。
- また、北陸地域へのインバウンドの誘客を促進するため、日本政府観光局(JNTO)を通じて北陸地域の集中的なプロモーションにも取り組んでまいります。
- 先ほど申し上げましたように、北陸応援割は、キャンセルにより失われた旅行需要を新たに喚起することが目的の制度です。
- 様々な取組を通じて、引き続き官民一体となって切れ目なく取り組んでいくことで、北陸4県の観光振興に繋げていきたいと、心より志すとともに期待しています。
(答)
- そのようなご要望があるということについては承知しています。
- この北陸応援割の制度、趣旨というのが、キャンセルによって失われた分の旅行需要を新たに喚起するということであり、しっかりと必要な予算を講じて執行いただいているところです。
- 繰り返しになりますけれども、一部の宿泊施設では予算の上限に達し予約を締め切っていると承知していますが、現在も予約を受付けている宿泊施設、あるいは今後予約受付を開始する宿泊施設もありますので、引き続き、予算を活用して旅行需要の喚起を図ることを期待しています。
- また、民間事業者による観光キャンペーンや日本政府観光局(JNTO)を通じた北陸地域の集中的なプロモーションなど、引き続き、官一体となって切れ目なく北陸4県の観光振興に取り組んでまいりたいと思います。
以上