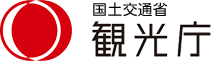秡川長官会見要旨
最終更新日:2024年9月20日
日時:2024年11月20日(水)16:15~17:00
場所:国土交通省会見室
場所:国土交通省会見室
冒頭発言
(2024年10月の訪日外国人旅行者数)
1点目は、今年の10月の訪日外国人の旅行者数について、331万人、1つの月で過去最高の数字になりました。
コロナ前の2019年10月と比べると33パーセント増えています。
1月から10月まででは、3,020万人で、3,000万人を超えました。
10月の出国者数、アウトバウンドについては、115万人で、コロナ前の2019年の10月と比べると、単月で約70パーセントの回復率となりました。
1月から10月まで10か月間で1060万人、昨年の実績が962万人でしたので、それを超え、コロナの前の2019年以来、5年ぶりに1,000万人を超えました。
(旅行・観光消費動向調査の結果(2024年7-9月期速報)について)
2点目は、日本人の国内旅行について、旅行・観光消費動向調査の7月から9月期の速報です。
延べ旅行者数が約1.5億人、2019年の同じ期間の9割ぐらいまで回復しました。
1人あたりの旅行の支出は 平均4.8万円、2019年と比べると20パーセント程度増えて、それを掛け合わせた国内旅行の消費額は7.3兆円で、四半期としては過去最高、2019年に比べると10パーセント程度増えています。
(イタリアで開催されたG7観光大臣会合への参加報告について)
3点目は、13日から15日までイタリアでG7観光大臣会合が開かれ、私が出席しました。
イタリアが今年はサミットの議長国ですが、大臣会合がイタリアの各地で開かれており、観光大臣会合がフィレンツェで開かれたということです。
G7の枠組みとしては、観光大臣会合は初めての開催になりました。
フィレンツェは、ルネッサンスの中心的な町で、素晴らしい建築物や美術、作品が集積している町です。
会合自体も、ヴェッキオ宮殿という、ルネッサンスを支えたメディチ家が栄えていた頃の彼らのオフィスが会場として開催され、ユニークベニューの活用策として非常に勉強になりました。
議長国イタリアをはじめ、各国や機関の代表者の方と意見交換を行い、持続可能な観光、人材、AIなど、各国とも課題や悩みなど、状況は似ているという印象を受けました。
1点目は、今年の10月の訪日外国人の旅行者数について、331万人、1つの月で過去最高の数字になりました。
コロナ前の2019年10月と比べると33パーセント増えています。
1月から10月まででは、3,020万人で、3,000万人を超えました。
10月の出国者数、アウトバウンドについては、115万人で、コロナ前の2019年の10月と比べると、単月で約70パーセントの回復率となりました。
1月から10月まで10か月間で1060万人、昨年の実績が962万人でしたので、それを超え、コロナの前の2019年以来、5年ぶりに1,000万人を超えました。
(旅行・観光消費動向調査の結果(2024年7-9月期速報)について)
2点目は、日本人の国内旅行について、旅行・観光消費動向調査の7月から9月期の速報です。
延べ旅行者数が約1.5億人、2019年の同じ期間の9割ぐらいまで回復しました。
1人あたりの旅行の支出は 平均4.8万円、2019年と比べると20パーセント程度増えて、それを掛け合わせた国内旅行の消費額は7.3兆円で、四半期としては過去最高、2019年に比べると10パーセント程度増えています。
(イタリアで開催されたG7観光大臣会合への参加報告について)
3点目は、13日から15日までイタリアでG7観光大臣会合が開かれ、私が出席しました。
イタリアが今年はサミットの議長国ですが、大臣会合がイタリアの各地で開かれており、観光大臣会合がフィレンツェで開かれたということです。
G7の枠組みとしては、観光大臣会合は初めての開催になりました。
フィレンツェは、ルネッサンスの中心的な町で、素晴らしい建築物や美術、作品が集積している町です。
会合自体も、ヴェッキオ宮殿という、ルネッサンスを支えたメディチ家が栄えていた頃の彼らのオフィスが会場として開催され、ユニークベニューの活用策として非常に勉強になりました。
議長国イタリアをはじめ、各国や機関の代表者の方と意見交換を行い、持続可能な観光、人材、AIなど、各国とも課題や悩みなど、状況は似ているという印象を受けました。
質疑応答
(問)G7の観光大臣会合に参加された受け止めと、参加されて、改めて観光庁としてどういった取り組みを進めていきたいかをお聞かせください。
(答)
今回の会合でイタリアが設定した課題が、持続可能な観光、多様性への理解、異文化間の相互理解でしたが、そういった面で観光は効果があるため、改めて国際平和に資する大事な手段であると、各国が認識を共有しました。
持続可能かつ包摂的、つまり誰でも楽しめる観光について、そして、人材不足や人材をどう確保していくのかという点、また、これからAIをどう取り込んで利用しつつ観光に生かしていくのかという3つの分野について議論をし、方向性を確認しました。
会議自体は2日間あり、G7だけの会議だけではなく、今回招待国としてのインド、サウジアラビア、エジプトとブラジルの4カ国、加えてOECDの事務局も参加した拡大セッションもあり、多くの方々と意見交換ができました。
また、プログラムの一環でフィレンツェ郊外にある、かつての城郭だったところに現在も人が住んでいている小さな村を訪問しましたが、平日であるにもかかわらず、大人子ども問わず皆さんに非常に歓迎していただき思い出深かったです。
3日間会議に参加して、各国の大臣やそれを補佐する幹部の方も女性が多く活躍しておられること、そしてヴェッキオ宮殿のような国宝級の建物を会議会場として使うイタリアの懐の深さの2点を特に印象的に感じたところです。
(問)10月の訪日客数について、単月で過去最多ということだが、それに対する受け止めと要因があれば、教えてください。
(答)
引き続き順調と思います。
夏休みがあったあと、9月はちょっと一息という感じがありますが、10月の特に後半ぐらいから紅葉のシーズンということで、増えたと思います。
地域別に見ると、約7割を占めるアジアの国が、2019年の10月と比べると概ね10パーセント以上伸びています。
さらに欧米諸国は、2019年の10月と比べると 概ね60パーセント増加しており、欧米の伸びが顕著です。
(問)インバウンドは盛り上がっているが、日本人の国内旅行客の延べ人数は2019年より減っており、それについて課題になっていることがあれば、教えてほしい。また、国内需要喚起をどうしていきたいかという考えがありましたらお聞かせください。
(答)
インバウンドの政策で、地域の観光地づくりを色々な手段で支援しておりますが、発端はインバウンドであっても、日本人の旅行者にとっても素敵な観光地になることから、インバウンドだけということではないと思っています。
地域の魅力を上げる、そういった部分で観光庁は役割を果たしていくことが必要と思います。
(問)先日、ユネスコ無形文化遺産の方に日本の伝統的酒造りが登録される見通しとなりました。旅館業界、自治体を中心に温泉文化を登録しようという動きがあります。こうした取り組みへの所感をお願いします。
(答)
色々情報がありますけども、国民全体でそれが根付いて、伝統と文化として定着しているということが1つのポイントだと聞きます。
例えばフランスは、フランスパンやバケットが位置付けられており、温泉も日本人からすると同じような位置付けではないかと思います。
このユネスコの無形文化遺産になるためには、その前段階として、文化財保護法に基づく無形文化財に日本で位置付けられることが必要です。
我々も温泉文化がこの無形文化財になるようにというお話を地域の方から伺いますし、文化庁の方にも要望をしていると思いますが、そういった活動からまず第1歩が踏み出せるといいのかなと思っています。
(問)ロケ地紹介ショートフィルムコンペティションが行われましたが、 寄せられた作品をご覧になった感想、またロケツーリズムを通じた日米観光交流や地方誘客への期待についてお伺いします。
(答)
ショートフィルムというのは1つの作品1分半と決まっており、その時間に凝縮するために工夫をされていました。
素晴らしい作品が多く、どの作品を観光庁長官賞とするか迷いましたが、岩手県奥州市の衣川に決定しました。
非常にシンプルな作品でしたが、滝の音と稲穂の揺れる映像が非常に綺麗で心が癒されました。
映画等のロケ地は、映像を見て、この作品はあの場所で撮ったから行ってみたいと思わせる観光資源になると思います。
今回のイベントは、日米観光交流年の取り組みの1つにも位置付けられており、アメリカの方も結構来られていたため、そういう作品を見ていただいて、また日米交流のきっかけになったらいいなと思います。
(問)先日、観光レジリエンスサミットが仙台で初めて開催されましたが、開催されたことへの所感と観光分野の危機管理についての施策や今後取り組んでいきたい施策についてお聞かせください。
(答)
各国の皆様は、初めて仙台にいらっしゃる方が多く、地震の時の状況を映像で知っているため、仙台はもうこんなに復興したのか、と大変驚いていらっしゃいました。
アジア・太平洋地域の枠組みで、レジリエンスを切り口にした閣僚会合は初めてであり、仙台市と観光庁から津波などの被害から10年経ってここまで復興していると説明すると、各国の皆様から取組が素晴らしい、非常に勉強になったと言っていただいたのでよかったと感じています。
また、2日目の後半から翌日にかけて、3つのコースでエクスカーションを行い、多くの方々に参加していただいて、また仙台市内だけでなく、岩手や福島の方に行くコースもあり、皆さんすごく楽しんで、また来たいと喜んでお帰りいただいたのがよかったと思います。
自国に帰って、東北の魅力を発信してもらえることを期待しています。
(問)訪日者数は引き続き好調とのことですが、アウトバウンドは回復が遅れています。アウトバウンドの伸び悩みは大きな課題かと思いますが、その要因と観光庁としてアウトバウンドの回復にどのように取り組んでいくのかお聞かせください。
(答)
円安や海外の物価高などが影響していると思いますが、アウトバウンド自体、実際に行ってみたり、様々な人の話を聞いてみたりすることが、国際感覚の向上や相互理解の増進の観点から大事であることと、そのようなことを通じて安定的な国際関係の構築につながることから重要であると考えています。
また、航空ネットワークの維持・強化という点でもお客さんがきちんといることが大事であり、ニーズがあれば路線もはれると思いますので、アウトバウンドの促進には取り組んでいきたいと思います。
最近は修学旅行などで海外に行く学校があり、そういった部分は、文科省と引き続き連携するなど、できることはしっかりやっていきたいと思います。
なお、今年の年末年始は最大で9連休となるため、さらに人数が増えることを期待しています。
(問)G7という枠組みの中での観光大臣会合が初めて行われたことの意義や価値について、改めてお聞かせください。また、AIがここまで大きく観光大臣会合でクローズアップされたというのは初めてではないかという印象ですが、実際、どこまでAIの活用が進んでいているか、どういうリスクを抱えているかなど、具体的に共有できたことがあれば教えてください。
(答)
今回の議論では、3つ主題があり、1つが高齢者とか障害者も含めて包括的に観光を楽しめるように「持続可能かつ包摂的な観光」、2つ目が「観光産業の人材育成」、3つ目が「観光産業へのAI導入」です。
持続可能かつ包摂的な観光については、観光産業は地方や中小企業が支えており、これをどのように支援していくのかという観点は各国からも問題提起がありました。
税制や補助金による支援という事例の紹介もあれば、ビジネスそのものに国が支援することへの是非についての意見もありました。
また、高齢者や障害者の方に旅行を楽しんでいただくというのは非常に重要で、障害者や高齢者は、日本全体の人口からすると約3割ですが、実際に観光している方の中の割合は2割切るぐらいという日本の状況を共有したところ、各国の方には印象的だったようです。
この10パーセントの方々に旅に出てもらうのかが大事であり、そのために何ができるかという議論をしました。
バリアフリーやユニバーサルデザインという観点もありますし、旅に出ると元気になり、また次も行ってみたいとなることから生きる活力にもなると思いますので、なるべくそういった方が旅行に行けるように取り組んでいきたいということです。
観光産業の人材育成については、これも各国共通で、人材が定着しないといった課題について発言がありました。
このほか、言語能力とかコミュニケーション能力も含めて、そういう人材を育てる取り組みが非常に大事で、そういうこともやらなければいけないという議論になりました。
人材の問題に関連して、AIについても、人がやらなくてはいけないところに人材を集中することが必要で、人がやらなくても済む部分はなるべくAI や新しい技術に代替してもらうということが重要で、場合によっては電話の対応なども可能ということもありますので、極力AIを活用していくのが必要だと思います。
AIについては、まだ我々全員がうまく使い切れてない部分もあり、偽情報流布など潜在的なリスクがあることから、どうコントロールして、観光全体にうまく使っていくのかということが大事との議論になりました。
(問)観光地域づくり法人「DMO」について、例えば愛媛県大洲市では、DMOが中心になって城下町に古民家ホテルを作るなど観光で街を再生し、実際にコロナ前と比べて日本人観光客は1.2倍、訪日外国人数は2倍に増えています。こうした DMO による観光地域づくりへの今後の期待や役割についてお考えをお願いします。また、今後の補助制度の変更について検討状況と、取り組むべき課題があればお聞かせください。
(答)
例に挙げていただいた大洲市の例では、お城や古い屋敷をうまく活用しており、とてもいい取組だと思います。
DMOは、観光地域づくりにおいて、狭い意味での観光業者だけではなく、自治体、農業、交通、製造業など、多様な関係者を巻き込み、司令塔としての役割を果たす存在です。
今までの経験や勘に頼るのではなく、データに基づく科学的分析、お客様が何を求めているのかを丁寧にキャッチして、作戦を立て、それを粘り強くやっていくという取組の中心になるのがDMOです。
その地域にどういう資源や素質や気候風土があり、何をやらなければいけないのかはそれぞれ違いますから、地域でよく考えてやっていただくということだと思います。
また、補助制度については、現時点では変更する予定はなく、引き続き一定のことをやっていただき支援をしてまいります。
登録DMOに位置づけられているものは現在300以上ありますが、DMOの中にもいくつか段階があり、登録までのプロセスや、3年に一回の更新時には、きちんと質が確保できるような、ある意味厳しいチェックができるようなものになっているかということを、有識者会議で議論しています。
有識者会議での議論をふまえ、来年春先ぐらいには、方向性が出せる見込みです。
(問)大洲市以外での、DMOの動きもあるかと思いますが、今後のDMOの存在への期待について教えてください。
(答)
期待しているのはもちろんですし、自発的にそれぞれの地域の状況に応じて一生懸命やっていただくことが大事だと思っています。
(問)中国について、コロナ前は圧倒的なインバウンドの方が来ていましたが、またここに来て大幅に伸びています。今後、これから中国のインバウンドの動向をどのように見ているか教えてください。一方、アウトバウンドは、短期のビザ免除が再開されるとの報道もありますが、そうなった場合の双方向の観光の動向も含め、これからの動きへの考えを聞かせてください。
(答)
中国は、様々な報道等で、数年前に比べると、ビジネスがうまくいかないというような報道があり、そういった影響が全体なのか一部なのかわかりませんが、観光という面で見ても、数年前に比べると、みんなどっと日本に来るという感じではなくなっているように思います。
短期のビザについては、報道は承知していますが、現段階ではそのような確定的な事実は確認されていないものと思っています。
(問)中国市場の現状について、10月初頭に中国の国慶節があり、2019年の8割程度まで戻ってきて、少しずつ回復してきているのかなと思いますが、中国市場の現状、特に国慶節の状況について伺います。
(答)
国慶節については、数字が上がっており、このタイミングで日本に来ているようにも思います。
大きなトレンドとしては、夏ぐらいからも結構上がったり下がったりしているので、中国については、もう少し様子を見つつ、フォローする必要があると思っています。
数ヶ月のトレンドで見ると、だいぶ少なかった時よりは、上がってきているなという感じはしますけれども、国慶節は、1つのチャンスというか、きっかけにはなるかと思いますが、もう少し期間を見る必要があると思っています。
(問)G7観光大臣会合で、日本の観光に関する事例の紹介や海外諸国からの事例紹介の中で、気になったトピックスがあれば教えてください。
(答)
日本からは、高齢者・障害者の潜在的な旅行需要について説明したほか、東北が10年経って復興した話などをさせていただきました。
AIに関しては、具体的事例というわけではありませんが、日本の若い人は旅行の申込みなどにAIを非常に活用しており、リスクがないわけではありませんが、アクセスしやすいことが重要だという話をしました。
外国の方は、具体的な事例や課題という話もなかったわけではありませんが、どちらかといえば理念や目標といった話が中心であったという印象です。
(答)
今回の会合でイタリアが設定した課題が、持続可能な観光、多様性への理解、異文化間の相互理解でしたが、そういった面で観光は効果があるため、改めて国際平和に資する大事な手段であると、各国が認識を共有しました。
持続可能かつ包摂的、つまり誰でも楽しめる観光について、そして、人材不足や人材をどう確保していくのかという点、また、これからAIをどう取り込んで利用しつつ観光に生かしていくのかという3つの分野について議論をし、方向性を確認しました。
会議自体は2日間あり、G7だけの会議だけではなく、今回招待国としてのインド、サウジアラビア、エジプトとブラジルの4カ国、加えてOECDの事務局も参加した拡大セッションもあり、多くの方々と意見交換ができました。
また、プログラムの一環でフィレンツェ郊外にある、かつての城郭だったところに現在も人が住んでいている小さな村を訪問しましたが、平日であるにもかかわらず、大人子ども問わず皆さんに非常に歓迎していただき思い出深かったです。
3日間会議に参加して、各国の大臣やそれを補佐する幹部の方も女性が多く活躍しておられること、そしてヴェッキオ宮殿のような国宝級の建物を会議会場として使うイタリアの懐の深さの2点を特に印象的に感じたところです。
(問)10月の訪日客数について、単月で過去最多ということだが、それに対する受け止めと要因があれば、教えてください。
(答)
引き続き順調と思います。
夏休みがあったあと、9月はちょっと一息という感じがありますが、10月の特に後半ぐらいから紅葉のシーズンということで、増えたと思います。
地域別に見ると、約7割を占めるアジアの国が、2019年の10月と比べると概ね10パーセント以上伸びています。
さらに欧米諸国は、2019年の10月と比べると 概ね60パーセント増加しており、欧米の伸びが顕著です。
(問)インバウンドは盛り上がっているが、日本人の国内旅行客の延べ人数は2019年より減っており、それについて課題になっていることがあれば、教えてほしい。また、国内需要喚起をどうしていきたいかという考えがありましたらお聞かせください。
(答)
インバウンドの政策で、地域の観光地づくりを色々な手段で支援しておりますが、発端はインバウンドであっても、日本人の旅行者にとっても素敵な観光地になることから、インバウンドだけということではないと思っています。
地域の魅力を上げる、そういった部分で観光庁は役割を果たしていくことが必要と思います。
(問)先日、ユネスコ無形文化遺産の方に日本の伝統的酒造りが登録される見通しとなりました。旅館業界、自治体を中心に温泉文化を登録しようという動きがあります。こうした取り組みへの所感をお願いします。
(答)
色々情報がありますけども、国民全体でそれが根付いて、伝統と文化として定着しているということが1つのポイントだと聞きます。
例えばフランスは、フランスパンやバケットが位置付けられており、温泉も日本人からすると同じような位置付けではないかと思います。
このユネスコの無形文化遺産になるためには、その前段階として、文化財保護法に基づく無形文化財に日本で位置付けられることが必要です。
我々も温泉文化がこの無形文化財になるようにというお話を地域の方から伺いますし、文化庁の方にも要望をしていると思いますが、そういった活動からまず第1歩が踏み出せるといいのかなと思っています。
(問)ロケ地紹介ショートフィルムコンペティションが行われましたが、 寄せられた作品をご覧になった感想、またロケツーリズムを通じた日米観光交流や地方誘客への期待についてお伺いします。
(答)
ショートフィルムというのは1つの作品1分半と決まっており、その時間に凝縮するために工夫をされていました。
素晴らしい作品が多く、どの作品を観光庁長官賞とするか迷いましたが、岩手県奥州市の衣川に決定しました。
非常にシンプルな作品でしたが、滝の音と稲穂の揺れる映像が非常に綺麗で心が癒されました。
映画等のロケ地は、映像を見て、この作品はあの場所で撮ったから行ってみたいと思わせる観光資源になると思います。
今回のイベントは、日米観光交流年の取り組みの1つにも位置付けられており、アメリカの方も結構来られていたため、そういう作品を見ていただいて、また日米交流のきっかけになったらいいなと思います。
(問)先日、観光レジリエンスサミットが仙台で初めて開催されましたが、開催されたことへの所感と観光分野の危機管理についての施策や今後取り組んでいきたい施策についてお聞かせください。
(答)
各国の皆様は、初めて仙台にいらっしゃる方が多く、地震の時の状況を映像で知っているため、仙台はもうこんなに復興したのか、と大変驚いていらっしゃいました。
アジア・太平洋地域の枠組みで、レジリエンスを切り口にした閣僚会合は初めてであり、仙台市と観光庁から津波などの被害から10年経ってここまで復興していると説明すると、各国の皆様から取組が素晴らしい、非常に勉強になったと言っていただいたのでよかったと感じています。
また、2日目の後半から翌日にかけて、3つのコースでエクスカーションを行い、多くの方々に参加していただいて、また仙台市内だけでなく、岩手や福島の方に行くコースもあり、皆さんすごく楽しんで、また来たいと喜んでお帰りいただいたのがよかったと思います。
自国に帰って、東北の魅力を発信してもらえることを期待しています。
(問)訪日者数は引き続き好調とのことですが、アウトバウンドは回復が遅れています。アウトバウンドの伸び悩みは大きな課題かと思いますが、その要因と観光庁としてアウトバウンドの回復にどのように取り組んでいくのかお聞かせください。
(答)
円安や海外の物価高などが影響していると思いますが、アウトバウンド自体、実際に行ってみたり、様々な人の話を聞いてみたりすることが、国際感覚の向上や相互理解の増進の観点から大事であることと、そのようなことを通じて安定的な国際関係の構築につながることから重要であると考えています。
また、航空ネットワークの維持・強化という点でもお客さんがきちんといることが大事であり、ニーズがあれば路線もはれると思いますので、アウトバウンドの促進には取り組んでいきたいと思います。
最近は修学旅行などで海外に行く学校があり、そういった部分は、文科省と引き続き連携するなど、できることはしっかりやっていきたいと思います。
なお、今年の年末年始は最大で9連休となるため、さらに人数が増えることを期待しています。
(問)G7という枠組みの中での観光大臣会合が初めて行われたことの意義や価値について、改めてお聞かせください。また、AIがここまで大きく観光大臣会合でクローズアップされたというのは初めてではないかという印象ですが、実際、どこまでAIの活用が進んでいているか、どういうリスクを抱えているかなど、具体的に共有できたことがあれば教えてください。
(答)
今回の議論では、3つ主題があり、1つが高齢者とか障害者も含めて包括的に観光を楽しめるように「持続可能かつ包摂的な観光」、2つ目が「観光産業の人材育成」、3つ目が「観光産業へのAI導入」です。
持続可能かつ包摂的な観光については、観光産業は地方や中小企業が支えており、これをどのように支援していくのかという観点は各国からも問題提起がありました。
税制や補助金による支援という事例の紹介もあれば、ビジネスそのものに国が支援することへの是非についての意見もありました。
また、高齢者や障害者の方に旅行を楽しんでいただくというのは非常に重要で、障害者や高齢者は、日本全体の人口からすると約3割ですが、実際に観光している方の中の割合は2割切るぐらいという日本の状況を共有したところ、各国の方には印象的だったようです。
この10パーセントの方々に旅に出てもらうのかが大事であり、そのために何ができるかという議論をしました。
バリアフリーやユニバーサルデザインという観点もありますし、旅に出ると元気になり、また次も行ってみたいとなることから生きる活力にもなると思いますので、なるべくそういった方が旅行に行けるように取り組んでいきたいということです。
観光産業の人材育成については、これも各国共通で、人材が定着しないといった課題について発言がありました。
このほか、言語能力とかコミュニケーション能力も含めて、そういう人材を育てる取り組みが非常に大事で、そういうこともやらなければいけないという議論になりました。
人材の問題に関連して、AIについても、人がやらなくてはいけないところに人材を集中することが必要で、人がやらなくても済む部分はなるべくAI や新しい技術に代替してもらうということが重要で、場合によっては電話の対応なども可能ということもありますので、極力AIを活用していくのが必要だと思います。
AIについては、まだ我々全員がうまく使い切れてない部分もあり、偽情報流布など潜在的なリスクがあることから、どうコントロールして、観光全体にうまく使っていくのかということが大事との議論になりました。
(問)観光地域づくり法人「DMO」について、例えば愛媛県大洲市では、DMOが中心になって城下町に古民家ホテルを作るなど観光で街を再生し、実際にコロナ前と比べて日本人観光客は1.2倍、訪日外国人数は2倍に増えています。こうした DMO による観光地域づくりへの今後の期待や役割についてお考えをお願いします。また、今後の補助制度の変更について検討状況と、取り組むべき課題があればお聞かせください。
(答)
例に挙げていただいた大洲市の例では、お城や古い屋敷をうまく活用しており、とてもいい取組だと思います。
DMOは、観光地域づくりにおいて、狭い意味での観光業者だけではなく、自治体、農業、交通、製造業など、多様な関係者を巻き込み、司令塔としての役割を果たす存在です。
今までの経験や勘に頼るのではなく、データに基づく科学的分析、お客様が何を求めているのかを丁寧にキャッチして、作戦を立て、それを粘り強くやっていくという取組の中心になるのがDMOです。
その地域にどういう資源や素質や気候風土があり、何をやらなければいけないのかはそれぞれ違いますから、地域でよく考えてやっていただくということだと思います。
また、補助制度については、現時点では変更する予定はなく、引き続き一定のことをやっていただき支援をしてまいります。
登録DMOに位置づけられているものは現在300以上ありますが、DMOの中にもいくつか段階があり、登録までのプロセスや、3年に一回の更新時には、きちんと質が確保できるような、ある意味厳しいチェックができるようなものになっているかということを、有識者会議で議論しています。
有識者会議での議論をふまえ、来年春先ぐらいには、方向性が出せる見込みです。
(問)大洲市以外での、DMOの動きもあるかと思いますが、今後のDMOの存在への期待について教えてください。
(答)
期待しているのはもちろんですし、自発的にそれぞれの地域の状況に応じて一生懸命やっていただくことが大事だと思っています。
(問)中国について、コロナ前は圧倒的なインバウンドの方が来ていましたが、またここに来て大幅に伸びています。今後、これから中国のインバウンドの動向をどのように見ているか教えてください。一方、アウトバウンドは、短期のビザ免除が再開されるとの報道もありますが、そうなった場合の双方向の観光の動向も含め、これからの動きへの考えを聞かせてください。
(答)
中国は、様々な報道等で、数年前に比べると、ビジネスがうまくいかないというような報道があり、そういった影響が全体なのか一部なのかわかりませんが、観光という面で見ても、数年前に比べると、みんなどっと日本に来るという感じではなくなっているように思います。
短期のビザについては、報道は承知していますが、現段階ではそのような確定的な事実は確認されていないものと思っています。
(問)中国市場の現状について、10月初頭に中国の国慶節があり、2019年の8割程度まで戻ってきて、少しずつ回復してきているのかなと思いますが、中国市場の現状、特に国慶節の状況について伺います。
(答)
国慶節については、数字が上がっており、このタイミングで日本に来ているようにも思います。
大きなトレンドとしては、夏ぐらいからも結構上がったり下がったりしているので、中国については、もう少し様子を見つつ、フォローする必要があると思っています。
数ヶ月のトレンドで見ると、だいぶ少なかった時よりは、上がってきているなという感じはしますけれども、国慶節は、1つのチャンスというか、きっかけにはなるかと思いますが、もう少し期間を見る必要があると思っています。
(問)G7観光大臣会合で、日本の観光に関する事例の紹介や海外諸国からの事例紹介の中で、気になったトピックスがあれば教えてください。
(答)
日本からは、高齢者・障害者の潜在的な旅行需要について説明したほか、東北が10年経って復興した話などをさせていただきました。
AIに関しては、具体的事例というわけではありませんが、日本の若い人は旅行の申込みなどにAIを非常に活用しており、リスクがないわけではありませんが、アクセスしやすいことが重要だという話をしました。
外国の方は、具体的な事例や課題という話もなかったわけではありませんが、どちらかといえば理念や目標といった話が中心であったという印象です。
以上