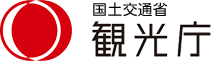秡川長官会見要旨
最終更新日:2024年12月23日
日時:2024年12月18日(水)16:15~16:50
場所:国土交通省会見室
場所:国土交通省会見室
冒頭発言
(訪日外国人旅行者数(2024年11月)について)
本年11月の訪日外国人旅行者数は、約319万人となりました。
コロナ前の2019年11月と比べた回復率は131%となり、2023年10月以降、毎月コロナ前の水準を回復しております。
1月~11月までの11ヶ月間累計では、約3,300万人と過去最高を記録した2019年の年間値を超えました。
本年11月の出国日本人数は、約118万人となりました。コロナ前の2019年11月と比べた回復率は、単月で72%となりました。
(日韓観光ビジネスフォーラムの開催報告について)
今月9日に韓国で開催され、私が出席した「日韓観光ビジネスフォーラム」についてご報告いたします。
本フォーラムは、来年の日韓国交正常化60周年を控え、両国間の観光交流拡大のため、初めて開催されたものです。
本フォーラムでは、両国の政府関係者の他、観光業界や関係団体などから約120名参加し、観光の最近の傾向や取組などについて両国からの発表及び活発な質疑が行われ、非常に活況のあるイベントとなりました。
今般のビジネスフォーラムをひとつの契機として、日韓間の協力を持続的に強化していきたいと思います。
本年11月の訪日外国人旅行者数は、約319万人となりました。
コロナ前の2019年11月と比べた回復率は131%となり、2023年10月以降、毎月コロナ前の水準を回復しております。
1月~11月までの11ヶ月間累計では、約3,300万人と過去最高を記録した2019年の年間値を超えました。
本年11月の出国日本人数は、約118万人となりました。コロナ前の2019年11月と比べた回復率は、単月で72%となりました。
(日韓観光ビジネスフォーラムの開催報告について)
今月9日に韓国で開催され、私が出席した「日韓観光ビジネスフォーラム」についてご報告いたします。
本フォーラムは、来年の日韓国交正常化60周年を控え、両国間の観光交流拡大のため、初めて開催されたものです。
本フォーラムでは、両国の政府関係者の他、観光業界や関係団体などから約120名参加し、観光の最近の傾向や取組などについて両国からの発表及び活発な質疑が行われ、非常に活況のあるイベントとなりました。
今般のビジネスフォーラムをひとつの契機として、日韓間の協力を持続的に強化していきたいと思います。
質疑応答
(問)訪日旅行者数について、11月までの実績で早くも年間過去最高を更新しましたが、この好調なインバウンドの状況について改めて長官の受け止めと今後の見通しを教えてください。
(答)
11月は数字が落ちる年もありますが、今年は訪日需要の高まりが引き続き続いています。
地域別に見ますと、インバウンドの約7割を占めるアジア諸国が2019年の11月に比べると約25%伸び、欧米諸国は約50%増えているということなので、それが非常に大きかったと思います。
12月は11月よりも多少増えることが毎年の傾向なので、今後このまま順調にいけば、3500万人を達成することが予想されます。
(問)訪日者数も訪日消費額も過去最多となり、観光を取り巻く環境は新しい局面を迎えている中、2030年の目標も見据え、観光地や観光業界など受け入れる側の課題認識と今後の観光施策について、教えてください。
(答)
今の状況を引き続き維持して継続していくように取り組みを続けていきますが、よりインバウンドが増えていく傾向からすると、宿泊産業では人手不足の課題があると思います。
また、インバウンドの宿泊を見ると約70%は三大都市圏へ集中しています。
したがって、インバウンドの地方での宿泊に取り組んでいくことが必要です。
人手不足の関係では、外国人人材を活用する制度があり、活用し始めていただいている事業者もありますが、もっと働きかけることが必要だと思います。
インバウンドの宿泊の都市圏への偏在という部分については、地方に滞在していただくため、地方により行ってみたいと思うように、素敵な観光地づくりを地方に色々取り組んでいただいていますが、そういう取り組みを引き続き続けていただくとともに、地方へもどうぞというような発信もしっかりやっていくということだと思います。
当然、人数が増えてくるとオーバーツーリズムの問題もまた出てくると思いますが、今、全国でオーバーツーリズム対策を支援させていただき、いろんな対応策の事例を作りつつありますが、そのようなものを活用しながら、場所によって色々状況は違うと思いますが、その場所にあったやり方を相談しながら、進めていければと思います。
(問)昨日、補正予算が成立しました。改めて、観光庁の補正予算 の内容や狙いについて教えてください。
(答)
補正予算については、観光庁全体で約540億円であり、大きな額を確保することができたと思っています。
内容は、先ほど申し上げた課題をふまえ、なるべく地方に行っていただくため、その地域の観光地とか観光産業の高付加価値化、オーバーツーリズムの未然防止、訪日外国人の受入環境整備、能登半島地震からの復興支援となっております。
能登半島地震からの復興については、建物も随分痛んでいて、まずはどういう方向で再建していくのかという検討や計画を作る1番最初の段階のところを支援してくださいという声がすごく強かったので、そういうものに使っていただけるような予算を確保しています。
(問)観光庁は「未来のための旅のエチケット」と「観光ピクトグラム」を作成されました。観光客および観光関連事業者に呼び掛けたいことなどお考えをお聞かせください。 また、これをしっかり浸透させていくことが重要だと思いますが、旅行者や観光関係者への周知にどのように取り組みますか。
(答)
これも、オーバーツーリズムの事例に対応する1つの有効な手段だと思っており、 観光客のマナー啓発等のお役に立てるよう、「未来のための旅のエチケット」と「観光ピクトグラム」を11月29日に公表したところです。
「未来のための旅のエチケット」については、観光に来てくださる方も悪気があるわけではなく、文化の違いというところがすごく大きいと思うので、 旅先の環境とか地元の方たちにも配慮しながら、旅を楽しんでいただくにはこうした方がいいということをわかりやすくお伝えすることだと思っています。
これは、知っていただかないといけないと思いますので、JNTOのウェブサイトや海外メディア向けの発信、全国の観光案内所などにおけるポスター掲示やパンフレット配布などを通して周知を図りたいと思っています。
「観光ピクトグラム」については、こういうことをするのは良くないですよということなどが瞬時にわかるようにする目的で作っております。
私有地に立ち入っての写真撮影などのマナー違反行為や手ぶら観光などを示しており、自治体や関係事業者の方から意見をいただいて作ったものなので、ぜひ効果が出るように取組を進めてまいります。
(問)中国人からの訪日客数ですが、まだコロナ前水準には戻っておらず、7割ぐらいかと思います。先日、中国が日本人向け訪中ビザ免除措置を再開し、報道によると、日本側も中国人向けの訪日ビザの発給要件の緩和を検討しているとのことですが、こういったビザの緩和は、中国からの訪日客数の増加にどういった影響があると思うか、所感をお願いします。
(答)
中国は、今年の前半は、2019年と前の年に比べても非常に少なかったですけども、 夏以降、少ないながらも増えてきているという状況で、11月は70%ぐらいの回復で、人数では韓国についで2位です。コロナ前よりはまだ少ない状況ですが、回復傾向にあり、この傾向が来年まで続くようにしていきたいです。
先月末から日本人に対する中国の短期滞在ビザの免除措置が再開され、日本から中国に行きやすくなったと思います。経済の活性化や相互理解の促進につながればと思っています。
それから、報道があった日本側がビザの発給要件緩和をするのではということですが、確認した範囲内ではそういうことを決めたという事実はないようですが、もしそういうことが実現すれば、インバウンドの拡大にはプラスの方向だと思っています。
(問)先般、ベストツーリズムビレッジに新たに2地域が認定された。観光立国推進基本計画において、「令和7年までに持続可能な観光地域づくりに取り組む地域数を100地域にする、うち国際認証・表彰地域を50地域」にする目標がたてられていますが、これまでの実績とこれに対する長官の所感・評価を教えてください。また、「持続的な観光地域づくりに取り組む地域」を増やしていく、支援していくための来年以降の取り組みや施策を教えてください。
(答)
今年の11月にUN Tourismが持続可能な観光地域づくりに取り組む優良な地域を認定するベストツーリズムビレッジということで、鹿児島県の天城町と山形県の西川町、この2つが選ばれました。
10月には、グリーンデスティネーションズが表彰するグリーンデスティネーションズアワードと世界の持続的な観光地トップ100選に、愛媛県大洲市と岐阜県高山市などの9地域が選ばれました。
基本計画における持続可能な観光地づくりについて、現時点での進捗状況は、取り組む地域数が46、そのうち国際表彰などを受けた地域数が19まで拡大しています。
前者については、この1年間で15増加しています。年度内をめどに、さらに10地域程度の申請が見込まれています。
非常にいい傾向ですので、こういう意欲のある地域への後押しを引き続きやっていきたいと思います。
(問)2030 年に6000 万人との目標がありますが、現在の構成ですとアジアが7割ぐらいですが、今後、よりパイを増やしていくために、重点的に取り組みたい誘客プロモーションや地域などの考えをお聞かせください。
(答)
2030年6000万人という大きな目標がありますが、昨年の6月に観光庁とJNTOが訪日マーケティング戦略を策定しました。この戦略を基に重点市場として23の国と地域があり、それぞれ特性に応じて戦略的かつきめ細やかな訪日プロモーションを実施しているところです。
来年も引き続きその戦略に基づいて取り組みを進めていくことを考えています。
(問)2030年の目標についてですが、長官はこれは可能だと考えていますか。
(答)
かなり高い目標ですが、可能だと思っています。かつて500万人ぐらいしか来てない時に1000万人という目標を作って、実際達成しています。その後、4000万、6000万という目標ができて、4000万人には今迫ってきています。かなり意欲的な目標ではありますが、全体で力を合わせて進めれば、6000万人もできるだろうと個人的には思っています。
(問)すでに11月の段階で年間の過去最多を上回ったということについての所感を伺いたいが、 観光庁の取り組みが功を奏しているのか、あるいは自治体あるいは事業者の取り組みの効果が出ているのかなどコメントをお願いします。また、要因として、やはり為替、円安というのが背景にあると多くのところで指摘されていると思いますが、円安を背景にインバウンドが増えているなら、逆に円高になると 少なくなってしまうのか、こういった為替の影響についても併せてコメントいただければと思います。
(答)
まず、受け止めですが、要因というのは、今月頑張ったから来月効果が出るというものではなく、数年前からの個々の観光地の取り組み、観光庁とか政府の取り組みなど、色々な効果がかみ合ってきている結果だと思っています。
今調子がいいのはありがたい結果ですが、さらに目標がありますので、そこに向かって、それぞれのプレイヤーで引き続きやっていただくとともに我々も必要な支援を続けるということに尽きると思っています。
それから、円安の効果はあると思いますが、訪日旅行者がお帰りになる時に、直接声を聞くことをやっていて、日本はどこがいいかや何を目的に来たのかを聞く問に対して、季節がいいとか、ご飯が美味しいとか安全だという回答はありますが、上位の回答のなかに円安でお得だからというのはあまりないです。
日本に来て相当お金使っていただくようなインバウンドの方たちは、まず日本に行ってみようという気持ちがあって来ていただいて、その上で、円安なので、さらにお買い物をするということかと思います。
我々が思っているよりも、日本の魅力は非常に高いということが浸透していると思っています。
まだ円高の局面になっていないので、そうなった時どういうことが起こるのかは現時点では、わからないところです。
(問)先月、アゼルバイジャンで開催されたCOP29について、バクー宣言でも、COPでは初めて、観光政策に環境変動対策を統合することを強化せよ、という宣言が盛り込まれました。これは初めての宣言だと思いますが、そういった方向性が示されたことに対して、受け止めをお聞かせください。
また、現在の観光立国推進基本計画は、持続可能な観光地づくりの促進や需要分散化を推進していますが、温室効果ガスの削減にはまだ十分に踏み込んでいないと思っています。これに対して、今後どういう風に取り組んでいくべきとお考えか、お聞かせください。
(答)
「環境に配慮した」や「持続可能な」ということが、コロナ禍の間に随分意識が高まったと、分析としてありましたが、G7の会議でも、環境の議論がとても多かったため、日本に比べるととても意識が高い印象です。
今後の取り組みについては、2030年に向けた政府の次期観光立国推進基本計画の議論の中で、そのような視点も重要な論点になると思います。
そこで議論しつつ、観光の政策や、現場の様々な取り組みに反映していくようになるかと思います。
(問)韓国の戒厳令が出され、不安定な政治状況だが、旅行市場やマインドについてなにか変化は感じるか。
(答)
連日トップで報道されていますが、現地の友人に聞くと、国会周辺等で反対派の方が活動されていますが、市民としては全く普通で、何にも生活は変わりませんということでした。
先日、韓国に実際行きましたが、情報のとおり全く普通で、市内を移動してみても、普通に皆さん生活されている印象を受けました。
韓国の文化体育観光部長官などは、風評やイメージで人が来なくなるのではないかということを心配されており、観光庁が来て、会議を一緒にしてくれたのは、アピールになって嬉しいと、喜んでおられました。
そういった情報も報道されているため、見ていただければと思います。
韓国から日本に来ることに関しては何も問題はなく、生活も普通のため、旅行する人は来ると思います。
日本から韓国に行く方にも、そういった情報が少しずつ分かっていけば、影響はあまりないのではないかとの印象を持っています。
(問)日米観光交流年が発表されて1年間となるが、今時点での成果をどのように見ているか、教えていただきたい。
(答)
ワシントンの大使公邸で実施されたイベントについては、現地の大使館からも非常に盛況だったと聞いています。
今回は、比叡山延暦寺の僧侶の方も現地に行かれて、様々なプレゼンをしていただいたり、美味しい日本食の提供があったりして、非常に刺激的であったと思います。
また、お寺の僧侶に会えたので、実際に行ってみたいといった方も多く、非常にいいチャンスになったかと思います。
アウトバウンドについては、全体的に回復傾向ではありますが、まだ2019年に比べると少ないので、アメリカとの行き来に関して、インバウンドはたくさん来ていますので、アウトバウンドがもう少し伸びればと思っています。
(問)自治体交流について、約400件がこの1年間で実施され、札幌や大分などが好事例として挙げられていますが、全般的な人材交流の成果をどのように見ているか教えてください。
(答)
自治体交流は、とてもありがたいチャンネルであり、実績が積み重なると、信用ができて、ルーティン化していくのでよいと思っています。
地域によりますが、学生さんなどの若い方の行き来がすごく多いので、若い方が海外に行くチャンスであり、海外のことを理解して友達ができるなど、その時だけではなく、その後にも続いていくような交流のチャンスになっていると思います。
日本は今、若い方があまり海外に出ていかないということが言われていますが、学校での活動などで姉妹都市交流を利用することも多いように聞いています。
以上
(答)
11月は数字が落ちる年もありますが、今年は訪日需要の高まりが引き続き続いています。
地域別に見ますと、インバウンドの約7割を占めるアジア諸国が2019年の11月に比べると約25%伸び、欧米諸国は約50%増えているということなので、それが非常に大きかったと思います。
12月は11月よりも多少増えることが毎年の傾向なので、今後このまま順調にいけば、3500万人を達成することが予想されます。
(問)訪日者数も訪日消費額も過去最多となり、観光を取り巻く環境は新しい局面を迎えている中、2030年の目標も見据え、観光地や観光業界など受け入れる側の課題認識と今後の観光施策について、教えてください。
(答)
今の状況を引き続き維持して継続していくように取り組みを続けていきますが、よりインバウンドが増えていく傾向からすると、宿泊産業では人手不足の課題があると思います。
また、インバウンドの宿泊を見ると約70%は三大都市圏へ集中しています。
したがって、インバウンドの地方での宿泊に取り組んでいくことが必要です。
人手不足の関係では、外国人人材を活用する制度があり、活用し始めていただいている事業者もありますが、もっと働きかけることが必要だと思います。
インバウンドの宿泊の都市圏への偏在という部分については、地方に滞在していただくため、地方により行ってみたいと思うように、素敵な観光地づくりを地方に色々取り組んでいただいていますが、そういう取り組みを引き続き続けていただくとともに、地方へもどうぞというような発信もしっかりやっていくということだと思います。
当然、人数が増えてくるとオーバーツーリズムの問題もまた出てくると思いますが、今、全国でオーバーツーリズム対策を支援させていただき、いろんな対応策の事例を作りつつありますが、そのようなものを活用しながら、場所によって色々状況は違うと思いますが、その場所にあったやり方を相談しながら、進めていければと思います。
(問)昨日、補正予算が成立しました。改めて、観光庁の補正予算 の内容や狙いについて教えてください。
(答)
補正予算については、観光庁全体で約540億円であり、大きな額を確保することができたと思っています。
内容は、先ほど申し上げた課題をふまえ、なるべく地方に行っていただくため、その地域の観光地とか観光産業の高付加価値化、オーバーツーリズムの未然防止、訪日外国人の受入環境整備、能登半島地震からの復興支援となっております。
能登半島地震からの復興については、建物も随分痛んでいて、まずはどういう方向で再建していくのかという検討や計画を作る1番最初の段階のところを支援してくださいという声がすごく強かったので、そういうものに使っていただけるような予算を確保しています。
(問)観光庁は「未来のための旅のエチケット」と「観光ピクトグラム」を作成されました。観光客および観光関連事業者に呼び掛けたいことなどお考えをお聞かせください。 また、これをしっかり浸透させていくことが重要だと思いますが、旅行者や観光関係者への周知にどのように取り組みますか。
(答)
これも、オーバーツーリズムの事例に対応する1つの有効な手段だと思っており、 観光客のマナー啓発等のお役に立てるよう、「未来のための旅のエチケット」と「観光ピクトグラム」を11月29日に公表したところです。
「未来のための旅のエチケット」については、観光に来てくださる方も悪気があるわけではなく、文化の違いというところがすごく大きいと思うので、 旅先の環境とか地元の方たちにも配慮しながら、旅を楽しんでいただくにはこうした方がいいということをわかりやすくお伝えすることだと思っています。
これは、知っていただかないといけないと思いますので、JNTOのウェブサイトや海外メディア向けの発信、全国の観光案内所などにおけるポスター掲示やパンフレット配布などを通して周知を図りたいと思っています。
「観光ピクトグラム」については、こういうことをするのは良くないですよということなどが瞬時にわかるようにする目的で作っております。
私有地に立ち入っての写真撮影などのマナー違反行為や手ぶら観光などを示しており、自治体や関係事業者の方から意見をいただいて作ったものなので、ぜひ効果が出るように取組を進めてまいります。
(問)中国人からの訪日客数ですが、まだコロナ前水準には戻っておらず、7割ぐらいかと思います。先日、中国が日本人向け訪中ビザ免除措置を再開し、報道によると、日本側も中国人向けの訪日ビザの発給要件の緩和を検討しているとのことですが、こういったビザの緩和は、中国からの訪日客数の増加にどういった影響があると思うか、所感をお願いします。
(答)
中国は、今年の前半は、2019年と前の年に比べても非常に少なかったですけども、 夏以降、少ないながらも増えてきているという状況で、11月は70%ぐらいの回復で、人数では韓国についで2位です。コロナ前よりはまだ少ない状況ですが、回復傾向にあり、この傾向が来年まで続くようにしていきたいです。
先月末から日本人に対する中国の短期滞在ビザの免除措置が再開され、日本から中国に行きやすくなったと思います。経済の活性化や相互理解の促進につながればと思っています。
それから、報道があった日本側がビザの発給要件緩和をするのではということですが、確認した範囲内ではそういうことを決めたという事実はないようですが、もしそういうことが実現すれば、インバウンドの拡大にはプラスの方向だと思っています。
(問)先般、ベストツーリズムビレッジに新たに2地域が認定された。観光立国推進基本計画において、「令和7年までに持続可能な観光地域づくりに取り組む地域数を100地域にする、うち国際認証・表彰地域を50地域」にする目標がたてられていますが、これまでの実績とこれに対する長官の所感・評価を教えてください。また、「持続的な観光地域づくりに取り組む地域」を増やしていく、支援していくための来年以降の取り組みや施策を教えてください。
(答)
今年の11月にUN Tourismが持続可能な観光地域づくりに取り組む優良な地域を認定するベストツーリズムビレッジということで、鹿児島県の天城町と山形県の西川町、この2つが選ばれました。
10月には、グリーンデスティネーションズが表彰するグリーンデスティネーションズアワードと世界の持続的な観光地トップ100選に、愛媛県大洲市と岐阜県高山市などの9地域が選ばれました。
基本計画における持続可能な観光地づくりについて、現時点での進捗状況は、取り組む地域数が46、そのうち国際表彰などを受けた地域数が19まで拡大しています。
前者については、この1年間で15増加しています。年度内をめどに、さらに10地域程度の申請が見込まれています。
非常にいい傾向ですので、こういう意欲のある地域への後押しを引き続きやっていきたいと思います。
(問)2030 年に6000 万人との目標がありますが、現在の構成ですとアジアが7割ぐらいですが、今後、よりパイを増やしていくために、重点的に取り組みたい誘客プロモーションや地域などの考えをお聞かせください。
(答)
2030年6000万人という大きな目標がありますが、昨年の6月に観光庁とJNTOが訪日マーケティング戦略を策定しました。この戦略を基に重点市場として23の国と地域があり、それぞれ特性に応じて戦略的かつきめ細やかな訪日プロモーションを実施しているところです。
来年も引き続きその戦略に基づいて取り組みを進めていくことを考えています。
(問)2030年の目標についてですが、長官はこれは可能だと考えていますか。
(答)
かなり高い目標ですが、可能だと思っています。かつて500万人ぐらいしか来てない時に1000万人という目標を作って、実際達成しています。その後、4000万、6000万という目標ができて、4000万人には今迫ってきています。かなり意欲的な目標ではありますが、全体で力を合わせて進めれば、6000万人もできるだろうと個人的には思っています。
(問)すでに11月の段階で年間の過去最多を上回ったということについての所感を伺いたいが、 観光庁の取り組みが功を奏しているのか、あるいは自治体あるいは事業者の取り組みの効果が出ているのかなどコメントをお願いします。また、要因として、やはり為替、円安というのが背景にあると多くのところで指摘されていると思いますが、円安を背景にインバウンドが増えているなら、逆に円高になると 少なくなってしまうのか、こういった為替の影響についても併せてコメントいただければと思います。
(答)
まず、受け止めですが、要因というのは、今月頑張ったから来月効果が出るというものではなく、数年前からの個々の観光地の取り組み、観光庁とか政府の取り組みなど、色々な効果がかみ合ってきている結果だと思っています。
今調子がいいのはありがたい結果ですが、さらに目標がありますので、そこに向かって、それぞれのプレイヤーで引き続きやっていただくとともに我々も必要な支援を続けるということに尽きると思っています。
それから、円安の効果はあると思いますが、訪日旅行者がお帰りになる時に、直接声を聞くことをやっていて、日本はどこがいいかや何を目的に来たのかを聞く問に対して、季節がいいとか、ご飯が美味しいとか安全だという回答はありますが、上位の回答のなかに円安でお得だからというのはあまりないです。
日本に来て相当お金使っていただくようなインバウンドの方たちは、まず日本に行ってみようという気持ちがあって来ていただいて、その上で、円安なので、さらにお買い物をするということかと思います。
我々が思っているよりも、日本の魅力は非常に高いということが浸透していると思っています。
まだ円高の局面になっていないので、そうなった時どういうことが起こるのかは現時点では、わからないところです。
(問)先月、アゼルバイジャンで開催されたCOP29について、バクー宣言でも、COPでは初めて、観光政策に環境変動対策を統合することを強化せよ、という宣言が盛り込まれました。これは初めての宣言だと思いますが、そういった方向性が示されたことに対して、受け止めをお聞かせください。
また、現在の観光立国推進基本計画は、持続可能な観光地づくりの促進や需要分散化を推進していますが、温室効果ガスの削減にはまだ十分に踏み込んでいないと思っています。これに対して、今後どういう風に取り組んでいくべきとお考えか、お聞かせください。
(答)
「環境に配慮した」や「持続可能な」ということが、コロナ禍の間に随分意識が高まったと、分析としてありましたが、G7の会議でも、環境の議論がとても多かったため、日本に比べるととても意識が高い印象です。
今後の取り組みについては、2030年に向けた政府の次期観光立国推進基本計画の議論の中で、そのような視点も重要な論点になると思います。
そこで議論しつつ、観光の政策や、現場の様々な取り組みに反映していくようになるかと思います。
(問)韓国の戒厳令が出され、不安定な政治状況だが、旅行市場やマインドについてなにか変化は感じるか。
(答)
連日トップで報道されていますが、現地の友人に聞くと、国会周辺等で反対派の方が活動されていますが、市民としては全く普通で、何にも生活は変わりませんということでした。
先日、韓国に実際行きましたが、情報のとおり全く普通で、市内を移動してみても、普通に皆さん生活されている印象を受けました。
韓国の文化体育観光部長官などは、風評やイメージで人が来なくなるのではないかということを心配されており、観光庁が来て、会議を一緒にしてくれたのは、アピールになって嬉しいと、喜んでおられました。
そういった情報も報道されているため、見ていただければと思います。
韓国から日本に来ることに関しては何も問題はなく、生活も普通のため、旅行する人は来ると思います。
日本から韓国に行く方にも、そういった情報が少しずつ分かっていけば、影響はあまりないのではないかとの印象を持っています。
(問)日米観光交流年が発表されて1年間となるが、今時点での成果をどのように見ているか、教えていただきたい。
(答)
ワシントンの大使公邸で実施されたイベントについては、現地の大使館からも非常に盛況だったと聞いています。
今回は、比叡山延暦寺の僧侶の方も現地に行かれて、様々なプレゼンをしていただいたり、美味しい日本食の提供があったりして、非常に刺激的であったと思います。
また、お寺の僧侶に会えたので、実際に行ってみたいといった方も多く、非常にいいチャンスになったかと思います。
アウトバウンドについては、全体的に回復傾向ではありますが、まだ2019年に比べると少ないので、アメリカとの行き来に関して、インバウンドはたくさん来ていますので、アウトバウンドがもう少し伸びればと思っています。
(問)自治体交流について、約400件がこの1年間で実施され、札幌や大分などが好事例として挙げられていますが、全般的な人材交流の成果をどのように見ているか教えてください。
(答)
自治体交流は、とてもありがたいチャンネルであり、実績が積み重なると、信用ができて、ルーティン化していくのでよいと思っています。
地域によりますが、学生さんなどの若い方の行き来がすごく多いので、若い方が海外に行くチャンスであり、海外のことを理解して友達ができるなど、その時だけではなく、その後にも続いていくような交流のチャンスになっていると思います。
日本は今、若い方があまり海外に出ていかないということが言われていますが、学校での活動などで姉妹都市交流を利用することも多いように聞いています。
以上