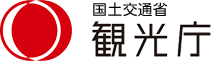秡川長官会見要旨
最終更新日:2025年1月20日
日時:2025年1月15日(水)16:15~17:00
場所:国土交通省会見室
場所:国土交通省会見室
冒頭発言
(2024年計及び同年12月の訪日外国人旅行者数について)
2024年12月の訪日外国人旅行者数は、約349万人となり、単月として過去最高となりました。
2024年の累計の訪日外国人旅行者数は、約3,700万人となり、年間の合計も過去最高となりました。
本年12月の出国日本人数は、約119万人となり、コロナ前の2019年12月と比べた回復率は、69%となりました。
2024年の累計の出国日本人数は、約1,300万人となりました。
2019年と比べた回復率は65%、2023年からは約340万人の増加となりました。
(インバウンド消費動向調査の結果(2024年暦年及び2024年10-12月期1次速報)について)
2024年の年間の訪日外国人旅行消費額は、約8.1兆円と推計され、前年比で53%増と過去最高の数字となりました。
訪日外国人1人当たり旅行支出は、約22.7万円、前年比で7%増となりました。
2024年12月の訪日外国人旅行者数は、約349万人となり、単月として過去最高となりました。
2024年の累計の訪日外国人旅行者数は、約3,700万人となり、年間の合計も過去最高となりました。
本年12月の出国日本人数は、約119万人となり、コロナ前の2019年12月と比べた回復率は、69%となりました。
2024年の累計の出国日本人数は、約1,300万人となりました。
2019年と比べた回復率は65%、2023年からは約340万人の増加となりました。
(インバウンド消費動向調査の結果(2024年暦年及び2024年10-12月期1次速報)について)
2024年の年間の訪日外国人旅行消費額は、約8.1兆円と推計され、前年比で53%増と過去最高の数字となりました。
訪日外国人1人当たり旅行支出は、約22.7万円、前年比で7%増となりました。
質疑応答
(問)2024年の訪日客数は過去最高となりました。過去最高となったことへの所感及び要因について、どのようにみていますか。また、今年も訪日者数の増加が見込まれますが、さらに訪日者数が増える中で、オーバーツーリズムなどの受入環境について、長官が課題に感じていらっしゃることについて、教えてください。
(答)
長年、色々取り組んできたことがかみ合ってきている結果だと思っています。
去年については、訪日需要が堅調だったということと、航空便が回復しているということがありました。
その結果、東アジアだけでなく、東南アジアや欧米豪、中東の国・地域からも月単位でも過去最高という月が多かったので、東アジアは引き続き多く、それに加えてそれ以外の国・地域が増えているというのが去年の傾向だったと思っています。
私も色々な方に会うと、昔と違って海外の方が随分来ていますということを聞くので、今までになかった海外の方が訪れるということが各地で起きていると思います。
そこに住んでいる方の生活環境が変わったり、様々な文化やマナーが日本人と合わないということもあると聞いていますが、そういった地域における課題や事情がそれぞれあると思いますので、それに対する各地の取り組みを観光庁としても後押ししながら良い成果を出し、その取り組みを全体で共有するということをやりながら引き続き取り組んでいきたいと思います。
(問)2024年は、訪日外国人旅行者の消費額も過去最高となりました。こちらも、所感と要因について、どのようにみていますか。
(答)
1人あたりの支出が増えているうえに人数も増えたということなので、その掛け算で、今8.1兆円ということです。
最終目標で15兆円という数字があります。その目標は非常に大きな目標だなと最初は思いましたが、引き続き訪日のトレンドは非常に旺盛だと思いますので、今の状況を大事にしながらうまく伸ばしていきたいと思います。
(問)訪日客数について、2024年が過去最高となり、今後6,000万人を目標に進めていくと思いますが、2025年の目標値があれば教えてください。
(答)
2025年としての目標値はありませんが、6,000万人の目標を作った時に2030年が6,000万人でその途中経過で2020年が4,000万人という目標はありました。
コロナになり、達成はできなかったですが、6,000万人が最終目標だとすれば、その途中に4,000万人という数字もありますので、3,700万人とかなり近いですから、引き続き今年も今の環境を大事にしつつ、色々な取り組みを頑張って、その途中経過の目標を達成できるように、力を合わせてやっていきたいと思います。
(問)本年の観光行政を進めていくにあたっての抱負を教えてください。
(答)
観光の取り組みは、行政だけではなく、民間の皆様方も含めて、息が長く正しい取り組みを続けるということが大事だと思います。
今ご報告した数字は一つの成果だと思いますが、今年取り組んでいくことも変わらないと思っています。
ただ、例えば観光客数がさらに増えていくなど新しい状況下では、色々な課題や今まで見えなかったことも起きてくるかもしれないので、なるべく早く情報を察知し、関係者で話し合って対処しつつ、さらに成果を出していきたいと思います。
(問)好調なインバウンドと対照的にアウトバウンドは回復が遅いと思いますが、その背景、原因と対策があれば、教えてください。
(答)
要因としては、今、円が非常に安いということと、人気の観光地はどこも非常に値段が高いということが重なっていると思います。
特に、若い層にとっては、引き続き環境が厳しいのかなと思いますが、アウトバウンドもトータルでは先ほどご報告したような数字ですが、月ベースで見ると、直近はコロナ前の7割程度まで回復しています。行政としてできることは、教育旅行は海外に行くというのが徐々に復活してきているようなので、そういったところをしっかり関係省庁と調整して促進していきたいと思います。
また、今年は万博があります。万博は、海外に触れて、興味を持ってもらうのに非常に良い機会だと思いますので、そういったところも活用してアウトバウンドが伸びればと思っております。
(問)航空需要の部分で、アウトバウンドが増えて、相互的な行き来がないと、インバウンドもこれから増えていかないというような指摘もあるかと思いますが、お考えをお聞かせください。
(答)
航空会社のお話では、インバウンドのお客さんが非常に多いことから、航空需要は非常に好調ということです。
アウトバウンドが増えてくれば、さらに便や席数が必要という環境になってくると思いますので、両方伸ばしていくことは大事だと思っています。
(問)インバウンド消費の三大都市圏と地方の配分がどれぐらいになっているか、あわせてその状況についての評価と対策について教えてください。
(答)
(観光庁事務方より)2024年暦年での消費額の都道府県別結果は、3月末に公表しますので、現時点では数字がありません。1月から9月までが最新値になりますが、三大都市圏が大体75%、地方部が25%で、7割か8割ぐらいが三大都市圏に集中しているという状況です。
2023年度から2025年度までの基本計画の目標の一つとして、三大都市圏以外の地方部に、訪日外国人旅行者一人当たり2泊していただくということを掲げています。
消費額においては、泊まることが非常に大きいと思いますが、例えば日光の方と話をすると、東京から日帰りできており、賑わってはいるが、あまり泊まらない状況で、その対策を考えているということでした。
やはり泊まっていただくことが非常に大事であり、遠い地方も含めて、まずいいところがあることを知ってもらって、そこでゆっくり過ごしてもらえるように取り組みたいと思っております。リピーターも増えてきていると思いますので、地方に行っていただくことに力を入れていきたいと思っています。
(問)2025年度は、観光立国推進基本計画の最終年度となります。今の泊数の件など、未達の目標に今後どう取り組むか、特に、未達で課題と感じているものがあれば、お教えください。また、次期の目標の検討はいつ頃から始めるのかも教えてください。
(答)
今の3カ年計画は、2022年の岸田政権時に策定したもので、当時、コロナは一定程度収まったが、外国人旅行者の方々が日本に来てくれるのか分からない面もあり、目標としては保守的というか、2019年のコロナ前の水準まで戻すことを目指したものになっています。
訪日外国人旅行者数や消費額は、昨年目標を超えましたが、まだ達していないのが地方部での1人当たり泊数です。地方に足を運ぶ方は増えていると思いますが、もっと長く滞在していただくことや、その滞在地で色々と消費してもらうことを促進していけるよう、これからさらに取り組む必要があると思います。
2026年度からはじまる次期計画は、今年から検討していかなければいけないと思っています。
(問)2030年6,000万人という目標があり、去年は3,700万人で順調なペースで来ていると感じますが、改めて2030年6,000万人という目標の実現可能性について、長官の手応えを教えてください。
(答)
過去の1,000万人の目標も達成していますし、4,000万、6,000万という目標も、設定された時は、かなり意欲的で高い目標だと感じましたが、今、実際には4,000万人に近づいてきています。ですから、難しい目標だと思っても、民間の方も含めて、色々な取り組みをして試行錯誤していければと思っています。
(問)そこに向けて特に課題や乗り越えなければいけない部分もあると思いますが、残り5年間で力を入れたい点などありましたら教えてください。
(答)
現状、大まかに4,000万人だとして、2030年6,000万人となりますと、その1.5倍となります。空港の機能、国内の移動、宿泊の施設など、そういったものが十分にあることが、まず大事です。
6,000万人ということになると当然初めて来られる方もいますが、リピーターの方も必ず増えていくと思いますので、地方に足を運んでいただいて、長く滞在していただくということをどう実現していくのかが重要だと考えています。
(問)中国人観光客についてお伺いします。2024年はインバウンド数が過去最高になりましたが、中国人観光客は回復が7割程度という実態があるかと思います。その受け止めと、今後予定されている中国人向けのビザ発給要件の緩和措置について、これに対する期待、また、どのようなタイミングでこの緩和措置の実施が行われるべきかお考えをお聞かせください。
(答)
中国は2019年で見ると960万人ぐらい来て、国・地域別で1位だったかと思います。昨年は韓国に次いで2位でしたが、2024年1年間で見ますと、前半の半年はかなり低調で後半随分良くなってきています。毎月毎月2019年に比べての回復率は上がってきています。経済の状態など原因が色々あると思いますが、トレンドとしては回復傾向と思っています。
岩屋外務大臣が中国に行かれ、王毅外務大臣とお会いされましたが、プラスの方に働く要因だと思いますので、今の中国からの回復傾向をさらに伸ばしていきたいと思っています。
ビザ発給要件緩和のタイミングは、観光庁では分かりませんが、準備しているところと聞いており、期待しているところです。
(問)長野県の白馬でのインバウンドバブルについて、白馬村の昨年の基準地価が、駅前で30%上がったり、海外からニセコと同じようにスキー客が来るので外資の不動産業者がコンドミニアムやホテルを作るなど、非常に潤っている一方、地元の方や日本人で白馬に移住した方が、ワンルームが10万円になったり、立ち退きを要請されているということで、なかなか観光客と地元がうまくいかない部分も出てきていると感じます。
ニセコも以前、外資が来て、ラーメン1杯3,000円のような状況になり、日本人が行きづらい状況があると聞いていますが、地方への誘客を進める一方、こういった一部偏在した地域でこのような状況が起きていることについて、持続的な観光を推進するために観光庁としてどのように受け止めているのか、地元との関係も含めて教えてください。
(答)
お客様がたくさん来ている状態は、地元の自治体の方からは、歓迎でありがたいことだと聞きますし、色々なものが観光関係で潤い、経済が回るのはよいことだと思います。
ニセコの町長さんとお話すると、3,000円のラーメンという話はよく耳にしますが、そういった方向けのサービスはありながら、地元の方は、普通の生活をしているし、それが成り立つような様々な工夫をしているという話をお聞きしました。
白馬においても、今、来ていただいているお客様を大事に、楽しんでいただくことをキープしながら、地元の方の生活もきちんと成り立つようにしなければならないということを、自治体の方はものすごく考えておられるなと思います。
我々もご相談に乗り、対話をして一緒に考えたり、他省庁の方をご紹介したりしておりますが、良いトレンドをキープしながらも、個別の問題が起きた時には、一緒になって考えるということを引き続きしていきたいと思います。
これからも観光客の人数が増えていくことは期待しつつも、今おっしゃったようなことは、色々なところで起こってくる可能性があるので、地域から丁寧に情報をいただきながらやっていきたいと思います。
(問)能登半島地震の発災から1年が経過した。2024年の補正予算で、被災地の観光再生支援事業を進めていくと思いますが、具体的にどのように取り組みを進めていくのか、お聞かせください。
(答)
能登については、補正予算を組む随分前から、どのような支援が本当に求められているのか、今どういう状況なのか、ということを細かく把握するという作業を観光庁で進めていました。
お客様を受け入れている宿も若干ありますが、半分以上がお客様を受け入れられる体制ではなく、受け入れているところでも、半分以上は災害対応で来てくださっているスタッフの方は泊めているが、観光のお客様を泊めるというところまではいかないという状況でした。
地元からは、観光客を送り込むことやキャンペーンの前に、どのように復興していくのか、個々の旅館やホテルも含めて、地域として復興の計画を作って作戦を立てる、というところをまずやらなければいけないので、そこを支援してくださいという意見が多かったところです。
そのための予算を補正予算で確保しており、これから予算を使っていただくための公募や選定のプロセスに入ります。
地域にも情報提供していますので、よくご活用いただき、有効な計画を作っていただいて、復興の第一歩になれば良いと思っています。
(問)具体的なコンテンツ造成や情報発信についてはもう少し時間がかかるというご認識でしょうか。
(答)
予算の内容としては、復興の計画を作る際に、コンテンツ造成や情報発信、プロモーションなど、その先にある一連の動作を取り込んでよいことになっていますので、今おっしゃったようなポイントも含めて、予算を使っていただき、ご検討いただければよいかと思っています。
(問)長官は交通空白解消本部にも参加されていて、地域のアシの確保とともに交通結節点や観光のアシの確保も1つのテーマになっていますが、今年はどのように進めていきたいか、教えてください。
(答)
地方に行っていただいて、駅に着いたらアシがありませんというのは、非常に困ってしまうわけですから、そこでお住まいの方の日常の交通ももちろんですが、訪れた方のアシを確保して十分楽しんでいただくということも同時に重要です。
補正予算の中で、観光庁に付いた補正予算の一部を、交通で使っていただけるようになっていますので、うまく活かしていただき、担当部局とよく連携し、良い成果が出るように努力していきたいと思います。
(問)バスやタクシーという従来の交通手段に加え、公共ライドシェアや日本版ライドシェアという新しい選択肢も出てきており、自治体と組んで様々な動きが出ているところですが、実際の事業者や自治体に向けた注文や期待があれば、教えてください。
(答)
全国の運輸局の局長が、所管する自治体のトップの方にライドシェアのことを説明するという活動を去年から続けていますが、運輸局からは、公共ライドシェアを知らない自治体の方が多く、今回の制度改正をお知らせすると、検討を始める自治体の方が随分多いと聞きます。
こういった営業活動に運輸局長が行くのは非常に良いことと思っており、少しでも知っていただいてご活用いただきたいと思います。
その土地の事情に合わせた輸送サービスをなるべくできるように一緒に考えましょうということで進めており、だんだん理解が浸透しつつあるなと思いましたので、よりよくご活用いただけたらと思います。
(問)次の観光立国推進基本計画の議論を始めていくと思いますが、6,000万人、15兆円という大きな目標に向けて政策面での大きなポイントになるのは国際観光旅客税の存在だと思います。次の計画の議論の中で、旅客税の使途の見直しまで踏み込んで議論していくべきか、お考えをお聞かせください。
(答)
令和7年度の観光庁予算案でも約500億円で、一般財源はだんだん少なくなり、旅客税財源の方が多いことから、観光の政策イコール旅客税財源のようなところがあり、また他省庁でも色々使っていただいております。
次の5年の計画に向けては、今具体的なものはないですが、当然、新しい課題が予想されますので、それに対してこういうことをやっていくべきだという内容になると予想されます。
そういった行政ニーズがあった時に、財源が必要になりますので、どのようにそこに対応していくのかという議論は当然あると思います。
年度当初の予算と補正予算で、コロナが落ち着いたここ1年2年ぐらいは、1,000億円くらい他省庁も含めて、観光で使わせていただいているので、それをどのように確保していくのかという議論にはなると思います。
以上
(答)
長年、色々取り組んできたことがかみ合ってきている結果だと思っています。
去年については、訪日需要が堅調だったということと、航空便が回復しているということがありました。
その結果、東アジアだけでなく、東南アジアや欧米豪、中東の国・地域からも月単位でも過去最高という月が多かったので、東アジアは引き続き多く、それに加えてそれ以外の国・地域が増えているというのが去年の傾向だったと思っています。
私も色々な方に会うと、昔と違って海外の方が随分来ていますということを聞くので、今までになかった海外の方が訪れるということが各地で起きていると思います。
そこに住んでいる方の生活環境が変わったり、様々な文化やマナーが日本人と合わないということもあると聞いていますが、そういった地域における課題や事情がそれぞれあると思いますので、それに対する各地の取り組みを観光庁としても後押ししながら良い成果を出し、その取り組みを全体で共有するということをやりながら引き続き取り組んでいきたいと思います。
(問)2024年は、訪日外国人旅行者の消費額も過去最高となりました。こちらも、所感と要因について、どのようにみていますか。
(答)
1人あたりの支出が増えているうえに人数も増えたということなので、その掛け算で、今8.1兆円ということです。
最終目標で15兆円という数字があります。その目標は非常に大きな目標だなと最初は思いましたが、引き続き訪日のトレンドは非常に旺盛だと思いますので、今の状況を大事にしながらうまく伸ばしていきたいと思います。
(問)訪日客数について、2024年が過去最高となり、今後6,000万人を目標に進めていくと思いますが、2025年の目標値があれば教えてください。
(答)
2025年としての目標値はありませんが、6,000万人の目標を作った時に2030年が6,000万人でその途中経過で2020年が4,000万人という目標はありました。
コロナになり、達成はできなかったですが、6,000万人が最終目標だとすれば、その途中に4,000万人という数字もありますので、3,700万人とかなり近いですから、引き続き今年も今の環境を大事にしつつ、色々な取り組みを頑張って、その途中経過の目標を達成できるように、力を合わせてやっていきたいと思います。
(問)本年の観光行政を進めていくにあたっての抱負を教えてください。
(答)
観光の取り組みは、行政だけではなく、民間の皆様方も含めて、息が長く正しい取り組みを続けるということが大事だと思います。
今ご報告した数字は一つの成果だと思いますが、今年取り組んでいくことも変わらないと思っています。
ただ、例えば観光客数がさらに増えていくなど新しい状況下では、色々な課題や今まで見えなかったことも起きてくるかもしれないので、なるべく早く情報を察知し、関係者で話し合って対処しつつ、さらに成果を出していきたいと思います。
(問)好調なインバウンドと対照的にアウトバウンドは回復が遅いと思いますが、その背景、原因と対策があれば、教えてください。
(答)
要因としては、今、円が非常に安いということと、人気の観光地はどこも非常に値段が高いということが重なっていると思います。
特に、若い層にとっては、引き続き環境が厳しいのかなと思いますが、アウトバウンドもトータルでは先ほどご報告したような数字ですが、月ベースで見ると、直近はコロナ前の7割程度まで回復しています。行政としてできることは、教育旅行は海外に行くというのが徐々に復活してきているようなので、そういったところをしっかり関係省庁と調整して促進していきたいと思います。
また、今年は万博があります。万博は、海外に触れて、興味を持ってもらうのに非常に良い機会だと思いますので、そういったところも活用してアウトバウンドが伸びればと思っております。
(問)航空需要の部分で、アウトバウンドが増えて、相互的な行き来がないと、インバウンドもこれから増えていかないというような指摘もあるかと思いますが、お考えをお聞かせください。
(答)
航空会社のお話では、インバウンドのお客さんが非常に多いことから、航空需要は非常に好調ということです。
アウトバウンドが増えてくれば、さらに便や席数が必要という環境になってくると思いますので、両方伸ばしていくことは大事だと思っています。
(問)インバウンド消費の三大都市圏と地方の配分がどれぐらいになっているか、あわせてその状況についての評価と対策について教えてください。
(答)
(観光庁事務方より)2024年暦年での消費額の都道府県別結果は、3月末に公表しますので、現時点では数字がありません。1月から9月までが最新値になりますが、三大都市圏が大体75%、地方部が25%で、7割か8割ぐらいが三大都市圏に集中しているという状況です。
2023年度から2025年度までの基本計画の目標の一つとして、三大都市圏以外の地方部に、訪日外国人旅行者一人当たり2泊していただくということを掲げています。
消費額においては、泊まることが非常に大きいと思いますが、例えば日光の方と話をすると、東京から日帰りできており、賑わってはいるが、あまり泊まらない状況で、その対策を考えているということでした。
やはり泊まっていただくことが非常に大事であり、遠い地方も含めて、まずいいところがあることを知ってもらって、そこでゆっくり過ごしてもらえるように取り組みたいと思っております。リピーターも増えてきていると思いますので、地方に行っていただくことに力を入れていきたいと思っています。
(問)2025年度は、観光立国推進基本計画の最終年度となります。今の泊数の件など、未達の目標に今後どう取り組むか、特に、未達で課題と感じているものがあれば、お教えください。また、次期の目標の検討はいつ頃から始めるのかも教えてください。
(答)
今の3カ年計画は、2022年の岸田政権時に策定したもので、当時、コロナは一定程度収まったが、外国人旅行者の方々が日本に来てくれるのか分からない面もあり、目標としては保守的というか、2019年のコロナ前の水準まで戻すことを目指したものになっています。
訪日外国人旅行者数や消費額は、昨年目標を超えましたが、まだ達していないのが地方部での1人当たり泊数です。地方に足を運ぶ方は増えていると思いますが、もっと長く滞在していただくことや、その滞在地で色々と消費してもらうことを促進していけるよう、これからさらに取り組む必要があると思います。
2026年度からはじまる次期計画は、今年から検討していかなければいけないと思っています。
(問)2030年6,000万人という目標があり、去年は3,700万人で順調なペースで来ていると感じますが、改めて2030年6,000万人という目標の実現可能性について、長官の手応えを教えてください。
(答)
過去の1,000万人の目標も達成していますし、4,000万、6,000万という目標も、設定された時は、かなり意欲的で高い目標だと感じましたが、今、実際には4,000万人に近づいてきています。ですから、難しい目標だと思っても、民間の方も含めて、色々な取り組みをして試行錯誤していければと思っています。
(問)そこに向けて特に課題や乗り越えなければいけない部分もあると思いますが、残り5年間で力を入れたい点などありましたら教えてください。
(答)
現状、大まかに4,000万人だとして、2030年6,000万人となりますと、その1.5倍となります。空港の機能、国内の移動、宿泊の施設など、そういったものが十分にあることが、まず大事です。
6,000万人ということになると当然初めて来られる方もいますが、リピーターの方も必ず増えていくと思いますので、地方に足を運んでいただいて、長く滞在していただくということをどう実現していくのかが重要だと考えています。
(問)中国人観光客についてお伺いします。2024年はインバウンド数が過去最高になりましたが、中国人観光客は回復が7割程度という実態があるかと思います。その受け止めと、今後予定されている中国人向けのビザ発給要件の緩和措置について、これに対する期待、また、どのようなタイミングでこの緩和措置の実施が行われるべきかお考えをお聞かせください。
(答)
中国は2019年で見ると960万人ぐらい来て、国・地域別で1位だったかと思います。昨年は韓国に次いで2位でしたが、2024年1年間で見ますと、前半の半年はかなり低調で後半随分良くなってきています。毎月毎月2019年に比べての回復率は上がってきています。経済の状態など原因が色々あると思いますが、トレンドとしては回復傾向と思っています。
岩屋外務大臣が中国に行かれ、王毅外務大臣とお会いされましたが、プラスの方に働く要因だと思いますので、今の中国からの回復傾向をさらに伸ばしていきたいと思っています。
ビザ発給要件緩和のタイミングは、観光庁では分かりませんが、準備しているところと聞いており、期待しているところです。
(問)長野県の白馬でのインバウンドバブルについて、白馬村の昨年の基準地価が、駅前で30%上がったり、海外からニセコと同じようにスキー客が来るので外資の不動産業者がコンドミニアムやホテルを作るなど、非常に潤っている一方、地元の方や日本人で白馬に移住した方が、ワンルームが10万円になったり、立ち退きを要請されているということで、なかなか観光客と地元がうまくいかない部分も出てきていると感じます。
ニセコも以前、外資が来て、ラーメン1杯3,000円のような状況になり、日本人が行きづらい状況があると聞いていますが、地方への誘客を進める一方、こういった一部偏在した地域でこのような状況が起きていることについて、持続的な観光を推進するために観光庁としてどのように受け止めているのか、地元との関係も含めて教えてください。
(答)
お客様がたくさん来ている状態は、地元の自治体の方からは、歓迎でありがたいことだと聞きますし、色々なものが観光関係で潤い、経済が回るのはよいことだと思います。
ニセコの町長さんとお話すると、3,000円のラーメンという話はよく耳にしますが、そういった方向けのサービスはありながら、地元の方は、普通の生活をしているし、それが成り立つような様々な工夫をしているという話をお聞きしました。
白馬においても、今、来ていただいているお客様を大事に、楽しんでいただくことをキープしながら、地元の方の生活もきちんと成り立つようにしなければならないということを、自治体の方はものすごく考えておられるなと思います。
我々もご相談に乗り、対話をして一緒に考えたり、他省庁の方をご紹介したりしておりますが、良いトレンドをキープしながらも、個別の問題が起きた時には、一緒になって考えるということを引き続きしていきたいと思います。
これからも観光客の人数が増えていくことは期待しつつも、今おっしゃったようなことは、色々なところで起こってくる可能性があるので、地域から丁寧に情報をいただきながらやっていきたいと思います。
(問)能登半島地震の発災から1年が経過した。2024年の補正予算で、被災地の観光再生支援事業を進めていくと思いますが、具体的にどのように取り組みを進めていくのか、お聞かせください。
(答)
能登については、補正予算を組む随分前から、どのような支援が本当に求められているのか、今どういう状況なのか、ということを細かく把握するという作業を観光庁で進めていました。
お客様を受け入れている宿も若干ありますが、半分以上がお客様を受け入れられる体制ではなく、受け入れているところでも、半分以上は災害対応で来てくださっているスタッフの方は泊めているが、観光のお客様を泊めるというところまではいかないという状況でした。
地元からは、観光客を送り込むことやキャンペーンの前に、どのように復興していくのか、個々の旅館やホテルも含めて、地域として復興の計画を作って作戦を立てる、というところをまずやらなければいけないので、そこを支援してくださいという意見が多かったところです。
そのための予算を補正予算で確保しており、これから予算を使っていただくための公募や選定のプロセスに入ります。
地域にも情報提供していますので、よくご活用いただき、有効な計画を作っていただいて、復興の第一歩になれば良いと思っています。
(問)具体的なコンテンツ造成や情報発信についてはもう少し時間がかかるというご認識でしょうか。
(答)
予算の内容としては、復興の計画を作る際に、コンテンツ造成や情報発信、プロモーションなど、その先にある一連の動作を取り込んでよいことになっていますので、今おっしゃったようなポイントも含めて、予算を使っていただき、ご検討いただければよいかと思っています。
(問)長官は交通空白解消本部にも参加されていて、地域のアシの確保とともに交通結節点や観光のアシの確保も1つのテーマになっていますが、今年はどのように進めていきたいか、教えてください。
(答)
地方に行っていただいて、駅に着いたらアシがありませんというのは、非常に困ってしまうわけですから、そこでお住まいの方の日常の交通ももちろんですが、訪れた方のアシを確保して十分楽しんでいただくということも同時に重要です。
補正予算の中で、観光庁に付いた補正予算の一部を、交通で使っていただけるようになっていますので、うまく活かしていただき、担当部局とよく連携し、良い成果が出るように努力していきたいと思います。
(問)バスやタクシーという従来の交通手段に加え、公共ライドシェアや日本版ライドシェアという新しい選択肢も出てきており、自治体と組んで様々な動きが出ているところですが、実際の事業者や自治体に向けた注文や期待があれば、教えてください。
(答)
全国の運輸局の局長が、所管する自治体のトップの方にライドシェアのことを説明するという活動を去年から続けていますが、運輸局からは、公共ライドシェアを知らない自治体の方が多く、今回の制度改正をお知らせすると、検討を始める自治体の方が随分多いと聞きます。
こういった営業活動に運輸局長が行くのは非常に良いことと思っており、少しでも知っていただいてご活用いただきたいと思います。
その土地の事情に合わせた輸送サービスをなるべくできるように一緒に考えましょうということで進めており、だんだん理解が浸透しつつあるなと思いましたので、よりよくご活用いただけたらと思います。
(問)次の観光立国推進基本計画の議論を始めていくと思いますが、6,000万人、15兆円という大きな目標に向けて政策面での大きなポイントになるのは国際観光旅客税の存在だと思います。次の計画の議論の中で、旅客税の使途の見直しまで踏み込んで議論していくべきか、お考えをお聞かせください。
(答)
令和7年度の観光庁予算案でも約500億円で、一般財源はだんだん少なくなり、旅客税財源の方が多いことから、観光の政策イコール旅客税財源のようなところがあり、また他省庁でも色々使っていただいております。
次の5年の計画に向けては、今具体的なものはないですが、当然、新しい課題が予想されますので、それに対してこういうことをやっていくべきだという内容になると予想されます。
そういった行政ニーズがあった時に、財源が必要になりますので、どのようにそこに対応していくのかという議論は当然あると思います。
年度当初の予算と補正予算で、コロナが落ち着いたここ1年2年ぐらいは、1,000億円くらい他省庁も含めて、観光で使わせていただいているので、それをどのように確保していくのかという議論にはなると思います。
以上