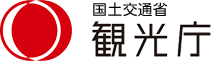秡川長官会見要旨
最終更新日:2025年2月25日
日時:2025年2月19日(水)16:15~17:00
場所:国土交通省会見室
場所:国土交通省会見室
冒頭発言
(訪日外国人旅行者数(2025年1月)について)
今年の1月の訪日外国人旅行者数は約378万人で、一つの月としては過去最高となりました。
昨年の1月と比べますと、伸び率は41%となり、大きく伸びています。
日本人の出国者数は、1月は91万人で、昨年の1月と比べると9%伸びました。
(旅行・観光消費動向調査の結果(2024年年間値及び2024年10-12月期速報)について)
2024年の日本人の国内の旅行者数は約5.4億人で、2019年のコロナ前の9割程度まで回復しました。
1回の旅行における支出額は約4.7万円で、2019年と比べると25%増えています。
それを掛け合わせた消費額は約25兆円で、過去最高です。2019年と比べると15%増えています。
10月から12月の3ヶ月間では人数が約1.3億人で、2019年と同じぐらいの水準です。
1回の旅行支出は約5万円で、2019年と比べると34%増えています。
10月から12月の消費額は6.4兆円で、10月から12月の3ヶ月間としては過去最高です。
今年の1月の訪日外国人旅行者数は約378万人で、一つの月としては過去最高となりました。
昨年の1月と比べますと、伸び率は41%となり、大きく伸びています。
日本人の出国者数は、1月は91万人で、昨年の1月と比べると9%伸びました。
(旅行・観光消費動向調査の結果(2024年年間値及び2024年10-12月期速報)について)
2024年の日本人の国内の旅行者数は約5.4億人で、2019年のコロナ前の9割程度まで回復しました。
1回の旅行における支出額は約4.7万円で、2019年と比べると25%増えています。
それを掛け合わせた消費額は約25兆円で、過去最高です。2019年と比べると15%増えています。
10月から12月の3ヶ月間では人数が約1.3億人で、2019年と同じぐらいの水準です。
1回の旅行支出は約5万円で、2019年と比べると34%増えています。
10月から12月の消費額は6.4兆円で、10月から12月の3ヶ月間としては過去最高です。
質疑応答
(問)1月の訪日外国人旅行者数が発表されましたが、その背景も含めて受け止めをお聞かせください。
続いて、今年の春節について、好調だったと聞いていますが、各地への動向についてお伺いします。また、オーバーツーリズムが問題になったケースもあったかと思いますが、各地で春節に対してどういった対策を行ったのかをお伺いします。
(答)
去年の11月、12月が非常に好調だったので、年明けはどのような感じになるかと、期待と不安が両方あったが、思っていたよりもずいぶん良い数字が出たと思っています。
地域別に見ると、インバウンドの約8割を占めているアジアの国が、前年の1月と比べ40%以上増加しており、欧米諸国でも30%以上増加しています。
要因としては、引き続き日本に対する需要があるということと、日本への航空便も回復しているため、お客様も非常に来やすい状況かと思います。
また、1月については、アジア諸国での春節の休暇に合わせて、さらに需要が高まったと思っています。
今年の春節の状況について、その期間だけの数字は把握できていませんが、中国の現地旅行業界に伺いますと、昨年の春節と比べて、全体的に日本向けの旅行商品の売り上げが非常に良いということでした。
ゴールデンルートや北海道はいつも人気ですが、特に主要都市に地方を周遊するプランを加えたツアー、温泉など日本特有のコンテンツを含む商品の売れ行きが、今年は特に好調だったと聞いております。地方に行って、そういった日本特有のコンテンツを楽しんでいただくことは、とてもありがたいと思います。
日系の航空会社からの情報では、春節期間中の日中間の航空便の搭乗率は、それ以外の期間よりも高かったと聞いております。
中国の旅行会社が実施した市場調査においては、今年の春節旅行の目的地は、中国の国外への海外旅行としては、日本が1位だったということです。
昨年の訪日数は、全体としては非常に良かったですが、中国が2019年に比べて2024年の数字が低かったので、今年はどうなるかと注目していましたが、スタートは非常に良かったということです。引き続き、中国からの旅行客の動向、実績を注視したいと思います。
オーバーツーリズムの問題については、お客様がたくさん来ていただいているのはありがたいことですが、混雑や地域住民の方からするとマナー違反だということをよく指摘を受けていると思っています。
具体的な取り組みとしては、例えば北海道の小樽港の景色を見下ろすことができる景勝地である船見坂の周辺に警備員を配置したり、美瑛町の人気撮影スポットであるクリスマスツリーの木の周辺で、駐車禁止の規制を導入したりしています。
また、京都では、中国の方に広く利用されているSNSを通じて、観光マナーの発信を行ったほか、浅草では、浅草寺や仲見世商店街の周辺で、地域住民だけではなく、観光客も一緒にゴミを拾っていただくイベントを行い、理解を求めるということも実施したということで、地域の実情に応じて、様々な工夫をしてやっていただいていると思います。
観光も楽しんでいただきたいですし、地域住民の方々の生活も大事ですので、引き続き観光庁としてもしっかり支援していきたいと思っています。
(問)地域の観光地域づくりを担うのがDMOの役割だと思いますが、DMOのオーバーツーリズムに対する働きやあり方について長官のお考えをお伺いします。
(答)
DMOのポイントは、狭い意味での観光業種だけではなく、その地域の商業、農業、交通や自治体、住んでいる方も含め、なるべく広い関係者を巻き込むということです。
また、全員で意見を出しつつ、地域がどの方向に向かうのかという作戦を立てて実行し、成果をフィードバックすることも重要です。
また、旅行者の様々な要望や情報をきめ細かく集め、今までの経験やカンだけではなく科学的に分析し、次に生かしていくということをDMOに求めているところです。
オーバーツーリズム対策においては、まさにそのような分析により、何が問題で、旅行者はどういう感覚なのかといったニーズ等を把握しながら、自分の地域に合ったやり方を実施していくことが、とても良い取り組みだと思います。
DMOが中心となって地域の実情に合った観光振興に取り組み、そういった対策でも大きな役割を果たしていただきたいと思います。
(問)春節にも関連しますが、中国人の旅行客に関して、中国系の旅行会社が取り込んでしまい、あまり日本の会社が取り込めていないのではないかという声もあります。実際、空港からホテル、土産物まで中国資本のところばかりを回って、あまり日本にお金が落ちてないというような指摘もあります。
ホテルなどは、繁盛しているところもあるとは思いますが、いずれにしてもだいぶ中華系の皆さんがその辺りを掌握しているというところで、日本の旅行会社にしてはビハインドかと思うのですが、その辺りの問題意識や対策などで考えられることがあればお伺いします。
(答)
中国からの旅行も様々な形態があり、個人で楽しむことができる方も多いですが、引き続き団体で来られている方もいらっしゃいます。
特に、団体で来られている方は、言葉の問題や、彼らが求めているものに対応しやすいという事情もあるかと思いますが、今ご指摘いただいたような形態というのが多いであろうということは承知しています。
そういった手法自体が法令やルールに違反しているわけではないですが、やはり中国人の旅行者のニーズにどれだけ応えられるのかというところがポイントなのだと思います。
我々もJNTOなどと協力して、中国のお客様はどのようなことを求めていて、どういったプロモーションをするとより効果的なのかを分析しながら、今後やっていきたいと思っています。
(問)今回、中国は春節があったこともあり、訪日客が多かったということでしたが、その辺りの背景や理由についてどのように見てらっしゃるのか、また、旅行会社の方からゴールデンルートだけでなく、地方や温泉にも行くような旅行商品の売れ行きもいいというお話もありましたが、そちらについても、背景などあればお伺いします。
(答)
中国からの旅行者は、春節や国慶節で数字が伸びる印象もありますが、毎年の中国人旅行者の動きを見ると、一番多いのは夏でして、春節や国慶節にピークがあるわけではないです。春節にかかわらず1月として多かったということかと思います。
2019年の1月よりも多く、単月で過去最高に近く、12月からの連続性で見ても、大きな数字が出ているとみております。春節期間ということではなく、日本に来る勢いが強いと思います。
地方に行っていただくのもありがたいし、温泉は、欧米の方は慣れていないようですが、中国の方は楽しんで頂けるようです。そういった日本的なものを楽しんでいただけるのは良いことだと思いますので、引き続き伸ばしていきたいと思います。
(問)春節の関係ですが、中国の方だけではないと思いますが、地方にも誘客が進んでいるという手応えのお話がありましたが、交通機関が整っていないところでは、タクシーや貸切バスの役割も大きいと思いますが、そのあたりどのように感じていますか。
(答)
鉄道駅を降りた後のアシに課題のある観光地もあると思いますが、省内では、公共も含めたライドシェアとして、地元の人や観光客のアシとして地元の方策を最大限活用して、そういったニーズに応える取り組みを進めていると思いますので、その活用を広げていきたいと思っています。
(問)Uberさんと電脳交通さんが組んで、地方でUberさんを呼べるようにしたり、都心のタクシー事業者さんでも貸切タクシーで観光地に行けるようなプランを用意し、結構使われているようですが、今後、個人客を取り込んでいくためにどのように事業を展開してほしいとか、こういったプランを用意してほしいとか何かご期待があればお教えください。
(答)
どういうニーズがあって何を求めているのか、ということだと思います。
おっしゃっていただいたリムジン的に、タクシーで1日、2日回るのは、一見高く見えますが、利用されている方にとっては、様々なところにきめ細かく行けますし、いいわけです。
そういうニーズがあることをキャッチして、そういうサービスを始めたと思うので、各社さんアンテナ高くして、いいことだと思います。
(問)スポーツ庁と文化庁と三庁で包括連携協定を今月締結されました。まだ始まったばかりだと思いますが、今どのような進捗で、今後どういうところに力入れていきたいかをお願いします。
(答)
連携協定をしたから、何か新しいことをやりましょうとか、今までできてなかったので新規で何かやりましょうというよりは、今までもお互い連携してやってきましたし、すごく親和性がありますので、引き続き、やっていきましょうということです。
そういったことを改めて確認し、トップ同士が会って話をできる関係を続けていくことも非常に大事だという話もでき、良かったと思います。
(問)欧米のお客様に対してですが、観光庁では、英米仏のメディアファム実証事業を展開されており、1月にも実際にファムツアーを実施されたと思います。改めてこの事業を展開した背景とファムツアーを通して見えてきた日本旅館の活用や海外への情報発信の課題などについて、改めてお聞かせください。
(答)
2023年を2019年と比べると、泊まった場所として、ビジネスホテルやシティホテルの割合は高いですが、旅館の割合は下がっています。
外国の方は、慣れたところに泊まりたいという気持ちもあり、なじみのない旅館は、選択肢になりにくいということもあるかと思います。
旅館は、日本の文化、温泉、食事など日本的なものを感じていただくという点で良いことと思いますが、特に欧米の方はあまり利用されてないということでした。
ですので、欧米の影響力のある方に体験してもらい、良いと思っていただきたいし、そういう方たちの目から見たご指摘もいただいて、生かしていけたらということで、事業をやっております。
たとえば、タトゥーをしている人への対応について、日本と海外の文化の違いを踏まえて、どう対処するのかについて何か得られないかとも考えておりますし、例えば、高低差がない玄関で、どこで靴を脱げば良いかなど、日本人には普通でも外国の方としては違和感がある部分はいろいろあるようです。
1月、2月で、いくつかの地方で、違った国の方に来ていただいて事業をしており、それらを集約するような作業をしております。
その成果を、旅館にフィードバックしていくとともに、ファムツアーの参加者が感じたことを、お帰りになった後でいろいろ発信していただいて、旅館に対する興味が広がったり、商品造成に繋がってほしいと考えております。
(問)春節について、今年は中国の方の訪日が日本は1位になった理由の分析の部分で、1月に中国の有名人がタイでミャンマーの詐欺団に拉致された影響で、中国人がタイに行くことに怖がり、キャンセルが相次いだという報道があったのですけれども、そういった影響があるのか、あるいは純粋にプロモーションが効いて、日本に対する評価が高まっているのかその辺の分析を教えてください。
(答)
報道される、されないに関わらず、毎月良いイベントも悪いイベントも起こっている中で、トレンドというのはあるかと思います。コロナは特別なので、数字が下がりましたが、毎月いろいろなことが起こっているにもかかわらず、毎年の変動で見ると、国ごとに一定です。
なので、1月が大きく出たというのは今おっしゃった要因もあるのかもしれませんが、2月、3月がどのようになるかということは注目しています。
(問)会計検査院が発表した旅行支援策に関する調査結果についてお聞きします。重要書類の保存ですとか、制度開始後のいくつかの変更点や、運営上の問題点といいますか、まずさというところが指摘されていました。これに対して改めてどういうふうに受け止めていらっしゃるかということと、算出根拠となる資料がないので難しいかもしれないですが、会計検査院が試算した、予算配分額、交付限度額等の乖離というのはかなり大きかったと思うのですけどもそれに関してもどのように捉えていたのかお聞かせください。
(答)
会計検査院にいろいろご指摘いただいて、全て事実なので反省して今後に生かすということに尽きます。
確かに旅行支援というのは、大きくやらせていただきましたが、刻々とニーズが変わり、また状況も変わる中で、機敏にやってくださいという部分があり、その中で我々としてはベストを尽くしたつもりではあるのですが、後から落ち着いた状態で会計検査院に見ていただくと、いろんなところがご指摘をいただいたというのも事実ですし、ご指摘はごもっともです。
今、能登は、現場の復興に注力しているので、旅行支援はまだ先かもしれないですが、そうなった時に、ご指摘いただいたようなことがまた起こらないように、きちんと活かしていくということを一生懸命やっていきたいと思っております。
(問)交付限度額の試算に関して何かお感じになったことはありますか。
(答)
過去にどれくらい旅行者が来ていて、ある県は他の県に比べてどのようになっているか、というようなデータで按分をしつつ、そのときの状況や、直近どうなっているのかといった要素を加味して、使っていただく額を決めました。
後から落ち着いた状態でもう1回検証してみると、数字が違うというご指摘があるとすれば、ものすごく違うということはおそらくないと思いますが、ある県に比べて他の県が何倍だ、という部分で違いが出てきているのかなと思います。
コロナの時に、なるべく早く支援をして、人を動かしてくださいという要求がすごく高かったこともあり、時間をかけてじっくりやるというやり方もあったのかもしれませんが、スピード感も相当求められた中でやったということです。
いずれにしても、今回ご指摘いただいているわけですから、次回以降にそれを生かしていくということだと思っています。
(問)今日同時に発表があった旅行観光消費動向調査です。コロナ前よりも、お客様は戻ってないけれども、消費額はすごく伸びているという、要は物価高で特に宿泊費なんかも高騰してこういう結果になっていると思うのですが、こちらに対する評価と、今年どうなりそうか、こんなに物価高が続いたら旅行もシュリンクしそうな気もしますが、逆に何か伸びる要素が何かあるかなど、その辺りの見立てを伺いたいと思います。
(答)
日本人の旅で言うと、国内旅行はぼちぼちですが、アウトバウンド、つまり海外旅行者数はコロナ前と比べると戻っていない状況です。
したがって、日本人の旅に行ってみたいという気持ちがまだ100%戻っていないとは思いますが、元々宿泊にしても、旅行業にしても、単価が安すぎるというお話はずいぶんあったかと思います。他の物価も上がっているという中での話ではありますが、きちんとコストに見合った値段がとれるようになってきていると考えれば、今まで課題だったことというのは少しずつ実現できているという面もあるのではないかと思っています。
(問)過去のコロナ前の値段は、むしろ安すぎたというようなことでしょうか。
(答)
サービスの対価ですから、旅行にしても宿泊にしても、それがどういう値段をつけるかはそれぞれだと思いますが、コロナの前にいろいろお話を伺っていても、適正な利潤が出るというところまでの値段がつけられるかといえばなかなか難しいという声が結構ありました。値段が高くなるということはありますが、やはり適正な利潤をきちんと取って、従業員さんにも払って、人を確保するという、順回転に入りたいのですけれど、なかなかそこが難しいというのが、長年この業界の悩みです。
ですから、きちんとしたサービスをしていただいているのであれば、その対価を、きちんと取るっていうのは、別に悪いことではないと思います。
利用者にとっては値段が上がるとちょっと行きにくくなると思ってしまうかもしれないのですけれど、そこはそういう考え方でいいのではないかと思います。
(問)外国人が増えたりとか、外国人向けに結構値段が高いものとかが出たりとか、二重価格もありますけれども、そういう傾向自体はそんなに好ましくないものではないというところでしょうか。
(答)
民間の事業は商売ですので、値づけというのが一番の商売の根幹なので、どういうお客様を狙ってどういう値段をつけるのかというのは、まさにそれぞれ個々の事業者の判断だと思います。ですから、良い悪いではないと思います。
ただ、こういう時代でも結構安くやっている方もいらっしゃるので、狙っている客層が違うのだと思います。
(問)先般、雇用調整助成金のHISの子会社による不適正受給の指摘があったという点で、ちょうど1年前ぐらいに、業界でコンプライアンス遵守に関する今後の再発防止に向けた議論が進められて具体的な取り組み等々をまとめられたと思います。ほぼ1年が経過する中で改めて旅行業界の法令順守、コンプライアンス遵守に関する取り組みの現状をどのように見ていらっしゃるかお伺いします。
(答)
今おっしゃっていただいた通り、1年ぐらい前からそのような事案があり、ちゃんとやってくださいというのはかなり厳しく申し上げたつもりですが、今回こういう事案が起こっているというのが非常に残念というか、良くないことだと思います。
HISに対しては、コンプライアンス遵守の徹底を求める指導をもう一度させていただいたところです。
内容を見たところ、本当に悪い事例もありますし、制度に対する理解が不十分で、悪意はなくとも、結果的に見ると、もらいすぎていたということもあります。
そういったところをきちんと理解してもらいながら支援を受けるということは大事なので、そこはきちんとやってくださいということを申し上げました。
今回はHISということなのですが、こういった事案がまたあったということは、業界全体で非常に良くないことだと、業界としても認識しておりますので、きちんとやっていただくきっかけになればと思っております。
続いて、今年の春節について、好調だったと聞いていますが、各地への動向についてお伺いします。また、オーバーツーリズムが問題になったケースもあったかと思いますが、各地で春節に対してどういった対策を行ったのかをお伺いします。
(答)
去年の11月、12月が非常に好調だったので、年明けはどのような感じになるかと、期待と不安が両方あったが、思っていたよりもずいぶん良い数字が出たと思っています。
地域別に見ると、インバウンドの約8割を占めているアジアの国が、前年の1月と比べ40%以上増加しており、欧米諸国でも30%以上増加しています。
要因としては、引き続き日本に対する需要があるということと、日本への航空便も回復しているため、お客様も非常に来やすい状況かと思います。
また、1月については、アジア諸国での春節の休暇に合わせて、さらに需要が高まったと思っています。
今年の春節の状況について、その期間だけの数字は把握できていませんが、中国の現地旅行業界に伺いますと、昨年の春節と比べて、全体的に日本向けの旅行商品の売り上げが非常に良いということでした。
ゴールデンルートや北海道はいつも人気ですが、特に主要都市に地方を周遊するプランを加えたツアー、温泉など日本特有のコンテンツを含む商品の売れ行きが、今年は特に好調だったと聞いております。地方に行って、そういった日本特有のコンテンツを楽しんでいただくことは、とてもありがたいと思います。
日系の航空会社からの情報では、春節期間中の日中間の航空便の搭乗率は、それ以外の期間よりも高かったと聞いております。
中国の旅行会社が実施した市場調査においては、今年の春節旅行の目的地は、中国の国外への海外旅行としては、日本が1位だったということです。
昨年の訪日数は、全体としては非常に良かったですが、中国が2019年に比べて2024年の数字が低かったので、今年はどうなるかと注目していましたが、スタートは非常に良かったということです。引き続き、中国からの旅行客の動向、実績を注視したいと思います。
オーバーツーリズムの問題については、お客様がたくさん来ていただいているのはありがたいことですが、混雑や地域住民の方からするとマナー違反だということをよく指摘を受けていると思っています。
具体的な取り組みとしては、例えば北海道の小樽港の景色を見下ろすことができる景勝地である船見坂の周辺に警備員を配置したり、美瑛町の人気撮影スポットであるクリスマスツリーの木の周辺で、駐車禁止の規制を導入したりしています。
また、京都では、中国の方に広く利用されているSNSを通じて、観光マナーの発信を行ったほか、浅草では、浅草寺や仲見世商店街の周辺で、地域住民だけではなく、観光客も一緒にゴミを拾っていただくイベントを行い、理解を求めるということも実施したということで、地域の実情に応じて、様々な工夫をしてやっていただいていると思います。
観光も楽しんでいただきたいですし、地域住民の方々の生活も大事ですので、引き続き観光庁としてもしっかり支援していきたいと思っています。
(問)地域の観光地域づくりを担うのがDMOの役割だと思いますが、DMOのオーバーツーリズムに対する働きやあり方について長官のお考えをお伺いします。
(答)
DMOのポイントは、狭い意味での観光業種だけではなく、その地域の商業、農業、交通や自治体、住んでいる方も含め、なるべく広い関係者を巻き込むということです。
また、全員で意見を出しつつ、地域がどの方向に向かうのかという作戦を立てて実行し、成果をフィードバックすることも重要です。
また、旅行者の様々な要望や情報をきめ細かく集め、今までの経験やカンだけではなく科学的に分析し、次に生かしていくということをDMOに求めているところです。
オーバーツーリズム対策においては、まさにそのような分析により、何が問題で、旅行者はどういう感覚なのかといったニーズ等を把握しながら、自分の地域に合ったやり方を実施していくことが、とても良い取り組みだと思います。
DMOが中心となって地域の実情に合った観光振興に取り組み、そういった対策でも大きな役割を果たしていただきたいと思います。
(問)春節にも関連しますが、中国人の旅行客に関して、中国系の旅行会社が取り込んでしまい、あまり日本の会社が取り込めていないのではないかという声もあります。実際、空港からホテル、土産物まで中国資本のところばかりを回って、あまり日本にお金が落ちてないというような指摘もあります。
ホテルなどは、繁盛しているところもあるとは思いますが、いずれにしてもだいぶ中華系の皆さんがその辺りを掌握しているというところで、日本の旅行会社にしてはビハインドかと思うのですが、その辺りの問題意識や対策などで考えられることがあればお伺いします。
(答)
中国からの旅行も様々な形態があり、個人で楽しむことができる方も多いですが、引き続き団体で来られている方もいらっしゃいます。
特に、団体で来られている方は、言葉の問題や、彼らが求めているものに対応しやすいという事情もあるかと思いますが、今ご指摘いただいたような形態というのが多いであろうということは承知しています。
そういった手法自体が法令やルールに違反しているわけではないですが、やはり中国人の旅行者のニーズにどれだけ応えられるのかというところがポイントなのだと思います。
我々もJNTOなどと協力して、中国のお客様はどのようなことを求めていて、どういったプロモーションをするとより効果的なのかを分析しながら、今後やっていきたいと思っています。
(問)今回、中国は春節があったこともあり、訪日客が多かったということでしたが、その辺りの背景や理由についてどのように見てらっしゃるのか、また、旅行会社の方からゴールデンルートだけでなく、地方や温泉にも行くような旅行商品の売れ行きもいいというお話もありましたが、そちらについても、背景などあればお伺いします。
(答)
中国からの旅行者は、春節や国慶節で数字が伸びる印象もありますが、毎年の中国人旅行者の動きを見ると、一番多いのは夏でして、春節や国慶節にピークがあるわけではないです。春節にかかわらず1月として多かったということかと思います。
2019年の1月よりも多く、単月で過去最高に近く、12月からの連続性で見ても、大きな数字が出ているとみております。春節期間ということではなく、日本に来る勢いが強いと思います。
地方に行っていただくのもありがたいし、温泉は、欧米の方は慣れていないようですが、中国の方は楽しんで頂けるようです。そういった日本的なものを楽しんでいただけるのは良いことだと思いますので、引き続き伸ばしていきたいと思います。
(問)春節の関係ですが、中国の方だけではないと思いますが、地方にも誘客が進んでいるという手応えのお話がありましたが、交通機関が整っていないところでは、タクシーや貸切バスの役割も大きいと思いますが、そのあたりどのように感じていますか。
(答)
鉄道駅を降りた後のアシに課題のある観光地もあると思いますが、省内では、公共も含めたライドシェアとして、地元の人や観光客のアシとして地元の方策を最大限活用して、そういったニーズに応える取り組みを進めていると思いますので、その活用を広げていきたいと思っています。
(問)Uberさんと電脳交通さんが組んで、地方でUberさんを呼べるようにしたり、都心のタクシー事業者さんでも貸切タクシーで観光地に行けるようなプランを用意し、結構使われているようですが、今後、個人客を取り込んでいくためにどのように事業を展開してほしいとか、こういったプランを用意してほしいとか何かご期待があればお教えください。
(答)
どういうニーズがあって何を求めているのか、ということだと思います。
おっしゃっていただいたリムジン的に、タクシーで1日、2日回るのは、一見高く見えますが、利用されている方にとっては、様々なところにきめ細かく行けますし、いいわけです。
そういうニーズがあることをキャッチして、そういうサービスを始めたと思うので、各社さんアンテナ高くして、いいことだと思います。
(問)スポーツ庁と文化庁と三庁で包括連携協定を今月締結されました。まだ始まったばかりだと思いますが、今どのような進捗で、今後どういうところに力入れていきたいかをお願いします。
(答)
連携協定をしたから、何か新しいことをやりましょうとか、今までできてなかったので新規で何かやりましょうというよりは、今までもお互い連携してやってきましたし、すごく親和性がありますので、引き続き、やっていきましょうということです。
そういったことを改めて確認し、トップ同士が会って話をできる関係を続けていくことも非常に大事だという話もでき、良かったと思います。
(問)欧米のお客様に対してですが、観光庁では、英米仏のメディアファム実証事業を展開されており、1月にも実際にファムツアーを実施されたと思います。改めてこの事業を展開した背景とファムツアーを通して見えてきた日本旅館の活用や海外への情報発信の課題などについて、改めてお聞かせください。
(答)
2023年を2019年と比べると、泊まった場所として、ビジネスホテルやシティホテルの割合は高いですが、旅館の割合は下がっています。
外国の方は、慣れたところに泊まりたいという気持ちもあり、なじみのない旅館は、選択肢になりにくいということもあるかと思います。
旅館は、日本の文化、温泉、食事など日本的なものを感じていただくという点で良いことと思いますが、特に欧米の方はあまり利用されてないということでした。
ですので、欧米の影響力のある方に体験してもらい、良いと思っていただきたいし、そういう方たちの目から見たご指摘もいただいて、生かしていけたらということで、事業をやっております。
たとえば、タトゥーをしている人への対応について、日本と海外の文化の違いを踏まえて、どう対処するのかについて何か得られないかとも考えておりますし、例えば、高低差がない玄関で、どこで靴を脱げば良いかなど、日本人には普通でも外国の方としては違和感がある部分はいろいろあるようです。
1月、2月で、いくつかの地方で、違った国の方に来ていただいて事業をしており、それらを集約するような作業をしております。
その成果を、旅館にフィードバックしていくとともに、ファムツアーの参加者が感じたことを、お帰りになった後でいろいろ発信していただいて、旅館に対する興味が広がったり、商品造成に繋がってほしいと考えております。
(問)春節について、今年は中国の方の訪日が日本は1位になった理由の分析の部分で、1月に中国の有名人がタイでミャンマーの詐欺団に拉致された影響で、中国人がタイに行くことに怖がり、キャンセルが相次いだという報道があったのですけれども、そういった影響があるのか、あるいは純粋にプロモーションが効いて、日本に対する評価が高まっているのかその辺の分析を教えてください。
(答)
報道される、されないに関わらず、毎月良いイベントも悪いイベントも起こっている中で、トレンドというのはあるかと思います。コロナは特別なので、数字が下がりましたが、毎月いろいろなことが起こっているにもかかわらず、毎年の変動で見ると、国ごとに一定です。
なので、1月が大きく出たというのは今おっしゃった要因もあるのかもしれませんが、2月、3月がどのようになるかということは注目しています。
(問)会計検査院が発表した旅行支援策に関する調査結果についてお聞きします。重要書類の保存ですとか、制度開始後のいくつかの変更点や、運営上の問題点といいますか、まずさというところが指摘されていました。これに対して改めてどういうふうに受け止めていらっしゃるかということと、算出根拠となる資料がないので難しいかもしれないですが、会計検査院が試算した、予算配分額、交付限度額等の乖離というのはかなり大きかったと思うのですけどもそれに関してもどのように捉えていたのかお聞かせください。
(答)
会計検査院にいろいろご指摘いただいて、全て事実なので反省して今後に生かすということに尽きます。
確かに旅行支援というのは、大きくやらせていただきましたが、刻々とニーズが変わり、また状況も変わる中で、機敏にやってくださいという部分があり、その中で我々としてはベストを尽くしたつもりではあるのですが、後から落ち着いた状態で会計検査院に見ていただくと、いろんなところがご指摘をいただいたというのも事実ですし、ご指摘はごもっともです。
今、能登は、現場の復興に注力しているので、旅行支援はまだ先かもしれないですが、そうなった時に、ご指摘いただいたようなことがまた起こらないように、きちんと活かしていくということを一生懸命やっていきたいと思っております。
(問)交付限度額の試算に関して何かお感じになったことはありますか。
(答)
過去にどれくらい旅行者が来ていて、ある県は他の県に比べてどのようになっているか、というようなデータで按分をしつつ、そのときの状況や、直近どうなっているのかといった要素を加味して、使っていただく額を決めました。
後から落ち着いた状態でもう1回検証してみると、数字が違うというご指摘があるとすれば、ものすごく違うということはおそらくないと思いますが、ある県に比べて他の県が何倍だ、という部分で違いが出てきているのかなと思います。
コロナの時に、なるべく早く支援をして、人を動かしてくださいという要求がすごく高かったこともあり、時間をかけてじっくりやるというやり方もあったのかもしれませんが、スピード感も相当求められた中でやったということです。
いずれにしても、今回ご指摘いただいているわけですから、次回以降にそれを生かしていくということだと思っています。
(問)今日同時に発表があった旅行観光消費動向調査です。コロナ前よりも、お客様は戻ってないけれども、消費額はすごく伸びているという、要は物価高で特に宿泊費なんかも高騰してこういう結果になっていると思うのですが、こちらに対する評価と、今年どうなりそうか、こんなに物価高が続いたら旅行もシュリンクしそうな気もしますが、逆に何か伸びる要素が何かあるかなど、その辺りの見立てを伺いたいと思います。
(答)
日本人の旅で言うと、国内旅行はぼちぼちですが、アウトバウンド、つまり海外旅行者数はコロナ前と比べると戻っていない状況です。
したがって、日本人の旅に行ってみたいという気持ちがまだ100%戻っていないとは思いますが、元々宿泊にしても、旅行業にしても、単価が安すぎるというお話はずいぶんあったかと思います。他の物価も上がっているという中での話ではありますが、きちんとコストに見合った値段がとれるようになってきていると考えれば、今まで課題だったことというのは少しずつ実現できているという面もあるのではないかと思っています。
(問)過去のコロナ前の値段は、むしろ安すぎたというようなことでしょうか。
(答)
サービスの対価ですから、旅行にしても宿泊にしても、それがどういう値段をつけるかはそれぞれだと思いますが、コロナの前にいろいろお話を伺っていても、適正な利潤が出るというところまでの値段がつけられるかといえばなかなか難しいという声が結構ありました。値段が高くなるということはありますが、やはり適正な利潤をきちんと取って、従業員さんにも払って、人を確保するという、順回転に入りたいのですけれど、なかなかそこが難しいというのが、長年この業界の悩みです。
ですから、きちんとしたサービスをしていただいているのであれば、その対価を、きちんと取るっていうのは、別に悪いことではないと思います。
利用者にとっては値段が上がるとちょっと行きにくくなると思ってしまうかもしれないのですけれど、そこはそういう考え方でいいのではないかと思います。
(問)外国人が増えたりとか、外国人向けに結構値段が高いものとかが出たりとか、二重価格もありますけれども、そういう傾向自体はそんなに好ましくないものではないというところでしょうか。
(答)
民間の事業は商売ですので、値づけというのが一番の商売の根幹なので、どういうお客様を狙ってどういう値段をつけるのかというのは、まさにそれぞれ個々の事業者の判断だと思います。ですから、良い悪いではないと思います。
ただ、こういう時代でも結構安くやっている方もいらっしゃるので、狙っている客層が違うのだと思います。
(問)先般、雇用調整助成金のHISの子会社による不適正受給の指摘があったという点で、ちょうど1年前ぐらいに、業界でコンプライアンス遵守に関する今後の再発防止に向けた議論が進められて具体的な取り組み等々をまとめられたと思います。ほぼ1年が経過する中で改めて旅行業界の法令順守、コンプライアンス遵守に関する取り組みの現状をどのように見ていらっしゃるかお伺いします。
(答)
今おっしゃっていただいた通り、1年ぐらい前からそのような事案があり、ちゃんとやってくださいというのはかなり厳しく申し上げたつもりですが、今回こういう事案が起こっているというのが非常に残念というか、良くないことだと思います。
HISに対しては、コンプライアンス遵守の徹底を求める指導をもう一度させていただいたところです。
内容を見たところ、本当に悪い事例もありますし、制度に対する理解が不十分で、悪意はなくとも、結果的に見ると、もらいすぎていたということもあります。
そういったところをきちんと理解してもらいながら支援を受けるということは大事なので、そこはきちんとやってくださいということを申し上げました。
今回はHISということなのですが、こういった事案がまたあったということは、業界全体で非常に良くないことだと、業界としても認識しておりますので、きちんとやっていただくきっかけになればと思っております。
以上