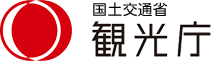秡川長官会見要旨
最終更新日:2025年4月3日
日時:2025年3月19日(水)16:15~16:40
場所:国土交通省会見室
場所:国土交通省会見室
冒頭発言
(訪日外国人旅行者数(2025年2月)について)
今年の2月の訪日外国人旅行者数は約326万人でした。
2月単月としては初めて300万人を超え、昨年の2月と比べると 17% 増えています。
日本人の出国者数は、2月は118万人で、昨年の2月に比べると 21% 伸びました。
(アウトバウンド促進に関する共同会見について)
アウトバウンドの促進に関する共同会見を、来週月曜日に予定しています。
コロナ後のアウトバンドの回復状況を踏まえ、官民一体でアウトバウンド促進に向けた取組を進め、海外旅行の機運の醸成を図りたいと思います。
来週24日月曜日に、外務省及び日本旅行業協会と共同で会見を行いますので、ご都合がよろしければぜひお越しください。
今年の2月の訪日外国人旅行者数は約326万人でした。
2月単月としては初めて300万人を超え、昨年の2月と比べると 17% 増えています。
日本人の出国者数は、2月は118万人で、昨年の2月に比べると 21% 伸びました。
(アウトバウンド促進に関する共同会見について)
アウトバウンドの促進に関する共同会見を、来週月曜日に予定しています。
コロナ後のアウトバンドの回復状況を踏まえ、官民一体でアウトバウンド促進に向けた取組を進め、海外旅行の機運の醸成を図りたいと思います。
来週24日月曜日に、外務省及び日本旅行業協会と共同で会見を行いますので、ご都合がよろしければぜひお越しください。
質疑応答
(問)2月の訪日旅行者数が発表され、中華圏の春節期の数字も含めた結果が出た形かと思いますが、長官の受け止めについてお伺いします。また、これを踏まえて、今年の目標や見通しがあれば、教えてください。
(答)
地域別でみますと、インバウンド全体の約8割を占めているアジアの国が、去年と比べて 10% 以上伸びています。
また、欧米諸国はさらに伸びていて、前の年に比べると 30% 以上増加しています。
分析としては、春節の期間が年によって動くということで、昨年は2月がメインだった春節の休暇が、今年は、ほとんどの国で1月であったため、2月の訪日者数は1月よりは減少しています。
ですが、春節休暇が2月だった去年と比べても、今年の2月のインバウンドの数字は増加していますので、1月よりは落ちていますが、引き続き好調だと思っています。
今年の見通しについては、1月の数字がとてもよく、2月はまあまあという感じなので、引き続きこの調子でいってもらえたらと思っています。
(問)来年度までの政府の観光立国推進基本計画で、インバウンド数やインバウンド消費額などすでに達成した目標や、地方2泊などまだ未達の目標がある中、今後次の計画を検討していくことになると思いますが、次期計画において盛り込みたい観点や重点を置きたい内容、2030年目標に向けた中間目標の設定はあるのかなど、長官のお考えをお聞かせください。
(答)
2024年の訪日数は過去最高で目標を達成していますが、地方部の訪日外国人の一人当たりの宿泊数2泊という目標が去年は 1.36泊とまだ達成できておりません。
昨日、第26回観光立国推進閣僚会議が開かれ、総理から、地方誘客をより一層促進すること、持続可能な観光を推進すること、2026年から2030年までの観光立国推進基本計画を策定すること、についてご指示をいただきました。
新たな基本計画については、現在の計画の目標の達成状況や総理からのご指示を踏まえ、地方誘客及び持続可能な観光に留意して、今後、どういう取組が求められるのか、検討を行っていくことになります。
中間的な目標は、今のところ特段考えておりませんが、これまでは2020年訪日客数4,000万人という目標があり、昨年はそれに近い数字が出ましたので、それも1つ頭に置きながら6,000万人を目指していくということになるかと思います。
(問)大阪・関西万博の開幕まであと一か月を切りました。海外からの万博関連の訪日ツアーの内容や販売状況について、現時点で観光庁として把握していることがあればお伺いします。
(答)
大阪・関西万博が近づいてきました。インバウンドを含めて多くのお客様が来ていただけると思いますが、観光庁としては万博をきっかけに万博プラスその他の観光を楽しんでいただき、できるだけ日本全国に行って頂くようにしたいと考えています。
JNTOが先月、中国市場の旅行会社約100社を対象に、万博関係の旅行商品の造成状況についてアンケートを実施しましたが、27%はすでに商品を作っており、65%が商品造成を予定していますという回答がありました。
ゴールデンルートや関西周遊旅行に万博を組み込んだような商品もすでに販売されているようです。
万博が近づきまして、各国のパビリオンやナショナルデーの情報が発信されてきておりますので、観光庁でもJNTOを通じて、万博情報の発信を強化しています。万博に対する認知度や関心は、これから東アジア中心に高まっていくと思いますが、ツアーの販売もしっかりサポートしていきたいと思っています。
(問)今月末で日米観光交流年が終わる見込みかと思いますが、その振り返りと4月以降同じ取組の延長を検討されているか、または他の日米間の観光促進の取り組みを何か検討されているか、お伺いします。
(答)
日米観光交流年は、昨年1月から今年の3月まで、スポーツや姉妹都市交流をテーマに、相互に観光交流の強化を図るということで進めてきました。
成果としては、アジア諸国の訪日客数が2019年のコロナ前のピークと比較して10% 伸びたことに比べて、アメリカ市場は58%伸び、国・地域別の訪日者数の順位も4位になりました。
一方で、円安や米国の物価上昇など色々要因はあろうかと思いますが、アウトバウンドはインバウンドほど伸びていない状況です。
ちょうど、メジャーリーグベースボールが開幕し、昨日、今日と試合がありますが、ロサンゼルスやシカゴの観光局の方も来られています。
話を聞くと、日本人選手がすごく活躍しているし、野球を見に行くためにアメリカに行く日本人も増えているということです。
今回、2日間ですけども、こういった機会を起爆剤にして、実際アメリカに行って野球を見ていただく方を今年はもっと増やしたいし、月曜日のレセプションには日本の旅行会社も参加していて、ぜひそういうところを伸ばしていきたいという話になりました。
今年は万博もありますので、さらに行き来が増えることを期待しています。
(問)日米間の取組は、今のところ新しくやる予定はないでしょうか。
(答)
交流年という形ではありませんが、日々の機会を活用して、引き続き交流を伸ばしていきたいと考えています。
(問)万博は、日本国内でも前売り券の話題が出るなど、関心、盛り上がりがいまいちとも言われていますが、日本人の国内旅行としての万博についての受け止めをお願いします。また、万博関連ツアーの売れ行きについて、把握していることがあれば、教えていただきたいと思います。
(答)
観光庁でも経産省や博覧会協会と連携して、旅行業協会に何回かお伺いしています。実際にお客様に万博に行って頂くために、チケットをどう売るか、どう旅行商品にしてもらうかが大事ということで、年末、年明けから活動をしています。
万博の進捗状況やどういった出し物があるのかなどを説明し、万博のチケットと組み合わせた旅行商品の造成を旅行業界にお願いしてきたところです。
旅行業界に聞き取りを行ったところ、直近では約 250の万博関係の旅行商品を造成していただいているということで、中には鳥取砂丘や有馬温泉といった地方の観光地も組み込んだ商品も販売されているとのことです。
販売状況はまだ分かりませんが、着実にその予約数を伸ばしている商品もあると聞いていますので、万博が近づいて、そのトレンドが強まればよいと思っています。
(問)最新の宿泊統計でもコロナ前と比較するとインバウンドの三大都市圏への集中が進んでいます。観光庁としても地方誘客を進めている中ですが、それに逆行する形になってしまっていることについて要因をどのように分析されていますか。また、今の対策でこのような現状になってしまっている中で、今後より一層地方誘客を推進するためにどのような対策を考えているのか教えてください。
(答)
宿泊統計によると、2024年の外国人の延べ宿泊者数 は約1.6 億人泊で、コロナ前の一番よかった2019年が、約1.1 億人泊だったので、全体は非常に伸びています。
ただ、2019年の大都市と地方の比率が6対4であったものが、去年は7対3になって大都市の方が多いという状況です。
都道府県別でも、東京、大阪、京都の三都府に限ってみても全体の6割です。
一方で、地方に泊まった方の絶対数は、2019年は 4,300 万人泊に対して2024年は5,000万人泊なので、伸びていますが、三大都市圏の方がより伸びているという状況です。
去年来ていただいたお客さまの人数としては、全体が伸びていますが、特に欧米諸国が伸びました。
細かい一人一人の分析はありませんが、おそらく初めて日本に行ってみようと思われた方が結構おられ、初めて来る時はやはり東京や大阪に行く傾向かと思います。
初めての方が来ていただいたらそこが増えるというのは自然なことで、2回目以降は同じところではなくて地方もいいですよということを一生懸命やっていくことが大事だと思います。
今までやっていることが効き目がないということではなく、引き続き、地方に素敵な観光地を作るということを引き続き行いつつ、地方も素敵な観光地がありますというお知らせをしていくことが大事だと思っています。
(問)訪日客数に関連して、宿泊税についてお伺いします。全国で宿泊税の導入や検討が広がっていますが、観光産業や地元住民への影響なども含め、これらの動きに関する長官の受け止めをお伺いします。
(答)
全国各地で、観光をきっかけにして、自主的な財源を確保する方法の一つとして、宿泊税を導入・検討している自治体が増えていることは承知しています。
観光の様々な政策の実現や問題に対処するために、独自の財源を確保するということは、世界中で非常にうまくいっている観光地において、地方公共団体やDMOが実践している取組であり、そういった取組自体は良いことではないかと思っています。
宿泊税については、地域の魅力を高め、観光振興を図ること等を目的に導入の是非や税額が判断されるものですので、地方公共団体や宿泊事業者をはじめとする関係者の方々の間でよく議論していただいて、その方針を決めていただくのが良いと思っています。
(問)アウトバンドの関連で、3月24日に改めて発表があると思いますが、前回の海外旅行喚起のキャンペーンが2023年で、少し時間が空いていますが、このタイミングでアウトバンドの喚起をする意義をお伺いします。
(答)
コロナ前の2019年には、インバウンドはもちろん、アウトバウンドも非常に良く、出国日本人数は2,000万人程いたかと思います。
コロナでそれぞれゼロに近くなってしまい、その後の回復ぶりがインバウンドは急激ですが、アウトバウンドの回復のスピード感がそれほどではないという状況です。
数字を見ますと、先月の日本人の出国者数は、去年と比べると 21% くらい増えているということなので、徐々に増加していますが、インバウンドほど急激には戻っていないと思っています。
若者の国際交流に資する海外教育旅行の取組や各国の政府観光局と連携した双方向の交流の活性化を進めるほか、関係者と連携しながらアウトバウンドの回復に向けて取組む必要があると思います。
文科省の方に聞くと、海外教育旅行に定期的に行っていた学校もコロナでやめてしまうと、再開するのはなかなかハードルが高いと聞きますので、そういったところも含めて今後機運醸成をしていきたいと思います。
(問)インバウンドの人数について、今年の2月は、多くの国で春節に当たらないことやそもそも日数が少ないという状況の中で、単月でも300万人を超えているということですが、その理由についてどのように考えているかお伺いします。
(答)
2月単月でどうかというよりは、特に去年の年末くらいから、中国もだいぶ戻ってきて、すべての国で前の年を上回るような状況となっています。
ですから、今日ご紹介したのは2月を切り取った数字ですが、そういった調子の良いトレンドは引き続き続いているという中での断面の一つだと思っています。
(答)
地域別でみますと、インバウンド全体の約8割を占めているアジアの国が、去年と比べて 10% 以上伸びています。
また、欧米諸国はさらに伸びていて、前の年に比べると 30% 以上増加しています。
分析としては、春節の期間が年によって動くということで、昨年は2月がメインだった春節の休暇が、今年は、ほとんどの国で1月であったため、2月の訪日者数は1月よりは減少しています。
ですが、春節休暇が2月だった去年と比べても、今年の2月のインバウンドの数字は増加していますので、1月よりは落ちていますが、引き続き好調だと思っています。
今年の見通しについては、1月の数字がとてもよく、2月はまあまあという感じなので、引き続きこの調子でいってもらえたらと思っています。
(問)来年度までの政府の観光立国推進基本計画で、インバウンド数やインバウンド消費額などすでに達成した目標や、地方2泊などまだ未達の目標がある中、今後次の計画を検討していくことになると思いますが、次期計画において盛り込みたい観点や重点を置きたい内容、2030年目標に向けた中間目標の設定はあるのかなど、長官のお考えをお聞かせください。
(答)
2024年の訪日数は過去最高で目標を達成していますが、地方部の訪日外国人の一人当たりの宿泊数2泊という目標が去年は 1.36泊とまだ達成できておりません。
昨日、第26回観光立国推進閣僚会議が開かれ、総理から、地方誘客をより一層促進すること、持続可能な観光を推進すること、2026年から2030年までの観光立国推進基本計画を策定すること、についてご指示をいただきました。
新たな基本計画については、現在の計画の目標の達成状況や総理からのご指示を踏まえ、地方誘客及び持続可能な観光に留意して、今後、どういう取組が求められるのか、検討を行っていくことになります。
中間的な目標は、今のところ特段考えておりませんが、これまでは2020年訪日客数4,000万人という目標があり、昨年はそれに近い数字が出ましたので、それも1つ頭に置きながら6,000万人を目指していくということになるかと思います。
(問)大阪・関西万博の開幕まであと一か月を切りました。海外からの万博関連の訪日ツアーの内容や販売状況について、現時点で観光庁として把握していることがあればお伺いします。
(答)
大阪・関西万博が近づいてきました。インバウンドを含めて多くのお客様が来ていただけると思いますが、観光庁としては万博をきっかけに万博プラスその他の観光を楽しんでいただき、できるだけ日本全国に行って頂くようにしたいと考えています。
JNTOが先月、中国市場の旅行会社約100社を対象に、万博関係の旅行商品の造成状況についてアンケートを実施しましたが、27%はすでに商品を作っており、65%が商品造成を予定していますという回答がありました。
ゴールデンルートや関西周遊旅行に万博を組み込んだような商品もすでに販売されているようです。
万博が近づきまして、各国のパビリオンやナショナルデーの情報が発信されてきておりますので、観光庁でもJNTOを通じて、万博情報の発信を強化しています。万博に対する認知度や関心は、これから東アジア中心に高まっていくと思いますが、ツアーの販売もしっかりサポートしていきたいと思っています。
(問)今月末で日米観光交流年が終わる見込みかと思いますが、その振り返りと4月以降同じ取組の延長を検討されているか、または他の日米間の観光促進の取り組みを何か検討されているか、お伺いします。
(答)
日米観光交流年は、昨年1月から今年の3月まで、スポーツや姉妹都市交流をテーマに、相互に観光交流の強化を図るということで進めてきました。
成果としては、アジア諸国の訪日客数が2019年のコロナ前のピークと比較して10% 伸びたことに比べて、アメリカ市場は58%伸び、国・地域別の訪日者数の順位も4位になりました。
一方で、円安や米国の物価上昇など色々要因はあろうかと思いますが、アウトバウンドはインバウンドほど伸びていない状況です。
ちょうど、メジャーリーグベースボールが開幕し、昨日、今日と試合がありますが、ロサンゼルスやシカゴの観光局の方も来られています。
話を聞くと、日本人選手がすごく活躍しているし、野球を見に行くためにアメリカに行く日本人も増えているということです。
今回、2日間ですけども、こういった機会を起爆剤にして、実際アメリカに行って野球を見ていただく方を今年はもっと増やしたいし、月曜日のレセプションには日本の旅行会社も参加していて、ぜひそういうところを伸ばしていきたいという話になりました。
今年は万博もありますので、さらに行き来が増えることを期待しています。
(問)日米間の取組は、今のところ新しくやる予定はないでしょうか。
(答)
交流年という形ではありませんが、日々の機会を活用して、引き続き交流を伸ばしていきたいと考えています。
(問)万博は、日本国内でも前売り券の話題が出るなど、関心、盛り上がりがいまいちとも言われていますが、日本人の国内旅行としての万博についての受け止めをお願いします。また、万博関連ツアーの売れ行きについて、把握していることがあれば、教えていただきたいと思います。
(答)
観光庁でも経産省や博覧会協会と連携して、旅行業協会に何回かお伺いしています。実際にお客様に万博に行って頂くために、チケットをどう売るか、どう旅行商品にしてもらうかが大事ということで、年末、年明けから活動をしています。
万博の進捗状況やどういった出し物があるのかなどを説明し、万博のチケットと組み合わせた旅行商品の造成を旅行業界にお願いしてきたところです。
旅行業界に聞き取りを行ったところ、直近では約 250の万博関係の旅行商品を造成していただいているということで、中には鳥取砂丘や有馬温泉といった地方の観光地も組み込んだ商品も販売されているとのことです。
販売状況はまだ分かりませんが、着実にその予約数を伸ばしている商品もあると聞いていますので、万博が近づいて、そのトレンドが強まればよいと思っています。
(問)最新の宿泊統計でもコロナ前と比較するとインバウンドの三大都市圏への集中が進んでいます。観光庁としても地方誘客を進めている中ですが、それに逆行する形になってしまっていることについて要因をどのように分析されていますか。また、今の対策でこのような現状になってしまっている中で、今後より一層地方誘客を推進するためにどのような対策を考えているのか教えてください。
(答)
宿泊統計によると、2024年の外国人の延べ宿泊者数 は約1.6 億人泊で、コロナ前の一番よかった2019年が、約1.1 億人泊だったので、全体は非常に伸びています。
ただ、2019年の大都市と地方の比率が6対4であったものが、去年は7対3になって大都市の方が多いという状況です。
都道府県別でも、東京、大阪、京都の三都府に限ってみても全体の6割です。
一方で、地方に泊まった方の絶対数は、2019年は 4,300 万人泊に対して2024年は5,000万人泊なので、伸びていますが、三大都市圏の方がより伸びているという状況です。
去年来ていただいたお客さまの人数としては、全体が伸びていますが、特に欧米諸国が伸びました。
細かい一人一人の分析はありませんが、おそらく初めて日本に行ってみようと思われた方が結構おられ、初めて来る時はやはり東京や大阪に行く傾向かと思います。
初めての方が来ていただいたらそこが増えるというのは自然なことで、2回目以降は同じところではなくて地方もいいですよということを一生懸命やっていくことが大事だと思います。
今までやっていることが効き目がないということではなく、引き続き、地方に素敵な観光地を作るということを引き続き行いつつ、地方も素敵な観光地がありますというお知らせをしていくことが大事だと思っています。
(問)訪日客数に関連して、宿泊税についてお伺いします。全国で宿泊税の導入や検討が広がっていますが、観光産業や地元住民への影響なども含め、これらの動きに関する長官の受け止めをお伺いします。
(答)
全国各地で、観光をきっかけにして、自主的な財源を確保する方法の一つとして、宿泊税を導入・検討している自治体が増えていることは承知しています。
観光の様々な政策の実現や問題に対処するために、独自の財源を確保するということは、世界中で非常にうまくいっている観光地において、地方公共団体やDMOが実践している取組であり、そういった取組自体は良いことではないかと思っています。
宿泊税については、地域の魅力を高め、観光振興を図ること等を目的に導入の是非や税額が判断されるものですので、地方公共団体や宿泊事業者をはじめとする関係者の方々の間でよく議論していただいて、その方針を決めていただくのが良いと思っています。
(問)アウトバンドの関連で、3月24日に改めて発表があると思いますが、前回の海外旅行喚起のキャンペーンが2023年で、少し時間が空いていますが、このタイミングでアウトバンドの喚起をする意義をお伺いします。
(答)
コロナ前の2019年には、インバウンドはもちろん、アウトバウンドも非常に良く、出国日本人数は2,000万人程いたかと思います。
コロナでそれぞれゼロに近くなってしまい、その後の回復ぶりがインバウンドは急激ですが、アウトバウンドの回復のスピード感がそれほどではないという状況です。
数字を見ますと、先月の日本人の出国者数は、去年と比べると 21% くらい増えているということなので、徐々に増加していますが、インバウンドほど急激には戻っていないと思っています。
若者の国際交流に資する海外教育旅行の取組や各国の政府観光局と連携した双方向の交流の活性化を進めるほか、関係者と連携しながらアウトバウンドの回復に向けて取組む必要があると思います。
文科省の方に聞くと、海外教育旅行に定期的に行っていた学校もコロナでやめてしまうと、再開するのはなかなかハードルが高いと聞きますので、そういったところも含めて今後機運醸成をしていきたいと思います。
(問)インバウンドの人数について、今年の2月は、多くの国で春節に当たらないことやそもそも日数が少ないという状況の中で、単月でも300万人を超えているということですが、その理由についてどのように考えているかお伺いします。
(答)
2月単月でどうかというよりは、特に去年の年末くらいから、中国もだいぶ戻ってきて、すべての国で前の年を上回るような状況となっています。
ですから、今日ご紹介したのは2月を切り取った数字ですが、そういった調子の良いトレンドは引き続き続いているという中での断面の一つだと思っています。
以上