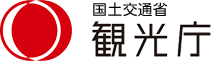秡川長官会見要旨
最終更新日:2025年6月2日
日時:2025年5月21日(水)16:15~16:45
場所:国土交通省会見室
場所:国土交通省会見室
冒頭発言
(訪日外国人旅行者数(2025年4月)について)
4月の訪日外国人旅行者数は、約391万人で、単月としては過去最高の数字です。昨年同月と比べ約30%伸びています。
4月の日本人の出国者数は、約96万人で、昨年同月と比べ8%の伸びになりました。
(旅行・観光消費動向調査2025年1-3月期(1次速報)について)
今年の1月から3月の3か月間の日本人の国内旅行を対象とした調査です。
この3か月間の日本人の国内延べ旅行者数は約1. 2億人で、前年の同じ期間と比べると6%増えています。
1回の旅行あたりの支出は、一人当たり約4. 7万円で、前年同期と比べると約9%増えています。
これらを掛け合わせた日本人の国内旅行消費額は約5.6兆円で、第一四半期としては過去最高、前年と比べると約16%増となりました。
過去を振り返りますと、旅行消費がもたらす波及効果は、消費額のおよそ2倍だということですので、この期間の経済効果はおおよそ11兆円となります。
4月の訪日外国人旅行者数は、約391万人で、単月としては過去最高の数字です。昨年同月と比べ約30%伸びています。
4月の日本人の出国者数は、約96万人で、昨年同月と比べ8%の伸びになりました。
(旅行・観光消費動向調査2025年1-3月期(1次速報)について)
今年の1月から3月の3か月間の日本人の国内旅行を対象とした調査です。
この3か月間の日本人の国内延べ旅行者数は約1. 2億人で、前年の同じ期間と比べると6%増えています。
1回の旅行あたりの支出は、一人当たり約4. 7万円で、前年同期と比べると約9%増えています。
これらを掛け合わせた日本人の国内旅行消費額は約5.6兆円で、第一四半期としては過去最高、前年と比べると約16%増となりました。
過去を振り返りますと、旅行消費がもたらす波及効果は、消費額のおよそ2倍だということですので、この期間の経済効果はおおよそ11兆円となります。
質疑応答
(問)米国の関税政策に伴う業界への影響についてお伺いします。各国の景気減退や円高が進んでいる中で、訪日外国人旅行者数や旅行中の消費の影響についてどのように考えておられるかお伺いします。また、日本人の国内旅行への影響についても教えてください。
(答)
旅行業界にヒアリングをしたところ、現時点ではご指摘いただいたアメリカの関税措置や経済の状況によって、我が国の旅行動向には特段影響を生じているということはないとのことです。
しかしながら、今後どのような動きになるかわかりませんので、状況は今後も注視していきたいと思います。
(問)国がインバウンド拡大を協力に推進する中で、特に地方部の温泉地では、バス、タクシーなど、二次交通の安定的な提供が喫緊の課題になっていると思いますが、長官の現状の認識をお聞かせください。また、今後、温泉地の二次交通の課題解消に向けて、ライドシェアを含めた方向性をお聞かせください。
(答)
日本人も含めた観光客の方々に、日本各地に行って楽しんでいただくために、今おっしゃった二次交通の確保・充実は非常に重要であり、併せてわかりやすく情報提供することも大事だと思っています。
現在、国交省では「交通空白」解消本部にて、地域の足や観光の足の確保に向けた様々な施策を進めています。
日本版・公共ライドシェアや観光客向け周遊バス、乗合タクシーといった交通手段に対する支援も行っており、また、経路検索アプリや訪日客向けの観光情報ウェブサイトにおける交通手段に関する情報の掲載充実などを行っています。
今後とも各地域のニーズに応じた移動手段を確保し、情報提供するということを行っていきたいと思います。
温泉地では、例えば銀山温泉では日本版ライドシェアが導入されておりますので、観光の足の確保・充実については、非常にライドシェアも有効な手段なのだろうと思います。
(問)先日の参議院予算委員会で、石破総理が国際観光旅客税、いわゆる出国税に関して触れ、外国人に対する出国税の見直しについて、政府で検討していくようなことを述べられましたが、長官の受け止めをお伺いいたします。
(答)
国際観光旅客税について、今おっしゃった国会のやり取りや報道が出ていることは承知しています。
現在、観光立国推進基本計画について、来年度から2030年までの5か年に向けて、6,000万人、15兆円という目標を目指すために何が必要なのか、新たな観光立国推進基本計画を今年度末までに作るという総理指示が出ており、対応しているところです。
観光政策として、今後その大きな目標に向けて何が必要なのかという施策の議論を今、しています。
施策に伴って財源が必要なものも当然ありますので、財源の話はその次の議論なのだろうと思っています。
今は、その施策の中身の議論をしているところであります。
(問)4月のインバウンドの結果について、過去最多ということですが、それに対する受け止めと、背景や要因についてお伺いします。国・地域別でみると、中国の人数が近年増えている傾向かと思いますが、その理由も教えてください。
また、2025年1-3月期の国内旅行消費額が過去最高ということですが、こちらについての評価・分析及び対応方針などがありましたら教えてください。
(答)
4月のインバウンド数については、地域別にみるとインバウンドの約7割を占めるアジア諸国が前年同月比で23%増えています。
欧米豪・中東諸国でも前年同月比46%増で非常に大きいです。
数か月引き続いて非常に好調で、ありがたい状況となったと思います。
4月については、3月に引き続き、桜シーズンによる訪日需要の高まりや4月中旬からのイースター休暇があったと思います。
特に香港ではイースターが昨年は3月でしたが今年は4月でしたので、香港だけ見てみると、3月と4月の数字が逆転しているような状況ですので、そういった部分も影響して数字に繋がったのかと思います。
中国については、中国国内における堅調な訪日需要や航空便の回復などが好調の理由かと思います。
日本人の旅行消費額については、国内の延べ旅行者数について、宿泊を伴う旅行者と日帰り旅行者ともに数字が良く、延べ旅行者数も前年同期比で6%増えているということです。また、物価上昇の影響もあったかもしれませんが、旅行単価が前年同期比9%増えたという部分も効いたのかと思います。
引き続き国内交流の拡大というのは重要なテーマですので、テレワークを活用したワーケーションの推進や、第2のふるさとづくりなど何度もその地域に通っていただくような取組の推進、また、ユニバーサルツーリズムの促進といったことを引き続き行っていきたいと思います。
(問)4月も過去最高更新ということですが、何ヶ月連続で過去最高更新なのか教えてください。
(答)
(観光庁事務方より)確認して後ほどお答えいたします。
(問)また、1,444万人というというのは、四半期ベースで見ても過去最多なのでしょうか。
(答)
そのとおりです。
(問)中国人の回復理由ですが、去年の段階では団体客があまり回復していないということがあったと思いますが、今年は回復してきているのでしょうか。
(答)
特に去年は、前半が非常に悪く、後半から盛り返してきて、11月12月はかなり元に戻ってきたという傾向でした。
その傾向が、年が明けても続いているということだと思います。
(問)後半盛り返してきたのは、団体客が戻ってきたということでしょうか。
(答)
団体客、個人客両方だと思いますが、去年の前半は非常に経済が悪く、旅行も含めた余暇を控える傾向でしたが、後半に徐々に増えてきて、年末にはかなり元に戻ったという分析です。
(問)日本側の団体客を受け入れるキャパシティについてお聞きします。日本の旅行会社は、コロナ禍で人が減って、団体客を受け入れにくい事情があると昨年聞きました。宿泊を伴うツアー客を受け入れるスタッフが、コロナ禍で大分切られて減ってしまって、なかなか戻ってこないため受入が大変と昨年は聞かれましたが、足元の状況はどうかお伺いします。
(答)
コロナの直後はかなり影響が大きかったです。
今も宿泊事業者によって程度は異なりますが、100%稼働しているところもあれば、従業員が不足しているため、フルになっていない例もあります。
全体で見ると、今来ている方を受け入れるキャパシティはあるようです。
(問)万博の影響についてお伺いします。足元の国内旅行客、訪日客への影響は現状ではいかがでしょうか。また見通しと比べてどうでしょうか。
(答)
万博協会や経済産業省からは、予想よりも多くの来場者や予約があり、良いスタートだと聞いています。
開幕から1ヶ月あまりですが、旅行会社や業界団体に聞くと、万博の旅行商品の売れ行きが好調で、予約もかなり入っているようです。
しかしながら、国内旅行全体の中で万博の効果を測る数字は出ていないため、影響というところまでは分からないところです。
(問)万博目的の訪日客もかなり来ているのでしょうか。
(答)
具体的な数字はありませんが、外国人もかなり来ているという情報を聞きます。
(問)出国日本人数ですが、4月は前年比8. 2%増で2月と3月に比べると増加率が半減していると思いますがそれはなぜでしょうか。
(答)
(観光庁事務方より)昨年のゴールデンウィークと比べ、今年のゴールデンウィークは日並びが悪かったのが要因としてあります。今年は連休の間に、4月28日の月曜日の平日が入っていて、その影響が大きいところです。また、3月末にミャンマーで大きな地震があり、タイへの旅行が減っているとヒアリングで聞いており、その結果、少し伸び率が低くなっています。
(問)統合型リゾートIRについてお伺いします。国内のIR整備は今、大阪で始まっていて法令では残り2か所整備できることになっていますが、観光庁としては残り2か所でもIRを整備していきたいという方針があるのでしょうか。そのような方針があるなら、今後2区域の申請に向けたスケジュールをどう描いているのかお聞かせください。
(答)
IR整備はIR整備法に基づいて進めていますが、この法律上、日本では3か所が認定の上限であり、1か所目として大阪が認定されたため、あと2か所残っています。
国土交通省が認定するには、まず自治体と事業者がチームを作って申請していただく必要がありますが、その申請期間は政令で定めることになっています。
そのため、入試のように毎年2月にありますとか、定例的なタイミングで認定するのでなく、申請者の準備ができ、申請できそうになったら政令を定めて申請期間を決めるという形でやっています。
また、法律には附帯決議があり、政令で期間を決めるときは、各自治体が公平に申請を受けられるような期間を設定することとなっています。早くやりたい方と、ちょっと時間かかる方の双方にやる気がある場合は、そのような自治体が一緒に申請できるようにすべきだという議論だったと思います。
自治体の検討状況を十分見極めた上で、政令を定める必要があるのかを判断していくということになりますので、現時点でいつを申請期間とするのかは決まっていません。
(問)昨年、各都道府県に意向調査をされたかと思いますが、関心を持っていたり、前向きな自治体は何か所あったのか、具体的にどの自治体なのか、お聞かせいただければと思います。
(答)
興味を持っている自治体は1回目の申請のときも結構ありました。その後も色々とご質問いただいたりする自治体もありますし、最近の状況はどうですかと定例的にお伺いすることもあります。そういうコミュニケーションの機会を持っているということです。
現時点で具体的にどこかの自治体がというところまでの話はないです。
(問)日本人の国内旅行についてお伺いしたいのですが、コロナ明け以降、消費額が伸びている一方で、高齢者の実施率低下が指摘されています。現状への認識や、対策の方向性をお聞かせ願えますでしょうか。
(答)
2024年の観光消費動向調査によると、観光・レクリエーション目的の国内宿泊旅行の率は若年層が60%を超えている一方で、高齢者層は、コロナ前の2019年は約39%でしたが、去年は約31%ということで10ポイントほど低下しています。若年層は20代以下、高齢者の70代以上です。
高齢者の旅行者は、一人当たりの旅行への支出が多い傾向があります。加えて平日の旅行も可能であり、需要の平準化が見込まれ、高齢者の旅行を振興していくことは非常に重要だと思います。
そのため、高齢者の旅行需要の喚起、旅行しやすい環境を整えていくことは大事だと思います。
ユニバーサルツーリズムの促進も従来から行っており、具体的には高齢者向けのモデルツアーなどの旅行商品を造成や、観光施設や宿泊施設のバリアフリー化に向けた施設整備のための支援などを行っています。引き続き高齢者の方にも楽しんでいただく環境を整えていきたいと思います。
(問)訪日客についての長官の見通しについてお伺いします。今年の1月から4月までの人数で大体1,500万人弱の人数で、この人数を1年間に直すと約4,500万人になります。この好調な状況は1年間持続するのか、年間訪日客数の見込み、またそのために重要な要素があれば教えてください。
(答)
今後の予測というのはありませんが、今、非常に好調ですので、好調な時期を大事にしつつ、増えた時に備えて対策を今から立てておくということだと思います。
国土交通省ではないですが、入管についても、人が増えていくと空港での入国に時間がかかりますが、例えば万博をやっている関空には、集中して人を配置してくださっており、ゴールデンウィークの待ち時間もそこまで悪くなっていないです。
20分以上待たせないことが目標になっており、70%くらい達成しています。そういった増えた場合の備えは色々行っていくということです。
(問)香港で、漫画の内容をもとに7月に日本で大災害が起きるという噂が広まって訪日客が減少していると報道がありましたが、その受け止めと風評被害対策について、考えをお伺いします。
(答)
香港で、そういった噂が広がっているという報道は承知しています。
一方で、4月の香港からのインバウンドを見ると、26万人来ていただいており、これは4月としては過去最高です。したがって、噂による影響というのは、現時点ではあまりないと思っています。
災害の予知については内閣府や気象庁が担当ですが、日時や場所などを特定して地震を予知することは現時点の科学的知見からは困難ということで、起こるという根拠はありません。
ホームページ等でお知らせはしていますが、香港はJNTOの事務所もありますので、もう少し心配な状況が続くようであれば、科学的にはそんなことはありませんというお知らせをするということあるのではと思いますが、状況を注視したいと思います。
(問)旅行消費に関して、宿泊費が高騰しており、今後も高止まりの流れが続くと見込まれる中、このトレンドが次の四半期も変わらないとなると、過去最高更新という可能性が出てきます。この状況を果たして喜んでよいのか疑問がありますが、消費のバランスや今後の動向も含めてお考えをお聞かせください。
(答)
個人的な旅行者という立場に立つと、宿泊費が高いというのは、以前泊まれたところに泊まりにくくなるという状況ですので、マイナスな要素もありますが、宿泊業界の方にお話を伺うと、外国と比べて日本の宿泊費は相対的に安すぎるということでした。そうなると従業員さんに対する支払いなどの部分で、コロナで離職した人が、戻って来ないということに繋がっていると思います。
各宿泊事業者さんの事情があると思いますが、適正な収益確保などを含めて値付けがあると思いますので、適切な値付けをしてもらうというのは本来あるべき姿ですのでそれはそれでよいと思います。
掛け算をすると数字が出来上がるので、人数も増えて値段も上がると、消費が増えるとことになりますが、マイナスとプラス両方あるのだろうと思います。
(問)観光立国推進基本計画について、次の計画の話も少し触れられていましたが、連休前に観光分科会があり、委員の方から色々な意見があったかと思いますが、今後の戦略の策定に向けて、委員の意見を聞かれた上で、今後の論点をどう捉えているか教えてください。
(答)
4月25日に観光分科会が開催され、次期計画策定に向けてのキックオフをしました。
委員の先生方から様々なご意見をいただきましたが、大きく要約すると、たくさん来ていただくために、魅力的な観光地を作らなければならないということです。そのためには、DMOの機能強化や地域住民の理解を得ながら観光客を受け入れる観光地域づくりをしていかなければなりません。
また、賃金も含めた労働条件の改善や生産性の向上に取り組み、観光産業自体をしっかりしたものにする必要があることや人手不足対策も非常に急務ですので、そこも見据えた計画にする必要があるといったご意見がありました。
(問)冒頭でライドシェアのお話があり銀山温泉の事例が複数出ていたが、観光でライドシェアが役に立っている他の地域の事例で把握されているものがあったら教えてください。
(答)
(観光庁事務方より)ライドシェアの制度自体は、様々な地域において「交通空白」解消本部の下、日本版ライドシェアそして公共ライドシェアについて観光地であるかどうかを問わず導入が進んでいます。先ほど長官からご発言があった銀山温泉の他、制度改善というか運用面の措置として、例えば京都においては昨年の秋の観光シーズンにおいて、一時的にライドシェアの時間を延長して、日本版ライドシェアの運行をするという運用をし、観光客の移動の足確保に向けた取組として、自治体の一つの選択肢として取り組まれているものと、承知しているところでございます。
(問)その中で何か具体的にこんな成果があったといった声が上がってきていますでしょうか。こんなに観光客に使われているとか、喜ばれているといった反応は観光庁に上がってきていますでしょうか。
(答)
個人的な話ですが、軽井沢は東京から1時間ちょっとで着くのに、タクシーで1時間半も待たされると私に文句を言う友人が多くいます。確かに大変だと思っていましたが、最近はすぐタクシーに乗れますと言っています。
軽井沢は、ライドシェアでいろいろ車両を持ってきたりしていて、明らかに良くなったという評価の報告もありました。効果が出ている地域として軽井沢は一例ですが、同じような地域もあるのではないかと思います。
(答)
旅行業界にヒアリングをしたところ、現時点ではご指摘いただいたアメリカの関税措置や経済の状況によって、我が国の旅行動向には特段影響を生じているということはないとのことです。
しかしながら、今後どのような動きになるかわかりませんので、状況は今後も注視していきたいと思います。
(問)国がインバウンド拡大を協力に推進する中で、特に地方部の温泉地では、バス、タクシーなど、二次交通の安定的な提供が喫緊の課題になっていると思いますが、長官の現状の認識をお聞かせください。また、今後、温泉地の二次交通の課題解消に向けて、ライドシェアを含めた方向性をお聞かせください。
(答)
日本人も含めた観光客の方々に、日本各地に行って楽しんでいただくために、今おっしゃった二次交通の確保・充実は非常に重要であり、併せてわかりやすく情報提供することも大事だと思っています。
現在、国交省では「交通空白」解消本部にて、地域の足や観光の足の確保に向けた様々な施策を進めています。
日本版・公共ライドシェアや観光客向け周遊バス、乗合タクシーといった交通手段に対する支援も行っており、また、経路検索アプリや訪日客向けの観光情報ウェブサイトにおける交通手段に関する情報の掲載充実などを行っています。
今後とも各地域のニーズに応じた移動手段を確保し、情報提供するということを行っていきたいと思います。
温泉地では、例えば銀山温泉では日本版ライドシェアが導入されておりますので、観光の足の確保・充実については、非常にライドシェアも有効な手段なのだろうと思います。
(問)先日の参議院予算委員会で、石破総理が国際観光旅客税、いわゆる出国税に関して触れ、外国人に対する出国税の見直しについて、政府で検討していくようなことを述べられましたが、長官の受け止めをお伺いいたします。
(答)
国際観光旅客税について、今おっしゃった国会のやり取りや報道が出ていることは承知しています。
現在、観光立国推進基本計画について、来年度から2030年までの5か年に向けて、6,000万人、15兆円という目標を目指すために何が必要なのか、新たな観光立国推進基本計画を今年度末までに作るという総理指示が出ており、対応しているところです。
観光政策として、今後その大きな目標に向けて何が必要なのかという施策の議論を今、しています。
施策に伴って財源が必要なものも当然ありますので、財源の話はその次の議論なのだろうと思っています。
今は、その施策の中身の議論をしているところであります。
(問)4月のインバウンドの結果について、過去最多ということですが、それに対する受け止めと、背景や要因についてお伺いします。国・地域別でみると、中国の人数が近年増えている傾向かと思いますが、その理由も教えてください。
また、2025年1-3月期の国内旅行消費額が過去最高ということですが、こちらについての評価・分析及び対応方針などがありましたら教えてください。
(答)
4月のインバウンド数については、地域別にみるとインバウンドの約7割を占めるアジア諸国が前年同月比で23%増えています。
欧米豪・中東諸国でも前年同月比46%増で非常に大きいです。
数か月引き続いて非常に好調で、ありがたい状況となったと思います。
4月については、3月に引き続き、桜シーズンによる訪日需要の高まりや4月中旬からのイースター休暇があったと思います。
特に香港ではイースターが昨年は3月でしたが今年は4月でしたので、香港だけ見てみると、3月と4月の数字が逆転しているような状況ですので、そういった部分も影響して数字に繋がったのかと思います。
中国については、中国国内における堅調な訪日需要や航空便の回復などが好調の理由かと思います。
日本人の旅行消費額については、国内の延べ旅行者数について、宿泊を伴う旅行者と日帰り旅行者ともに数字が良く、延べ旅行者数も前年同期比で6%増えているということです。また、物価上昇の影響もあったかもしれませんが、旅行単価が前年同期比9%増えたという部分も効いたのかと思います。
引き続き国内交流の拡大というのは重要なテーマですので、テレワークを活用したワーケーションの推進や、第2のふるさとづくりなど何度もその地域に通っていただくような取組の推進、また、ユニバーサルツーリズムの促進といったことを引き続き行っていきたいと思います。
(問)4月も過去最高更新ということですが、何ヶ月連続で過去最高更新なのか教えてください。
(答)
(観光庁事務方より)確認して後ほどお答えいたします。
(問)また、1,444万人というというのは、四半期ベースで見ても過去最多なのでしょうか。
(答)
そのとおりです。
(問)中国人の回復理由ですが、去年の段階では団体客があまり回復していないということがあったと思いますが、今年は回復してきているのでしょうか。
(答)
特に去年は、前半が非常に悪く、後半から盛り返してきて、11月12月はかなり元に戻ってきたという傾向でした。
その傾向が、年が明けても続いているということだと思います。
(問)後半盛り返してきたのは、団体客が戻ってきたということでしょうか。
(答)
団体客、個人客両方だと思いますが、去年の前半は非常に経済が悪く、旅行も含めた余暇を控える傾向でしたが、後半に徐々に増えてきて、年末にはかなり元に戻ったという分析です。
(問)日本側の団体客を受け入れるキャパシティについてお聞きします。日本の旅行会社は、コロナ禍で人が減って、団体客を受け入れにくい事情があると昨年聞きました。宿泊を伴うツアー客を受け入れるスタッフが、コロナ禍で大分切られて減ってしまって、なかなか戻ってこないため受入が大変と昨年は聞かれましたが、足元の状況はどうかお伺いします。
(答)
コロナの直後はかなり影響が大きかったです。
今も宿泊事業者によって程度は異なりますが、100%稼働しているところもあれば、従業員が不足しているため、フルになっていない例もあります。
全体で見ると、今来ている方を受け入れるキャパシティはあるようです。
(問)万博の影響についてお伺いします。足元の国内旅行客、訪日客への影響は現状ではいかがでしょうか。また見通しと比べてどうでしょうか。
(答)
万博協会や経済産業省からは、予想よりも多くの来場者や予約があり、良いスタートだと聞いています。
開幕から1ヶ月あまりですが、旅行会社や業界団体に聞くと、万博の旅行商品の売れ行きが好調で、予約もかなり入っているようです。
しかしながら、国内旅行全体の中で万博の効果を測る数字は出ていないため、影響というところまでは分からないところです。
(問)万博目的の訪日客もかなり来ているのでしょうか。
(答)
具体的な数字はありませんが、外国人もかなり来ているという情報を聞きます。
(問)出国日本人数ですが、4月は前年比8. 2%増で2月と3月に比べると増加率が半減していると思いますがそれはなぜでしょうか。
(答)
(観光庁事務方より)昨年のゴールデンウィークと比べ、今年のゴールデンウィークは日並びが悪かったのが要因としてあります。今年は連休の間に、4月28日の月曜日の平日が入っていて、その影響が大きいところです。また、3月末にミャンマーで大きな地震があり、タイへの旅行が減っているとヒアリングで聞いており、その結果、少し伸び率が低くなっています。
(問)統合型リゾートIRについてお伺いします。国内のIR整備は今、大阪で始まっていて法令では残り2か所整備できることになっていますが、観光庁としては残り2か所でもIRを整備していきたいという方針があるのでしょうか。そのような方針があるなら、今後2区域の申請に向けたスケジュールをどう描いているのかお聞かせください。
(答)
IR整備はIR整備法に基づいて進めていますが、この法律上、日本では3か所が認定の上限であり、1か所目として大阪が認定されたため、あと2か所残っています。
国土交通省が認定するには、まず自治体と事業者がチームを作って申請していただく必要がありますが、その申請期間は政令で定めることになっています。
そのため、入試のように毎年2月にありますとか、定例的なタイミングで認定するのでなく、申請者の準備ができ、申請できそうになったら政令を定めて申請期間を決めるという形でやっています。
また、法律には附帯決議があり、政令で期間を決めるときは、各自治体が公平に申請を受けられるような期間を設定することとなっています。早くやりたい方と、ちょっと時間かかる方の双方にやる気がある場合は、そのような自治体が一緒に申請できるようにすべきだという議論だったと思います。
自治体の検討状況を十分見極めた上で、政令を定める必要があるのかを判断していくということになりますので、現時点でいつを申請期間とするのかは決まっていません。
(問)昨年、各都道府県に意向調査をされたかと思いますが、関心を持っていたり、前向きな自治体は何か所あったのか、具体的にどの自治体なのか、お聞かせいただければと思います。
(答)
興味を持っている自治体は1回目の申請のときも結構ありました。その後も色々とご質問いただいたりする自治体もありますし、最近の状況はどうですかと定例的にお伺いすることもあります。そういうコミュニケーションの機会を持っているということです。
現時点で具体的にどこかの自治体がというところまでの話はないです。
(問)日本人の国内旅行についてお伺いしたいのですが、コロナ明け以降、消費額が伸びている一方で、高齢者の実施率低下が指摘されています。現状への認識や、対策の方向性をお聞かせ願えますでしょうか。
(答)
2024年の観光消費動向調査によると、観光・レクリエーション目的の国内宿泊旅行の率は若年層が60%を超えている一方で、高齢者層は、コロナ前の2019年は約39%でしたが、去年は約31%ということで10ポイントほど低下しています。若年層は20代以下、高齢者の70代以上です。
高齢者の旅行者は、一人当たりの旅行への支出が多い傾向があります。加えて平日の旅行も可能であり、需要の平準化が見込まれ、高齢者の旅行を振興していくことは非常に重要だと思います。
そのため、高齢者の旅行需要の喚起、旅行しやすい環境を整えていくことは大事だと思います。
ユニバーサルツーリズムの促進も従来から行っており、具体的には高齢者向けのモデルツアーなどの旅行商品を造成や、観光施設や宿泊施設のバリアフリー化に向けた施設整備のための支援などを行っています。引き続き高齢者の方にも楽しんでいただく環境を整えていきたいと思います。
(問)訪日客についての長官の見通しについてお伺いします。今年の1月から4月までの人数で大体1,500万人弱の人数で、この人数を1年間に直すと約4,500万人になります。この好調な状況は1年間持続するのか、年間訪日客数の見込み、またそのために重要な要素があれば教えてください。
(答)
今後の予測というのはありませんが、今、非常に好調ですので、好調な時期を大事にしつつ、増えた時に備えて対策を今から立てておくということだと思います。
国土交通省ではないですが、入管についても、人が増えていくと空港での入国に時間がかかりますが、例えば万博をやっている関空には、集中して人を配置してくださっており、ゴールデンウィークの待ち時間もそこまで悪くなっていないです。
20分以上待たせないことが目標になっており、70%くらい達成しています。そういった増えた場合の備えは色々行っていくということです。
(問)香港で、漫画の内容をもとに7月に日本で大災害が起きるという噂が広まって訪日客が減少していると報道がありましたが、その受け止めと風評被害対策について、考えをお伺いします。
(答)
香港で、そういった噂が広がっているという報道は承知しています。
一方で、4月の香港からのインバウンドを見ると、26万人来ていただいており、これは4月としては過去最高です。したがって、噂による影響というのは、現時点ではあまりないと思っています。
災害の予知については内閣府や気象庁が担当ですが、日時や場所などを特定して地震を予知することは現時点の科学的知見からは困難ということで、起こるという根拠はありません。
ホームページ等でお知らせはしていますが、香港はJNTOの事務所もありますので、もう少し心配な状況が続くようであれば、科学的にはそんなことはありませんというお知らせをするということあるのではと思いますが、状況を注視したいと思います。
(問)旅行消費に関して、宿泊費が高騰しており、今後も高止まりの流れが続くと見込まれる中、このトレンドが次の四半期も変わらないとなると、過去最高更新という可能性が出てきます。この状況を果たして喜んでよいのか疑問がありますが、消費のバランスや今後の動向も含めてお考えをお聞かせください。
(答)
個人的な旅行者という立場に立つと、宿泊費が高いというのは、以前泊まれたところに泊まりにくくなるという状況ですので、マイナスな要素もありますが、宿泊業界の方にお話を伺うと、外国と比べて日本の宿泊費は相対的に安すぎるということでした。そうなると従業員さんに対する支払いなどの部分で、コロナで離職した人が、戻って来ないということに繋がっていると思います。
各宿泊事業者さんの事情があると思いますが、適正な収益確保などを含めて値付けがあると思いますので、適切な値付けをしてもらうというのは本来あるべき姿ですのでそれはそれでよいと思います。
掛け算をすると数字が出来上がるので、人数も増えて値段も上がると、消費が増えるとことになりますが、マイナスとプラス両方あるのだろうと思います。
(問)観光立国推進基本計画について、次の計画の話も少し触れられていましたが、連休前に観光分科会があり、委員の方から色々な意見があったかと思いますが、今後の戦略の策定に向けて、委員の意見を聞かれた上で、今後の論点をどう捉えているか教えてください。
(答)
4月25日に観光分科会が開催され、次期計画策定に向けてのキックオフをしました。
委員の先生方から様々なご意見をいただきましたが、大きく要約すると、たくさん来ていただくために、魅力的な観光地を作らなければならないということです。そのためには、DMOの機能強化や地域住民の理解を得ながら観光客を受け入れる観光地域づくりをしていかなければなりません。
また、賃金も含めた労働条件の改善や生産性の向上に取り組み、観光産業自体をしっかりしたものにする必要があることや人手不足対策も非常に急務ですので、そこも見据えた計画にする必要があるといったご意見がありました。
(問)冒頭でライドシェアのお話があり銀山温泉の事例が複数出ていたが、観光でライドシェアが役に立っている他の地域の事例で把握されているものがあったら教えてください。
(答)
(観光庁事務方より)ライドシェアの制度自体は、様々な地域において「交通空白」解消本部の下、日本版ライドシェアそして公共ライドシェアについて観光地であるかどうかを問わず導入が進んでいます。先ほど長官からご発言があった銀山温泉の他、制度改善というか運用面の措置として、例えば京都においては昨年の秋の観光シーズンにおいて、一時的にライドシェアの時間を延長して、日本版ライドシェアの運行をするという運用をし、観光客の移動の足確保に向けた取組として、自治体の一つの選択肢として取り組まれているものと、承知しているところでございます。
(問)その中で何か具体的にこんな成果があったといった声が上がってきていますでしょうか。こんなに観光客に使われているとか、喜ばれているといった反応は観光庁に上がってきていますでしょうか。
(答)
個人的な話ですが、軽井沢は東京から1時間ちょっとで着くのに、タクシーで1時間半も待たされると私に文句を言う友人が多くいます。確かに大変だと思っていましたが、最近はすぐタクシーに乗れますと言っています。
軽井沢は、ライドシェアでいろいろ車両を持ってきたりしていて、明らかに良くなったという評価の報告もありました。効果が出ている地域として軽井沢は一例ですが、同じような地域もあるのではないかと思います。
以上